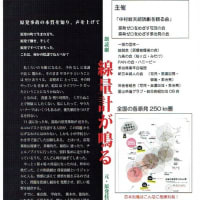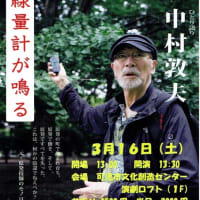デジタル監視社会 自由を死守する正念場 中島岳志
2020年11月1日 中日新聞
菅義偉内閣はデジタル庁創設に力を入れている。そこでは行政の一元化など、利便性ばかりが論じられているが、いま世界的に議論されているのはデジタル監視の危険性についてである。コロナ危機により、公衆衛生という観点からのデジタル監視が拡大した。私たちの行動はスマートフォンの位置情報によって追跡され、特定のアプリをダウンロードすれば、部分的ではあるものの感染者との接触の有無がわかる。
当然、これは個人の自由やプライバシーの侵害と表裏一体である。中国では、各人の感染可能性が三段階で表示され、治安当局は特定の個人の移動を強制的に制限する。香港の民主化運動では、若者たちが乗車履歴や買い物履歴から行動や情報を把握されることを恐れ、「デジタル断ち」を行った。
マルクス・ガブリエルは、中島隆博との対談(『全体主義の克服』集英社新書)の中で、「デジタル全体主義」という概念を提示する。現代人は、自分の行動を写真に撮り、オンラインで公開する。すると、プライベート空間がネット上に公開され、私的領域と公的領域の区別がなくなっていく。かつての全体主義体制では、人々は自分の考えを隠そうとしたが、今は自ら喜んで公に晒(さら)している。ガブリエルは、このような状態を「市民的服従」と呼び、全体主義を自ら引き寄せていくメカニズムに警告を発する。
「Netflix(ネットフリックス)」が独占配信し、世界的に話題となったドキュメンタリー「監視資本主義:デジタル社会がもたらす光と影」では、「人間の商品化」という問題が提起されている。私たちは、無料のソーシャルメディアを使ってコミュニケーションを行っているが、会員制交流サイト(SNS)を使えば使うほど、行動や嗜好(しこう)性についてのデータがネット企業に蓄積される。その情報によって、私たちは最適な広告を見るように誘導される。つまり、ネット企業にとって、「客」は広告主であり、ユーザーは「商品」である。
私たちは、常に不可視の存在から見られているのだ。私たちの行動パターンこそが、商品として管理されている。この「監視資本主義」と権力はどのように結びつくのか。
佐藤章「デジタル庁に忍び寄るアマゾン〜国家の機密情報や国民の個人情報は大丈夫か?」(論座、9月27日)は、菅首相が「マイナンバーカードの普及促進を一気呵成(かせい)に進める」と発言していることに注目する。政府は、しきりにマイナンバーと個人情報をリンクさせようとしている。マイナンバーカードを住民票や印鑑登録証明書、戸籍謄本をコンビニなどで交付する証明カードにするだけでなく、クレジットカードや銀行口座、各種ポイントカード、診察券、お薬手帳などの機能を付けることが検討されている。
政府はこの情報処理事業を、Amazonに一任しようとしている。一国の全ての個人情報が入っているものを、外国企業に任せて大丈夫なのだろうか。他国への情報漏洩(ろうえい)を防ぐことができるのか。
いや、それ以上に問題なのは、私たちの個人情報が、政府に筒抜けになることである。もちろん、政府は全ての国民のデータを逐次監視するわけではない。しかし、私たちは常に「見られている」という思いを抱くことになる。その時、国民の間に自主規制が起きるだろう。「この本を買ったら、反政府的な人間と思われて警戒されるのではないか」「だったら、買うのをやめておこう」ということになれば、言論は自発的に萎縮し、自主規制が蔓延(まんえん)する。フランスの哲学者ミシェル・フーコーは、「監視すること」よりも「監視されているという思い」を国民に植え付けることによって、国民を効率的・効果的に服従させるメカニズムがあることを明らかにしたが、現在はこの原理が起動する寸前にある。
鈴木哲夫「長期政権図る菅首相 恐るべき権力掌握の舞台裏」(『週刊金曜日』10月2日号)は、菅内閣における上川陽子法相と小此木八郎国家公安委員長の人事に注目する。二人は二〇一七年の安倍内閣で入閣した際と同じポストに就任しており、そこには菅内閣が検察と警察をコントロールしようとする意思が表れているという。
今起きていることに繊細にならなければ、取り返しの付かない事態を招くだろう。自由を死守する正念場だ。
(なかじま・たけし=東京工業大教授)