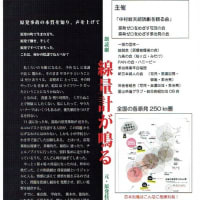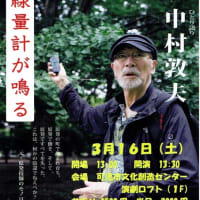労災基準の改定 働く人の救済を柔軟に
2021年11月10日 中日新聞
仕事により脳出血や心筋梗塞など脳や心臓の病を患った人に対する労災保険の認定基準が、二十年ぶりに見直された。
残業時間が認定基準の「過労死ライン」に達していなくても、過重労働を強いられ、病に倒れた人は労災が認められやすくなる。
働き方は多様化している。労災制度は、労働環境の変化に対応して柔軟に運営すべきだ。
従来の認定基準は、残業が「発症前一カ月に百時間超」「発症前二〜六カ月間平均で月八十時間超」のいずれかに該当し、業務と発症との関係が強いと判断される場合と規定されていた。
二〇二〇年度は脳・心臓疾患の労災百九十四件のうち、基準未満の残業時間でも労災が認められた事例は二十一件と一割程度だ。
認定基準を超えているかどうかを機械的に判断しているとの批判があり、申請自体を諦めてしまう場合もあったとみられる。
新しい認定基準では、過労死ラインに近ければ、休日のない連続勤務、終業から次の始業までの休息時間が短い勤務、身体的・心理的な負荷など労働時間以外の要因も含めて総合的に判断する。
この見直しで救済される人は増えるのではないか。
働き方の実態は職場や働き方によってさまざまだ。その把握は容易ではないのだろうが、労災が認定されるかどうかは労働者にとって切実な問題である。審査を担う労働基準監督署は労働実態を見極め、新基準に基づいて一人でも多く救済できるよう努めるべきだ。
国際労働機関(ILO)などは五月、残業が月六十五時間以上になると心疾患や脳卒中のリスクが高まるとの研究結果を公表した。過労死した人の遺族らは労災認定のハードルが高いとして、過労死ラインを「月六十五時間」に引き下げるよう求めている。
厚生労働省は過労死ライン自体が妥当かどうか、科学的知見を集め、検討する必要がある。
労災保険は仕事でけがをしたり病気になった際の治療費や生活費だけでなく、障害が残った本人や本人死亡の際は遺族に年金が支給されるなど、働く人と家族を支える重要な制度だ。常に実態に即した見直しは欠かせない。
そもそも健康に働けてこその職業人生だ。企業には、過労死のない職場環境の実現に取り組む社会的義務がある。