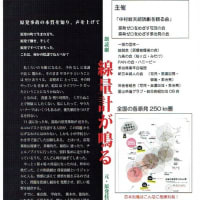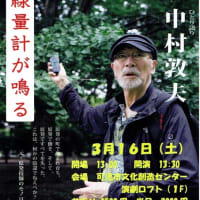生活保護の増加 貧困ビジネス切り離せ
2020年12月21日 中日新聞
コロナ禍で住まいを失い、生活保護を求める人に一部の自治体が無料低額宿泊所(無低)への入居を申請条件にしている。無低には「貧困ビジネス」と指摘される施設が多い。直ちにやめるべきだ。
コロナ禍による雇用情勢悪化に伴い、生活保護の申請が増えている。厚生労働省によると、四月の申請数は二万一千四百八十六件。前年同月比で24・8%増だった。 その後、各種の生活支援でやや落ち着いたが、コロナの第三波到来で再び解雇、雇い止めが増え、年末年始に急増する気配だ。
住まいを失った人びとが生活保護を申請する際、ハードルとなるのが無低だ。一部の自治体が入居を申請条件にしているためだ。
無低は社会福祉法に基づく民間施設で、全国に五百七十カ所(同省調べ)ある。良心的な施設もあるが、劣悪な環境で粗末な食事しか与えず、入居者から生活保護費を搾取する「貧困ビジネス」の温床となっているケースが多い。
なぜ、一部の自治体が無低を条件とするのか。自治体側は受給者の生活状況を把握しなくてはならないが、職員不足から無低に任せがちなことが一因だ。ただ、困窮者の支援団体からは「財政負担を減らすため、施設の劣悪さから申請を諦めさせる『水際作戦』に使っている」と指摘する声も強い。
生活保護はアパートなどで暮らす居宅保護が原則で、生活保護法は本人の意思に反して施設に入所させることを禁じている。それゆえ、一部自治体の申請条件は原則から逸脱し、違法でもある。大部屋をカーテンで仕切っただけの施設もあり、新型コロナの感染対策からも現状は看過できない。
厚労省は九月に各都道府県などに対し「申請権の侵害または侵害していると疑われるような行為」として、無低入居を条件化しないよう通知している。しかし、支援団体などによると、通知後も状況は改善されていないという。
かねて生活保護バッシングが繰り返され、菅義偉首相は「自助」を強調する。しかし、生活保護は憲法二五条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に基づく制度だ。生活保護基準を下回る経済状況で、実際に生活保護を受給している世帯は二割強にすぎない。
国は無低入居を申請条件にさせない指導を徹底し、空き家利用など住宅の供給にも一段と力を入れるべきだ。生活保護は「最後のセーフティーネット」だ。コロナ禍の厳冬期にその土台を固めたい。