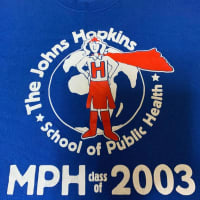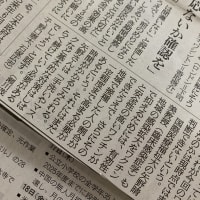帰国後5年間、日本語で、母国の学生、研修医の方に接し、日本語での症例提示とカルテ記載において、ほぼ全員に共通する問題点があることを発見しています。
それは、
1.「診断の可能性を評価する習慣、概念が乏しい」ということです。
2.診断名に、右、左、遠位、近位、解剖学的位置が、多くの場合欠如するということです。
解剖学的位置が欠如していては、診断としては非常に不十分。
例:腸腰筋膿瘍(どちらの?)、椎骨炎(どこの?)、脳膿瘍(どの部分の?)
腎盂腎炎(どちらの?)という感じです。
これは、「言語による限界」「概念の存在の有無」「文化的背景」などが原因ではないか、と感じています。
数年前に、日本人としてはじめて米国の感染症科専門医資格を取得され、沖縄県立中部病院で、感染症診療を確立された喜舎場朝和先生のご講演を拝聴したときに、私のなかでも、それまで「言語化できずにいた疑問」が、明確になりました。
在米時代には、「無意識レベル」で、rule out, most likely, less likely, unlikelyなどの用語を、自分の診断に合わせて認識していたことを思い出しました。
日本の現場で、患者の診断、臨床状態を把握する際に、「障壁」となっていると私が強く感じる面があります。
診断名が、「いつまでたっても、xxx疑い」に終始すること
あるいは、「xxxxを指摘されて・・・」という文章の意味、
「xxxxは否定的」
というように、「診断」の確実性を示すことばが非常に少ない現実です。
診断は、
確定診断 definate
推測診断 probable, or presumed
xx診断の可能性 possible (50%以上の可能性)
xx診断の可能性は低い less likely
xx診断の可能性はきわめて低い、または、ほぼない unlikely
xx診断は、除外された ruled out
と英語で診断名を記載する場合、上記のような「可能性のGrade評価」が必須です。
一方、日本語で記載されているカルテ記載を見ると、
確定しているのか、推測なのか、鑑別診断のひとつなのか、不明瞭の場合が多いです。
保険病名として、「xxx疑い」と記載せざるを得ない社会事情はありますが、教育面、臨床判断をトレーニングする場合、臨床試験を行う場合などに弊害があります。
日本語では、
確定
疑い
否定的
除外
の4通りが主ですが、「疑い」と「否定」にGradeが存在しないため、可能性が伝わってきません。したがって、カルテを見ても、その状態がわかりにくい、という状況である感じがします。
また、カルテ中の「xxxを指摘され」という表現も非常にあいまいです。
「確定診断がついているのか」「推測診断なのか」「保険病名だけなのか」「異常所見がみつかっただけなのか」「鑑別診断として上がっただけなのか」「患者さんが訴えているだけなのか」意味があいまいで、伝わりません。
学生、研修医の方は、「診断の可能性のGrade評価」を行い、それが伝わる表現を心がけると、記載やプレゼンテーションはかなりシャープになります。意識してみてください。
ちなみに、私が指導する場合、「疑い」「否定」は使用しないようにお願いしています。
上記のような国内で見られる共通の問題をクリアすることで、患者をより正確に精緻に把握し、質の高い診療を提供できるようにできれば、と考えています。そのためにも、学生時代から精緻な患者の把握とプレゼン、記載ができる教育体制が必須と考えています。
それは、
1.「診断の可能性を評価する習慣、概念が乏しい」ということです。
2.診断名に、右、左、遠位、近位、解剖学的位置が、多くの場合欠如するということです。
解剖学的位置が欠如していては、診断としては非常に不十分。
例:腸腰筋膿瘍(どちらの?)、椎骨炎(どこの?)、脳膿瘍(どの部分の?)
腎盂腎炎(どちらの?)という感じです。
これは、「言語による限界」「概念の存在の有無」「文化的背景」などが原因ではないか、と感じています。
数年前に、日本人としてはじめて米国の感染症科専門医資格を取得され、沖縄県立中部病院で、感染症診療を確立された喜舎場朝和先生のご講演を拝聴したときに、私のなかでも、それまで「言語化できずにいた疑問」が、明確になりました。
在米時代には、「無意識レベル」で、rule out, most likely, less likely, unlikelyなどの用語を、自分の診断に合わせて認識していたことを思い出しました。
日本の現場で、患者の診断、臨床状態を把握する際に、「障壁」となっていると私が強く感じる面があります。
診断名が、「いつまでたっても、xxx疑い」に終始すること
あるいは、「xxxxを指摘されて・・・」という文章の意味、
「xxxxは否定的」
というように、「診断」の確実性を示すことばが非常に少ない現実です。
診断は、
確定診断 definate
推測診断 probable, or presumed
xx診断の可能性 possible (50%以上の可能性)
xx診断の可能性は低い less likely
xx診断の可能性はきわめて低い、または、ほぼない unlikely
xx診断は、除外された ruled out
と英語で診断名を記載する場合、上記のような「可能性のGrade評価」が必須です。
一方、日本語で記載されているカルテ記載を見ると、
確定しているのか、推測なのか、鑑別診断のひとつなのか、不明瞭の場合が多いです。
保険病名として、「xxx疑い」と記載せざるを得ない社会事情はありますが、教育面、臨床判断をトレーニングする場合、臨床試験を行う場合などに弊害があります。
日本語では、
確定
疑い
否定的
除外
の4通りが主ですが、「疑い」と「否定」にGradeが存在しないため、可能性が伝わってきません。したがって、カルテを見ても、その状態がわかりにくい、という状況である感じがします。
また、カルテ中の「xxxを指摘され」という表現も非常にあいまいです。
「確定診断がついているのか」「推測診断なのか」「保険病名だけなのか」「異常所見がみつかっただけなのか」「鑑別診断として上がっただけなのか」「患者さんが訴えているだけなのか」意味があいまいで、伝わりません。
学生、研修医の方は、「診断の可能性のGrade評価」を行い、それが伝わる表現を心がけると、記載やプレゼンテーションはかなりシャープになります。意識してみてください。
ちなみに、私が指導する場合、「疑い」「否定」は使用しないようにお願いしています。
上記のような国内で見られる共通の問題をクリアすることで、患者をより正確に精緻に把握し、質の高い診療を提供できるようにできれば、と考えています。そのためにも、学生時代から精緻な患者の把握とプレゼン、記載ができる教育体制が必須と考えています。