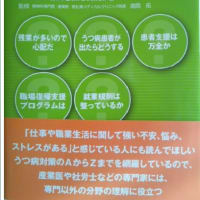小職の見解です。諸々のエビデンスからの推論です。
◎「うつ病」の始まりは、簡単に、素人的に、申し上げれば「眠れない」です。
それで「眠れなくなる」原因としては、繰り返しますが、
1. 長時間労働
2. 異動・転勤
3. 昇進・昇格
4. ハラスメント
に、集約されるでしょう。
そして、いろいろな事例をみていますと上記4つのうち2つが重なると、
「うつ病」を発症する確率が高くなるように感じています。
◎人間、基本的には「強い」生き物と思っています。数百万年間生存してきたのですからですから。
ですから、原因が1つだけなら、結構耐えられます。
しかし、これが私生活の理由(例えば、身内の不幸)なども含めて2つになると、耐えられなくなるようです。
多い事例ですが、長時間労働とハラスメントのように。
◎もっとも、「ストレス脆弱性理論」というのがありまして、
簡単に云えば、ストレスに強い体質であれば強いストレスにも耐えられるが、
ストレスに弱い体質だと、弱いストレスでも耐えられないという理論です。
これが、厚労省のメンタルヘルス諸対策の基本的理論にもなっています。
◎「ストレス-脆弱性理論」(厚労省資料;精神障害の労災認定の考え方について、より)
環境由来のストレスと個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まるという考え方であり、
ストレスが非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神障害が起こるし、
逆に脆弱性が大きければ、ストレスが小さくても破綻が生ずるとする考え方である。
この場合のストレス強度は、環境由来のストレスを、
多くの人々が一般的にどう受け止めるかという客観的な評価に基づくものによる。
対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷(ストレス)と、個体側の反応性、脆弱性との関係で
精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし、
逆に脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス-脆弱性理論」に依拠している。
次回以降、この睡眠について少し考察してみたいと考えます。