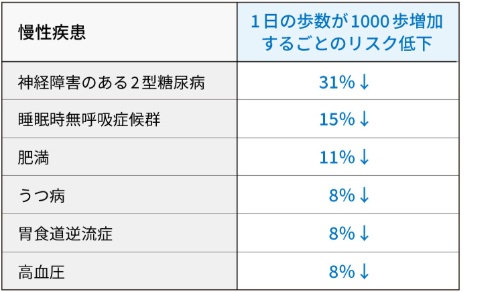一方で、障がいのある労働者を、法定基準以上に雇用し、
その持てる能力を十二分に引き出している企業がたくさんあることを理解してください。
法律で義務の障害者雇用 勧告後も改善見られない企業5社を公表
2023年3月29日NHK
法律で義務づけられる障害者の雇用が十分でなく、国が勧告したにもかかわらず改善が見られないとして、
厚生労働省は企業5社を公表しました。
障害者雇用促進法では、企業に対し一定以上の割合で障害者を雇用するよう義務づけていて、現在は2.3%以上となっています。
障害者の雇用が十分でない企業に対し、厚生労働省は達成に向けた計画の作成を求め、適切に実施するよう勧告しますが、
従わない場合、企業名を公表できるとしていて29日に法律に基づいて5社を公表しました。
このうち、
▽東京の不動産仲介会社「タウンハウジング」と、
▽東京のビルメンテナンス会社「シーレックス」
▽広島の雑貨販売会社「サンポークリエイト」の3社は、
おととし12月に同じ理由で公表されていましたが、その後も改善が見られないとして「再公表」となりました。
ほかに公表された2社は
▽東京のスポーツ関連商品販売「ボードライダーズジャパン」
▽横浜の宝飾品販売「ベリテ」でした。
各社は「真摯(しんし)に受け止め障害者雇用の改善に向けて取り組みたい」などとしています。
厚生労働省によりますと、障害者雇用率を達成している企業の割合は、去年6月時点で48.3%と半数以下にとどまっています。
障害者雇用率は3年後には2.7%に引き上げられることになっていて、厚生労働省は引き続き改善指導に取り組むとともに、
企業への助成金を拡充するなどして対応を促すことにしています。
公表された企業5社のコメント
企業名が公表された5社は次のようにコメントしています。
▽タウンハウジングは「再公表となり、障害者雇用が課題だと捉えている。
障害者雇用のための事業所を設置するなど強化はしているが、真摯に受け止めてさらなる改善に向けて取り組みたい」としています。
▽シーレックスは「公表されたことを真摯に受け止めて改善に向けて努力していきたい」としています。
▽サンポークリエイトは「4人の障害者を雇用できたが雇用率達成までに至らず、現在、募集をしている。
ただ、採用には結びつかず、難航している。引き続き、障害者雇用に取り組んでいきたい」としています。
▽ボードライダーズジャパンは「厚生労働省からの指導を真摯に受け止め、状況の改善に向けて取り組んでおります」としています。
▽ベリテは「コロナ禍の影響もあり、思うように障害者雇用を進めることが難しかった。
公表されたことを真摯に受け止め継続して取り組みを進めていきたい」としています。
企業の障害者雇用の支援にあたる障害者就業・生活支援センターWEL’S TOKYOの堀江美里センター長は、
障害者雇用に消極的と見られる企業があることについて、新たな対策が必要だとして、
「障害者雇用に力を入れている企業の障害者の定着率を公表していくことや、
障害者の側からも意見をもらい会社を評価してもらうような制度を進めてもいいのではないか」と指摘しています。
また、企業では障害者にどんな業務に取り組んでもらうかが課題になっているとして
「『障害者はこうした仕事しかできないだろう』という考えで、最初から決まった事務作業などにあてるのには限界がある。
個人の能力に合わせて『これはできるのでは』と考え本来業務に試験的に取り組んでもらうなどして、
できる仕事を増やしていくことが必要だ」と話していました。
◎関連資料(厚労省HPより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
事業主の方へ
目次
1.障害者雇用率制度
2.障害者雇用納付金制度
3.雇用の分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務
4.障害者職業生活相談員の選任
5.障害者雇用に関する届出
6.障害者の虐待防止
事業主に望まれること
1.障害者が能力や適性が発揮でき、生きがいを持って働けるような職場作り
2.障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度
事業主が利用できる支援策
1.障害者雇用に関する相談・支援
2.障害種別の支援策
3.精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の開催
4.障害者の在宅就業支援
5.障害者雇用に関する助成金
6.障害者雇用に係る税制の優遇措置
7.好事例集