春日部市立図書館の新着棚にあった本で、読まないだろうと思いながら手を出した本です。新聞の広告・書評に覚えがなく、第一、<鳥の仏教>というタイトルに内容が全く想像できなかったのです。
<彼岸>を少し覗いたせいか、いやそうではなく、ただの老化か、仏教、仏法の世界、あの世のことを、知りたくなることがあるのです。ネパールやインドの仏跡を訪ねたいと思うのも同じです。同じ自然、同じ空気に触れたいと思うことがあります。
編著者の<まえがき>は、こう解説しています。
<ブッダが亡くなってから数百年たって、インドで大乗仏教運動が起こり、その中でたくさんの経典が編まれました。そして、すぐれた経典の多くは「大蔵経」に収められて長い時間をかけ中国語に翻訳されて、日本人のもとにも届けられました(中沢)>
<鳥の仏教>のタイトルで日本語訳された<経典>は、<チベット人の仏教徒の手によって、大乗仏教の経典を模して書かれ、しかも近代17~19世紀あたりに書かれた<学問的価値の低い>偽作的な経典。いや、農民や牧畜民である一般の仏教信者に向けて書かれた、いたって大衆的な性格を持つ書物であり、一種の民間文学と見ることもできる(中沢)>のです。
この本が、知られるようになったのは、1903年(明治36年)にインドで復刻出版されてからで、チベット語の本は、その後、1953年にフランス語に訳され、1955年に英語版が出されたようです。
釈迦の教えを、わかりやすく書いています。教えを鳥たちの世界において説くのです。観音菩薩がカッコウとなって、鳥たちにダルマ(釈迦の言葉)を説くお話です。インコやクジャク、カラスなど19種の鳥が出てきて、それぞれの鳴き声でダルマを理解して発表していくストーリーです。
お話としては、やさしく、子ども達にも読め、わかる<ほとけの教え本>です。
大人の私には、ほんとうに理解できたのかと問われれば、返事にためらいます。仏教経典です。そう簡単には、理解できません。悟れません。
そういう理屈をいうことなく読める、接することのできる庶民向きの経典です。
きれいな作りの、小さな本です。ときどき、手にとると、日々胸にわだかまる諸々のことを忘れることができるかもしれません。
【おまけ】
* なぜ、かっこうが、鳥の中で一番<えらい>のか。なぜ、かっこうが、観音菩薩の役割りを与えられていたのか。
* カッコウを神聖な鳥とする考えが、チベットの人の間に古来からあった、と、編訳者の中沢さんは解説しています。古代のチベット人は「ポン」という宗教を持っており、その教えの中で、すでにカッコウ(トルコ石のように青い鳥)は重要な聖鳥と考えられていたようです。
* 日本には、仏法僧(ブッポウソウ)という、<いわくありげな>名の鳥がいることを思い出しました。ブッポウソウの学名をもつ鳥は、青い美しい鳥のようです。ところが、この鳥が、<ブッポウソウ>と鳴くから、ブッポウソウと呼ばれるということになっていたのです。ところが、この鳥は、<ギャア、ギャア>としか鳴かない。<ブッポウソウ>と鳴くのは、コノハズクだとわかったのです。昭和の初めのことのようです。
* 今では、ネット上でも、<姿のブッポウソウ>と<声のブッポウソウ>併記されています。
* わが家でも、5月ごろになると、カッコウの鳴くのが聞こえます。近くで鳴いています。夏近しを感ずる、とてもやすらぐ鳴き声です。ただ、そんなに美しい青色の鳥だとは思いません。
* 日本では、平安時代から、美しい青い鳥、ブッポウソウ(仏法僧)が霊鳥と思われてきたらしい。ただし、ブッポウソウと鳴くからのようですが、長い歴史の中で、仏教伝来中に、どこかで、こんがらがったのかもしれません。













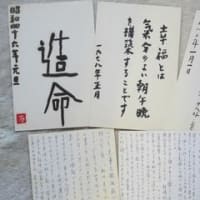
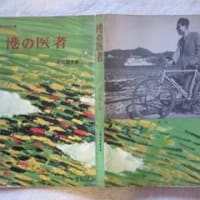
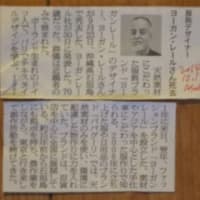







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます