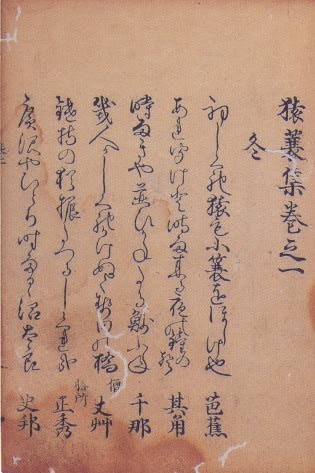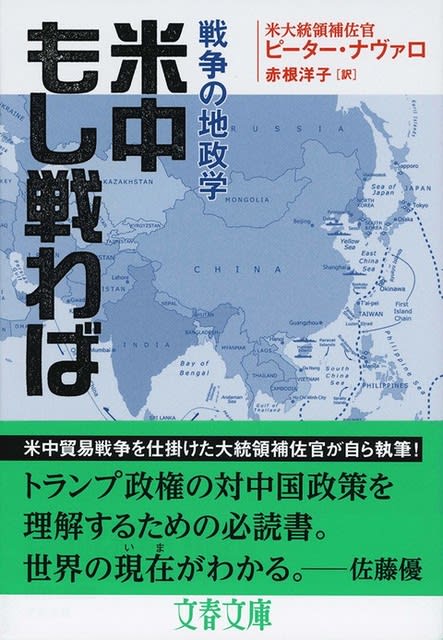この漱石が、東大で英語教師をしていたころ、
ある学生が「I love you.」という小説の一節を「我、汝を愛す。」と訳したのを受けて、
「日本人ならそういう言い方はせんだろう。月がとても綺麗ですね、とでも訳しておくところだ。」
と述べた。
……という通説がけっこうな規模で行きわたっているが、じつははっきりした典拠が見当たらず、後世の創作だろうと言われている。漱石じしんの随筆の中に見られないのは間違いないし、数多い弟子たちの遺した著作のうちにもそういった記述はない。
そもそも、初めのうちは、「月が青いですね。」であったのが、のちに「綺麗ですね」「きれいですね」に転化したとか。そこからも、文献として明確な出典がないことがわかる。
この件についてはネットの上にもたくさんの考証があふれているのだが、ぼくなりに整理したところ、
この逸話は昭和50年代にとつぜん現れた。そのときは「……青いですね。」であった。
1955(昭和30)年に「月がとっても青いから、遠回りして帰ろ」という歌詞をもつ歌が流行った。
1975(昭和50)年から翌年にかけて、NHKで『新 坊ちゃん』というドラマが放映され、その中にこの逸話が(脚本家の創作として)使われていた可能性がある。
とのことだ。あるいはこれが信憑性が高いか……とも思ったのだけれど、「そのドラマをみた。間違いなくそのエピソードがあった。」という証言は、ざっと探した限りでは見つからない。
書かれたものとして確認できるのは、1976年から連載が始まり、1979年に出版された豊田有恒のエッセイ、および1978年に行われた対談の中でのつかこうへいの発言とのこと。片やSF作家、片や劇作家ということで、「教壇から怒鳴りつけた。」などと、派手な脚色が加えられたりして、より人口に膾炙しやすくなっていた。
ともあれ、活字になった文章としては、今のところこれ以上遡ることは難しく、いずれかがネタ元になったと思われる。それがすっかり定着して、また新たにドラマやなにかで再利用され、ツイッターなどで拡散されて、今日に至っている。どうもそういうことらしい。
だとしたら、豊田さんにせよ、つかさんにせよ、妙な影響を及ぼしちゃったもんだな……。
この逸話が人気を集めるのはよくわかる。漱石という人の人柄と才気をよく表している(気がする)し、また、日本人(日本語)と欧米人(英語)との気質の相違を端的に言い当ててもいる。都市伝説と一蹴するには惜しいエピソードではあるが、確かな出所が見つからぬかぎり、誤伝は誤伝だ。
なお、漱石のことは脇に置いて、そもそも「月が綺麗だねェ……」という言い回しをもって愛情表現に当てる、といった感性が日本語の伝統において那辺に由来するのか……歌舞伎かなにかに先例があるのか……という考証もまた成り立つだろうし、それはそれで面白そうではある。でも時間がないからそこまではやらない。
☆☆☆☆
いっぽう、こんな通説もよく聞く。
「二葉亭四迷は、I love you.を 死んでもいいわ。と訳した。」
漱石の時は「月が青いね。」だった「I love you.」が、こちらでは「死んでもいいわ。」になっちゃうわけで、実話だったらさぞ面白かったんだけど、残念ながらやはり誤伝だ。
しかし、漱石の事例よりは、はっきりしたことが判明している。
というのは、風聞ではなく、翻訳のなかの文章だから。
ロシア文学者にして実作者。代表作は『浮雲』。その訳業と卓越した文学観によって漱石と共に近代日本文学の創始者のひとりとなった二葉亭だけど、その翻訳の一つにツルゲーネフの『片恋』があった。
ツルゲーネフの邦訳といえば『はつ恋』が有名で、二葉亭の訳では『あひゞき』『めぐりあひ』が知られているが、ここは『片恋』である。原題はヒロインの名前『アーシャ』。
その第16章から。
……私は何も彼も忘れて了って、握ってゐた手を引寄せると、手は素直に引寄せられる、それに随れて身躰も寄添ふ、シヨールは肩を滑落ちて、首はそつと私の胸元へ、炎えるばかりに熱くなつた唇の先へ來る……
「死んでも可いわ…」とアーシヤは云つたが、聞取れるか聞取れぬ程の小聲であつた。
私はあはやアーシヤを抱うとしたが…ふとガギンの事を憶出すと……
当時としてはなかなかの濡れ場……といっていいかと思うが、このくだり、英語版では以下のようになっているそうな。
……I forgot everything, I drew her to me, her hand yielded unresistingly, her whole body followed her hand, the shawl fell from her shoulders, and her head lay softly on my breast, lay under my burning lips.……
“Yours”…… she murmured, hardly above a breath.
My arms were slipping round her waist. But suddenly the thought of Gagin flashed like lightning before me.……
それで、この、「“Yours”」が「死んでも可いわ…」になっている。
ちなみに原文のロシア語では、「Ваша……」で、やはり「あなたの……」の意とのこと。
だから、「二葉亭四迷は“I love you.”を 死んでもいいわ、と訳した。」という説は誤りということになる。そういうことにはなるのだが、しかし真相を掠めてはいる。「ニアミス」という感じだろうか。しかし思えば、「“Yours”」を「死んでもいいわ」と訳すのだって相当に大胆であり、じゅうぶんに語り継がれるに値するだろう。
ちなみに後年、ロシア文学者の米川正夫氏は、この作品を改訳したおり、やはりタイトル『アーシャ』を『片恋』と訳して偉大な先達に敬意を表した。ただしこの「Ваша……」については、「(私は)あなたのものよ……」と原語に近い訳文にかえた。
ただ、どうなんだろう。ぼくは読んでないからわからないけど、ここだけ見れば「あなたの意のままに」とか「仰るとおりに致しますわ」くらいの意味でも通るんじゃないか……という気がした。「あなたのものよ。」だって、「死んでもいいわ。」ほどじゃないけど、なかなかに思いきった訳だ。
それにつけても二葉亭四迷、本名・長谷川辰之助。漱石や鷗外と並ぶ創始者が、こんな戯作者めいたペンネームを付けたところに近代日本文学の、ひいては近代日本文化の、ひいては近代日本そのものの悲劇と喜劇が綯い交ぜになっている。
1909年(明治42年)5月、45歳で逝去。
関川夏央×谷口ジローの名作マンガ『坊ちゃんの時代』の第二部・「秋の舞姫」は、その葬儀のもようから幕を開ける。
☆☆☆☆
ところで、「私を月まで連れてって」という曲がある。「フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン」。スタンダード中のスタンダード・ナンバーだ。宇多田ヒカルの素敵なカヴァーもあるし、竹宮惠子に同タイトルのSFコメディー漫画もあった。
1995年から翌96年にかけて放送されたテレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』のエンディングテーマとしても知られる。
全26話すべて「フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン」がエンディングテーマだったんだけど、アレンジがぜんぶ異なる、という趣向が凝らされていた。大人っぽいのから可愛らしいのまで、アップテンポからスローバラードまで、インストゥルメンタルから声優さんによる日本語歌唱まで、26とおりの「私を月まで連れてって」が流れたわけだ。
ぼくはずっと、音楽担当の鷺巣詩郎によるアレンジだとばかり思っていたが、調べたところ、そうではなかったらしい。
いずれにしても、『新世紀エヴァンゲリオン』テレビシリーズの謎めいた魅力の一端を、この週替わりのエンディングテーマが担っていたのは確かだと思う。
歌詞はこうだ。
☆☆☆☆
Fly me to the moon
Let me play among the stars
Let me see what spring is like
On a Jupiter and Mars
私を月まで連れてって
星々の海で遊ばせて
見せて欲しいの 春がどんなものなのか
木星と火星に訪れる春が
In other words: hold my hand
In other words: darling(baby),kiss me
わかるでしょ? 手を握って
わかるわね? ね キスして
Fill my heart with song
And let me sing for ever more
You are all I long for
All I worship and adore
わたしの心を歌で満たして
歌わせて いつまでもずっと
貴方は私が待ち望んでいたすべて
憧れと思慕のすべて
In other words: please, be true
In other words: I love you
わかるでしょ? 本気になって
わかるでしょ 好きなの あなたが
☆☆☆☆
繰り返される「In other words」は、「言い換えれば」だ。「つまり」とか「要するに」でもいいかと思う。
「わかるでしょ?」と訳してみたんだけど、どうだろう。睦言としては、こんなところだと思うんだけど。
「I love you.」を「In other words」でいえば、(残念ながら誤伝だけれど)「月が青いね……。」にも「死んでもいいわ。」にもなる。さらには「私を月まで連れてって」にもなる。ほかにも無限の意味になりうるだろう。言葉というのは底知れない。