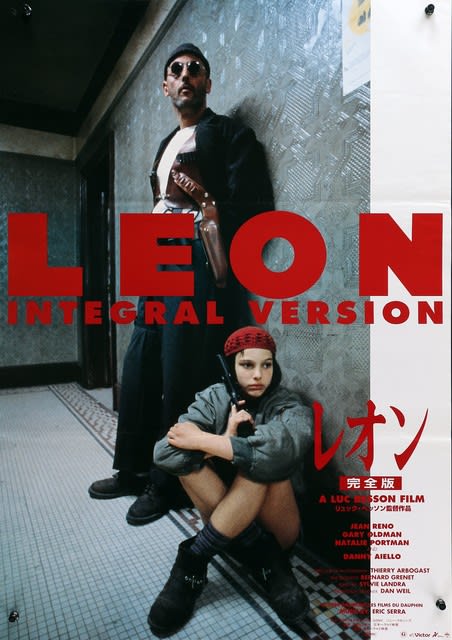きのうの日曜に当ブログの過去記事を読み返してたら、今と比べると文章はカタいが、意外と悪くなかった。最近のぼくがモヤモヤと考えていることを、ソリッドにまとめた記事があったりもし、勉強になった。いや勉強になってどうする。でも「えっオレ昔のほうがアタマよかったんかい?」とか思ったのは確かだ。ニーチェの話なんてだんぜん昔のほうがいい。今ニーチェについて書いてもあんな綺麗にまとまらない。
ただ、「物語」についての考えは今のほうが深くなっている(と思う)。広くなってもいるんじゃないかと思う。総じて、「思考が柔らかくなっているのだ。」と、前向きにとらえることにした。あと、たぶんそれとも関連してるが、じぶんより年下の論客、はっきり名をいえば東浩紀さんと宇野常寛さん(の著作)に対する評価が激変した。ぐーんと上がったのである。
これまで東さんや宇野さんの書かれたものを正面切って取り上げたことはないけれど、たとえば2016年6月25日に再掲した(初出は2013年6月)「佐藤優『功利主義者の読書術』/情報の集積体としての小説」のなかでぼくは、
「佐藤さんは根っこに≪神学≫をもっているからけしてポストモダニストにはならない。だから軸足がぶれることがなく、東浩紀のような人よりぼくにとっては重要だ。」みたいなイヤミな書き方をしてる。そして、ハーバマスの「公共圏」というアイデアを(佐藤さんからの孫引きの形で)紹介して、「ネットが公共圏になれば。」などと、まるで朝日新聞の社説レベルの、お気楽なことを述べている。
しかるに東浩紀さんの『一般意思2.0』(講談社文庫)を読むと、そんな発想はまるでもう小児の寝言であって、東さんのような人は遥かに高度なことを十数年も前に考えておられるのであった。この本が文庫になったのは2015年だから、遅くとも3年まえには読んでおかねばならなかったのだ。いやあ反省反省。
宇野さんの『ゼロ年代の想像力』(ハヤカワ文庫)『リトル・ピープルの時代』(幻冬舎文庫)も、やや状況を単純化しすぎてるかなとも思うけど、やっぱり面白くてタメになった。「後生畏るべし」という金言を、あらためて肝に銘じねばなるまい。
さて。「教養って何?」というカテゴリが、2017年12月1日の「05 政治の話は難しい。」で止まっているのだけれど、ここで完結ってわけではない。「もうちょっとだけ続くんじゃ。」という気分でいる。このセリフ、まんが好きの人でなきゃわからないかな? つまりまあ、成り行きしだいではまだ結構つづくかも、ということです。
文藝、歴史、科学、経済、政治ときて今回は「精神分析」なんだけれども、これは正直、「あまり素人が踏み込まんほうがよろしい」とそのむかし筒井康隆さんが言っておられた分野なので、挙げる本は一冊のみといたします。ただ、その前にちょっと雑談を。
大学に入ったとき、級友のひとりが「心理学をやる。」というので何の気なしに「なんで?」と訊いたら、「それで人間心理を学んで、対人関係に生かす。」という返事だったから、「あー、でもここの大学は実験心理学専門で、ネズミに迷路を走らせてどうの、という世界だから、それはあまり期待できんと思うよ。」と答えた。それは実際その通りだったんだけど、それでがっかりしたのかどうか、その人は途中で退学してしまった。
あのとき、「それはつまり人間の心についての洞察力を身につけたいってことだよね? それだったら何よりもまず、良質の純文学を読んだらいいよ。」と付け加えることができなかったのが、30数年経った今でもまだ心残りなのである。文学部なんだからそんなこと言わずもがなと思ったんだけど、なかなかそうでもないぞってことが後になってわかった。そう。優れた純文学は、かなり精度の高い「人間心理の研究記録」でもある。十分に「実用書」たりうるのだ。で、このことはあまりみんなに意識されていない。機会さえあれば繰り返し喧伝したいところだ。
こういうのはかえって現代小説より古いもののほうがよくて、漱石の『三四郎』なんて、「ここんとこ、このキャラはどういう気持ちでいるのかな?」と、学校の国語の授業みたいなつもりで気を張って読めば、それだけで相当なトレーニングになるはずだ。
ただ、そうやって身の周りにいる他人のこころに気を配るのも大切なことではあるけれど、心理学、というか、精神分析を学ぶのは、何よりもまず「自分を知る」ためじゃないかとぼくなんか思う。
自分語りはイヤなのだが、話が話だから自分のことを語らなければしょうがない。小学生の頃ぼくは、「ノストラダムスの大予言」にハマった。「1999年7の月、空から恐怖の大王が降ってくる」というアレである。
今ならば、これは聖書のなかの「黙示録」の当世風のバリエだよなってわかるんだけど、当時はなにしろガキなんで、かなり狼狽えた。中学、高校に上るとさすがに不安は薄れたが、「東西冷戦」がまだ続いていた時代でもあり、「ひょっとしたらアタマの上にミサイルが」みたいな気分はどこかにずっと持ち越していた。それは今日においてもまだ、北朝鮮などへの懸念となって残っている(仮に米朝首脳会談がうまくいっても、それでとたんにすっきりするってもんでもない)。
フクシマ以降は「原発」のほうにシフトしているけれど、大江健三郎さんも昔は「核ミサイル」「核ミサイル」と頻繁に言っておられたし、もろ作品の題材に取り上げたこともある。たぶんぼくと似た体質なのであろうし、逆にそれゆえぼくが大江文学に惹かれたところもあるんだろうけど、大江さんはさておき、ぼく自身についていうならば、この種の「根源的な不安」はぜんぜん政治的ではなくて、ひとえに心理的なものだったのである。
それが自分でわかったのは、ずいぶんと後になってからだ。
さらに自分語りになってしまうが、うちの母親はぼくを産んだ直後と、ぼくが3歳になるやならずの時と、2度にわたって長期入院した。すなわちぼくは、生後間もなく、さらに物心つくかつかぬかのころ、2度にわたって母親から引き離されたわけだ。まあ、ふつうに考えてなかなかにクリティカルな生育環境といえよう。これにより、「自分を守ってくれるひとが傍にいない」「いつ自分の足元が崩れ落ちるかわからない」といった不安が根付き、小学生の頃から、おそらく今に至るまで、ずっと持ち越してるわけだ。
てるわけだ、などと、あっさり書いているけれど、自らのこういった本質的な資質というのは客観視ができないゆえに自己分析が難しく、ぼくにしても、素人なりに精神分析の本を読みかじらなければ、たぶん気づかなかったと思う。
気づかなかったらどうなるか、というと、その「不安」に突き動かされて、いらざる「欲望」が生じ、たとえば怪しげなカルトに嵌ったりなどして、人生が無駄にややこしくなる可能性があるのだ。そういうリスクを減殺してくれるのだから、やはり本代を惜しんではいけない。
以上、「精神分析を学ぶのは、何よりもまず自分を知るためだ」とぼくが考える理由を述べました。
では最後に本の紹介。2018年5月22日の「物語/反物語をめぐる50冊 2018.05 アップデート版」でも再三再四お名前をだした河合隼雄さんの『こころの最終講義』(新潮文庫)。『こころの処方箋』のほうがより平易で、ロングセラーになってるけど、今回はこちらを推したい。講演集だが、河合さんらしい柔らかな語り口でなされた講義録といったほうがよい。このたびの記事で述べたことがらのほとんどを含み、さらなる深みへと読み手を導く好著だと思う。
ただ、「物語」についての考えは今のほうが深くなっている(と思う)。広くなってもいるんじゃないかと思う。総じて、「思考が柔らかくなっているのだ。」と、前向きにとらえることにした。あと、たぶんそれとも関連してるが、じぶんより年下の論客、はっきり名をいえば東浩紀さんと宇野常寛さん(の著作)に対する評価が激変した。ぐーんと上がったのである。
これまで東さんや宇野さんの書かれたものを正面切って取り上げたことはないけれど、たとえば2016年6月25日に再掲した(初出は2013年6月)「佐藤優『功利主義者の読書術』/情報の集積体としての小説」のなかでぼくは、
「佐藤さんは根っこに≪神学≫をもっているからけしてポストモダニストにはならない。だから軸足がぶれることがなく、東浩紀のような人よりぼくにとっては重要だ。」みたいなイヤミな書き方をしてる。そして、ハーバマスの「公共圏」というアイデアを(佐藤さんからの孫引きの形で)紹介して、「ネットが公共圏になれば。」などと、まるで朝日新聞の社説レベルの、お気楽なことを述べている。
しかるに東浩紀さんの『一般意思2.0』(講談社文庫)を読むと、そんな発想はまるでもう小児の寝言であって、東さんのような人は遥かに高度なことを十数年も前に考えておられるのであった。この本が文庫になったのは2015年だから、遅くとも3年まえには読んでおかねばならなかったのだ。いやあ反省反省。
宇野さんの『ゼロ年代の想像力』(ハヤカワ文庫)『リトル・ピープルの時代』(幻冬舎文庫)も、やや状況を単純化しすぎてるかなとも思うけど、やっぱり面白くてタメになった。「後生畏るべし」という金言を、あらためて肝に銘じねばなるまい。
さて。「教養って何?」というカテゴリが、2017年12月1日の「05 政治の話は難しい。」で止まっているのだけれど、ここで完結ってわけではない。「もうちょっとだけ続くんじゃ。」という気分でいる。このセリフ、まんが好きの人でなきゃわからないかな? つまりまあ、成り行きしだいではまだ結構つづくかも、ということです。
文藝、歴史、科学、経済、政治ときて今回は「精神分析」なんだけれども、これは正直、「あまり素人が踏み込まんほうがよろしい」とそのむかし筒井康隆さんが言っておられた分野なので、挙げる本は一冊のみといたします。ただ、その前にちょっと雑談を。
大学に入ったとき、級友のひとりが「心理学をやる。」というので何の気なしに「なんで?」と訊いたら、「それで人間心理を学んで、対人関係に生かす。」という返事だったから、「あー、でもここの大学は実験心理学専門で、ネズミに迷路を走らせてどうの、という世界だから、それはあまり期待できんと思うよ。」と答えた。それは実際その通りだったんだけど、それでがっかりしたのかどうか、その人は途中で退学してしまった。
あのとき、「それはつまり人間の心についての洞察力を身につけたいってことだよね? それだったら何よりもまず、良質の純文学を読んだらいいよ。」と付け加えることができなかったのが、30数年経った今でもまだ心残りなのである。文学部なんだからそんなこと言わずもがなと思ったんだけど、なかなかそうでもないぞってことが後になってわかった。そう。優れた純文学は、かなり精度の高い「人間心理の研究記録」でもある。十分に「実用書」たりうるのだ。で、このことはあまりみんなに意識されていない。機会さえあれば繰り返し喧伝したいところだ。
こういうのはかえって現代小説より古いもののほうがよくて、漱石の『三四郎』なんて、「ここんとこ、このキャラはどういう気持ちでいるのかな?」と、学校の国語の授業みたいなつもりで気を張って読めば、それだけで相当なトレーニングになるはずだ。
ただ、そうやって身の周りにいる他人のこころに気を配るのも大切なことではあるけれど、心理学、というか、精神分析を学ぶのは、何よりもまず「自分を知る」ためじゃないかとぼくなんか思う。
自分語りはイヤなのだが、話が話だから自分のことを語らなければしょうがない。小学生の頃ぼくは、「ノストラダムスの大予言」にハマった。「1999年7の月、空から恐怖の大王が降ってくる」というアレである。
今ならば、これは聖書のなかの「黙示録」の当世風のバリエだよなってわかるんだけど、当時はなにしろガキなんで、かなり狼狽えた。中学、高校に上るとさすがに不安は薄れたが、「東西冷戦」がまだ続いていた時代でもあり、「ひょっとしたらアタマの上にミサイルが」みたいな気分はどこかにずっと持ち越していた。それは今日においてもまだ、北朝鮮などへの懸念となって残っている(仮に米朝首脳会談がうまくいっても、それでとたんにすっきりするってもんでもない)。
フクシマ以降は「原発」のほうにシフトしているけれど、大江健三郎さんも昔は「核ミサイル」「核ミサイル」と頻繁に言っておられたし、もろ作品の題材に取り上げたこともある。たぶんぼくと似た体質なのであろうし、逆にそれゆえぼくが大江文学に惹かれたところもあるんだろうけど、大江さんはさておき、ぼく自身についていうならば、この種の「根源的な不安」はぜんぜん政治的ではなくて、ひとえに心理的なものだったのである。
それが自分でわかったのは、ずいぶんと後になってからだ。
さらに自分語りになってしまうが、うちの母親はぼくを産んだ直後と、ぼくが3歳になるやならずの時と、2度にわたって長期入院した。すなわちぼくは、生後間もなく、さらに物心つくかつかぬかのころ、2度にわたって母親から引き離されたわけだ。まあ、ふつうに考えてなかなかにクリティカルな生育環境といえよう。これにより、「自分を守ってくれるひとが傍にいない」「いつ自分の足元が崩れ落ちるかわからない」といった不安が根付き、小学生の頃から、おそらく今に至るまで、ずっと持ち越してるわけだ。
てるわけだ、などと、あっさり書いているけれど、自らのこういった本質的な資質というのは客観視ができないゆえに自己分析が難しく、ぼくにしても、素人なりに精神分析の本を読みかじらなければ、たぶん気づかなかったと思う。
気づかなかったらどうなるか、というと、その「不安」に突き動かされて、いらざる「欲望」が生じ、たとえば怪しげなカルトに嵌ったりなどして、人生が無駄にややこしくなる可能性があるのだ。そういうリスクを減殺してくれるのだから、やはり本代を惜しんではいけない。
以上、「精神分析を学ぶのは、何よりもまず自分を知るためだ」とぼくが考える理由を述べました。
では最後に本の紹介。2018年5月22日の「物語/反物語をめぐる50冊 2018.05 アップデート版」でも再三再四お名前をだした河合隼雄さんの『こころの最終講義』(新潮文庫)。『こころの処方箋』のほうがより平易で、ロングセラーになってるけど、今回はこちらを推したい。講演集だが、河合さんらしい柔らかな語り口でなされた講義録といったほうがよい。このたびの記事で述べたことがらのほとんどを含み、さらなる深みへと読み手を導く好著だと思う。