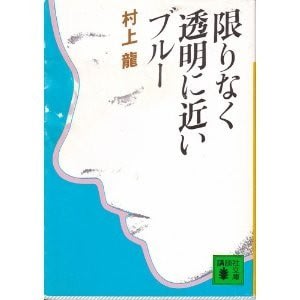「『ゼロ年代の想像力』(ハヤカワ文庫)のなかで、目につく「純文学作家」の名前は中上健次のみ。しかも、「(映画監督の)青山真治は、とても優秀なのだが、いつまでも中上健次にこだわってるのが玉に瑕だ」みたいな言い方で出てくるのだ。とほほ。」
と、前回の記事で書いたのだけれど、あらためて確認したら、これは正確ではなかった。
円城塔『Self-Reference ENGINE』、諏訪哲史『アサッテの人』、川上未映子『わたくし率イン歯―、または世界』、岡田利規『わたしたちに許された特別な時間の終り』。
この4作が、「2007年はある種のポストモダン文学のリバイバル・ブームが起きた年として記憶されるだろう。」との前置きを附して、リストアップされている。
諏訪哲史『アサッテの人』は芥川賞受賞作である。岡田さんの『わたしたちに許された特別な時間の終り』は芥川賞の候補にすらならなかったが(なぜだろう)、大江健三郎さんが単独で選考を務める「大江健三郎賞」に選ばれ、作品そのものの面白さもあって話題になったし映画化もされた。円城さんと川上さんは、この作品では選ばれなかったけれど、のちに芥川賞を取った。
こういう実力派たちに目をつけてるんだから、宇野さんはけっして、純文学をおろそかにしてるわけではない。
その前の段には、黒川創の名前もある。
そもそもこの本の序盤では、W村上(春樹&龍)および吉本ばななと、定番のビッグネームをちゃんと抑えてあったのだ。後のほうでは、綿矢りさ、金原ひとみの名も見える。
ほかに辻仁成、佐藤友哉、津村記久子らの名もある。なかなかどうして、「中上健次のみ」どころじゃない。くまなく目配りしてるのだ。
ただ、W村上とばななについては軽くコメントがなされているが、綿矢、金原、そして辻、佐藤、津村ら各氏については、ほかとのカラミで名前を挙げてるだけである。
円城、諏訪、川上、岡田、それに黒川さんを加えた5人については、本文ではなく、ポイントの小さい活字で組まれた「註」のなかでふれられてるんだけど、宇野さんはどうやら、この5人に対しては、一定の評価を与えているようだ。ほかの作家には、わりと冷たい。
中上健次は論外として(とほほ……)、龍もばななも、もはや「現代」をきちんと捉えてはいない。ただし春樹さんだけは別格。ほかの作家たちは、どうもいまいち。しかしその中で、円城塔と諏訪哲史と川上未映子と岡田利規と黒川創は健闘している。そのように、宇野常寛は評価を下している(とぼくには読める)。
念のためいうが、この文庫がでたのは2011年で、その親本となる単行本は2008年刊、宇野さんがこの論考を書いたのはたぶん2007年の終り頃だ。そのご、純文学シーンもかわっているし、宇野さんの考えも大きくかわっているだろう。ぼくがここで、10年も前のハナシをしてるってことは、アタマに留めて頂きたい。
さて、「2007年はある種のポストモダン文学のリバイバル・ブームが起きた年として記憶され」ているんだろうか。世間は純文学になんか興味ないので、たぶん誰もそんなもん記憶してないと思うが、とにもかくにも宇野さんが、『Self-Reference ENGINE』『アサッテの人』『わたくし率イン歯―、または世界』『わたしたちに許された特別な時間の終り』の4作を、「ある種のポストモダン文学」として捉えてるのは間違いない。
はい。ポストモダン文学って何ですか。
答は風に吹かれている。じゃなくて、はっきりと同じパラグラフの中に書かれている。
「広義の意味で、近代的な主体の解体を描く作品」である。
ここんとこ、すこぶる重要なんで、ぼくのことばで補おう。
「近代的な主体」とは、いいかえれば「近代的自我」だ。ぼくがこれまでの記事のなかで述べてきたとおり、「内面」をもち、「苦悩」をかかえ、それを「告白」したりなんかする、めんどくさそうな主体のことである。
いや、この「めんどくさそう」と感じるセンスがまさしく「ポストモダン」の産物であって、「近代(モダン)」においては、それはけっしておかしなことではなかった。
そういう主体がいま解体されている。それに伴って「世界」もまた壊れつつある。だって、「世界」を認識して意味づけるのは主体(自我)なんだから、これが崩れりゃ世界のほうも崩れますわな。
そんなポストモダンな状況を作品化してるのが、2007年度における優れた「純文学」だ、というわけだ。
ところが、そんな姿勢すらもう古いぜ、と宇野さんはここでいうのである。
「しかし、円城塔に象徴的だが、彼らが描くような意味で世界が≪壊れて≫いるということはもはや前提化しており、むしろ彼らが描くポストモダン的な解体の結果として、現在の物語回帰は存在している。(後略)」
つまり、今さら「近代的な主体の解体」なんかをテーマに掲げて作品化したって、べつに新しかねぇんだよ純文学さんよ、状況は、つーか現実はもっとシビアに切羽詰まってて、むしろ「物語」がまた復権してきてるんだよ、と宇野さんはいっておられるわけである。そのことは、芥川賞受賞作よりも『バトル・ロワイヤル』のほうを重要視する(!)この『ゼロ年代の想像力』の論調をみればおのずから明らかだ。
春樹さんに対する評価の高さもここからわかる。だって、村上春樹って純文学作家というより、純文学くさい物語作家じゃん。
ところでぼく自身は、復権もなにも、物語ってのは今も昔も圧倒的な市場を誇ってて、純文学なんて、もはやその傍らで細々とやってるだけなんだから、そもそも同じ俎上(そじょう)で論じることがムリなんじゃないかなあ、と考える。
ここでの、というか、『ゼロ年代の想像力』における「物語」とは、エンタメ小説(活字の物語)だけでなく、例によってドラマ、アニメ、マンガ、特撮、ゲームなどを含む。こういうものは、復権もなにも、以前から強いし、ネットの普及でさらにまた強い。これについてはぼくも、ここんとこ何回かにわたってずっと述べてきた。
純文学は、物語に回収されぬからこそ純文学なわけであり、そこにこそ存在意義(レーゾンデートル)があるわけだから、「いまどきの純文学には物語がないからダメ」というのは、魚屋さんに行って、「人参と玉ねぎとじゃが芋を売ってないからダメ」というようなものだ。
あっ。いやいや。ちょっと待った。それより何より。
ぼくは批評は読むのもやるのも好きだけれども、いちおうは実作者でもある。
実作者としての立場からいうと、そもそも、『Self-Reference ENGINE』『アサッテの人』『わたくし率イン歯―、または世界』『わたしたちに許された特別な時間の終り』の4作を、「ポストモダン文学」と一括りにすることはできない。
それがおかしい、というのではない。もちろん妥当である。もしぼくが批評プロパーでやってたら、たぶんそうするだろう。
だが、じっさい手に取って、つぶさに読んでみるならば、とうぜんながらこの4作、それぞれに肌合いも違えば作者の問題意識もちがう。
『Self-Reference ENGINE』はポップなSFだ。サイエンス・フィクション(科学小説)というよりスペキュレイティブ・フィクション(思弁小説)のほうだが。
『アサッテの人』は、これはもうメタフィクっぽい哲学小説としかいいようがない。よく芥川賞を取ったもんである。
『わたくし率イン歯―、または世界』は、初期の川上さんらしい、身体性をそなえた瑞々しい佳品だ。
『わたしたちに許された特別な時間の終り』は、物語性には乏しいが、この中では、いちばんふつうの小説に近くて読みやすい。
いずれも「広義の意味で、近代的な主体の解体を描く作品」には違いないけれど、技術てきなこと、方法論、コトバの手ざわり、それぞれに味わいがあって、こちらの心がけしだいでは、たっぷりと可能性を秘めている。じつに旨そうな素材なのである。
ゆえに、「あっこいつらポストモダン小説、それ古い、それダメ」と、あっさり切り捨てることはできない。
『ゼロ年代の想像力』は、面白くて勉強になる一冊だけど、とりあえず、ぼくの専門分野たる純文学にかんしては、このほかにも、異を唱えたいところがいくつかある。むろんそれは、「刺激的」ということでもあり、それゆえにこそ面白いわけだが。