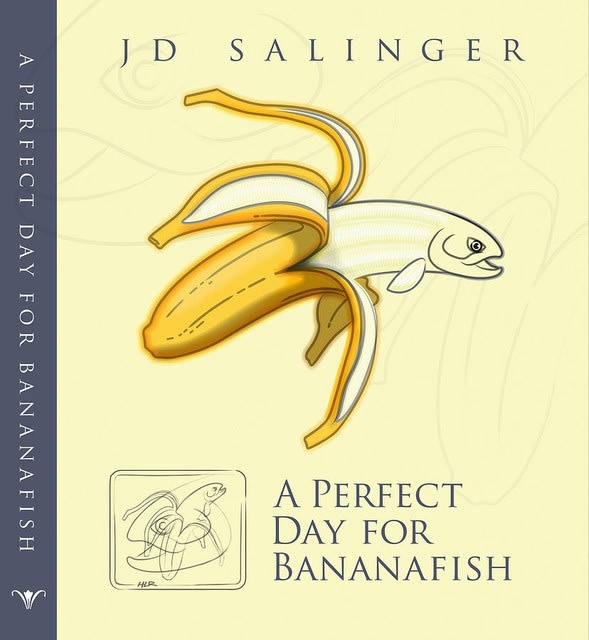「note」に移して削除しちゃった古井由吉さんの記事に、どういうわけか今になってアクセスが多いようで……。「記事がありません。」って表示が出て、無駄足になるんで申し訳がない。自分で書いたものなんだから別に差支えはないし、こちらにも再掲載しましょう。そのままコピペも芸がないので、少し書き足しておきます。
☆☆☆☆☆☆☆
dig フカボリスト。
e-minor 当ブログ管理人eminusの別人格。
☆☆☆☆☆☆☆
こんにちは。e-minorです。
digです。
いや古井由吉さんがお亡くなりになってたんだね。ぜんぜん知らなくて、いま軽くショック受けてるんだけど。
今年の2月18日だってな。
ちょうどコロナ禍が広がってた頃だ。こちらのアタマもそっちのことでいっぱいだった……。なにしろ新聞とってないし、テレビも見ないからなあ……。そういう生活になって随分になるけど、今回初めて支障をおぼえたよ。
なんで今になって知ったんだ?
面白いツイートを見つけたんで、その人の投稿を遡ってたら、古井さんへの追悼の辞があった。それでネットを調べて、「ええっ。」てなもんだよ。ほんの2、3日前の話さ。digは知ってたの?
おれもリアルタイムでは知らなかった。夏になる手前くらいだったかな。
7月にdigと喋ったとき、大江健三郎さんの話になって、ぼくはこんなこと言ったよね。
「モダンうんぬんをいうなら、大江さんと同世代でもうひとり、古井由吉という巨匠がいる。お二人による対談集も出ているが、この方のばあい、デビュー作からすでに「私」が蜃気楼のごとく妖しく揺らめいていた。それはホーフマンスタールの「チャンドス卿の手紙」(1902=明治35)に源をもつと思うけど、「私(近代的自我)」の揺らぎがすでに生理的な前提としてあるわけだね。今や古井文学は日本語の極限に挑むかのような境地に達しているが、大江さんと古井さん、このお二人によって現代日本文学の水準が達成されてきたとはいえると思う。このお二方が厳然として聳えておられるから、ほかの作家たちは自分なりの器に応じて好きなことをやってられるってところはあるよ。」
あのときはもう知ってたわけ?
知ってたし、そっちもそれを踏まえて喋ってるもんだと思ってた。
そうかあ……それにしても、いちおうネットのニュースには毎日いちどは目を通してるんだけどなあ。現代日本文学最高峰の作家の逝去が、トップニュースのヘッドラインにも入らんとは……
この国における文学の現状を如実にあらわしてるわな。
そんなだからぼくも、ついアニメの話に傾いちゃうわけだ……いや日本のアニメは世界に誇れる文化だけどね、その一方、ことばでつくる芸術に対する取扱いがぞんざいすぎるよ。
憤懣はわかったから、もうちょい建設的なほうに行こうか。
言いたいことが多すぎると、何から喋っていいかわからず、かえって下らぬ話をしてしまうもんだよ……
そうだなあ。
まず、古井さんの文章の魅惑を伝える一助として、手元にある著作から、とりあえず2つ引用してみようか。これは夢の情景を叙したものだが……。
「……たとえば、静まりかえった虚空に柔らかな光が遍くひろがる。水が見える。山が染まる。日が浮んで、照り輝かずに、過剰な輝きをむしろ吸い集めて、光り静まる。水中から花が咲き、蝶が群れ飛ぶ。空を横切る鳥の頭がふと赤光を集め、山肌の色が変る……」
エッセイ「湖山の夢」より
もうひとつ。
「空には雲が垂れて東からさらに押し出し、雨も近い風の中で、人の胸から頭の高さに薄明かりが漂っていた。顔ばかりが浮いて、足もとも暗いような。何人かが寄れば顔が一様の白さを付けて、いちいち事ありげな物腰がまつわり、声は抑えぎみに、眉は思わしげに遠くをうかがう、そんな刻限だ。何事もない。ただ、雲が刻々地へ傾きかかり、熱っぽい色が天にふくらんで、頭がかすかに痛む。奥歯が、腹が疼きかける。互いに、悪い噂を引き寄せあう。毒々しい言葉を尽くしたあげくに、どの話も禍々しさが足らず、もどかしい息の下で声も詰まり、何事もないとつぶやいて目は殺気立ち、あらぬ方を睨み据える。結局はだらけた声を掛けあって散り、雨もまもなく軒を叩き、宵の残りを家の者たちと過して、為ることもなくなり寝床に入るわけだが。」
短編「眉雨」より
……稠密だな。
息苦しいほどにね。理知的でありつつ耽美的というか、知的であることが美的であることに直結してるんだな。これは良質の哲学者の文章にも似ている。しかしこういう文章が纏綿とつづくわけだから、古井文学を読むには、正直それなりの体力がいる。しかし、ひとたび憑りつかれると、金輪際抜けられないね。定期的に読み返さずにはいられぬし、新刊が出たと聞いたらそわそわする。
本もけっこう持ってたろ、文庫で。
福武文庫ってのが昔あってね。福武書店はベネッセと社名を変えて路線転換しちまったが、80年代には文芸部門に力を入れてたんだ。「海燕」という文芸誌も出してたし、単行本でユニークな海外文学を紹介してもいた。それは文庫もしかりで、福武文庫っつったら当時はなかなかのラインナップだったよ。代表作の『槿(あさがお)』『眉雨』『夜の香り』あたりが出ていた。ぜんぶ発売当日に買った。
『槿』なんて、いま講談社文芸文庫でけっこうな価格つけてるよな。
そこなんだよ。古井さんの著作で入手困難になったものは、おおむねあそこが拾ってるんだけど、講談社文芸文庫はとにかく高い。2000円以上付けてたりするでしょ。そりゃ絶版になるよりはだんぜん良いけど、やはり文庫の小説ってものは高くとも1000円までで買えないと、若い世代が手を出せないじゃん。いや若い世代のみならず、ぼくみたいな貧乏人も困る(苦笑)。
それは採算の取れるだけの市場を形成してないってことで、結局はさっきの話に戻るわな。
「純文学の衰退」っていう、当ブログ創設いらいのメインテーマに帰するんだけどね。出版史的な証言として、もう少し続けると、集英社文庫も古井作品をわりと出してたんだよね。『山躁賦』『水』『行隠れ』が出ているな。短編集『水』はぼくなんか20代の頃にどれだけ読み返したかわからない。『行隠れ』も大好きだ。「若い人に古井由吉をどれか一冊」といったらたいてい「杳子」が上がるんだけど(『杳子・妻隠』として新潮文庫に収録)、ぼくは『行隠れ』のほうを薦める。
上に画像貼ったやつだな。こちらは単行本の表紙だが。そうか。初の長編だったのか。
純文学であり幻想小説でありミステリでありサスペンスであり……いろいろな意味でスリリングな一作だよ。主人公の青年の、姉への思慕が根底にある。シスコン気味のぼくにとっては、その点でも蠱惑的だったな。ただし入手が難しい。「杳子」だったら文庫でも電子書籍でも読めるんだけど、こっちは絶版だからね。河出書房新社の「古井由吉自撰作品 1」に入っちゃいるが、4000円近い。まあ図書館かな。ただ、ネクラ(死語?)っていったらこれほどネクラな世界もないんで、ライトノベルで育ったひとが生半可な気持ちで読んだら、おなかにもたれると思うけど。
ライトノベルをポテトチップスだとしたら……
脂身こってりのビフテキがいきなり前菜に出てくるフルコースっていうか。
新潮文庫も『杳子・妻隠』のほかにいくつか出してただろ。
『辻』だけは入手可能だが、ほかは残念ながら絶版だね。
……いや、いまスマホで確認してるけど、『櫛の火』『聖・栖(すみか)』『白髪の唄』『楽天記』と、ぜんぶ電子で読めるぞ。
あっ、そうなのか。新潮社は頑張ってるな。それだけ需要もあるんだね。安心した。あと、文芸文庫じゃなく、ふつうの講談社文庫で出てた『野川』も電子書籍になってるね。600円ちょっとか。これならまあ……
でも代表作とされる『山躁賦』と『仮往生伝試文』は文芸文庫でしか読めないんだな。
そっちがなあ……。あ、でも『山躁賦』は電子になってるか。ただ『仮往生伝試文』は紙媒体のみで、価格が……
税込み2200円。
文庫の値段じゃないよなあ。
まあ、どれか一作を読んで興味がわいたら、河出の「古井由吉自撰作品」を図書館で借りて順に読んでいくのが上策じゃないかね。
でもやっぱり優れた作家はひとりでも多くの人に文庫で手元に置いててもらいたいんだよね。ぼくとしてはね。
気持はわかるが、本の値段の話ばっかしてるのもどんなもんかね。なんかこのたびネットで「古井由吉」で検索かけて、いい記事を見つけたって言ってなかったか?
「古井由吉は日本文学に何を遺したのか 82年の生涯を新鋭日本現代文学研究者が説く」
ぼくはこの竹永さんって方のお名前は初見だったんだけど、すばらしいねこれ。とても的確な紹介になってる。
一部を(といってもメインの部分になっちゃうんだけど)抜粋させていただこう。では。
50年に渡る古井由吉の営みを網羅的に説明することはむずかしい。ここでは作風の面から私流に4つに区分して、説明を試みようと思う。
①初期(1968年~1971年、代表作『円陣を組む女たち』『男たちの円居』)。
デビュー作は、登山中の記憶喪失をめぐる短編「木曜日に」。小説家になる以前、古井はドイツ文学研究者としてロベルト・ムージルやヘルマン・ブロッホ、ニーチェなどの翻訳をおこなっており、その影響が濃いとされる一時期。「群衆の熱狂」や「共同体と個人」といったテーマを抽象的な物語内容と濃密な描写で追求する作品が多い。
②前期(1971~1980年、代表作『杳子・妻隠』『水』『櫛の火』『聖』3部作など)
一定の物語性をもった作品が多く、入門するのにうってつけの時期だと思う(わたし自身がそうだった)。作家史的には、連作短編『水』や長編『櫛の火』のように古典的な物語風土に題材を借りた作品が多く、ドイツ文学由来の作風から抜け出そうという意思が見てとれる。連作や長編など、形式面の実験を積極的におこなった時期でもある。が、順風満帆であったわけではなく、のちのインタビューでは、この頃に「フィクションということに行き詰まった」と漏らしている。
③中期(1980年~1989年、代表作『山躁賦』『槿』『仮往生伝試文』など)
そこで古井は自らの原点に立ち返り、ムージル的な「エッセイズム」の探求を開始する。このジャンル解体的な、かつ現在進行形の散文を古井は「試文」と呼んで概念化した。その結晶が連歌や説話、日記などを縦横無尽に引用しながら言葉がつむがれていく『山躁賦』と『仮往生伝試文』という記念碑的傑作である。変わりゆく文学状況のなかで、もっとも試行=実験を激化させた一時期だと言える。一方で「小説らしい小説」への「最後のご奉公」として書いたという『槿』も初期から続く「恋愛小説」の系譜の到達点として見逃せない。
④後期(1989年~2020年、代表作『楽天記』『白髪の唄』『野川』『辻』など)
古井自身と重なる「私」が、老いや災害、記憶などについて思弁をめぐらす連作群。それぞれがすぐれた短編として成立していると同時に、たとえば単行本といった単位が消滅し、古井が書くすべてのものがひとつながりであるような境地に至っている。その中心にいるのは体を病み、老いた「私」。同じことを何度も繰り返し、執拗に書き続ける「私」の筆致は「私小説」というジャンルを抱えた日本文学全体の宿痾を明るみにしようとしている。
以上、古井の試行錯誤のおおまかな見取り図である。「文学」の存立基盤をたえず問い直す、自壊さながらの実験の連続により「内向」という態度を貫いた小説家による作品の数々にふれるとき、わたしたちもまた「小説とはなにか?」を考えずにはいられない。自身の文学観をゆさぶってみたいと思うひとは、ぜひ手にとってみてほしい。
引用ここまで。いやほんとに見事な紹介だ。ぼくとして付言すべきことはほとんどないな。この竹永さんは1991年生まれとのことで、つまりまだ20代ってことになるけど、こんな若い方が出てこられるのなら、この国の文化もまだ大丈夫かなって思う。
後生畏るべしだよ。若い人で優秀なのは増えてるよ。おれたちの頃と比べて、多くの情報にアクセスしやすくなってることも大きいと思うが。
ほんとにね。あ。いちおう念を押しとくと、『行隠れ』はもちろん②前期(1971~1980年)の作品だよ。
今回はバナナフィッシュを中断して、急遽こういう話になったわけだが……
でもさ、やはり文学ってものはみんなどこかで繋がっていて、上のほうで言った大江・古井両巨匠による対談集って『文学の淵を渡る』(新潮文庫)のことなんだけど、これを昨日改めて読み返してたら、ふしぎなくらい「バナナフィッシュ」に通底するところが見つかったんだよね。少しぼくのことばに変換するけど、「罪の暗い穴の底から抜け出して生還する」というイメージとか、あと、「生の営みのなかに自ずから死が混じりあっている」といったイメージとかね。「げに恐ろしきはブンガクなり。」って思ったね。
晩期の古井文学はまことに生死が渾然となってる感じだった。たしかにあれが文学の神髄だと思う。哲学もそうだが、結局のところ文学ってのは「己の死」を僅かずつ先取りしていく営為じゃないか。そうすることで、かえって「生」の力を取り戻す。そうやってよろよろ歩いていくしかない。おれはそう思ってる。
いい警句が出たね。それを〆のせりふにしようか。
好きにすればいいさ。
それでは、この談義を以って、当ブログとしての追悼の辞に代えさせていただきます。