フェルメールほど謎めいて、作品にまつわるスキャンダルの多い画家も少ないだろう。まず生涯がはっきりしていない。デルフトの画家の組合に所属していたこと以外、確実なことはわかっていないらしい。
生前はそれなりの評価をされていた様子なのに死後急速に忘れ去られ、再評価されたのは19世紀も後半に入ってからである。
ゴッホは手紙の中でたしか「デルフトの風景」について熱っぽく語っていたように記憶するが、これは再評価の時期とほぼ重なる。ルノアールも「お針子」(僕が勝手に呼んでいるのだけで、どうやら刺繍をする女、と呼ばれるのが一般らしい)の手前の赤だけのためにルーブルに行く価値があると言ったそうだ。こうした19世紀の画家達の目も再評価の機運を高めたのだろうか。それとも再評価されるような時代の空気が画家達の目を育んだのだろうか。忘却の長さから言えばバッハをも凌ぐ。
絵にまつわるエピソードもドラマティックである。貸し出された先で額から切り裂かれて盗まれたり、アイルランドのテロリストに強奪されて仲間の釈放を要求されたり!この辺の状況に関心がある人はお調べ下さい。僕はうろ覚えで書き連ねているので。
なんと言っても極めつけに面白いのは贋作事件、ナチスドイツがからんだ事件であろう。ヒトラーが「画家のアトリエ」を買い上げ、それに触発されたゲーリングが「キリストと悔恨の女」と題する絵を買った。戦後それがオランダの至宝を敵国に売った売国行為として、売り主のメーヘレンという画家が逮捕された。(Meegerenというのはオランダでは多分メーヘレンと読むのだと思う)
メーヘレンは裁判の過程で、それが自分の描いた贋作であると告白した。それどころか、本物であると名だたる専門家から折り紙付きの数点も彼の手による贋作だという。メーヘレンは自らの才能に自信を持っていたらしい。しかし認められなかった。贋作に手を染めたのは彼の画家としての才能を認めなかった「専門家」たちへの復讐の念ゆえであったというのだ。
この告白は誰にとってもにわかには信じられることではなかった。そこでメーヘレンは証拠としてもう一点「フェルメール」を人々の前で描いた。このあたりの経緯も興味のある人はもっと詳しくどうぞ。
日本でも永仁の壺事件というのがある。陶工加藤唐九郎による贋作?事件である。重要文化財に指定されるなど、その道の専門家の目をも欺いた点も似ている。白州正子さんとの対談の中で、そのうち真相を語ると言っているが果たさぬまま他界した。
メーヘレンは結局詐欺罪で禁固1年だったか服役中に獄死し、忘れ去られたが、加藤唐九郎はますます有名になった。僕の関心はそちらへ向く。この違いは何なのか?柳宗悦らの民芸運動をはじめ、作者の分からない陶磁器に本物の美を発見しようという、日本独特の美観が作用しているのだろうか。こんなことはいくら考えたところで結論は出ない。でも面白いことではないか。ものを考えるとは結論を出すこととは限らない。
生前はそれなりの評価をされていた様子なのに死後急速に忘れ去られ、再評価されたのは19世紀も後半に入ってからである。
ゴッホは手紙の中でたしか「デルフトの風景」について熱っぽく語っていたように記憶するが、これは再評価の時期とほぼ重なる。ルノアールも「お針子」(僕が勝手に呼んでいるのだけで、どうやら刺繍をする女、と呼ばれるのが一般らしい)の手前の赤だけのためにルーブルに行く価値があると言ったそうだ。こうした19世紀の画家達の目も再評価の機運を高めたのだろうか。それとも再評価されるような時代の空気が画家達の目を育んだのだろうか。忘却の長さから言えばバッハをも凌ぐ。
絵にまつわるエピソードもドラマティックである。貸し出された先で額から切り裂かれて盗まれたり、アイルランドのテロリストに強奪されて仲間の釈放を要求されたり!この辺の状況に関心がある人はお調べ下さい。僕はうろ覚えで書き連ねているので。
なんと言っても極めつけに面白いのは贋作事件、ナチスドイツがからんだ事件であろう。ヒトラーが「画家のアトリエ」を買い上げ、それに触発されたゲーリングが「キリストと悔恨の女」と題する絵を買った。戦後それがオランダの至宝を敵国に売った売国行為として、売り主のメーヘレンという画家が逮捕された。(Meegerenというのはオランダでは多分メーヘレンと読むのだと思う)
メーヘレンは裁判の過程で、それが自分の描いた贋作であると告白した。それどころか、本物であると名だたる専門家から折り紙付きの数点も彼の手による贋作だという。メーヘレンは自らの才能に自信を持っていたらしい。しかし認められなかった。贋作に手を染めたのは彼の画家としての才能を認めなかった「専門家」たちへの復讐の念ゆえであったというのだ。
この告白は誰にとってもにわかには信じられることではなかった。そこでメーヘレンは証拠としてもう一点「フェルメール」を人々の前で描いた。このあたりの経緯も興味のある人はもっと詳しくどうぞ。
日本でも永仁の壺事件というのがある。陶工加藤唐九郎による贋作?事件である。重要文化財に指定されるなど、その道の専門家の目をも欺いた点も似ている。白州正子さんとの対談の中で、そのうち真相を語ると言っているが果たさぬまま他界した。
メーヘレンは結局詐欺罪で禁固1年だったか服役中に獄死し、忘れ去られたが、加藤唐九郎はますます有名になった。僕の関心はそちらへ向く。この違いは何なのか?柳宗悦らの民芸運動をはじめ、作者の分からない陶磁器に本物の美を発見しようという、日本独特の美観が作用しているのだろうか。こんなことはいくら考えたところで結論は出ない。でも面白いことではないか。ものを考えるとは結論を出すこととは限らない。










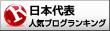

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます