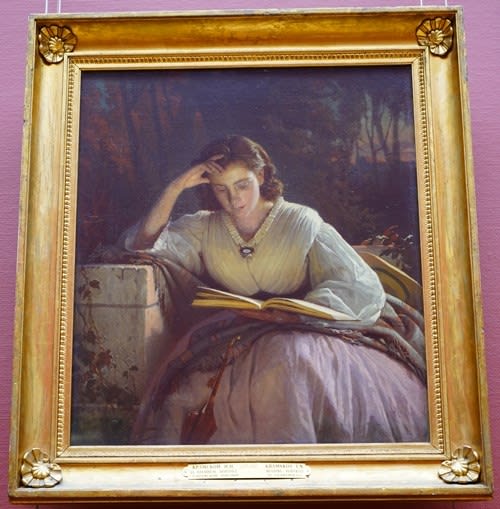本館とヨーロッパコレクション部に分かれていますが、私たちはヨーロッパコレクションだけを観てまわりました。イコンやロシア美術を主体とするロシア美術館やトレチャコフ美術館と異なり、ここでは西欧絵画が集中的に集められています。

ベラスケスと並び、スペイン最高の画家と称されるフランシスコ・ゴヤ 『ローラ・ヒメネスの肖像』

バレエをテーマとする作品で知られるフランス人画家エドガー・ドガのコーナー。ドガがバレエの絵を多く描いたのは、「動き」を表現するためだったそうです。実際、ドガの作品の半分以上はバレエを主題としています。
左から『写真スタジオでポーズする踊り子』、『バレエの稽古』、『青色の踊り子たち』

ドガの作品だと思って観ていたのですが、この絵はピエール・カイエ=ベルーズの『踊り子(Dancer)』。バレリーナの息づかいが聞こえてきそうなほどリアルで、写実的な絵でした。ベルーズはドガと同じく、多くのバレエダンサーの絵を描いたそうです。

オーギュスト・ロダン 『去りゆく愛(Love Running Away)』

オーギュスト・ルノワール 『ジャンヌ・サマリの肖像』。ルノワールの傑作のひとつとされる肖像画ですが、人物を際立たせるために肖像画の背景は暗く描くのが常識だったこの時代、背景をピンクとしたこの絵はかなり物議を醸したそうです。
ジャンヌ・サマリは当時のフランスの人気女優で、ルノワールと親密な関係にあったとされています。サマリの全身像はサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館新館が収蔵していたので、ジャンヌ・サマリの二つの肖像画を観ることができました。

同じくルノワール 『セーヌの水浴(ラ・グルヌイエール)』
ラ・グルヌイエールはセーヌ河のほとりの町で、ルノワールとモネが共同制作を行なった場所です。二人は、ラ・グルヌイエールの同じ風景を何枚か描いていますが、ルノワールが人物の姿や表情を精細に表現しているのに対し、モネは水面の反射など光を描くことに集中していることが窺われて興味深いです。

『草上の昼食』は、クロード・モネ初期の作品。エドァール・マネの同名の作品(裸体の女性を含めて描いた森の中のピクニック)に強い影響を受けて描かれたものだそうです。

同じくモネ、1870年代の作品『カピュシーヌ大通り』。パリのオペラ座に面するカピュシーヌ大通りを描いたものですが、左側の建物や並木には眩いばかりの光が差し込んでいるのに対し、大通りを行き交う人々は建物の影に暗く沈んだように描かれているのが印象的でした。また、画面右端で、ベランダからこの風景を眺めているシルクハットの二人の男が、不思議な緊張感を醸し出しています。

『ヴェトゥイユ』は、アルジャントゥイユと並んでモネが好んで訪れ、その風景を描いたセーヌ川ほとりの小さな町です。セーヌ川越しに見るヴェトゥイユの町は連作で描かれており、そのうちの一枚は日本の国立西洋美術館が所蔵しているそうです。

一見、モネの『日傘を差す女』に似ていますが、こちらはポール・セザール・エルーの『白い服の婦人(Lady in White)』

カミーユ・ピサロ 『オペラ座通り(雪の効果・朝)』

ポール・セザンヌの部屋。左から、『マルヌ川にかかるクレテイルの橋』、『パイプをくわえた男』、『池に架かる橋』

ポール・シニャック 『サン・ブリアックの浜辺』

フィンセント・ファン・ゴッホの部屋です。一番右は『雨上がりのオーヴェールの風景』、2番目は『医師フェリックス・レイの肖像』。レイ医師は、アルル時代のゴッホの主治医で、ゴッホはこの肖像画を彼に贈りますが、本人はあまり気に入らず手離してしまったそうです。

『サント・マリー・ド・ラ・メールの海』
絵の具をチューブから直接キャンバスに塗りつけているような絵でした。

唯一、ゴッホの生前に売れた絵と言われている『アルルの赤い葡萄畑』。

右側の壁に掛けられた絵は、ゴーギャンの『ルペ・ルペ(タヒチは不思議の土地,果物を集める)』。正面の壁は、同じくゴーギャン『馬のいる風景』
ブロンズ像を撮ったのに、そちらの作者やタイトルはわからずじまいでした (^-^)ゞ

アンリ・マティスの部屋。左から、『ヴェネツィアン・レッドの静物』、『フルーツとブロンズ像のある静物』、『スヒーダム・ジンの酒瓶』

マティスだけではなく、青の時代を中心として、ピカソの作品の充実ぶりにも驚きました。この美術館のコレクションの基礎を築いたシチューキンは、まだ評価の定まっていなかった頃からマティスやピカソを支援していたそうです。財力にものを言わせて美術品を蒐集したのではなく、その審美眼が優れていたことの証と言えるでしょう。
左から、『ハイメ・サバルテースの肖像』、『年老いたユダヤ人と少年』、『逢引(抱擁)』

パブロ・ピカソ 『ハイメ・サバルテースの肖像』

『扇子を持つ女』と『女王イザボー』

『ヴァイオリン』

エルミタージュ美術館新館(旧参謀本部)で観たロシア出身の抽象画家ワシリー・カンディンスキーの絵もありました。『青とさまざまな色(Blue over Multicoloured)』

モーリス・ユトリロ 『モンマルトル モン・スニ通り』。ユトリロはパリのモンマルトル生まれ。生涯のほとんどをモンマルトルで暮らし、この街の風景を多く描きました。

私は知らなかったのですが、マルク・シャガールはユダヤ系ロシア人だったそうです。
右から『ノクターン』、『画家と婚約者』、『白い馬』

フリッツ・タウロー 『マドレーヌ大通り、パリ』

1階ではポスターの企画展が行われていたので、そちらも覗いてみました。

展示の主体は、チェコ出身の画家・イラストレータ、アルフォンス・ミュシャの作品。

ちょうど1年前、福岡アジア美術館で行われた『ミュシャ展 〜 運命の女たち』を思い出しながら観てまわりました。

19世紀から20世紀にかけての西欧絵画を広く収蔵するプーシキン美術館(ヨーロッパコレクション部)。ゴヤにドガ、ルノワールやモネ、ゴッホ、マティスにピカソ・・・・・。写真は載せませんでしたが、このほかにもシスレーやクールベ、マネにコローなど見応えたっぷり。絵画好きには垂涎のコレクションだと思います。さほど混みあうこともなく、ゆったり観賞できたのも高ポイント。日本の展覧会ではそんな訳にはいきませんね。サンクトペテルブルクのエルミタージュとモスクワのプーシキン美術館は、ロシアを訪れたら是非とも立ち寄ってほしい場所です。