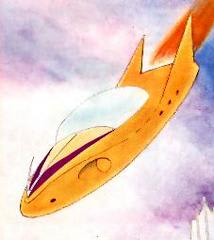エレクトリック・ギターの世界では、ヴィブラートとトレモロは意味を取り違えられてきた。フェンダーのせいだね。本来ヴィブラートは音程を変化させることで音を揺らし、トレモロは音量を変化させることによって音を揺らすということなんだけど、ヴィブラートをかけるアームをトレモロアームとし、アンプのトレモロをヴィブラートとしてしまった。でも、今さら変えられないね。
というわけで、ダンエレクトロのヴィブラート・ペダルの話。これもFRENCH TOASTと同様に隠された秘密があって、新映のUNIVIBEとそっくりのサウンドを持っているという。クローンなのかどうかは定かではない。
UNIVIBEはジミ・ヘンドリックスが使用したことで知られている。あのウッドストック・フェスティヴァルにおいてもヘンドリックスの足下にはこのペダルがあった。例の「スター・スパングルド・バナー」の凄絶な演奏に日本製のUNIVIBEが貢献したことは日本人としてやはり嬉しくなってしまう。

UNIVIBEはレスリーなどのロータリースピーカーのサウンドを再現するべく開発されたもので、ペダルをワウのように踏みこんでスピードを調整できるようにしている。ダンエレクトロのヴィブラート・ペダルはINTENSITYとSPEEDの2つのノブにより、揺れの強さと速さを調節する。ヘンドリックスのようなサウンドにするならINTENSITYはフルにしてSPEEDは12時の位置くらいかな。ウッドストックのDVDを見ながら合わせてたらそうなった。そしてつなぐときは歪みの前のほうがいい感じ。そうするとギターを弾いていないときのノイズの揺れかたも雰囲気ばっちり。
ダンエレクトロのヴィブラート・ペダルはCHICKEN SALADと名づけられたが、なぜそうなったかは、ウッドストックでジミ・ヘンドリックスがUNIVIBEを使用したということによるものと推測される。

チキン・サラダは野菜サラダに焼いた鶏肉をあわせたものだが、この料理そのものはどうでもよく、CHICKENとSALADそれぞれの単語の意味が重要なのである。どちらも青二才というような意味で使われることがある語で、SALAD DAYSといえば、モンティ・パイソンがやったサム・ペキンパーのパロディが思い出されてしまうわけだが、ここではそうではなく、経験のない青年時代ということ。ウッドストック・フェスティヴァルが、まさに経験のない青二才により企画され運営されたものであり、それに象徴されるようなヒッピー文化が隆盛したアメリカの60年代がSALAD DAYSということになるわけ。ということで、この時代を象徴するミュージシャンがジミ・ヘンドリックスであり、彼が使用したUNIVIBEのサウンドを再現するペダルをCHICKEN SALADと名づけたのではないかと、まあ勝手に考えた次第。
というわけで、ダンエレクトロのヴィブラート・ペダルの話。これもFRENCH TOASTと同様に隠された秘密があって、新映のUNIVIBEとそっくりのサウンドを持っているという。クローンなのかどうかは定かではない。
UNIVIBEはジミ・ヘンドリックスが使用したことで知られている。あのウッドストック・フェスティヴァルにおいてもヘンドリックスの足下にはこのペダルがあった。例の「スター・スパングルド・バナー」の凄絶な演奏に日本製のUNIVIBEが貢献したことは日本人としてやはり嬉しくなってしまう。

UNIVIBEはレスリーなどのロータリースピーカーのサウンドを再現するべく開発されたもので、ペダルをワウのように踏みこんでスピードを調整できるようにしている。ダンエレクトロのヴィブラート・ペダルはINTENSITYとSPEEDの2つのノブにより、揺れの強さと速さを調節する。ヘンドリックスのようなサウンドにするならINTENSITYはフルにしてSPEEDは12時の位置くらいかな。ウッドストックのDVDを見ながら合わせてたらそうなった。そしてつなぐときは歪みの前のほうがいい感じ。そうするとギターを弾いていないときのノイズの揺れかたも雰囲気ばっちり。
ダンエレクトロのヴィブラート・ペダルはCHICKEN SALADと名づけられたが、なぜそうなったかは、ウッドストックでジミ・ヘンドリックスがUNIVIBEを使用したということによるものと推測される。

チキン・サラダは野菜サラダに焼いた鶏肉をあわせたものだが、この料理そのものはどうでもよく、CHICKENとSALADそれぞれの単語の意味が重要なのである。どちらも青二才というような意味で使われることがある語で、SALAD DAYSといえば、モンティ・パイソンがやったサム・ペキンパーのパロディが思い出されてしまうわけだが、ここではそうではなく、経験のない青年時代ということ。ウッドストック・フェスティヴァルが、まさに経験のない青二才により企画され運営されたものであり、それに象徴されるようなヒッピー文化が隆盛したアメリカの60年代がSALAD DAYSということになるわけ。ということで、この時代を象徴するミュージシャンがジミ・ヘンドリックスであり、彼が使用したUNIVIBEのサウンドを再現するペダルをCHICKEN SALADと名づけたのではないかと、まあ勝手に考えた次第。