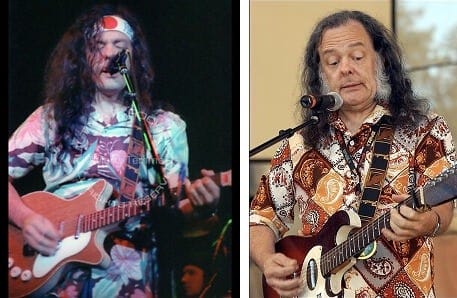音楽やバンドをテーマにしたマンガの人気が楽器業界にも波及した例としては、ハロルド作石の「BECK」、かきふらいの「けいおん!」、最近では、はまじあきの「ぼっち・ざ・ろっく!」などが思い浮かぶ。実際、これらのマンガの人気が上昇するとともに、物語に共感し、主人公たちと同じようにギターを弾き、バンドを組みたいと思う少年少女たちが増え、登場人物が使用した楽器(主にギター)と同じタイプのものが売れるようになったり、こうした動きに合わせ、初心者を対象にしたリーズナブルなシグネチャーモデルがつくられたりもして、楽器業界は大いに盛り上がることになった。「ぼっち・ざ・ろっく!」に至ってはギターマガジン2023年8月号の表紙を飾り、特集記事も組まれたが、ギターマガジン史上、マンガやアニメの架空のキャラクターが表紙になったのはそのときが初めてなのだそうだ。
ハロルド作石の「BECK」は1999年から2008年まで月刊少年マガジンに連載された。平凡な中学生だったが、天性の歌声を持つコユキ(田中幸雄)と7つの弾痕があるレスポールですさまじいサウンドを紡ぎ出す南竜介を中心に、様々な挫折を経ながらも成長していくバンドの物語が描かれている。
かきふらいの「けいおん!」は2007年から2012年までまんがタイムきららに連載された。女子高の軽音楽部の物語であるが、音楽的なことよりも日常生活が中心に描かれたことによって、バンド活動を身近なものにし、バンド人口の裾野を広げた。主人公の平沢唯も平凡な中学生だったが、高校で何かやろうと思い立って軽音楽部に入り、実は音感に優れているなど、隠れた能力を発揮していく。
はまじあきの「ぼっち・ざ・ろっく!」は2018年からまんがタイムきららMAXで連載中である。いわゆる陰キャ、コミュ障である主人公後藤ひとりが、父親から借りたギターにのめりこみ、動画投稿サイトでは評判になるほどの演奏技術を獲得したものの、人前での演奏となるとその性格のゆえうまくできないというところからバンド活動を通じて成長していく物語が描かれている。
これらの作品に共通しているのは、特に何の取柄もない平凡な少年少女がバンド活動を通じて隠れた才能を開花させ、やがて奇跡を起こしていくといった物語であり、ギターを弾ければカッコイイ、バンド活動は楽しく、気心の知れた仲間でバンドを組めば小さな奇跡を起こせるかも、と誰しもを夢見させる。しかし、ギターを始めてみればすぐに気がつくが、マンガの主人公たちのようにすぐに弾けるようにはならないのである。そこで、弾けない原因はギターにあるのではないかと考えだすと、チューニングが気になり、弦高が気になり、ネックの反りが気になり、しかし何をどうすればいいのかがわからないとなると、弾いていてもだんだん楽しくなくなってきてしまい、楽しくなくなればそのうち弾かなくなってしまうというわけだ。弾かなくなれば弾けないままギターのことなどそのうち忘れてしまうだろう。ギター初心者が直面するこうした問題に、今までの音楽マンガは応えることはできなかったと思う。
そんな中、それまでとはちょっと変わった音楽マンガが現れた。2018年からビッグコミックで連載中の髙橋ツトム「ギターショップロージー」がそれである。この店名はAC/DCの楽曲「ホール・ロッタ・ロージー」から取られたものであり、店を切り盛りする兄弟の名前もアンガスとマルコムというくらい、AC/DC愛に溢れているのだが、このショップを舞台に、ギターの修理を頼みに来る客とギター自体の物語が展開していくのである。こうしたリペアショップを題材にすることによって、ギターを弾くというだけではなく、ギターの構造、修理やモディファイのノウハウ、ひいてはギターの歴史やギターが担ってきた音楽の歴史など幅広い内容を盛り込むことが可能となる。

「ギターショップロージー」は現在3巻まで単行本化されており、第3巻の第14話にダンエレクトロの59DCが登場する。オリジナルの3021とは違うのだが、例えばヘッドに角度がついている部分などはきちんと描かれていたりする。物語は、ギターは低い位置で構えるのがやはりカッコイイというところで、ジミー・ペイジやポール・シムノンの話をしているところにジミー・ペイジのそっくりさんが店に現れるというところから始まる。そっくりさんはダンエレクトロを持ってきて、ネック側のピックアップが断線して音が出なくなったのをすぐに直したいと言ってくる。ブリッジ側のピックアップだけで乗り切るのはどうかと言えば、「そんなのはダメに決まっている」と言っているのに、結局ブリッジ側のピックアップをネック側に移して、ネック側のピックアップだけで通すことにするというのはどういうことなのか、今一つよくわからないところではあるが、いずれにせよ、このそっくりさんは新潟県出身であることも含めてジミー桜井氏をモデルにしていることは言うまでもないだろう。名前を赤船平次というのだが、赤はレッドを鉛のLEDではなく赤のREDに読み換え、船は当然のことながらツェッペリン伯爵が開発した硬式飛行船から取られているわけで、このキャラクターは今後も登場するだろうし、その伏線も張られている。
ギターというものは安いものでなくても、弾いているうちにどこかしら調子が悪くなってくるもので、ジャックの接触が悪くなるだの、トーンやボリュームのノブにガリが出てくるだの、ボディをぶつけて傷つけてしまうだの、ネックが反るだの、ピックアップが断線して音が出なくなってしまうだの、色々ある。なのでギターを弾くようになったら、本来なら自らハンダゴテを手にして電装系のパーツを交換するくらいはできるようになっておくべきなのだが、それがかなわないのなら、近所にギターのことを相談できる店があるとよい。「BECK」、「けいおん!」、「ぼっち・ざ・ろっく!」をきっかけにギターを手にしたら、その次には「ギターショップロージー」を読んで、リペアショップとのつきあい方を学ぶのもよいかもしれない。
ハロルド作石の「BECK」は1999年から2008年まで月刊少年マガジンに連載された。平凡な中学生だったが、天性の歌声を持つコユキ(田中幸雄)と7つの弾痕があるレスポールですさまじいサウンドを紡ぎ出す南竜介を中心に、様々な挫折を経ながらも成長していくバンドの物語が描かれている。
かきふらいの「けいおん!」は2007年から2012年までまんがタイムきららに連載された。女子高の軽音楽部の物語であるが、音楽的なことよりも日常生活が中心に描かれたことによって、バンド活動を身近なものにし、バンド人口の裾野を広げた。主人公の平沢唯も平凡な中学生だったが、高校で何かやろうと思い立って軽音楽部に入り、実は音感に優れているなど、隠れた能力を発揮していく。
はまじあきの「ぼっち・ざ・ろっく!」は2018年からまんがタイムきららMAXで連載中である。いわゆる陰キャ、コミュ障である主人公後藤ひとりが、父親から借りたギターにのめりこみ、動画投稿サイトでは評判になるほどの演奏技術を獲得したものの、人前での演奏となるとその性格のゆえうまくできないというところからバンド活動を通じて成長していく物語が描かれている。
これらの作品に共通しているのは、特に何の取柄もない平凡な少年少女がバンド活動を通じて隠れた才能を開花させ、やがて奇跡を起こしていくといった物語であり、ギターを弾ければカッコイイ、バンド活動は楽しく、気心の知れた仲間でバンドを組めば小さな奇跡を起こせるかも、と誰しもを夢見させる。しかし、ギターを始めてみればすぐに気がつくが、マンガの主人公たちのようにすぐに弾けるようにはならないのである。そこで、弾けない原因はギターにあるのではないかと考えだすと、チューニングが気になり、弦高が気になり、ネックの反りが気になり、しかし何をどうすればいいのかがわからないとなると、弾いていてもだんだん楽しくなくなってきてしまい、楽しくなくなればそのうち弾かなくなってしまうというわけだ。弾かなくなれば弾けないままギターのことなどそのうち忘れてしまうだろう。ギター初心者が直面するこうした問題に、今までの音楽マンガは応えることはできなかったと思う。
そんな中、それまでとはちょっと変わった音楽マンガが現れた。2018年からビッグコミックで連載中の髙橋ツトム「ギターショップロージー」がそれである。この店名はAC/DCの楽曲「ホール・ロッタ・ロージー」から取られたものであり、店を切り盛りする兄弟の名前もアンガスとマルコムというくらい、AC/DC愛に溢れているのだが、このショップを舞台に、ギターの修理を頼みに来る客とギター自体の物語が展開していくのである。こうしたリペアショップを題材にすることによって、ギターを弾くというだけではなく、ギターの構造、修理やモディファイのノウハウ、ひいてはギターの歴史やギターが担ってきた音楽の歴史など幅広い内容を盛り込むことが可能となる。

「ギターショップロージー」は現在3巻まで単行本化されており、第3巻の第14話にダンエレクトロの59DCが登場する。オリジナルの3021とは違うのだが、例えばヘッドに角度がついている部分などはきちんと描かれていたりする。物語は、ギターは低い位置で構えるのがやはりカッコイイというところで、ジミー・ペイジやポール・シムノンの話をしているところにジミー・ペイジのそっくりさんが店に現れるというところから始まる。そっくりさんはダンエレクトロを持ってきて、ネック側のピックアップが断線して音が出なくなったのをすぐに直したいと言ってくる。ブリッジ側のピックアップだけで乗り切るのはどうかと言えば、「そんなのはダメに決まっている」と言っているのに、結局ブリッジ側のピックアップをネック側に移して、ネック側のピックアップだけで通すことにするというのはどういうことなのか、今一つよくわからないところではあるが、いずれにせよ、このそっくりさんは新潟県出身であることも含めてジミー桜井氏をモデルにしていることは言うまでもないだろう。名前を赤船平次というのだが、赤はレッドを鉛のLEDではなく赤のREDに読み換え、船は当然のことながらツェッペリン伯爵が開発した硬式飛行船から取られているわけで、このキャラクターは今後も登場するだろうし、その伏線も張られている。
ギターというものは安いものでなくても、弾いているうちにどこかしら調子が悪くなってくるもので、ジャックの接触が悪くなるだの、トーンやボリュームのノブにガリが出てくるだの、ボディをぶつけて傷つけてしまうだの、ネックが反るだの、ピックアップが断線して音が出なくなってしまうだの、色々ある。なのでギターを弾くようになったら、本来なら自らハンダゴテを手にして電装系のパーツを交換するくらいはできるようになっておくべきなのだが、それがかなわないのなら、近所にギターのことを相談できる店があるとよい。「BECK」、「けいおん!」、「ぼっち・ざ・ろっく!」をきっかけにギターを手にしたら、その次には「ギターショップロージー」を読んで、リペアショップとのつきあい方を学ぶのもよいかもしれない。