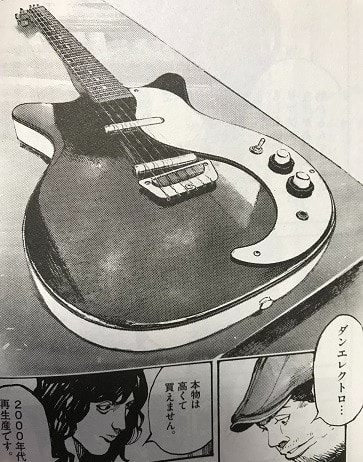この小さいアンプは VOX MB1 Escort という。これを手に入れたのはもう3~4年前のことになるだろうか、記憶はもう定かではない。何の気なしに私がよく行く楽器店のウェブサイトを見ていたとき、商品の背後に VOX の小さいアンプが映りこんでいるのに気がついた。しかも Pathfinder 10 とは明らかに違う。これはひょっとすると Escort か。それを確かめるために私はすぐにその店に向かい、そのアンプが Escort であることを確認し、その場で買い求めたというわけだ。ただし、イギリス製で電圧が230Vの仕様なので、ステップアップトランスがなければ使えない。そこで帰りに西田製作所にお邪魔して相談すると、たまたまあったトランスを譲っていただくこととなり、事なきを得たという次第。自宅の近所にこうしたショップがあるというのは本当に心強い限りである。
ところで VOX Escort とは一体どのようなアンプなのかといえば、電池駆動が可能な小さなソリッドステートアンプということになる。2種類あり、電池駆動のみのタイプを B2 といい、1974年から生産が始まったそうだ。それからしばらくして電池だけでなく壁のコンセントから電源の取れるタイプ BM1 が登場し、1983年まで生産が続けられた。電池駆動ができるといっても、当時のイギリスということもあり、使用する電池は PP9 といって、通常私たちがエフェクターなどに使用する 9V角電池と比較するとかなり大きいもので、それを2個使用することになっている。アンプの背中のフタを開けると確かに電池2個分のスナップが確認できる。今となってはこの PP9、日本では手に入れることがなかなか困難となっていて、あったとしても高額な値がつけられたりしている。なので、結局電池を使用した動作確認はできないまま今に至っている。機会に恵まれれば試してみたい。

このアンプは発売された当初、バスカーと呼ばれる路上ミュージシャンたちの間で広まった。彼らが演奏する路上や地下鉄の駅構内には電源がないため、電池駆動のアンプはとても有用だった。それは確かにそうだろう、しかしそれだけではなく、この小さいアンプは自宅での練習用にも使えそうだということで、そうしたニーズに応えるべく、電池に加えてコンセントから電源の取れる新たなタイプ(BM1)が生産されるようになったのである。

私が所有している Escort もその BM1 なのだが、その外観は VOX アンプの伝統的なデザインをそのまま縮小したもので、サイズは高さが22㎝、幅が33㎝、奥行は14㎝くらい。コントロール部は、インプットジャックが2つ、ヴォリュームとトーンのコントロールがひとつずつある。そして電源のセレクターがあり、ON/OFF のトグルスイッチがあるというシンプルなものである。スピーカーは5インチ程度のものがひとつ。VOXのウェブサイトによれば ELAC (ドイツのメーカー) のスピーカーのようだ。

実際に音を出してみると、そもそも出力も高くない (2.5W程度) ので大きな音はしない。ナチュラルに歪んだりもしないので、3~4年ギターを弾かずに過ごした私のブランクを埋める練習相手としてはちょうどいいかもしれない。とてもかわいいアンプで、私はこうしたものに目がないのだ。