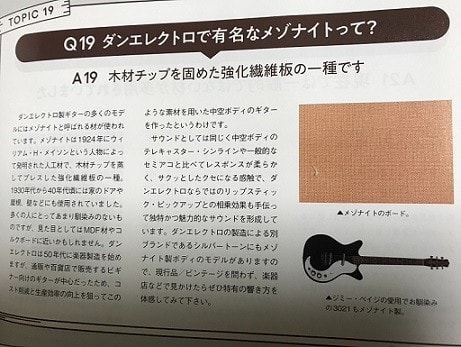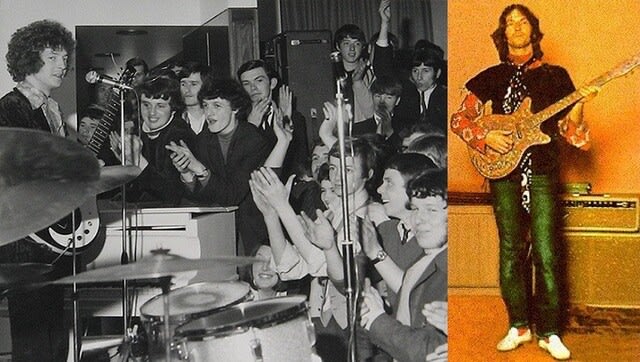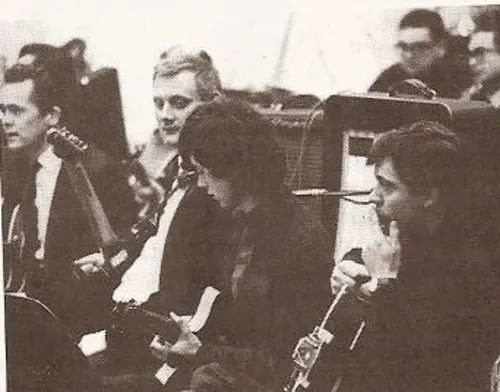1994年12月30日付のニューヨークタイムズにネイサン・ダニエルの死亡記事が掲載されていたことは以前から知ってはいたのだが、お盆休みで暇だったので訳出してみた。当然のことながらその内容は過去のブログ記事「ネイサン・ダニエルとダンエレクトロ小史」と重複してしまうのだが、コンパクトにまとまっているのでよしとしておく。訳文中のカッコ書きは私が補足したもの。
Nathan I. Daniel, the creator of Danelectro guitars and amplifiers, which offered a point of entry for a generation of would-be rock-and-roll musicians, died on Saturday at Queen's Medical Center in Honolulu. He was 82 and lived in Honolulu.
ダンエレクトロの創設者で、ロックンロール・ミュージシャン志望の若者たちに向け、初心者用のギターやアンプを提供したネイサン・I・ダニエルが土曜日(命日である1994年12月24日のこと)、ホノルルのクイーンズ・メディカル・センターで死去した。82歳だった。彼はホノルルに暮らした。
The cause was a heart attack, said his son, Howard.
息子であるハワードの言によれば死因は心不全とのこと。
Most of Mr. Daniel's popular electric guitars and amplifiers were sold through Sears under the Silvertone brand name.
ダニエル氏による、よく知られたエレクトリック・ギターやアンプの大半は「シルヴァートーン」のブランド名のもとシアーズを通じて販売された。
He was born in New York City, the son of Jews who had fled Lithuania. After dropping out of City College during the Depression, he began assembling and selling amplifiers of his own design to the Epiphone Company. During World War II, he served as a civilian designer for the Army Signal Corps at Fort Monmouth, in New Jersey, where he developed a simple, inexpensive shield for motorcycle engines that prevented their electronic noise from interfering with radio communications on the battlefield.
彼はリトアニアから逃れてきたユダヤ人の子としてニューヨークに生まれた。大恐慌のさなかにニューヨーク・シティ・カレッジを中退した後、エピフォンで彼独自の設計によるアンプの組み立てと販売を始めた。第二次大戦中はニュージャージー州フォート・マンモスの陸軍通信隊で民間人設計者として職務に従事、戦場での無線交信中に電子ノイズが干渉するのを防止するシンプルで費用のかからないオートバイ・エンジン用のシールドを開発した。
After the war, Mr. Daniel set up an amplifier manufacturing business, Daniel Electric, in Red Bank, N.J., and soon began selling his amplifiers to Montgomery Ward and Sears. In 1947, he brought out the first tremolo amplifier, and in 1950, he introduced a reverb device for guitar.
大戦後、ダニエル氏はニュージャージーのレッドバンクにアンプ製造事業を行う「ダニエル・エレクトリック」を創設するとすぐに、モンゴメリー・ウォードやシアーズでアンプの販売を始めた。1947年には業界初となるトレモロ(回路を内蔵した)アンプを発表、1950年にはギター用のリバーブ装置を(市場に)導入した。
In 1954, Mr. Daniel began making inexpensive, durable electric guitars, encasing the pickups in chrome lipstick covers that he bought from a cosmetics packing company, and facing the pine body of the instrument with tempered masonite. The original single cutaway model cost less than $40.
1954年にダニエル氏は低価格で頑丈なエレクトリック・ギターの製造を開始、化粧品容器会社から買いつけたクロームのリップスティックケースにピックアップを収納し、パイン材のボディでトップはメゾナイト(加熱式硬質繊維板)であった。オリジナルのシングル・カッタウェイ・モデルにかかった製造コストは40ドルに満たなかった。
Over the years, Mr. Daniel continued to experiment. He brought out a six-string electric bass guitar in 1956, and in 1958 he introduced the Longhorn, a guitar with two deep cutaways in the body, which made the frets more accessible. One of the company's biggest sellers was Amp-in-a-Case, a Silvertone guitar whose case contained an amplifier.
何年にもわたりダニエル氏は実験を続け、1956年には6弦ベース(通常ギターの1オクターヴ下の音域を持つ)を発表し、1958年にはロングホーンと呼ばれる、よりフレットに(指が)届きやすくなるよう、ボディの両側に深いカッタウェイを施したギターを(市場に)導入した。ダンエレクトロ製品の中で売り上げが最も大きかったものの一つはシルヴァートーンの「アンプ・イン・ケース」で、ギターを収納するケースにアンプが内蔵されたものであった。
At its peak, in 1964, Danelectro had 500 employees and annual sales of nearly $600 million. In 1966, Mr. Daniel sold the business to MCA but remained head of the company. In 1969, MCA closed the company down.
ダンエレクトロは1964年のピーク時には従業員数500人を抱え、年間売上高は6億ドルに到達しようとしていた。1966年にダニエル氏はMCA(Music Corporation of America 現ユニバーサル・ミュージック)に事業を売却したが、会社の責任者として残った。1969年にMCAは会社を閉じた。
In 1974, Mr. Daniel retired and moved to Honolulu, where he tried to come up with a solution to the lack of a ferry service between the Hawaiian Islands. In 1978, he designed a craft called the Superoutrigger; eight years later he launched a 58-foot demonstration model but he was not able to attract investors.
1974年にダニエル氏は引退してホノルルへと移住、そこで彼はハワイ諸島間の客船運行上にある欠点(暴風による転覆を回避するために度々欠航となってしまうこと)の解決に迫った。1978年にスーパーアウトリガーと呼ばれる舷外浮材を設計し、8年後には58フィートの試作品を発表したものの、投資家をひきつけることはできなかった。
Besides, his son, Howard, he is survived by his wife, Connie, and three grandchildren, all of Honolulu, and two sisters, Sally Rose of Valley Stream, L.I., and Ray Sobel of Levittown, L.I.
彼の遺族には息子のハワード以外に、妻コニーと三人の孫がホノルルにいて、ヴァレーストリームにはサリー・ローズ、レヴィットタウンにはレイ・ソベルという二人の姉妹がいる。(ヴァレーストリームもレヴィットタウンもニューヨークのロングアイランドにある住宅地)。