「こんにちわァ、テディちゃでス!
いつのまにィかァ、なつやすみィ~??」
「がるる!ぐるがるぐるる~!」(←訳:虎です!まだ梅雨なのに~!)
こんにちは、ネーさです。
7月後半になってチビっ子たちも夏休み突入!のはずが、
今日の多摩地域は空気ひんやり、
濃霧で景色はぼんやり……
ならば、本日の読書タイムは
こんなお天気によく似合いそうな一冊を、
さあ、どうぞ~♪

―― 黒澤明の羅生門 ――
著者はポール・アンドラさん、原著は2016年に、
画像の日本語版は2019年5月に発行されました。
英語原題は『KOROSAWA'S RASHOMON』、
『フィルムに籠めた告白と鎮魂』と日本語副題が付されています。
「めいさくゥでスねッ!」
「ぐるるるるがるるぐるる!」(←訳:日本映画の大傑作だよう!)
映画『羅生門』――
言うまでもありません、
黒澤明さんの代表作のひとつ、ですね。
1951年、ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞し、
黒澤さんの令名は一気に世界へと広がり、
また、日本映画が国際的に注目される契機となった作品です。
『羅生門(RASHOMON)』は、
英語読みだと『らしょうもん』、
イタリア語読みだと『らじょうもん』となって、
この響きがとてもミステリアスで魅了されたのだと、
フェデリコ・フェリーニ監督が
かつてインタビューで述べていましたが。
ここにも、
『RASHOMON』に魅せられた映画人さんが、ひとり。
「めんみつゥにィ、ぶんせきィ~!」
「がるぐるるる!」(←訳:徹底してます!)
現在はコロンビア大学の教授である著者・アンドラさんの専攻は、
日本文学、映画、批評、アジアの人文科学。
この御本は、
『羅生門』をテーマにしての映画研究本……
とは、ちょっと違って。
映画『羅生門』を入り口に、
黒澤明さんを論ずる《クロサワ論》
というべきでしょうか。
「かぎにィなるゥのはァ、しょうねんじだいィ?」
「ぐるるるるがるるる!」(←訳:お兄さんがいたんだ!)
著者・アンドラさんは
黒澤さんの『蝦蟇の油――自伝のようなもの』
を読み込み、
他にも多くの資料にあたって、
黒澤少年の心を占めた兄との関係、
その後の人生への影響の深さを検証してゆきます。
サイレント映画の弁士さんをしていた兄。
黒澤さんが映画を撮っていた時期、
既にサイレントは過去のものとなっていましたが、
黒澤さんのフィルムの中には、
『羅生門』の映像には、
サイレント映画の要素が確かに存在する。
白と黒の、あの画面は、
兄にふり回された少年時代の記憶の残像……?
「いつもォ、こころのォどこかにィ~…」
「がるるるる……?」(←訳:お兄さんが……?)
『羅生門』だけでなく、
『生きる』を、
『七人の侍』を、
アンドラさんは解析してゆきます。
黒澤明さんを動かし、
映画を創らせた原動力とは何であったのか。
「しらなかッたことォ、いろいろあッたでス!」
「ぐるるがるる!」(←訳:新発見でした!)
黒澤さんが、
映画にしなかったことをもっとも後悔したとされるのは
『平家物語』――
と本文66ページに書かれていて、
私ネーさ、唸りました。
ああ、そうかぁ、
黒澤さんは『平家物語』を撮りたかったのかぁ……
もし作っていたとしたら、
配役はどうなっていたでしょう?
『平家物語』のどのエピソードが中心になるの?
平家と源家、どちらの視点で描くの?
「ぎもんッ、つきませんッ!」
「がるぐるぅるる!」(←訳:想像しちゃうね!)
御本の冒頭には、
チャン・イーモウさんによる
『序文 闇の中の光』
が収録されています。
この文章が素晴らしいので、
どうか映画マニアの皆さま、
しっかり序文を読んでから
本文に取り掛かってくださいね。
訳者・北村匡平さんによる『訳者あとがき』も
必読ですので、ぜひ~♪
いつのまにィかァ、なつやすみィ~??」
「がるる!ぐるがるぐるる~!」(←訳:虎です!まだ梅雨なのに~!)
こんにちは、ネーさです。
7月後半になってチビっ子たちも夏休み突入!のはずが、
今日の多摩地域は空気ひんやり、
濃霧で景色はぼんやり……
ならば、本日の読書タイムは
こんなお天気によく似合いそうな一冊を、
さあ、どうぞ~♪

―― 黒澤明の羅生門 ――
著者はポール・アンドラさん、原著は2016年に、
画像の日本語版は2019年5月に発行されました。
英語原題は『KOROSAWA'S RASHOMON』、
『フィルムに籠めた告白と鎮魂』と日本語副題が付されています。
「めいさくゥでスねッ!」
「ぐるるるるがるるぐるる!」(←訳:日本映画の大傑作だよう!)
映画『羅生門』――
言うまでもありません、
黒澤明さんの代表作のひとつ、ですね。
1951年、ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞し、
黒澤さんの令名は一気に世界へと広がり、
また、日本映画が国際的に注目される契機となった作品です。
『羅生門(RASHOMON)』は、
英語読みだと『らしょうもん』、
イタリア語読みだと『らじょうもん』となって、
この響きがとてもミステリアスで魅了されたのだと、
フェデリコ・フェリーニ監督が
かつてインタビューで述べていましたが。
ここにも、
『RASHOMON』に魅せられた映画人さんが、ひとり。
「めんみつゥにィ、ぶんせきィ~!」
「がるぐるるる!」(←訳:徹底してます!)
現在はコロンビア大学の教授である著者・アンドラさんの専攻は、
日本文学、映画、批評、アジアの人文科学。
この御本は、
『羅生門』をテーマにしての映画研究本……
とは、ちょっと違って。
映画『羅生門』を入り口に、
黒澤明さんを論ずる《クロサワ論》
というべきでしょうか。
「かぎにィなるゥのはァ、しょうねんじだいィ?」
「ぐるるるるがるるる!」(←訳:お兄さんがいたんだ!)
著者・アンドラさんは
黒澤さんの『蝦蟇の油――自伝のようなもの』
を読み込み、
他にも多くの資料にあたって、
黒澤少年の心を占めた兄との関係、
その後の人生への影響の深さを検証してゆきます。
サイレント映画の弁士さんをしていた兄。
黒澤さんが映画を撮っていた時期、
既にサイレントは過去のものとなっていましたが、
黒澤さんのフィルムの中には、
『羅生門』の映像には、
サイレント映画の要素が確かに存在する。
白と黒の、あの画面は、
兄にふり回された少年時代の記憶の残像……?
「いつもォ、こころのォどこかにィ~…」
「がるるるる……?」(←訳:お兄さんが……?)
『羅生門』だけでなく、
『生きる』を、
『七人の侍』を、
アンドラさんは解析してゆきます。
黒澤明さんを動かし、
映画を創らせた原動力とは何であったのか。
「しらなかッたことォ、いろいろあッたでス!」
「ぐるるがるる!」(←訳:新発見でした!)
黒澤さんが、
映画にしなかったことをもっとも後悔したとされるのは
『平家物語』――
と本文66ページに書かれていて、
私ネーさ、唸りました。
ああ、そうかぁ、
黒澤さんは『平家物語』を撮りたかったのかぁ……
もし作っていたとしたら、
配役はどうなっていたでしょう?
『平家物語』のどのエピソードが中心になるの?
平家と源家、どちらの視点で描くの?
「ぎもんッ、つきませんッ!」
「がるぐるぅるる!」(←訳:想像しちゃうね!)
御本の冒頭には、
チャン・イーモウさんによる
『序文 闇の中の光』
が収録されています。
この文章が素晴らしいので、
どうか映画マニアの皆さま、
しっかり序文を読んでから
本文に取り掛かってくださいね。
訳者・北村匡平さんによる『訳者あとがき』も
必読ですので、ぜひ~♪



















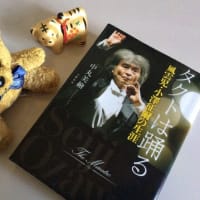





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます