日中の風邪が止んで、雨が降り出した。
昼間より暖かくなって14℃。ストーブもいらない。
しかし、明日の最高気温は6℃の予報。10℃近く下がるようです。
ダウン症の息子は11月27日に二十歳になりました。
いろいろ いろいろあって、ここまできました。
“やっときた”というよりは、その時その時の流れに、周りの人たちの支援を受けながら流されてきたので、大変さを強調するような気にはなりません。
ところで、やっと障害者年金をもらえることになりますが、提出書類が大変です。
きょうは、診断書を書いてもらう医師から、本人と親と施設の担当者が呼ばれて日常の生活の様子などを聞かれました。
ありのままのことを伝えましたが、この書類で障害者としての級が決定されるので、とても大事な面接になるのです。
一旦決定されると、実態が重くても変更されなくなるのでとても大事な面接だったのです。
社会全体が不安定です。そんな社会の中では、障害者の存在は邪魔になります。
来年には、障害者自立支援法の見直しがなされることになっていますが、障害者も安心して生活できる社会にしていかねばなりません。
当面、今の自・公政治を、国民に目を向ける政治に変えるしかありません。
昼間より暖かくなって14℃。ストーブもいらない。
しかし、明日の最高気温は6℃の予報。10℃近く下がるようです。
ダウン症の息子は11月27日に二十歳になりました。
いろいろ いろいろあって、ここまできました。
“やっときた”というよりは、その時その時の流れに、周りの人たちの支援を受けながら流されてきたので、大変さを強調するような気にはなりません。
ところで、やっと障害者年金をもらえることになりますが、提出書類が大変です。
きょうは、診断書を書いてもらう医師から、本人と親と施設の担当者が呼ばれて日常の生活の様子などを聞かれました。
ありのままのことを伝えましたが、この書類で障害者としての級が決定されるので、とても大事な面接になるのです。
一旦決定されると、実態が重くても変更されなくなるのでとても大事な面接だったのです。
社会全体が不安定です。そんな社会の中では、障害者の存在は邪魔になります。
来年には、障害者自立支援法の見直しがなされることになっていますが、障害者も安心して生活できる社会にしていかねばなりません。
当面、今の自・公政治を、国民に目を向ける政治に変えるしかありません。













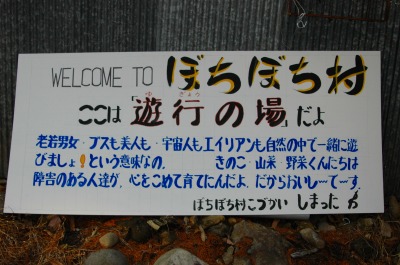


 分解したいのですが、30年以上になるので鉄製のネジは錆びついて取れません。
分解したいのですが、30年以上になるので鉄製のネジは錆びついて取れません。

