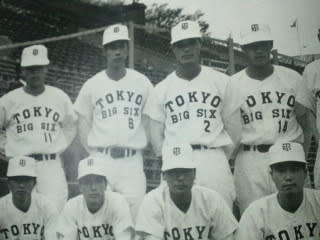
私が在学中の早稲田の法学部では、履修科目の登録は年一度。
つまり、春に履修科目を登録すると、語学と体育を除いて、試験は翌年1月に行なわれる一度っきりでした。
また、語学の試験の多くは6月の月末前後に行なわれましたので、7月早々から実質的に夏休みに入りました。
既に語学の履修を終えた上級生たちは、6月下旬に帰省してしまい、郷里で夏のアルバイトに励むことも少なくありませんでした。
当時、多くの運動部では、7月を集中的な基礎練習にあて、8月からは実戦形式の練習メニューを増やして、9月から始まる公式戦に備えました。
すなわち、夏の本格的な練習期間が約2ヶ月間確保できていたわけです。
以前にも話題にしたことがありますが、現在は、1年を2つの学期に分け、各学期で授業を完結して単位を取得する制度、いわゆるセメスター制度が早稲田でも幅広く導入されているようです。
具体的には、4年間で8セメスターに分けることで、学生の科目選択自由度が高まるメリットがあり、学部によっては6セメスターで単位取得が可能なシステムを採用するケースが多いのだそうです。
単位を取得しないで済むセメスターを設けることができるので、かつての通年授業では多くの困難が伴った、海外留学や社会活動に参加することが可能となるメリットもあるとのことです。
ただし、このセメスター制度によって、7月に多くの科目で試験やレポート提出が必要となりました。
そして、後期の授業開始時期は、セメスター制導入にあわせて9月の月末あたりに遅らされましたけれど、スポーツの各競技の公式戦日程は、従来と変わらずに9月前半に始まります。
したがって、早稲田の運動部が本格的な夏の練習を行なうのは、8月の一ヶ月間のみとなってしまいました。
その貴重な一ヶ月間に、日米大学野球などの催しも行なわれます。
セメスター制度を導入していない大学では従来と特に変わることはないのですから、仕方ないことなのでしょう。
でも、少なくとも早稲田については、夏の練習時間を削られることは本当に痛いです。
大学ジャパンに参加することで、もちろん得ることも多いのでしょうけれど、練習時間を削られる悪影響も、決して無視できるものではないからです。
週べ今週号で、石田雄太さんが、崩れたフォームを修正しようと理想を掲げるも、目先の勝利を主将として優先せざるを得なかった斎藤佑樹投手に、ピッチャーとしての未来を大事にしてほしいとおっしゃっています。
私も全く同感で、そのためには、1日でも多く東伏見で汗を流して、万全のコンディションで秋季リーグ戦に臨んでもらいたいと、そして秋のリーグ戦が終わった時に、早稲田ナインが「最高のシーズンでした。」と、嬉し涙を流して欲しいと心から願うものです。
このような状況を考えるに、大学ジャパンなど公式戦以外の試合は、できる限り秋季リーグ戦終了後の日程としてもらいたいと、私は思っています。
それが難しいならば、セメスター制度という新しい時代の要請に応えて、二週間程度、秋季リーグ戦の日程を後ろにズラすべきです。
そもそも大学の夏休み期間中にリーグ戦を開幕しても、学生さんたちが神宮に大勢集まるはずもないですから。
大学野球は、プレーする、あるいは応援する現役の学生さんたちが一番やりやすいような日程で開催されるべきです。
さて、1965年(昭和40年)、マニラで第6回アジア野球大会が開催されましたのは、秋季リーグ戦が終わった12月のことでした。
この派遣チームを選考するために、東京六大学、東都、首都、神奈川五大学、愛知大学、関西大学連合、九州六大学の選抜チームによる選考試合が、予選と決勝リーグ戦という形式で行われ、その結果、東京六大学の選抜チームが代表に選ばれ、本番のマニラでも見事に優勝しました。
直前の秋季リーグ戦で完全優勝していた早稲田から、多くのメンバーが参加しています。
監督:石井藤吉郎(早、水戸商業)
投手:
八木沢荘六(早、作新学院)
三輪田勝利(早、中京)
村井俊夫(明)
井出峻(東、都立新宿)
捕手:
大塚弥寿男(早、浪商)
田淵幸一(法、法政一高)

内野手:
小淵進(早、早実)
矢野洋制(早、松山商業)
小西亮之祐(早、天理)
西田暢(早、早実)
広野功(慶、徳島商業)
江藤省三(慶、中京商業。冒頭の写真の前列左から二人目)
池谷勝(立)
外野手:
林田真人(早、岡山東商業)
飯田修(早、高松一高)
萩原陸洋(早、甲府一高)
高田繁(明、浪商)

各リーグ同士の対抗心に火を点ける、このような選抜方法も、なかなか面白いアイデアだと思います。
つまり、春に履修科目を登録すると、語学と体育を除いて、試験は翌年1月に行なわれる一度っきりでした。
また、語学の試験の多くは6月の月末前後に行なわれましたので、7月早々から実質的に夏休みに入りました。
既に語学の履修を終えた上級生たちは、6月下旬に帰省してしまい、郷里で夏のアルバイトに励むことも少なくありませんでした。
当時、多くの運動部では、7月を集中的な基礎練習にあて、8月からは実戦形式の練習メニューを増やして、9月から始まる公式戦に備えました。
すなわち、夏の本格的な練習期間が約2ヶ月間確保できていたわけです。
以前にも話題にしたことがありますが、現在は、1年を2つの学期に分け、各学期で授業を完結して単位を取得する制度、いわゆるセメスター制度が早稲田でも幅広く導入されているようです。
具体的には、4年間で8セメスターに分けることで、学生の科目選択自由度が高まるメリットがあり、学部によっては6セメスターで単位取得が可能なシステムを採用するケースが多いのだそうです。
単位を取得しないで済むセメスターを設けることができるので、かつての通年授業では多くの困難が伴った、海外留学や社会活動に参加することが可能となるメリットもあるとのことです。
ただし、このセメスター制度によって、7月に多くの科目で試験やレポート提出が必要となりました。
そして、後期の授業開始時期は、セメスター制導入にあわせて9月の月末あたりに遅らされましたけれど、スポーツの各競技の公式戦日程は、従来と変わらずに9月前半に始まります。
したがって、早稲田の運動部が本格的な夏の練習を行なうのは、8月の一ヶ月間のみとなってしまいました。
その貴重な一ヶ月間に、日米大学野球などの催しも行なわれます。
セメスター制度を導入していない大学では従来と特に変わることはないのですから、仕方ないことなのでしょう。
でも、少なくとも早稲田については、夏の練習時間を削られることは本当に痛いです。
大学ジャパンに参加することで、もちろん得ることも多いのでしょうけれど、練習時間を削られる悪影響も、決して無視できるものではないからです。
週べ今週号で、石田雄太さんが、崩れたフォームを修正しようと理想を掲げるも、目先の勝利を主将として優先せざるを得なかった斎藤佑樹投手に、ピッチャーとしての未来を大事にしてほしいとおっしゃっています。
私も全く同感で、そのためには、1日でも多く東伏見で汗を流して、万全のコンディションで秋季リーグ戦に臨んでもらいたいと、そして秋のリーグ戦が終わった時に、早稲田ナインが「最高のシーズンでした。」と、嬉し涙を流して欲しいと心から願うものです。
このような状況を考えるに、大学ジャパンなど公式戦以外の試合は、できる限り秋季リーグ戦終了後の日程としてもらいたいと、私は思っています。
それが難しいならば、セメスター制度という新しい時代の要請に応えて、二週間程度、秋季リーグ戦の日程を後ろにズラすべきです。
そもそも大学の夏休み期間中にリーグ戦を開幕しても、学生さんたちが神宮に大勢集まるはずもないですから。
大学野球は、プレーする、あるいは応援する現役の学生さんたちが一番やりやすいような日程で開催されるべきです。
さて、1965年(昭和40年)、マニラで第6回アジア野球大会が開催されましたのは、秋季リーグ戦が終わった12月のことでした。
この派遣チームを選考するために、東京六大学、東都、首都、神奈川五大学、愛知大学、関西大学連合、九州六大学の選抜チームによる選考試合が、予選と決勝リーグ戦という形式で行われ、その結果、東京六大学の選抜チームが代表に選ばれ、本番のマニラでも見事に優勝しました。
直前の秋季リーグ戦で完全優勝していた早稲田から、多くのメンバーが参加しています。
監督:石井藤吉郎(早、水戸商業)
投手:
八木沢荘六(早、作新学院)
三輪田勝利(早、中京)
村井俊夫(明)
井出峻(東、都立新宿)
捕手:
大塚弥寿男(早、浪商)
田淵幸一(法、法政一高)

内野手:
小淵進(早、早実)
矢野洋制(早、松山商業)
小西亮之祐(早、天理)
西田暢(早、早実)
広野功(慶、徳島商業)
江藤省三(慶、中京商業。冒頭の写真の前列左から二人目)
池谷勝(立)
外野手:
林田真人(早、岡山東商業)
飯田修(早、高松一高)
萩原陸洋(早、甲府一高)
高田繁(明、浪商)

各リーグ同士の対抗心に火を点ける、このような選抜方法も、なかなか面白いアイデアだと思います。

















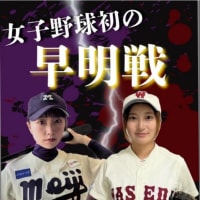







就任早々の春にリーグ優勝し1965年秋、1966年秋に優勝しました
1964年春の優勝での談話では「連ちゃん(石井連蔵監督)が基礎をしっかり叩き込んでくれたお陰だよ」と語っていました
投手 星野(明)山中(法)
野手は田淵、山本、富田、佐藤(法)谷沢、荒川、阿野、小田(早)
小野寺(明)島村(慶)秋山(立)など
荒川と富田が一番を打ったりしていますがクリーンアップは
谷沢・田淵・山本で固定でした。
長嶋時代には投手は及びませんが
主軸三人は凄いと思います。
なお小田選手は8番一塁でした。
松永さんが監督をしたと思いますが
楽しかったでしょうね。