どうしたことか。2週連続で丹波・篠山へ行った時のことを書いてみようと思う。
少し前のこと。
その日は、昼過ぎまで仕事をしていて、2時をまわってから家を出たので(車)、夕方前に到着。
いちばんの目的は、篠山城の堀端にある旧武家屋敷を改装して、うまれた『岩茶房丹波ことり』だった。
来訪は2度目だが、何年も前なので道を忘れてしまっている。
お堀の周りを2週くらい回って、ようやくiPhoneナビが指し示す小道がみつかり、
駐車場の案内がある。
店の前には柿の木があって、オレンジに熟した実がおいしそうに見えた。

古い古民家風の玄関を入ると、上がり口はギャラリーのようになっていて、
地元の作家さんの作品(ボタンやお皿、便箋、絵画用品のようなもの)や、海外の小さな用品も展示されている。
ここは、篠山駅からも少し離れた田舎町(城下町)だというのに、
どこから集まってこられたのか、40~70代くらいの大人のお客さんがこんなに!
それもご夫婦づれや家族づれで、お茶を飲みにこられているのが、いいなあと。
30分ほど待って奥へ案内していただいた。
都心では感じることのできない、静かで、心がはだかんぼうになるような時間。
縁側に近い席だったので、茫々とした庭が見える。
室内は、ゆったりと木のテーブルと椅子が配されていて、日本家屋独得の、不思議だけど味のある空間。
部屋と部屋を仕切るガラス戸は曇っていて、
昭和初期のような佇まいだった。
私たちは、武夷山でとれた茶葉を使う岩茶を注文。
3人で訪れたので、それぞれ3種を。

鉄羅漢(てつらかん)1400円
…鉄観音にも少し似た清浄な青茶のよい香り、奥深い後味が特徴。
鳳凰水仙(ほうおうすいせん)1100円
…茶葉にフルーツのような爽やかなさがあるやわらかいお茶。
佛手(ぶっしゅ) 800円
…重みはあるが飲みやすい番茶にも似た味わい。肝臓によい。
岩茶は始めてではないのだが、(神戸岩茶荘という店を仕事で取材したことがあった)、久しぶりだ。
中国茶や台湾茶に比べて、味わいが、やわらかい。
それに、ほんのり甘みもあって、青茶なのに「ほわん、」としている。
その「ほわん、」が体の中をしんしんと温めるので、私は昔よく飲み過ぎてお茶酔いしたものである。
岩茶とは、世界遺産に指定されている武夷山(中国大陸東南部の最高峰)という標高の高い山でしか採種されないお茶。
雲に届くほどの崖だった山々の岩肌に貼り付いた茶葉を収穫するのだから、
貴重で栄養価も高い。
そんな懐かしーいお茶を、いい茶器でいただけるのがここ「ことり」さんの、よいところ。


赤ちゃんを背なかにおぶった楚々とした女店主のお父様は、
日本を代表するスリップウエア(英国の古陶。器の表面を泥と粘土を程度な濃度に混ぜた化粧土で装飾して焼く)の
名手・柴田雅章さん。



表面の飴彩のこっくりとした色合いと、カドのないまるみの、
かたちの茶器は、やはり、いいなぁーと改めて思う。
茶には茶の、グレーにはグレーの。
この人の器でしか表現できない独得の品格のようなものに見惚れてしまう。
(柴田さんの器は、大山崎山荘美術館や大阪府島本町水無瀬にある「花染」で目にして以来、憧れる陶芸家のおひとりになりました)
この店の、お茶道具、用品はすべて、父上である柴田氏が丹精込めた、灰釉スリップウエアというのが、どれだけ贅沢なことか。
そう考えれば、お茶代も高くはなし。
店内の棚という棚には、さりげなく
柴田さんの花器や茶器などが整列されているのだから、こんなに豊かな気持ちでお茶をいただけるのかもしれない。

私たちは、お茶のほかに、
皮から手作り野菜まん・豚まん、ミルクまん、「馬拉カオ(マーラカオ)」(各300円)
ココナッツ豆腐、乾燥フルーツなども沢山いただいて、
ほっこりした気持になって店を後にした。
お茶は、ひとり10煎以上いただいたと思う。


相方が、お茶代とは思えない金額だね、といっていたのを、
聞こえないフリして鼻うたをふん、ふーんと、唄ってやりすごす。
それから、国道173号線をまっすぐ北上し、京都府との境にある草山温泉(観音湯)ということころまで足を延ばし、
秋の山の香りを感じながら、外湯の金泉に入湯。
ほかに客が2名ばかり。2名!?
「みてごらん、この人たちきっと、お尻に尻尾あるよ」と、
いいながら湯浴み、する。おかしくてたまらない。
最後は私たちだけになったので、露天風呂で泳いでしまった。それくらい広~い秘湯の温泉だった。
虫の声と、ケモノのけはいがする不思議なお湯。
金泉だが有馬温泉より泉質は軽い。塩分濃度が海水に近いのだという。
しばしの、仕事の一服。秋の篠山を、愉しんだ。













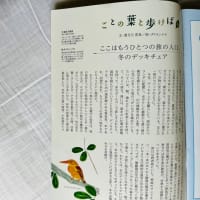







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます