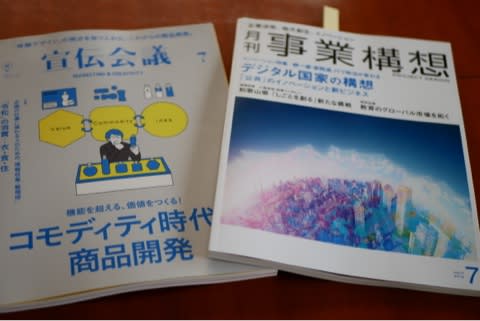高野山のバス停「奥の院前」で降りると、日射しが斜めに傾いて、いくぶん弱くなっていた。
「奥の院口」でバスを降りて一の橋コースを歩いていくと織田信長や豊臣家、徳川家の墓、武田信玄など戦国武将の墓を一堂に見ることができるという。
なので、本来は一の橋コースからの奥行き2キロにわたる高野山の「奥の院」を歩かせてもらうのが正式なルート。それでも私たちは、金剛峯寺の「阿字観瞑想」を体験して時計は夕方の4時をまわろうとしていて、「壇上伽藍」、「御影堂」までも足を延ばしてしまったので今回は仕方なし。次回は宿坊に宿泊するか、「奥の院」を先にまわるコースを執ろうと決めた。
Yちゃんとふたり、てくてくと霊山・高野山を登っていく。
後ろにもう一組いらしたはずなのに、振り返ると人の気配はすでになかった。
見上げると、白い空からおびのような光が差し込んでいるのがみえてほっとする。
白がたくさん溶けた水色の空。中の橋コースも道の両端には広大な墓地だ。Yちゃんが、墓に刻まれた文字を時々、思い出したように読み上げる。
次第に杉の木立が深くなり、木の皮や葉のゆらぎ、木漏れ日で世界はつくられていく。墓地は混み合っていた。
戦国武将や江戸、明治、大正、昭和と近世の故人の墓が延々と続くのだろう。こうなれば、生きている人間より死んでいる人間のほうが圧倒的な数で迫り来る。霊場という雰囲気がぴったりだな、とぼんやりと遠い脳裏の彼方からそう思う。霊界へと続く道。
途中、石の橋をわたり細い道のほうに出る。
まだ、弘法大師御陵前に鎮座する燈籠堂はみえない。
墓地はさらに深く、石燈籠や墓石の苔も陰湿で暗い。
気配のなかを分け入って進む。足が重い。墓地はさらに深くなり、途中、大きなものに包まれて脳の波動が、あやめらえるような所にでくわす。よくわからないが、少し苦しいような…、微かな気配の波を感じる。こんなのは始めてだ。車酔いをしたように、脳裏のバランスがくずれた。一瞬だけ。
考えてみれば、刀一本で斬った、斬られたの時代を生き、葬られた人の墓が集積しているのだ。当然か。死者の哀しみに接したようだ。
Yちゃんが、「ほらね」「わかるでしょ」「しんどいでしょ」という。
Yちゃんは昨年の秋も、気分が悪くてずっと頭が痛かったのだそうだ。私は全くもって頭は痛くない。
Yちゃんは途中、何を思ったのか、白い立て看板の注意書きを全部大きな声で暗唱しはじめるので、大急ぎで止めた。
10分くらい押し黙ったまま、もくもくと歩くと、ほんのりオレンジの明かりが遠くにかすんで見えた。もうひとつ石の橋を渡る、御陵橋だ。
あぁ、御代の国か。杉木立が林立しているむこうにぼーと霞んでいる。希望の灯のように。こうして燈籠堂に到着した。
目が痛くなるほどの線香の煙と香りにつつまれて、燈籠堂の前で手をあわせて中にはいった。
燈籠堂は、1964年に立て替えられた建物という。
弘法大師のあとを継いだ、第2世座主・真然大徳(しんぜんだいとく)によって創建。藤原道長氏が今の近い規模のものに建立したらしい。
オレンジの灯は無数の燈籠なのだった。昭和の時代にある宮様と首相の手によって献じられた昭和燈が燃え続け、たくさんの人の願いが込められた燈籠が奉納されていた。
沈んだ金地で精緻な彫と細工に包まれた燈籠の群は美しい。中には千年前から消えない灯もあるという。平安な心。墓地の先にこれほどの安泰で静謐な御堂が待ち受けていたとは。
御大師様の像がいらっしゃった。わたしたちは、深い安堵と満ち足りた幸福に包まれた。言葉はいらないほど、心の奥で感動していた。
燈籠堂を出て、周囲をまわる。裏手には弘法大師の御陵、手を合わせて参拝。燈籠堂内でも「消えずの火」の向こう側の窓越しに見える。Yちゃんに導かれて、さらにお経が響きわたる地下までおりていく。燈籠の灯り。通路の両側には小さな弘法大師像がずらりとならび、その数は5万体とのこと。
通路の先には奥行のある神聖なところがあり、正面には今も御大師様(弘法大師)がおわします、と聴いた。
この時刻、ちょうどオレンジの袈裟をきた僧が夕方の読経をあげる最中であったので、手を合わせて一礼だけして、すぐに地上へとあがった
そして、大黒堂にある納経所で御朱印を頂戴し、塔婆を求めて我が本家の先祖代々の名前を書いていただき、先祖供養をさせてもらった。
奥の院を訪れる前に、「金剛峯寺」で阿字観瞑想をしたのが本当によかったように思う。一仕事を終えた満足感である。父を近くに感じたのがうれしかった。あ、あ!お大師様を敬いながら、父が近くに来て見ていてくれるような、いい気配を覚えていた。(父の郷里は真言宗高野山の高照寺)
帰りは、バスで小田原通りまで下っていき、胡麻豆腐の老舗「濱田屋」でおみやげを買うことができた。これまで頂いた中で一番というお味(紹介したい)


バスの時間まで、あと少し。「みろく石本舗」で名物のやきもちと、くるみ餅で一服する。

不思議なことなのだが、奥の院を訪れてから、偶然にもバスやケーブルカー、電車が絶妙のタイミングでやってくる。まるで「ようきたな。気をつけてかえりよ」と御大師さんに、おくられているような心地で高野山をおりる。南海電車 高野線特急に乗り換えて座ってなんば駅まで帰る。