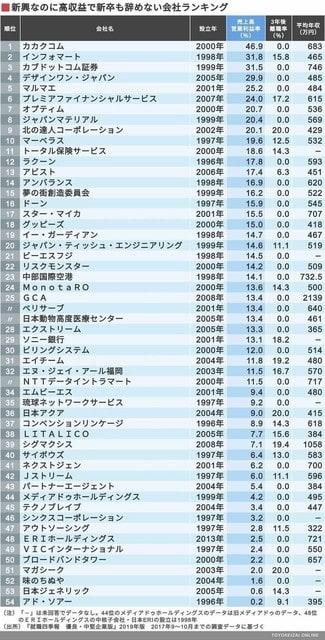裁量労働の拡大が国会で基礎調査不備、不正確などでとん挫したが、日経などのマスコミや経団連はこれでは生産性が向上しない等とコメントしている。裁量労働拡大は生産性を上げることができるのだろうか?裁量労働適用部門の生産性を上げるには、対象従業員のモラール(勤労意欲)が上がるかどうかに掛かっている。裁量労働イコール生産性アップではない。こんな簡単なことが判らないはずはない。適材適所の下、自分の裁量権を自由に持ち、働く意欲が出て来る職場を経営側が提供することが生産性向上への前提条件だ。
丁度、裁量労働法違反で野村不動産の営業社員が月180時間残業で自殺というニュースが報道された。野村不動産では違法と知りつつ営業部門に裁量労働を適用していたようだ。これを見ても経団連は裁量労働→時間に捕らわれないで働かせられる→見かけは生産性が上がっている。人手不足の折、旧来の1人当たり労働時間を無視した成果を無意識のうちに狙っていると思わざるを得ない。財界の労務部門日経連が経団連に吸収されてからおかしくなってきた。
高プロ制度と名前を変えた「ホワイトカラーイグゼンプション」にしても、経団連は年収制限を500万弱にしようなどと言い出している。安倍首相はこの高プロ制度は是非やると法案提出に意欲を燃やしているが、政府案の歯止め年収1075万円以上の高度専門職ということも、いったん法ができると適用が準専門職となり、年収の歯止めも経団連レベルに下がる可能性がある。
労働者派遣法でも当初は14業種の専門職に限っていたが、派遣の業務制限は拡大し、大きな禍根を残してる歴史がある。裁量労働制も入れた以上、拡大しようとしているし、高プロ制度も同じ歴史を繰り返すことは目に見えている。時間外労働が世界でも希なくらい多い日本では、生産性を上げるには1人1人が自分の仕事を見直し、有給も100%とり、休日をきちんと休み、労働時間を短縮するしかない。経営はそれを実現させる環境を作り上げることが必要で、働き方改革というかけ声だけでは過労死は防げない。