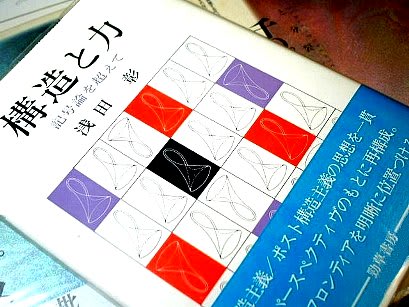
『構造と力-記号論を超えて』は、勁草書房より1983年に出版された現代思想の解説書。著者の浅田彰氏(現・京都造形芸術大学大学院長)が、京都大学人文科学研究所の助手時代に若干26歳で出版されたもので、難解な哲学書としては異例の15万部を超すベストセラーとなり、ある種の社会現象にまでなりました。これは80年代を覆った空気を考える際には、外せないもののひとつだと思います。
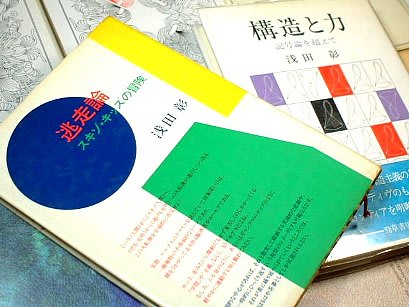
構造と力のブームを受けて、雑誌などに掲載されたエッセイや対談記事などを収めた『逃走論-スキゾキッズの冒険』(84年)。パラノとスキゾという言葉も流行語に。『チベットのモーツアルト』の宗教学者・中沢新一氏らとともに、ニューアカデミズムなどという言葉も。

構造と力は、フランス現代思想の構造主義やポスト構造主義を、チャート式に平易にまとめた解説本なのですが、その元ネタとなったドゥルーズ・ガタリの『アンチ・オイディプス』と『ミル・プラトー』。ドゥルーズ・ガタリとは、哲学者ジル・ドゥルーズと精神分析学者フェリックス・ガタリの共著によるもの。藤子不二雄みたいなもんですな。
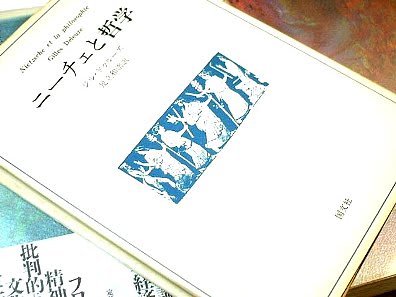
ドゥルーズ『ニーチェと哲学』。ドゥルーズの思想の根幹、元ネタとも言えるニーチェの研究本。もっと平易に書かれた『ニーチェ』という著作もあります。この本の日本語訳版は、裏表紙が何故か山口智子氏。
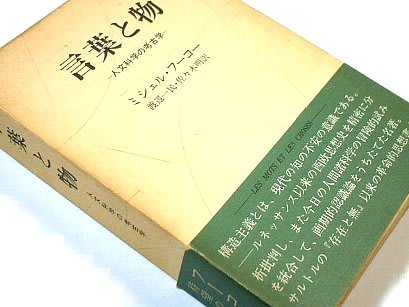
フランス現代思想の大御所、ミシェル・フーコーの『言葉と物』。他には『監獄の誕生』などが有名。

こちらも大御所ジャック・デリダの『エクリチュールと差異』。なんだかよくわからないけれど、脱構築という響きがかっこよすぎでした。
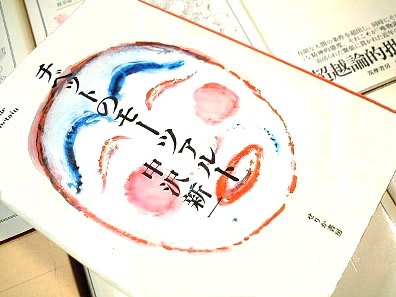
浅田氏と同じ頃にニューアカデミズムのスターとなった、宗教学者・中沢新一氏の『チベットのモーツアルト』

同じくニューアカデミズムのスターのひとりだった、柄谷行人氏の『ヒューモアとしての唯物論』

ポストモダンの代表的な思想家のひとりとされるジャン・ボードリヤール『象徴交換と死』

記号論などを論じたフランスの批評家ロラン・バルトの『物語の構造分析』。『テクストの快楽』なども有名。
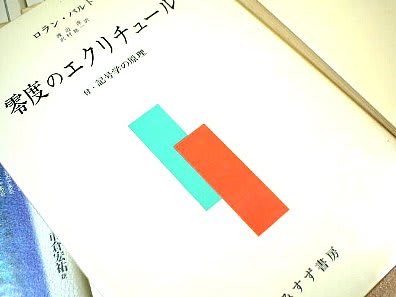
ロラン・バルト『零度のエクリチュール』。バルトには、日本を論じた『表徴の帝国』という本も。

蕩尽、祝祭などで有名なフランスの思想家ジョルジュ・バタイユ『呪われた部分 普遍経済学の試み』、『エロティシズムの歴史』

構造主義、ポスト構造主義の全ての発火点となった、社会人類学者レヴィ・ストロースの『野生の思考』。旅の記録をまとめた紀行文『悲しき熱帯』も有名。
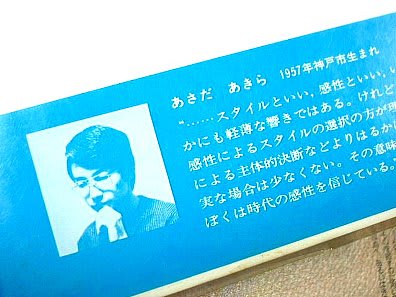
個人的な思い出としては、80年代のブーム当時には、リアルタイムでは知りませんでした。90年代に入ってから学校近くの古本屋などで見つけて、10年遅れではまることになりました。90年代頃にはブームのおかげもあってか、このような現代思想本が古本屋にちょうどゴロゴロ置いてありました。自分の学生の頃の気分といえば、これらの本と村上春樹氏だったように思い出します。
参考:Wiki ポスト構造主義、ニューアカデミズム、浅田彰、柄谷行人、中沢新一、ジル・ドゥルーズ、ミシェル・フーコー、ジャック・デリダ、ジャン・ボードリヤール、ロラン・バルト、ジョルジュ・バタイユ、レヴィ・ストロースの項













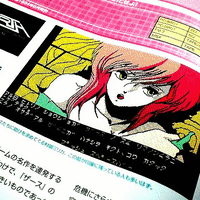




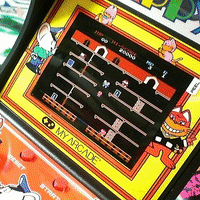

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます