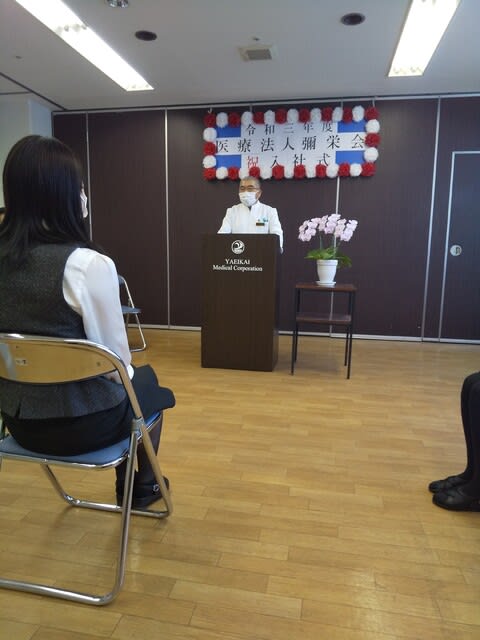今回は骨を強くする栄養素に注目してお話ししたいと思います。
丈夫な骨を作るのに必要な栄養素は、みなさんご存知の通り「カルシウム」がよく知られていますが、ビタミンD、ビタミンK、たんぱく質、その他マグネシウムやビタミンB群(ビタミンB6、B12、葉酸)なども大切な栄養素です。中でも特に心がけたいビタミンDとカルシウムについて紹介します。
1.
ビタミンD(1日にとりたい量) ※上限量は100μg/日

ビタミンDは、腸管からのカルシウムの吸収を助ける働きがあります。上記の図は1日にとりたい量ですが、1日に1回でも魚料理を食べると種類によりますが、まずまず補える量です。魚を食べない方は食べる方に比べて不足する傾向にあります。また、きのこ類・卵にも含まれています。ビタミンDは日光を浴びると私たちの皮膚でも作られます。しいたけは干すとビタミンDが増します。

ビタミンD不足が特に高齢者では多いそうです。65歳以上の高齢者の中でも施設入所や自宅にいることが多い方は日光を浴びる機会が非常に少なく、それを考慮して「骨折予防と治療ガイドライン2015年度版(日本骨粗鬆症学会)」では10~20μg/日の摂取を推奨しています。
ビタミンD不足は骨折のリスクを高めることはもちろんのこと、最近ではビタミンDの筋力維持における役割が注目され、転倒のリスクの1つであることがわかっています。
1日1回は魚料理・きのこ・卵を食べ、適度な日光浴を心がけましょう。
2.
カルシウム(1日にとりたい量) ※上限量は2500㎎/日

令和元年の「国民健康・栄養調査の結果」において、私たち日本人のカルシウム摂取量は1日505㎎で、上の図の1日にとりたい量に比べて不足しています。
全年齢で不足しており、特に15歳~59歳が少ない傾向です。
現在私たちは学校給食で、毎日牛乳を200ml飲む環境で育ちます。ところが牛乳・ヨーグルトなどの乳類の摂取量(g)に注目すると、15歳以降で徐々に減り、30代・40代では1日100gも満たない結果でした。
乳類は意識しないと、飲まない・食べられていないことがわかります。


※大豆に含まれるイソフラボンは骨粗鬆症の予防・改善に効果があると考えられています。
食事以外にホルモンバランスの変化など避けられない因子はありますが、それまでの骨の貯金は毎日の積み重ねです。成長期の極端なダイエットも将来の骨密度に悪影響を及ぼします。骨量・骨密度の維持のためには、バランスのいい食事に加え、毎日カルシウムを多く含んだ食品の摂取を心がけましょう。
参考文献:日本人の食事摂取基準2020年版、e-ヘルスネット(厚生労働省)
※医師から糖尿病や腎臓病などで食事指導を受けられている方は指導内容を優先してください。
http://www.yaeikai.com/medical-index.html
投稿者:やよいメディカルクリニック 管理栄養士 柑本