忘れていませんか? 牛は本来、自然の中で自分で生きていける動物だということを。人は自分の都合でこれを家畜にしました。農耕に必要なときは動物トラクターとして利用し、日本では耕耘機が普及したので和牛を肉用牛として改良して残してきました。しかも、和食に最適なスライス肉市場を確立して、霜降り肉を作り出し、今では和牛は霜降り肉の代名詞のように有名になり、誰もが霜降り肉の生産を目指すようになりました。
牛の放牧で自然と人、人と人を結ぶ

共役リノール酸 共役リノール酸(CLA)と抗アレルギー作用
しかし、時代が変わり里山や耕作放棄地の管理に牛が必要になってきました。ところが牛が必要になったとき、牛を飼育する農家がいなくなっていました。里山の資源を循環的に活用し、里山の公園化や獣害対策として牛の放牧に期待が寄せられています。里山で牛を放牧するには、おとなしくて放牧に慣れ、草をもりもり食べてくれる牛、そして子牛が元気に育つように乳も出て子育ての上手な牛が最高の牛です。
里山に面積(ha)当たり牛を0,5~1頭の放牧をすると、牛糞、草、昆虫、野鳥、微生物の生態系が肥沃な土と美しい景観を作り出してくれます。稲作の副産物である「米ぬか」は、大規模経営では保存できないので「脱脂米ぬか」の使用が常識となっていますが、地域で必要に応じて精米すれば、保存の心配をする必要がないので最高の飼料となります。
牛の繁殖は地域の自給飼料を基本に考えるべきです。牛を飼うために草を作るのではなく、地域資源を管理するために繁殖牛を飼うのが世界の常識です。アメリカでもオーストラリアでも、広大な不毛の土地に雌牛30頭に雄牛を1頭程度の割合で一緒に放牧することで、土地は肥沃になり、子牛が生まれて収入源となります。
高く売れる子牛生産を目指す日本の和牛生産は、肉質は世界一でも規模拡大により飼料基盤が脆弱となりました。家畜の飼育頭数の増加を目標としてきた畜産行政ですが、酪農家や乳牛頭数は減少し、バター不足が問題とされるようになりました。ビジネスは原料輸送、生産物の加工、販売という6次産業をシステムとして確立することで成立します。グローバル経済ではアメリカから中国への原料輸送も考えられます。輸入飼料に依存した日本の畜産の将来はどうなるのでしょうか。地域資源を活用するための畜産に考え方を変える時代が来ているのではないでしょうか。

草をつくるために牛を飼う アメリカのHRMに学ぶ

里山を管理するために牛を飼う 理想と現実のギャップをどう埋めるか
日本の里山は資源が豊富です。里山を放置すると草木が茂り、鹿やイノシシなどの獣害が増えます。一方、農村人口は減少し、高齢化が進んで耕作放棄地も増加していますので、これまでのように人手で里山を管理できなくなりました。牛やヤギや羊の出番です。稲わら、芋づる、野菜くず、河川敷等の野草の乾草など地域で自給できる飼料資源を地域で協力して利用すれば、牛やヤギなどが里山を管理し、美しい景観と地域の絆を与えてくれます。

乳牛も肉牛も草資源の活用の為に飼われているのが世界の常識です。アメリカやオーストリアでは砂漠化防止のために牛を飼っている牧場もあります。過放牧による砂漠化というのは、放牧管理を知らない人達が犯す誤りです。日本は国土は狭いけれども草資源には恵まれています。和牛は農耕用に家族の一員として、同じ屋根の下で1、2頭程度飼われていましたが、その役目を終り、世界一の霜降り肉として生き残っています。その特徴を活かして、乳牛に和牛を人工授精により交配して活力あるハイブリッドを生産し、そのF1雌牛を放牧して子牛生産している「富士山岡村牧場」があります。和牛が霜降り肉なら、放牧によるF1雌牛は健康なおいしい肉として、これからの酪農と肉牛生産を支えていくでしょう。
この「富士山岡村牧場」を目標として、牛を飼った経験がない地域の草刈隊が協力して、耕作放棄地の草の管理を中心にして、地域で放置していた稲わらを乾燥し、廃棄に困っていた芋づるや野菜くずなどを持ち寄ることで、自給飼料だけで繁殖牛を飼い子牛を生産することに成功している事例(大谷山里山牧場)があります。

大谷山里山牧場
反芻動物である牛は第一胃に生息するバクテリアと共生して、草を食べて生きています。放牧により、第一胃内のバクテリアも増加して牛乳や牛肉中の共役リノール酸も増加します。
経産牛放牧で肉質向上(中國新聞)
参考資料
肉用牛放牧の手引き」改訂版(近畿農政局畜産課)
山口型移動放牧マニュアル 放牧技術編
山村地域住民と野生鳥獣との共生
家畜の有毒植物と中毒(農研機構)
2014.12.11 ブログ移転更新 追加更新 2016.11.2
牛の放牧で自然と人、人と人を結ぶ

共役リノール酸 共役リノール酸(CLA)と抗アレルギー作用
しかし、時代が変わり里山や耕作放棄地の管理に牛が必要になってきました。ところが牛が必要になったとき、牛を飼育する農家がいなくなっていました。里山の資源を循環的に活用し、里山の公園化や獣害対策として牛の放牧に期待が寄せられています。里山で牛を放牧するには、おとなしくて放牧に慣れ、草をもりもり食べてくれる牛、そして子牛が元気に育つように乳も出て子育ての上手な牛が最高の牛です。
里山に面積(ha)当たり牛を0,5~1頭の放牧をすると、牛糞、草、昆虫、野鳥、微生物の生態系が肥沃な土と美しい景観を作り出してくれます。稲作の副産物である「米ぬか」は、大規模経営では保存できないので「脱脂米ぬか」の使用が常識となっていますが、地域で必要に応じて精米すれば、保存の心配をする必要がないので最高の飼料となります。
牛の繁殖は地域の自給飼料を基本に考えるべきです。牛を飼うために草を作るのではなく、地域資源を管理するために繁殖牛を飼うのが世界の常識です。アメリカでもオーストラリアでも、広大な不毛の土地に雌牛30頭に雄牛を1頭程度の割合で一緒に放牧することで、土地は肥沃になり、子牛が生まれて収入源となります。
高く売れる子牛生産を目指す日本の和牛生産は、肉質は世界一でも規模拡大により飼料基盤が脆弱となりました。家畜の飼育頭数の増加を目標としてきた畜産行政ですが、酪農家や乳牛頭数は減少し、バター不足が問題とされるようになりました。ビジネスは原料輸送、生産物の加工、販売という6次産業をシステムとして確立することで成立します。グローバル経済ではアメリカから中国への原料輸送も考えられます。輸入飼料に依存した日本の畜産の将来はどうなるのでしょうか。地域資源を活用するための畜産に考え方を変える時代が来ているのではないでしょうか。

草をつくるために牛を飼う アメリカのHRMに学ぶ

里山を管理するために牛を飼う 理想と現実のギャップをどう埋めるか
日本の里山は資源が豊富です。里山を放置すると草木が茂り、鹿やイノシシなどの獣害が増えます。一方、農村人口は減少し、高齢化が進んで耕作放棄地も増加していますので、これまでのように人手で里山を管理できなくなりました。牛やヤギや羊の出番です。稲わら、芋づる、野菜くず、河川敷等の野草の乾草など地域で自給できる飼料資源を地域で協力して利用すれば、牛やヤギなどが里山を管理し、美しい景観と地域の絆を与えてくれます。

乳牛も肉牛も草資源の活用の為に飼われているのが世界の常識です。アメリカやオーストリアでは砂漠化防止のために牛を飼っている牧場もあります。過放牧による砂漠化というのは、放牧管理を知らない人達が犯す誤りです。日本は国土は狭いけれども草資源には恵まれています。和牛は農耕用に家族の一員として、同じ屋根の下で1、2頭程度飼われていましたが、その役目を終り、世界一の霜降り肉として生き残っています。その特徴を活かして、乳牛に和牛を人工授精により交配して活力あるハイブリッドを生産し、そのF1雌牛を放牧して子牛生産している「富士山岡村牧場」があります。和牛が霜降り肉なら、放牧によるF1雌牛は健康なおいしい肉として、これからの酪農と肉牛生産を支えていくでしょう。
この「富士山岡村牧場」を目標として、牛を飼った経験がない地域の草刈隊が協力して、耕作放棄地の草の管理を中心にして、地域で放置していた稲わらを乾燥し、廃棄に困っていた芋づるや野菜くずなどを持ち寄ることで、自給飼料だけで繁殖牛を飼い子牛を生産することに成功している事例(大谷山里山牧場)があります。

大谷山里山牧場
反芻動物である牛は第一胃に生息するバクテリアと共生して、草を食べて生きています。放牧により、第一胃内のバクテリアも増加して牛乳や牛肉中の共役リノール酸も増加します。
経産牛放牧で肉質向上(中國新聞)
参考資料
肉用牛放牧の手引き」改訂版(近畿農政局畜産課)
山口型移動放牧マニュアル 放牧技術編
山村地域住民と野生鳥獣との共生
家畜の有毒植物と中毒(農研機構)
2014.12.11 ブログ移転更新 追加更新 2016.11.2










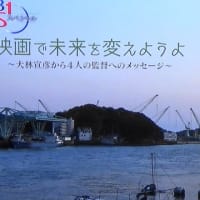



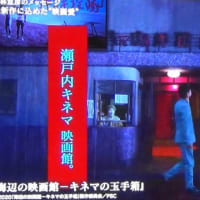
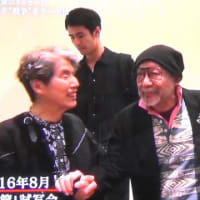

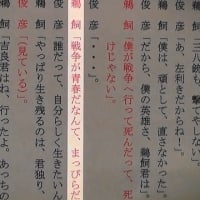



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます