2.アメリカのHRMに学ぶ
アメリカのフィードロットで様々な交雑種が肥育されていることはご存知の方も多かろう。 あるフィードロットのマネージャーが「農家が勝手に様々な牛を飼うので肥育素牛の能力が 不揃である」と嘆いているのを聞いたとき、私はそれを農家の意識の低さと聞きとり、日本は 技術力でアメリカに負けないぞと、内心ほくそ笑んだのを憶えている。
しかしその後、農家が繁殖牛を飼う意味を肥育素牛の生産という一つのモノサシでしか評価 していなかった自分の愚かさを、アメリカのHRM協会の農家から教えられることになる。
「個が一つの全体であると同時に、より大きな全体の部分として、全体との関連のなかで 成り立つ」というホロンの概念は、多くの分野に影響を与え、ホリスティック医学とかホリスティック教育 という言葉を耳にするようになってきた。HRMとは、ホリスティック・リソース・マネイジメントといって、生物,水,ミネラル,エネルギー などの資源(リソース)を、生態系や物質循環を考慮しながら、全体論的(ホリスティック)に管理 (マネイジメント)しようとする考え方である。
アメリカの牧場の新しい動き、HRM協会
パラダイムの転換(草を作るために牛を飼う,牛の搾乳)
HRMは、アメリカの牧場経営者を中心とした集まりである。HRMに関するテキストブックとワークブックが発行され、 牧場の経営と草地管理の方法が具体的に示されている。 また、牧場主を中心に研究者,行政関係者,教育関係者,自然保護に関係している人,弁護士,芸術家, 一般市民など、多様な分野の人達が参加してHRM協会が組織され、活動している。アメリカの牧場経営は放牧が 主体となるが、草地の状態が良くて同じ面積で飼える家畜頭数が増加すると収入も増加することになる。 また、草地の状態が良いと裸地も少ないことになるので、表土がエロージョンで失われることも少ない。 牧場が草で覆われるとき、牧場主も市民も健全な生活を営むことができるのである。 しかし、牧場が破綻するときには、表土が流失し水質を汚染することによって、市民生活も脅かされる。 彼らにとっては、牧場経営と市民生活は一体なのである。
HRMは、まずチームを大切にする。農家経営の場合にはチームは家族であり、さらに 周辺の人々がチームに加わることもある。HRM協会の場合は、農家と都市住民をメンバ ーとしたチームと言える。チームを大切にするとは、チームのメンバー全員の「生活の 質」を向上させることであり、そのためにメンバーの間でつねに「生活の質」の向上と は何か、というコミュニケーションが図られる。さらに、そのような生活の質を維持して いくためには、どのような「生産方式」が考えられるか、そしてどのような「生活空間(風 景,環境)」を創りだしていきたいのか。これらの3点を考えながら、チームが進むべき 目標を設定する。目標は実践の中で微調整しながら、目標から大きくはずれないように 進んでいこうとする。すなわち、HRMはチーム運営のための意思決定手法と言える。
また、HRMでは「自然の力」を大切にする。土壌微生物,昆虫,植物,家畜,水など の相互の関係をうまく活用することによって、土地を肥沃にすることを考える。例えば、 表土を深く耕起することは、さらされた表土を雨や風で損失するだけでなく、土壌微生物と そこに棲息する昆虫や小動物の世界をも失うことになるので、彼らは不耕起または浅く 耕起する方法を選択し、機械は自然の力を補完させるために最小限必要なときに使われる。 また、彼らは自然を守ることとは、自然を放置することではないと考えている。広い土地に放置された家 畜は、草のあるところに集り、草のないところには移動しないので、草のあるところは過放 牧となり、草のないところはますます砂漠化する。彼らは、家畜の頭数と土地条件を考え た牧柵管理に熱心であり、草のないところには、エサを撒いたりエサ場を作って家畜を誘 導している。彼らにとって「競争」は無縁の世界であり、自然との共生とコミュニティ ーの豊かさを両立させようとする世界がそこにある。
3.多くの顔を持つ牧場
アメリカのバージニア州にあるサルトン氏の牧場は、ポリフェイス(多くの顔を持つ) 牧場という名前がついている。日本語では「百姓」牧場と訳すのが良いかもしれない。 その名が示す通り採卵鶏,ブロイラ-,家兎,豚,肉牛を組合わせて、実に資源をうま く活用した経営が行われている。
サルトン牧場
肉牛を放牧肥育しているが、放牧後の草地には採卵鶏 とブロイラ-を移動しながら飼育し、さらにその後を追うように豚を移動していく。そ のことで草を最大限に活用しながら、施肥と耕起までやってしまう。この農法の発想の原 点は、「どうすれば儲かるか」ということではなく、「どうすれば家畜を飼いながら土を 肥沃にすることができるか」というところにあり、そのような視点で農業を考えると、 様々なアイデアが生れて、自由な農業の展開が可能になったと言う。
しかも、まず自給自足のための生産を行い、次に自信がついたら近所の人に食べてもらう。 さらに自信がついたから販売をする、というステップを踏むことによって、500人の消費者と直結した確かな販売ルートも確立されている。
ブロイラーの解体処理も家族で行っており、電話 と手紙の連絡により500km離れた所からも直接購買に来る業者もあるという。サル トン氏は、「販売に関しては立地条件なんて関係ないですよ」と快活に笑う。
13才になる彼の息子も家業を手伝っているが、その少年の生き生きとした逞しい姿と家族のくっ たくのない笑顔が今も脳裏を離れない。少年は学校には行っていない。日本の少年たち の幼稚さとこの少年の逞しさの間の大きなギャップに、教育とは何かという問題につい てあらためて深く考えさせられる。
戻る 次へ
アメリカのフィードロットで様々な交雑種が肥育されていることはご存知の方も多かろう。 あるフィードロットのマネージャーが「農家が勝手に様々な牛を飼うので肥育素牛の能力が 不揃である」と嘆いているのを聞いたとき、私はそれを農家の意識の低さと聞きとり、日本は 技術力でアメリカに負けないぞと、内心ほくそ笑んだのを憶えている。
しかしその後、農家が繁殖牛を飼う意味を肥育素牛の生産という一つのモノサシでしか評価 していなかった自分の愚かさを、アメリカのHRM協会の農家から教えられることになる。
「個が一つの全体であると同時に、より大きな全体の部分として、全体との関連のなかで 成り立つ」というホロンの概念は、多くの分野に影響を与え、ホリスティック医学とかホリスティック教育 という言葉を耳にするようになってきた。HRMとは、ホリスティック・リソース・マネイジメントといって、生物,水,ミネラル,エネルギー などの資源(リソース)を、生態系や物質循環を考慮しながら、全体論的(ホリスティック)に管理 (マネイジメント)しようとする考え方である。
アメリカの牧場の新しい動き、HRM協会
パラダイムの転換(草を作るために牛を飼う,牛の搾乳)
HRMは、アメリカの牧場経営者を中心とした集まりである。HRMに関するテキストブックとワークブックが発行され、 牧場の経営と草地管理の方法が具体的に示されている。 また、牧場主を中心に研究者,行政関係者,教育関係者,自然保護に関係している人,弁護士,芸術家, 一般市民など、多様な分野の人達が参加してHRM協会が組織され、活動している。アメリカの牧場経営は放牧が 主体となるが、草地の状態が良くて同じ面積で飼える家畜頭数が増加すると収入も増加することになる。 また、草地の状態が良いと裸地も少ないことになるので、表土がエロージョンで失われることも少ない。 牧場が草で覆われるとき、牧場主も市民も健全な生活を営むことができるのである。 しかし、牧場が破綻するときには、表土が流失し水質を汚染することによって、市民生活も脅かされる。 彼らにとっては、牧場経営と市民生活は一体なのである。
HRMは、まずチームを大切にする。農家経営の場合にはチームは家族であり、さらに 周辺の人々がチームに加わることもある。HRM協会の場合は、農家と都市住民をメンバ ーとしたチームと言える。チームを大切にするとは、チームのメンバー全員の「生活の 質」を向上させることであり、そのためにメンバーの間でつねに「生活の質」の向上と は何か、というコミュニケーションが図られる。さらに、そのような生活の質を維持して いくためには、どのような「生産方式」が考えられるか、そしてどのような「生活空間(風 景,環境)」を創りだしていきたいのか。これらの3点を考えながら、チームが進むべき 目標を設定する。目標は実践の中で微調整しながら、目標から大きくはずれないように 進んでいこうとする。すなわち、HRMはチーム運営のための意思決定手法と言える。
また、HRMでは「自然の力」を大切にする。土壌微生物,昆虫,植物,家畜,水など の相互の関係をうまく活用することによって、土地を肥沃にすることを考える。例えば、 表土を深く耕起することは、さらされた表土を雨や風で損失するだけでなく、土壌微生物と そこに棲息する昆虫や小動物の世界をも失うことになるので、彼らは不耕起または浅く 耕起する方法を選択し、機械は自然の力を補完させるために最小限必要なときに使われる。 また、彼らは自然を守ることとは、自然を放置することではないと考えている。広い土地に放置された家 畜は、草のあるところに集り、草のないところには移動しないので、草のあるところは過放 牧となり、草のないところはますます砂漠化する。彼らは、家畜の頭数と土地条件を考え た牧柵管理に熱心であり、草のないところには、エサを撒いたりエサ場を作って家畜を誘 導している。彼らにとって「競争」は無縁の世界であり、自然との共生とコミュニティ ーの豊かさを両立させようとする世界がそこにある。
3.多くの顔を持つ牧場
アメリカのバージニア州にあるサルトン氏の牧場は、ポリフェイス(多くの顔を持つ) 牧場という名前がついている。日本語では「百姓」牧場と訳すのが良いかもしれない。 その名が示す通り採卵鶏,ブロイラ-,家兎,豚,肉牛を組合わせて、実に資源をうま く活用した経営が行われている。
サルトン牧場
肉牛を放牧肥育しているが、放牧後の草地には採卵鶏 とブロイラ-を移動しながら飼育し、さらにその後を追うように豚を移動していく。そ のことで草を最大限に活用しながら、施肥と耕起までやってしまう。この農法の発想の原 点は、「どうすれば儲かるか」ということではなく、「どうすれば家畜を飼いながら土を 肥沃にすることができるか」というところにあり、そのような視点で農業を考えると、 様々なアイデアが生れて、自由な農業の展開が可能になったと言う。
しかも、まず自給自足のための生産を行い、次に自信がついたら近所の人に食べてもらう。 さらに自信がついたから販売をする、というステップを踏むことによって、500人の消費者と直結した確かな販売ルートも確立されている。
ブロイラーの解体処理も家族で行っており、電話 と手紙の連絡により500km離れた所からも直接購買に来る業者もあるという。サル トン氏は、「販売に関しては立地条件なんて関係ないですよ」と快活に笑う。
13才になる彼の息子も家業を手伝っているが、その少年の生き生きとした逞しい姿と家族のくっ たくのない笑顔が今も脳裏を離れない。少年は学校には行っていない。日本の少年たち の幼稚さとこの少年の逞しさの間の大きなギャップに、教育とは何かという問題につい てあらためて深く考えさせられる。
戻る 次へ










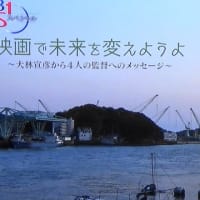



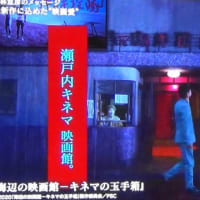
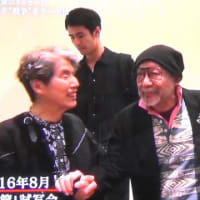

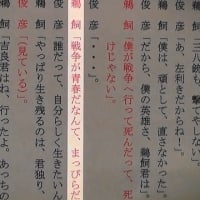



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます