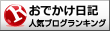群馬県沼田市に、生方鼎齋(ていさい)さんという、
1799年生まれの、書にたけた方がいて、
1799年生まれの、書にたけた方がいて、
優れた書家になってからは、
女性に飽きっぽいのか、
大間々でも、月夜野でも、
娘の婿に迎えられは離縁する。
女性に飽きっぽいのか、
大間々でも、月夜野でも、
娘の婿に迎えられは離縁する。
江戸に出てからは絵にも通じ描いたのは、
欄竹梅菊の水墨画・四君子。
欄竹梅菊の水墨画・四君子。
その方が描いたのかわからないのですが、
龍の絵。
襖を表装に出した時、見つかった下張りは、
ぎっしりと漢字ばかり。
ぎっしりと漢字ばかり。

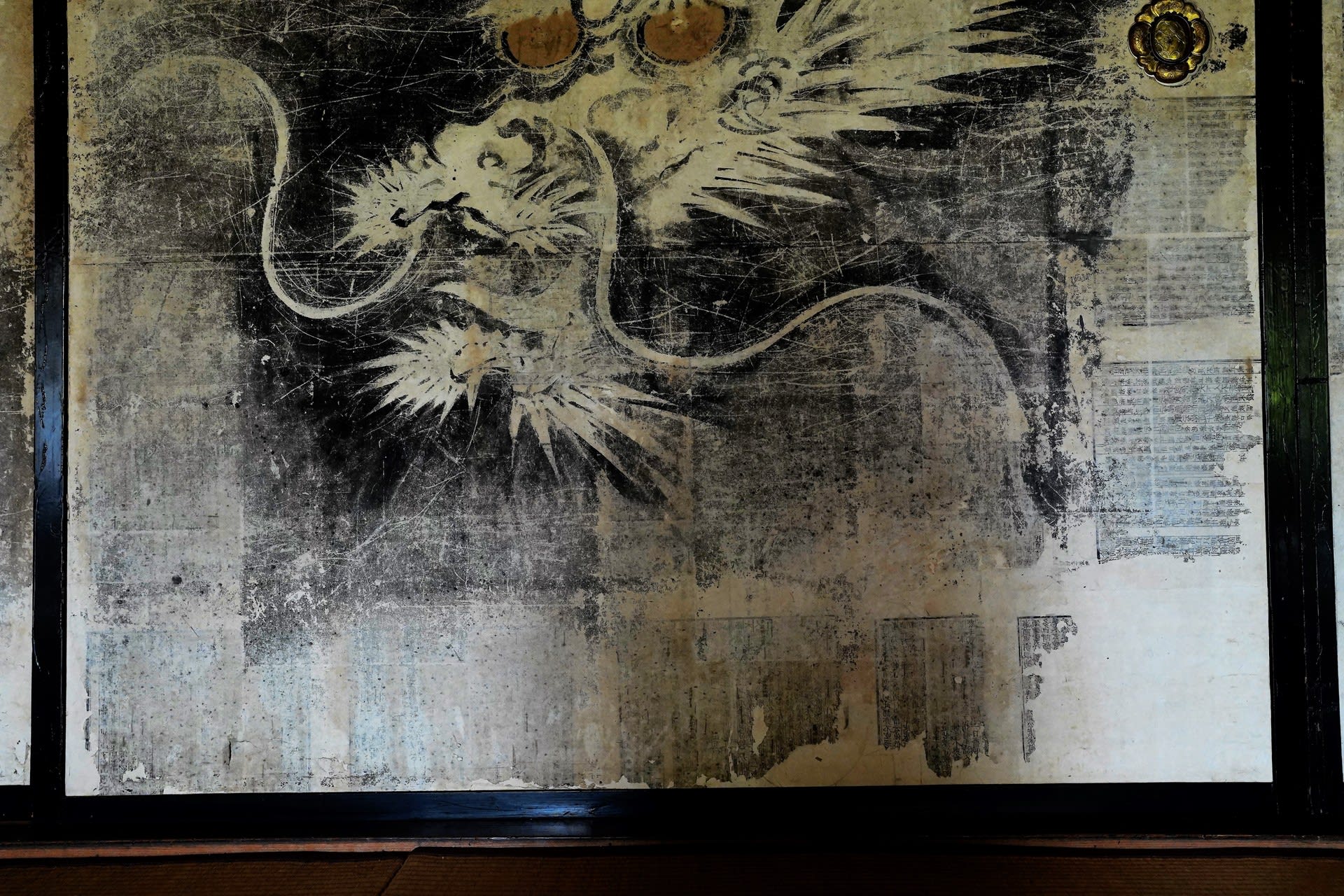
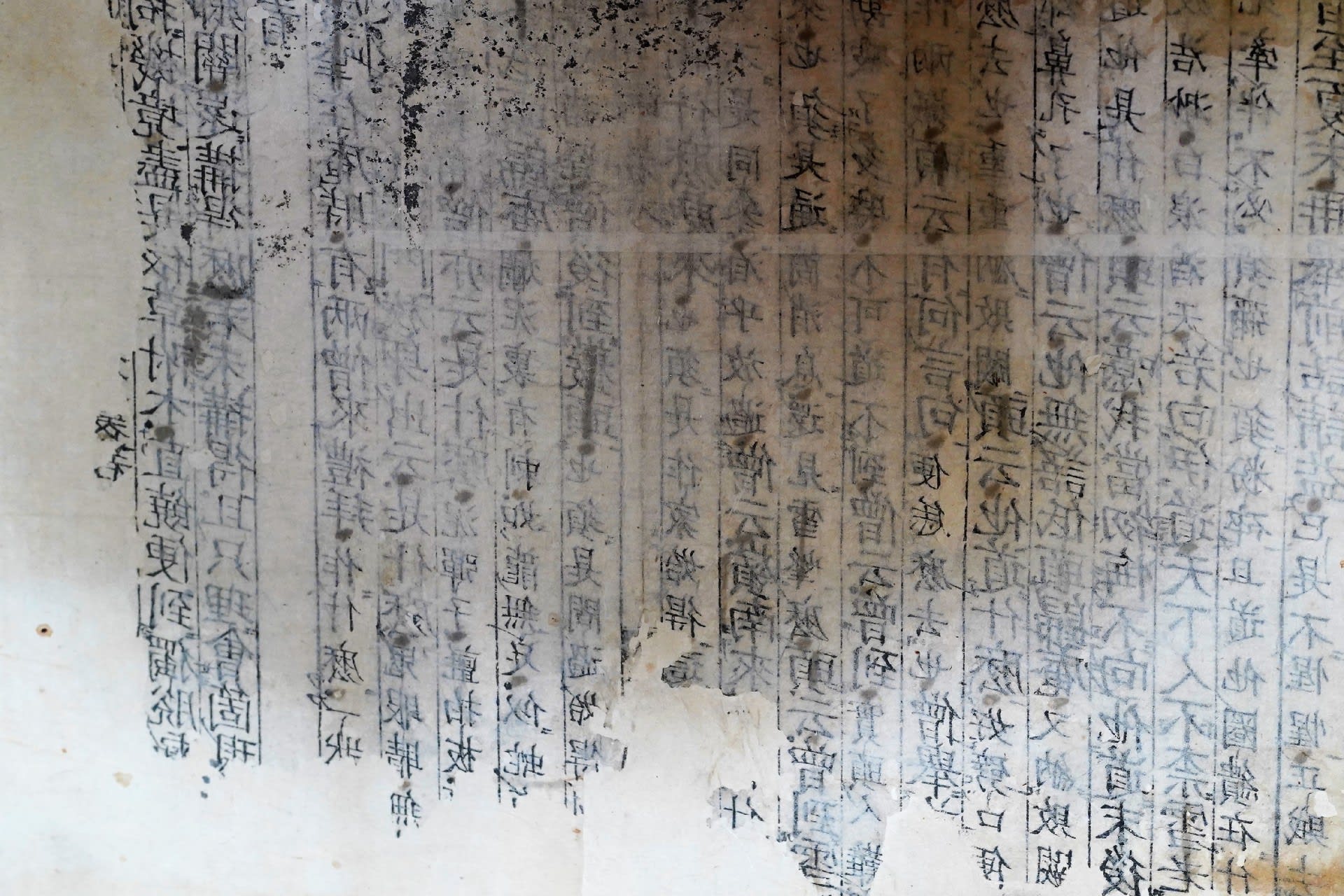
江戸後期の襖の秘密が、後年になって知ると、
当たらなくても、想像が膨らんできて、
小躍りしてしまいます。
当たらなくても、想像が膨らんできて、
小躍りしてしまいます。
👇生方鼎齋さんではないのです・・ね‼
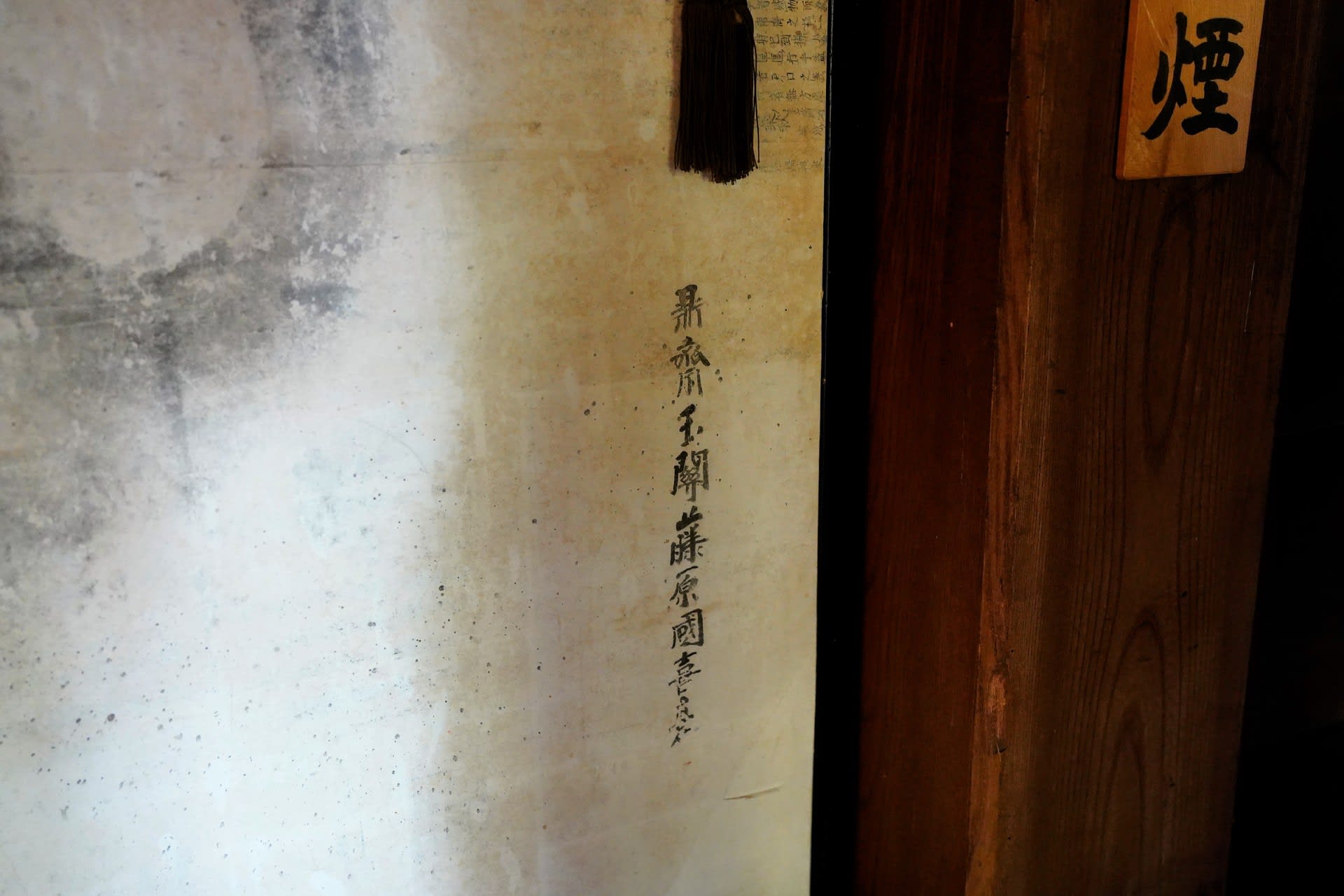


本堂台間の天井には
狩野法橋水春源義信さん・う~ん・の龍が
狩野法橋水春源義信さん・う~ん・の龍が

泰寧寺本堂には、
群馬県花輪村で生まれた、
高瀬忠七さんと繁八さんの彫刻が3点、
外陣欄間に・・1804年の作。
外陣欄間に・・1804年の作。
関口文次郎さんの兄弟弟子の、
高瀬万之助さんの子らで、彫り物師。
高瀬万之助さんの子らで、彫り物師。
👇中国伝説上の巣父許由をモチーフに。
♪1688年絵本宝鑑から♬


👇観瀑の図

内縁の欄間には、
平成の彫り物師の作が・。





桃山時代・江戸時代・平成と彫刻で時の証を残して
泰寧寺はこれから100年、200年と・・
泰寧寺はこれから100年、200年と・・

高瀬忠七さんを記事にしてます
見て頂きたいと思ってます
見て頂きたいと思ってます