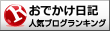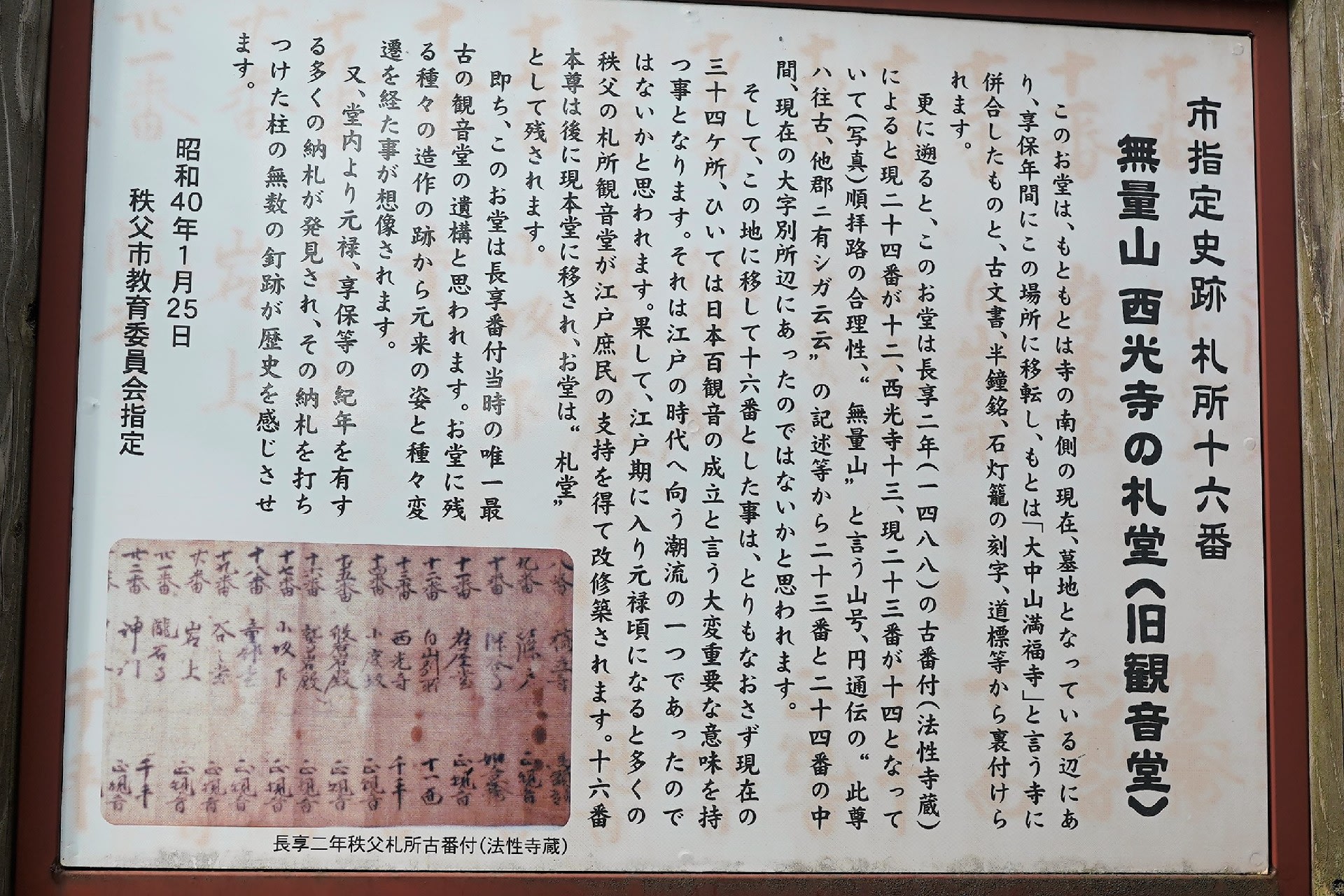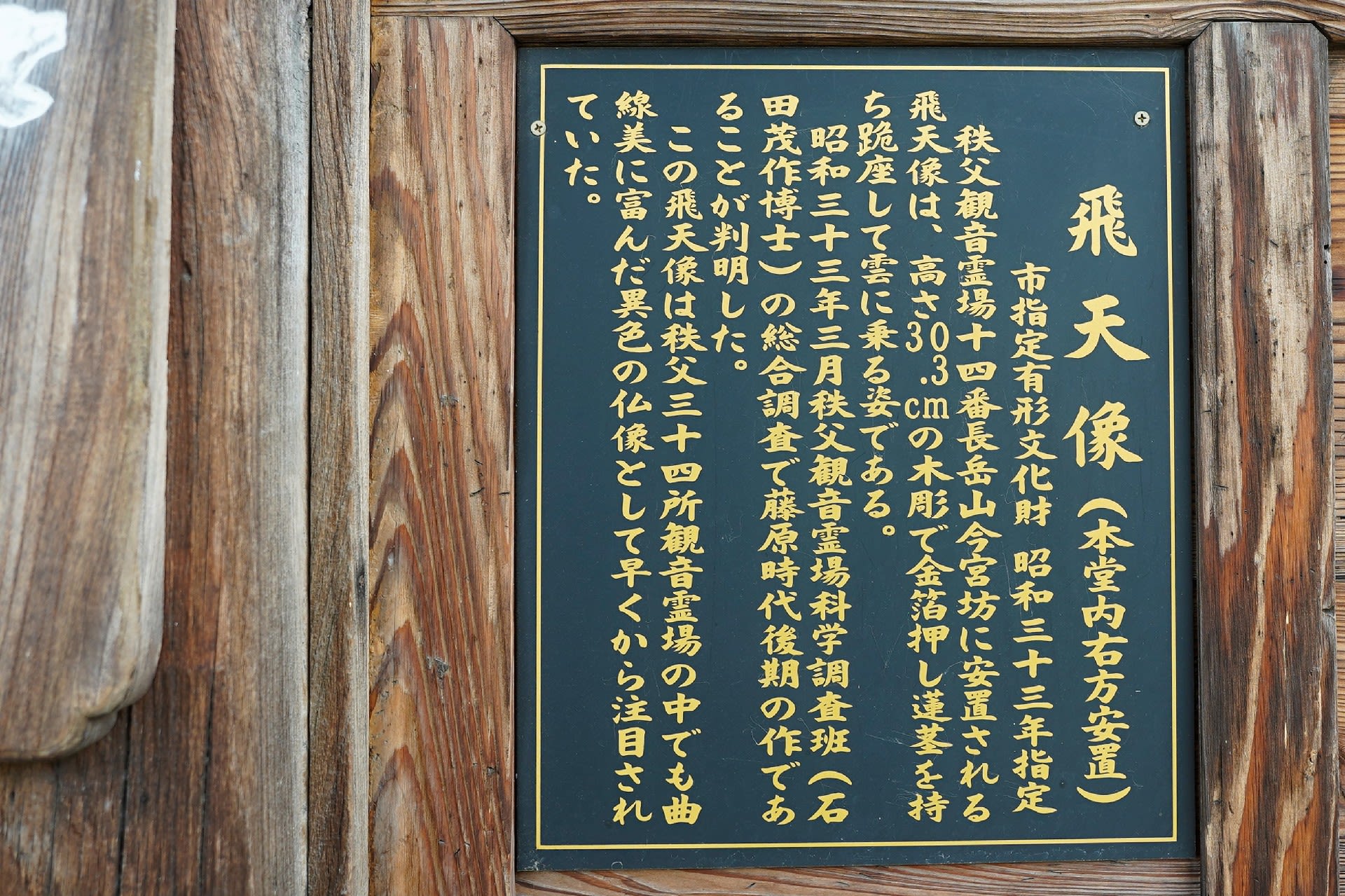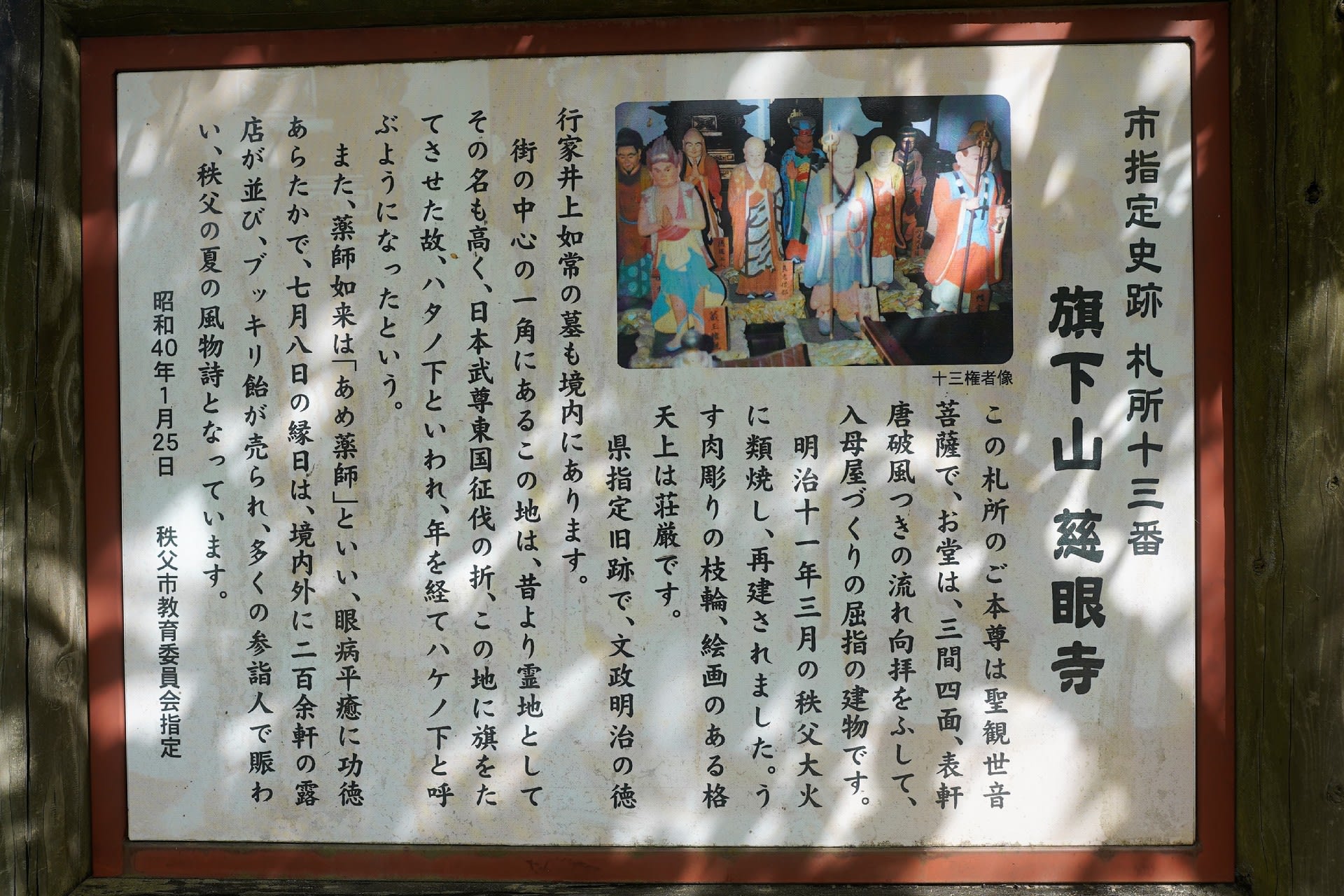昭和の1枚の写真、
10人ばかり、雪融けのわだちを、
菅笠、白衣、金剛杖に鈴を鳴らしてる巡礼の人たち。
車で、ひょいひょいと「巡礼です」と言うのも、
なんか、浅ましいよな気がして・・。
秩父霊場が最も盛んだったのは江戸時代で、
1750年の名主報告では、
正月から3月21日までに、
4万余の参拝者が訪れ、
1日約3000人余りの巡礼、
当時は日帰りもない頃ですから、
秩父領16か村で1万7千人の総人口で、
受け入れは容易ではなかったことでしょう。
👇の御夫婦に、秩父観光の二人と思いましたが、
あれよ、あれよで、聖観世音菩薩様に
きれいな響きの御詠歌、納経所で頂いた、
笈摺をきれいにたたんで・・。
看板👆今宮神社は、この場所から2~3分にあり、
神仏分離令のあおりに、ちと寂しい・・・。
納経所にはこんな👇人形が置かれ、
ほとんどの札所に置いてあります。
秩父の半世紀前は銘仙産業が盛んで、
夜の町もかなりの賑わいだったようで、
御朱印をいただいた後、寄り合いの夜の酒席、
資産家から、しこたま大人への、
語れない手ほどきをいただいたと・・。
宗教家から、なんかほっとした思い出話。
ここの先代の住職が、
さびれていく秩父巡礼を憂い、
民族博物館を作り、版画を集め、霊場の保存や巡礼への、
サービス機関として、奉賀界会を作成して、
今、注目されるようになさった方・・・。
各札所ご本尊の撮影は禁止されていて、
唯一撮ったもの・・・
撮ったのはあくまで飛天像・・で・・す・・ウン!
本来は長岳山正覚院金剛寺といい、
歴史は古く、平安時代・・
秩父札所14番・今宮坊