
稜線の深けた八王子
満月、おぼろでもまるく、
真夜中のシャワー、乾いた素肌が心地いい。
きょうは、まもなく眠りにつきましょう!


















☝ 写真 2018.4.29 箱根湿地園

稜線の深けた八王子
満月、おぼろでもまるく、
真夜中のシャワー、乾いた素肌が心地いい。
きょうは、まもなく眠りにつきましょう!


















☝ 写真 2018.4.29 箱根湿地園

今年の5月の休みは、誰もから誘いが、無く、
無ければ無いで、やはり少し寂しい。
得意なのは、誘われて「忙しい」と断るのが、
至福の瞬間だったけど、
無いとなると、やはりネ・・・つまらない。
必ず無謀な誘いだと判っても、声をかけてくる、
気が置けない仲間も今はおらず、
先方も、私が黄泉の国に行かなければ、
声もかけられないわけで・・・。
そんなこと、ふと浮べ、箱根湿地園まで出かけました。
花を見て名前を言う、
後であんちょこ・・ウン。
少しは利口になっている。
そんな一日、撮ったり、あんちょこ見たり、
ほとんど、家族連れ、一人は見当たらない、が、
のんびりと、仙石原を散歩です。

👇 姫シャガ

👇 オダマキ






👇 アメリカローバイ・においなし





☝ 写真 2018.4.29

建長寺を見学した後、道路を挟んで向かい側の、
こじんまりしたお寺に寄りました。
ここは長寿寺で、足利尊氏が邸宅跡に、建てたお寺で、
金、土、日曜日しか拝観できません。
簡素なたたずまいで、
小方丈から眺める庭のボタン、つつじやシャガ、が満開、
坐って庭を眺めていますと、
不謹慎ですが、ゴロリ、横になって肘枕で過ごしてみたくなります。















足利尊氏の遺髪を埋葬したお墓。


向こうに、観音堂が。




☝ 写真 2018.4.22



☝ 長寿寺の花 写真 2018.4.22
ムラーノ島
15世紀から19世紀
ガラスの可能性に挑戦し
奇跡のガラスを生んだ
パロヴィエール一族展
4月28日~11月25日
箱根ガラスの森美術館

高水準の透明ガラスが生み出されたのは、
15世紀中頃のヴェネチア。
アンジェロ・バロヴィエールは、
哲学者で錬金術に携わっていたパオロ・ダ・ペルゴラの下で、
ガラスの成分を研究し、透明なガラスの中でも、
より純度の高い「クリスタッロ」(水晶を意味するイタリア語)
と呼ばれるガラスを生み出しました。
アンジェロ・パロヴィエールや娘マリアの発明や研究は、
ヴェネチアン・グラスの礎となり、
その後の約3万色とも言われる色彩表現や、
透明なガラスと乳白色ガラスを捻じり合せて作られる
繊細優美なレース・グラス技法の発明につながり、
豊かな装飾に彩られた
ヴェネチアン・グラスの黄金時代を築き上げました。
※
取材で世界を撮っていらっしゃる、プロ写真家がいます。
針さす指に、漁を獲る夫の帰りを待つ、情景が、
ムラーノ島、数キロ先の海に浮かぶブラーノ島の、
レース編みの伝統を鮮やかに・・・。
お借りいたしました。
fujikuma-junさん
JFK-world世界の撮影・取材地トピック
Freelance Film Director
TV-CMおよびTVドキュメンタリー番組のディレクター & カメラマン

♫~♪
な~べ な~べ
そこぬけた~
そ~こが ぬけたら
かえりましょ
~♪♫♬
茶~壺 茶~壺
茶壺にゃ~蓋がない
底とって蓋にしょ
♪♫♬♪~

息づかい・所作


茶
すべてを敬い、もてなし清廉に日々を過ごし、
満開の花に、野辺の一輪。
雪間の緑の葉もまた春待つ緑の葉。
呼吸整え、見上げる半月も、また麗し。
・・・か・・・。



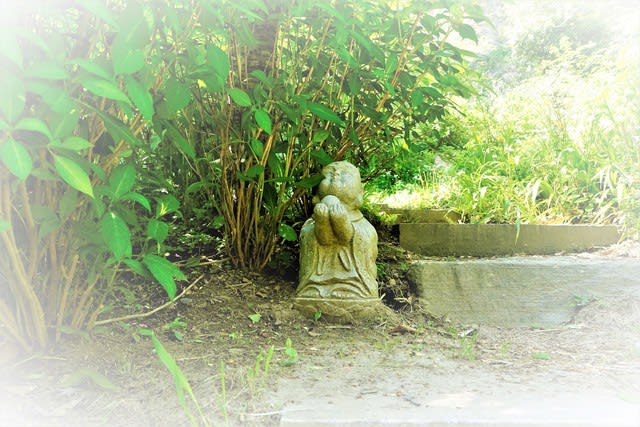
☝ 鎌倉・建長寺 写真 2018.4.22
ムラーノ島
15世紀から19世紀
ガラスの可能性に挑戦し
奇跡のガラスを生んだ
パロヴィエール一族展
4月28日~11月25日
箱根ガラスの森美術館


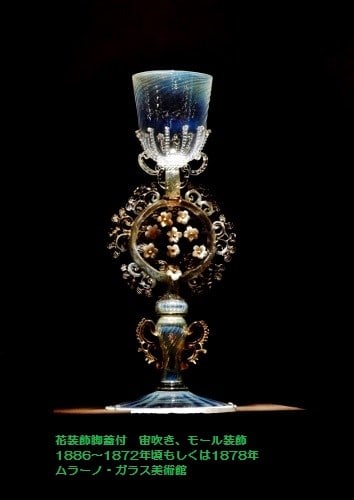




 ヶ
ヶ
建長寺、御深草天皇が定めた、
建長❝1249年❞の元号を頂戴したというもの。
三門を抜けると、仏殿があり、
写真現在の仏殿は、
徳川秀忠夫人の亡くなって20年、
芝増上寺の霊屋を造替した1647年の折に、
建長寺が譲り受けた建物、と。


贅沢に施された漆塗りの剥がれには、歴史の重みを感じます。

仏殿の後ろには、関東では最も大きい法堂が建っていて、

天井には、やや新しめの「龍」が輝いている。
聞けば2002年、日本画家が描いたとのこと、


ここで一服し、「未来・連福プロジェクト」収益で、
福島の子供を支援している、ボランティアの方が販売をしてた、
麦ごはんの酢飯と、柴漬け、切り干し大根、卵焼き、大福豆をおかずに、
お茶で腹ごしらえします。
唐門、本院寺務所を後にして、得月楼の
やはり「未来・連福プロジェクト」
裏千家・水野宗典氏を招いて、チャリティーお茶会に。

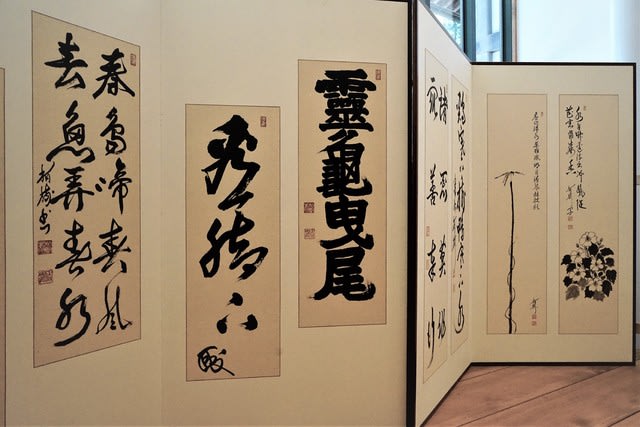
足を曲げ膝を折ることができない、私は、椅子に坐るのですが、
収益金は8月に福島の子どもを鎌倉に招待するイベントの費用として、
活用する、この会の趣旨とは別個に、
お茶の所作に、目を奪われて行きます。




後5日で箱根ガラスの森美術館の、パロヴィエール一家の作品展示ですが、
展示作品の掲載は本日、休みます。




👇 鎌倉、建長寺、
見上げて眩しく足もとが、ふらついてしまった三門。
三解脱門、この三門をくぐると、空、無相、無作、
あらゆる執着から解き放たれるという。
半分くぐり、もともと飽きっぽい性格ながら、
煩悩捨てるには、まだ年が若く?
あれもこれもの執着、一つくらいは何か残したい。
実存を優先し、
困った、小走り逆戻りをして、通り抜けることなく。
それでも建長寺。
魅力たっぷりでした。

👇 鐘楼が向こうに。


夏目漱石の1895年9月6日の「海南新聞」
建長寺を訪れて、
【 鐘つけば銀杏ちるなり建長寺 】
故郷松山の親友、正岡子規、11月8日の「海南新聞」
奈良の宿先で
【 柿くえば鐘が鳴るなり法隆寺 】
夏目漱石がたたずんで読んだ俳句が、建長寺のこの鐘。
造った時期は1255年だそうで・・・。
俳句、なんとなく正岡子規ののほほんとして、達人?

入り口から、、シャクナゲ?ボタン?の花が赤、白、黄色。
赤い花もいいし、白もいい、黄色はひよこ色、
色の鮮やかさは、オクラの花とどっこいどっこい。
一際、観光客の目を引いていました。





このあと「東日本大震災」の復興支援のお茶会に。 ☝ 写真 2018.4.22
まもなく、あと6日。
ムラーノ島の、バロベィエール一家の作品が、
箱根仙石原の、❝箱根ガラスの森美術館❞ で・・・。




煩悩・・・・ウン?
貪,瞋,痴,慢,疑,悪見の6種。
私の生涯、煩悩1000万本の薔薇に匹敵する煩悩だらけ。
が、これだけは清貧、譲れない少年時代の心。
無神論者ながら、消したい煩悩「悪見」
これだけは、
座禅組んでも、すがすがしくなる修業。
後は、肩にあざができ、膏薬貼れども、失神。
「修業が足りません」と。
ふてくされて、岩間のノスミレに、心を奪われ、
ウン、あしたがあるさ、あしたがある~と、ハミング。
花、覚えるのに必死、とにかく必死。
庭に咲いた、山に咲いた、花、花、花、は~な。
♬♪~すみれのは~な咲くころ~♫・
氷嚢額に当てて、スミレは私の眼には百変化、
すみれ。
ちがいが判るまで、歩けという~のか!
ヘェック・ション!
スミレを見ると、これもスミレ、それもスミレ?
あれは・・・スミレ、うん、スミレ。
来年は、きちんと、言える。
高尾の◎〇スミレの皆さん、
待って、くれる?
148・・・年、忘れた。
ヴロヴィエール一家のムラーノ島に渡った先代。
マリア、パロヴィエールは、女性の感覚で、現代の私たちの美観に、
素直に受け入れられる、文鎮をつくっていました。
画像は、マリア・パロヴッティエールではありません・・・・。
Making an Implosion Marble in Soft Glass

一の谷の戦い。
海の中に「敵にせを向けるとは卑怯者なり・・」
いざ覚悟、逃げた16歳平敦盛。
追いつき、顔を見れば美しき美少年、16歳と名乗り、哀れ、
逃がそうとして、手を抜いた熊谷直美16歳。
源氏の追っ手を知り、泣く泣く敦盛を手にかけ、
熊谷直美、やがて、
武家の無常を悟って高野山へ。
クマガイソウ、熊谷直美が背負った幌(母衣)に似ているところから、
付いたものです、と。
平家物語、よく知らないので、ここまでです。







☝ 写真 2018.4.17 高尾山
私は、ジュゼッぺ・パロヴィエール。
まもなく、ムラーノ島から、みなさんと、日本の森と湖の町箱根で、
お会いすることになります。
パロヴィエール一族展・あと9日。

まもなく私の作品と
パロヴィエール家の名工たちの、作品とともに、
森と湖の箱根でお会いできる日が来ます。
すでに『風にそよぐグラス』は
現代作家のディル・チフリー氏が、制作した美術館の池にある、
パラッツォ・ドゥカーレ・シャンデリアのを見下ろす、建物に、
常時飾られ、
私が1893年の肖像画を描いていただいた、
2年後、
芸術家集団「パロヴィエール」が、
1895年、ヴェネツィア・ビエンナーレに出品した作品で、
当時、ガラス工芸の常識を破り、技術は奇跡のグラスと、
世界の注目を集めたものでした。
それが、
宙吹き、
高 24.1cm 幅 22.8cm
わずかな風にもゆらゆら、ゆれ動く、淡いピンクのグラス。




八王子、予報通り雨。
感情押し殺して流される一粒の・・涙のしずくに比べれば、
こんな雨「へ」でもない、とばかり、出かけた高尾山。
山頂付近はさすが寒く、背中に雨の冷たさ、
身震いするも、犬の身震いには到底及ばず、
3度のくしゃみに、元気いっぱいの登山者、
振り向いて「風邪ひかないで!」と
ニッコリ!
噂のくしゃみでもなく、花粉症のくしゃみでもなし、
下種の後知恵、せいぜい 「温かい風呂につかる」程度の知恵!
ベランダに出れば、奥高尾連峰・・・南無、南無、なむ~!







☝ 高尾山 写真 2018.4.17
あと10日 4月28日 パロヴィエール一族展 箱根で
ガラスの歴史は5000年前、
西アジアで青銅器が作られ、
日本では、
世界に誇る、新潟の火焔型土器が作られた頃と一緒。
天然ガラス黒曜石の鋭い破片が狩猟に使われたと、
解明されているけど、人間が、どのようにしてガラスを創ったかは、
タイムスリップをし、古代に戻らないと、記録に残せない。
ムラーノ島に渡って500年、バロベィエール一家が残した、
最大の技法、クリスタル・ガラス。
色を排除した、透き通るグラス。
ジュースを水をワイン、カクテルと、オールパーハス、
最も使用頻度の高いグラス。
今も変わらないのでは。
玉脚コブレット
17世紀
宙吹き
高 14.5cm 幅 8.7cm 新潟・火焔型土器

