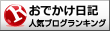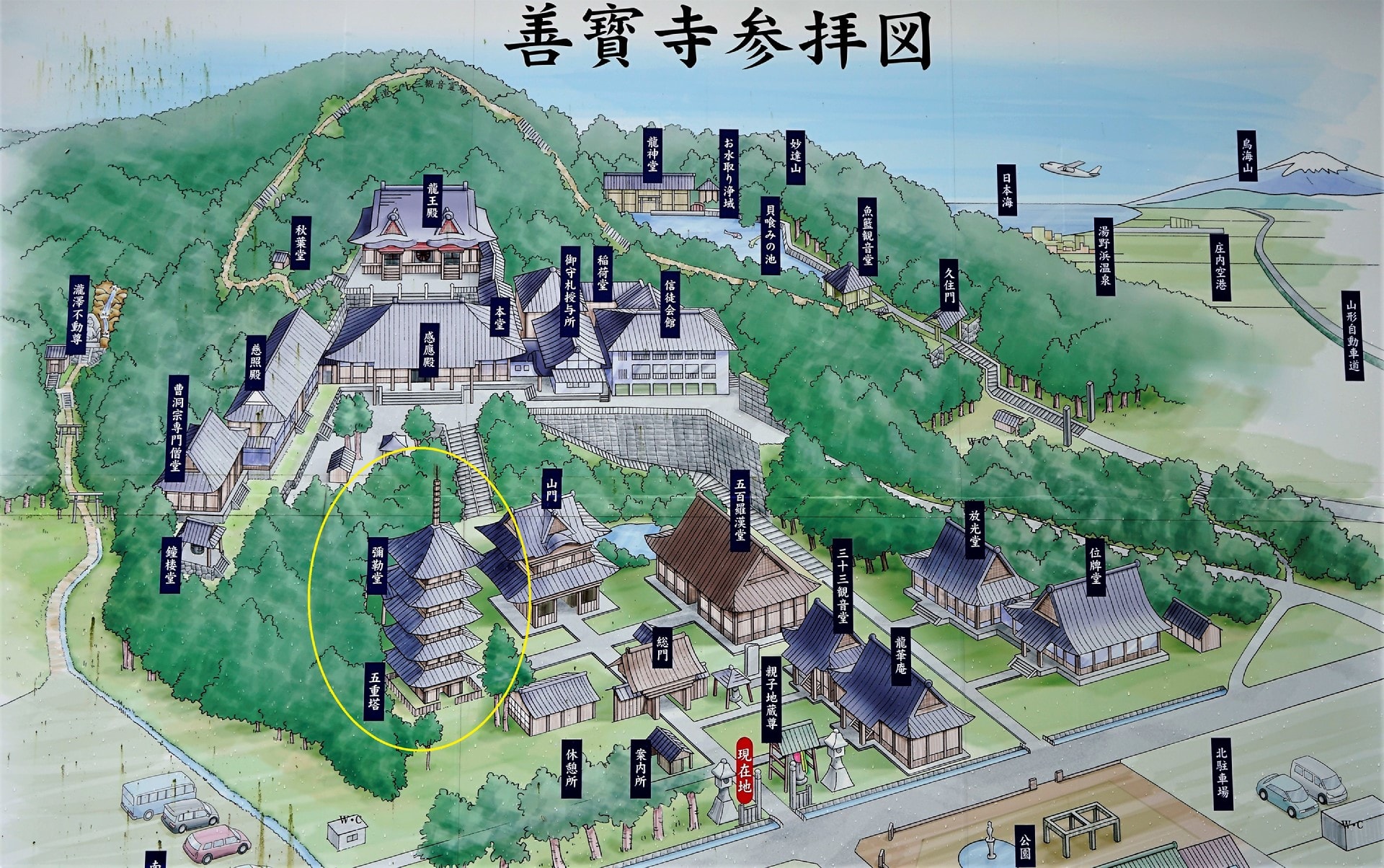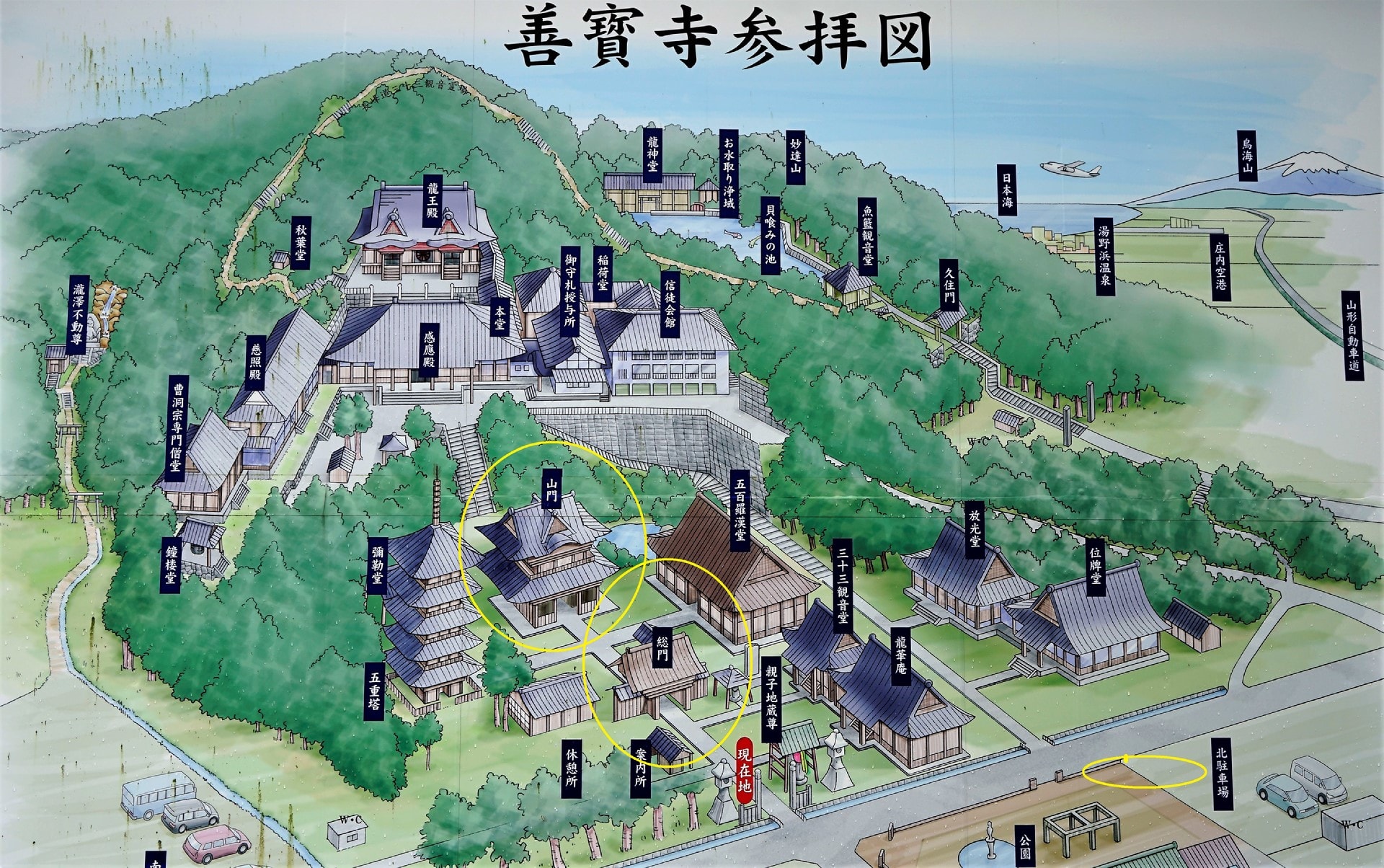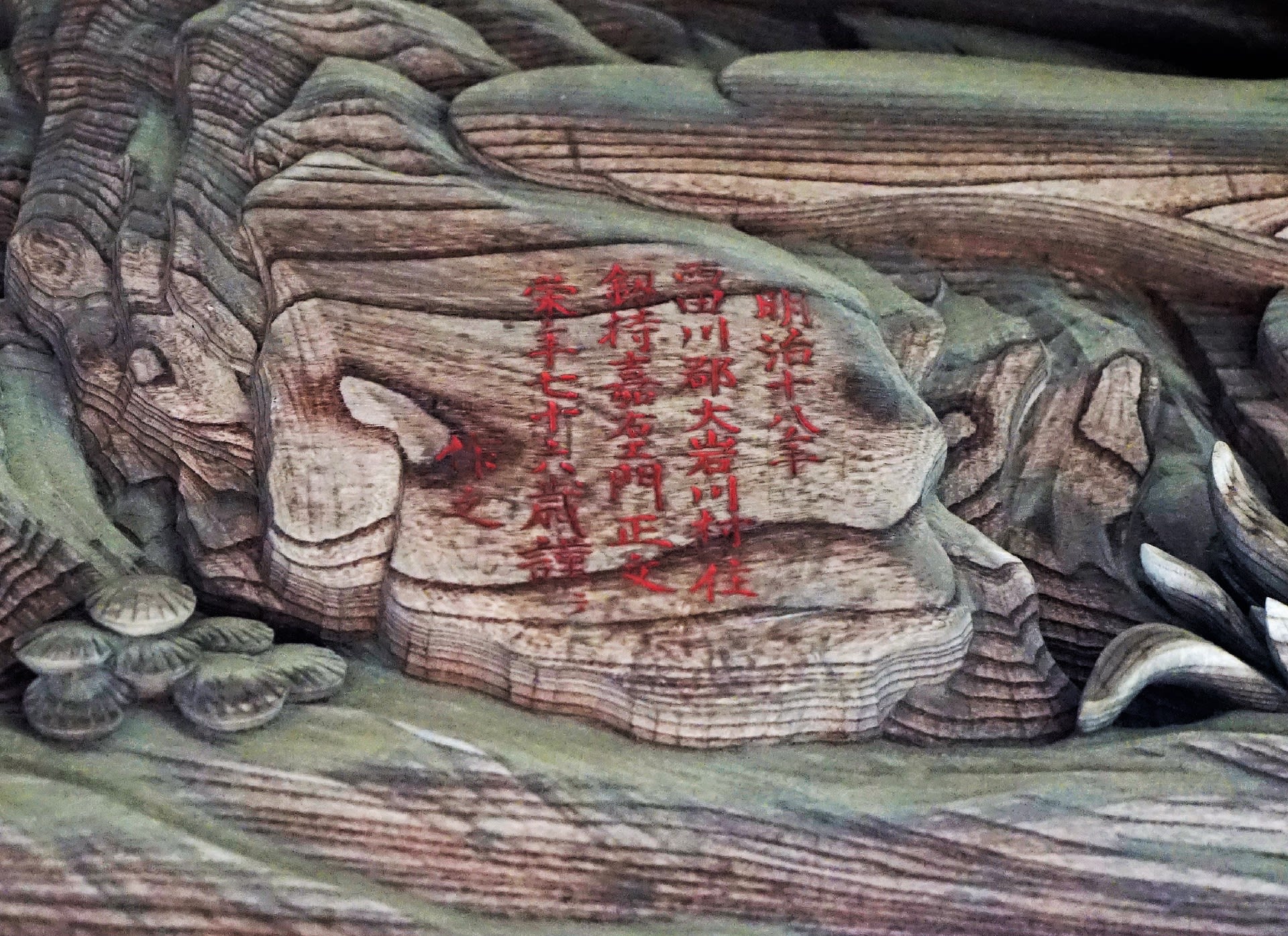埼玉県日高市巾着田公園。
俯瞰した公園の形が、巾着袋に似ていて、
高麗川が巾着袋をくるり、
悠々と流れている。
地獄花。子供の頃、
高麗川が巾着袋をくるり、
悠々と流れている。
地獄花。子供の頃、
遊び場お寺のお墓にちょっとだけ咲いていた花。
花を見ると、脳裏を自在に行き来する故郷が、
花を見ると、脳裏を自在に行き来する故郷が、
いきなり、パッ、と広がる。
彼岸花と名前を覚えたのは、
ずっと、ずっと後から。
彼岸花の名は、方言を含めて、
全国1000もあるという。
9月27日、群生している巾着田をテレビで見て、
好奇心、
出店の雰囲気も手伝って、行ってきました。
入り口辺りまだ3分咲きの看板に、
気落ちしたけど、歩く、歩くで、
帰着袋底の辺りでは満開。
花音痴、
彼岸花と名前を覚えたのは、
ずっと、ずっと後から。
彼岸花の名は、方言を含めて、
全国1000もあるという。
9月27日、群生している巾着田をテレビで見て、
好奇心、
出店の雰囲気も手伝って、行ってきました。
入り口辺りまだ3分咲きの看板に、
気落ちしたけど、歩く、歩くで、
帰着袋底の辺りでは満開。
花音痴、
河原でポットの味噌汁と握り飯を、
頬張りながら、解説書を読んで、
触れず観賞すれば、
頬張りながら、解説書を読んで、
触れず観賞すれば、
触るなと言われ、怖かった郷での地獄花も、
今日は、可愛く曼殊沙華。
今日は、可愛く曼殊沙華。
スポーツの秋、昨日から、
ラグビー・バレーボール・世界陸上のテレビ観戦、
今日も又。
ラグビー、ウェルズが勝って、
曼殊沙華の投稿写真も、ここでポン!
ラグビー・バレーボール・世界陸上のテレビ観戦、
今日も又。
ラグビー、ウェルズが勝って、
曼殊沙華の投稿写真も、ここでポン!