
折れ線グラフはそれほど難しい単元ではない。
できれば、全員にテストでいい点数をとらせてあげたい。
そのためには、基本事項を理解してもらうことが大切だと思う。
第1時に、これを教えて理解させたい。
これは、考えさせることでなく、知識として身につける事項だからが。
これが分かっていれば、2時以降はこれを使って子どもたちは考えることができる。
このようなところで、無駄な時間をとって、考えさせ混乱させない方がいい。
教科書では、最初に横軸は何を表しているかを聞いている。
子どもたちは「横軸」といわれても、何のことが分からない。
私なら、こういう。
「グラフの下に数字があります。今から言うところに赤丸をつけなさい。」
「8 9 10 11 12 13 14 15 16 それから(時)も。」
「これらが表すものを横軸と言います。横軸は何を表しているか分かりますか?」
教科書では、次に縦軸は何を表しているかを聞いている。
子どもたちは「縦軸」といわれても、何のことが分からない。
私なら、こういう。
「グラフの左横に数字があります。今から言うところに青丸をつけなさい。」
「0 5 10 15 20 25 30 それから(度)も。」
「これらが表すものを縦軸と言います。縦軸は何を表しているか分かりますか?」
次は、12時の気温を調べる活動になる。
横軸を使って資料を読む練習だ。
これも、12時から垂直に線を引かせ、グラフとぶつかるところに赤丸をつけさせる。
そして、こんなふうに、定規をあて横軸を読ませる。
「こうやって、12時の気温を調べます。」と教える。
次は、19度の時刻を調べる活動になる。
縦軸を使って資料を読む練習だ。
これも、19度から垂直に線を引かせ、グラフとぶつかるところに青丸をつけさせる。
そして、こんなふうに、定規をあて縦軸を読ませる。
「こうやって、19度の時刻を調べます。」と教える。
分かりきっているだろうと思うけれど、それぞれが曖昧に分かったつもりでいる。
クラス全員で学ぶために、これをきっちり押さえておく。
絶対に分かるようにしておく。
見えない部分も、こうして「線」「丸」で他の資料と分けることで、明確になる。
温度の変化によるグラフの向きは、分かっているようで初めて出ることなので押さえておくと便利だ。
「8時と9時は同じ? ちがう?」
と聞く。
同じは「水平」と理解させる。
「9時と10時は同じ? ちがう?」
と聞く。
上向きの変化は「上がる」と理解させる。
「10時と11時は同じ? ちがう?」
と聞く。
子どもから、上向きの変化は「上がる」とつぶやきがでる。

まとめておく。
「気温が上がると、線の向きはどうなるの?」
「じゃあ、13時から16時は?」
もう一つ大切な事項を押さえる。
これも、分かっているようでおそらく曖昧にしか分からない子がいる。
そのためにこんな学びをする。
どちらが、変わり方が大きいですか?
この場合は、どちらが、変わり方が大きいですか?
この場合は、どちらが、変わり方が大きいですか?

これを押さえてから、気温の上がり方の一番大きいのは「何時から何時」
これを押さえてから、気温の下がり方の一番大きいのは「何時から何時」
これでまとめが書ける。
このあと、教科書の例題に取り組ませる。(ひまわりの高さ)
ここまで1時間目にやっておくと、2時間目以降が楽になる。
| 第33回 | 2013年6月8日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第2会議室 |
| 第34回 | 2013年7月13日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第2会議室 |










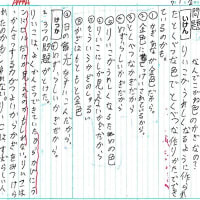
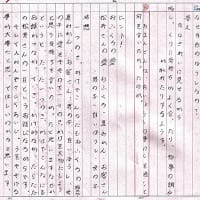
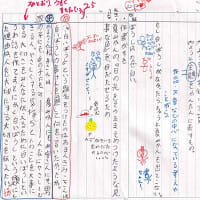
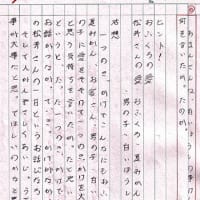
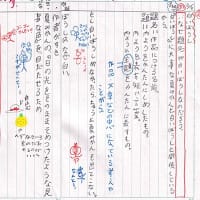
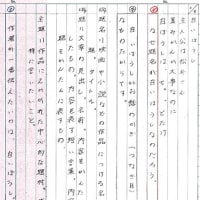
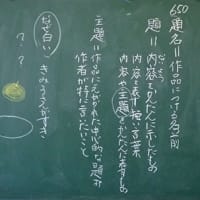
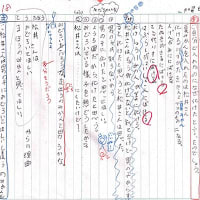
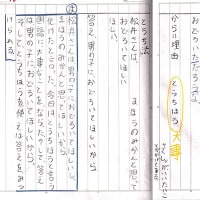
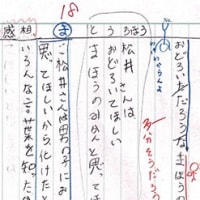
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます