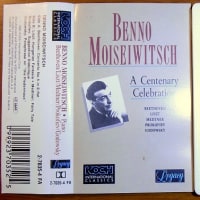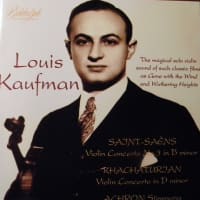フルトヴェングラーの提琴奏鳴曲第1番を聴いてゐる。今日、これを聴くのは7回目である。僕は、少し気にいるとこのやうに一度に何度も繰り返し聴いて、その日のうちに自分の頭に仕舞いこんでいく習性がある。しかし、最近はアルチュウハイマーの影響で記憶に残る作品が激減してゐる。
1934年の夏、ポーランドに滞在中のフルトヴェングラーは、広大な景色の中を日に2時間程度乗馬をしたりしながら、世間の見聞を断ち切ってこの提琴奏鳴曲を作曲したのだそうだ。その後、1937年には伯林フィルハーモニーのコンサートマスターであったフーゴ・コールベルクとフルトヴェングラー自身の洋琴演奏によって初演された。
当時、各地の演目に何度か乗ったやうな記録があるが、作者自身が言ってゐるとおり、この曲の演奏には相当なヴィルトゥオージティが必要で、凡庸な奏者には演奏不能な作品である。1939年6月16日付けのヘルムート・グローエ宛ての手紙にも、ヴュルツブルグ音楽院長であったツィルヒャーの演奏が良くなかったと聞いたが本当か?と尋ねてゐる。
ところで、この手紙の文中に気になる一節がある。「私の奏鳴曲をレコヲドにとっていただき厚くお礼申し上げます」・・・これはいったいどういふことか?どうも前後から推察するに、ミュンヘンでのツィルヒャーの演奏を録音してゐたといふことらしい。そして、手紙は「7月にミュンヘンを訪れるつもりなので、そのときに聴かせてください」と続くのである。ちなみに、このグローエといふ人物は、フルトヴェングラーをマンハイムに招聘した劇場支配人で、ヘルムートはそのご子息である。何処からかこのレコヲドが出てきて、CDに復刻されるやうなことはないものだらうか。
ところで、この曲の第3楽章の浪漫的な旋律とそれを華やかに支える洋琴は実に美しく、フルトヴェングラーらしくないかも知れない。第1楽章は重厚で一つの主題を徹底的に展開していく独逸伝統の構築を聴かせてくれる。ドン=スク・カンの鼻息を聞いてゐるのか提琴を聴いてゐるのか分からぬ部分もあるが、それだけ熱の入った演奏なのだらう。終楽章もフルトヴェングラーらしい楽想で、エンディングなどは第2交響曲を彷彿とさせる。

盤は、仏蘭西TimpaniによるCD 1C1029。
1934年の夏、ポーランドに滞在中のフルトヴェングラーは、広大な景色の中を日に2時間程度乗馬をしたりしながら、世間の見聞を断ち切ってこの提琴奏鳴曲を作曲したのだそうだ。その後、1937年には伯林フィルハーモニーのコンサートマスターであったフーゴ・コールベルクとフルトヴェングラー自身の洋琴演奏によって初演された。
当時、各地の演目に何度か乗ったやうな記録があるが、作者自身が言ってゐるとおり、この曲の演奏には相当なヴィルトゥオージティが必要で、凡庸な奏者には演奏不能な作品である。1939年6月16日付けのヘルムート・グローエ宛ての手紙にも、ヴュルツブルグ音楽院長であったツィルヒャーの演奏が良くなかったと聞いたが本当か?と尋ねてゐる。
ところで、この手紙の文中に気になる一節がある。「私の奏鳴曲をレコヲドにとっていただき厚くお礼申し上げます」・・・これはいったいどういふことか?どうも前後から推察するに、ミュンヘンでのツィルヒャーの演奏を録音してゐたといふことらしい。そして、手紙は「7月にミュンヘンを訪れるつもりなので、そのときに聴かせてください」と続くのである。ちなみに、このグローエといふ人物は、フルトヴェングラーをマンハイムに招聘した劇場支配人で、ヘルムートはそのご子息である。何処からかこのレコヲドが出てきて、CDに復刻されるやうなことはないものだらうか。
ところで、この曲の第3楽章の浪漫的な旋律とそれを華やかに支える洋琴は実に美しく、フルトヴェングラーらしくないかも知れない。第1楽章は重厚で一つの主題を徹底的に展開していく独逸伝統の構築を聴かせてくれる。ドン=スク・カンの鼻息を聞いてゐるのか提琴を聴いてゐるのか分からぬ部分もあるが、それだけ熱の入った演奏なのだらう。終楽章もフルトヴェングラーらしい楽想で、エンディングなどは第2交響曲を彷彿とさせる。

盤は、仏蘭西TimpaniによるCD 1C1029。