(50)小樽公園の歌碑 昭和26年11月建立(『一握の砂』より)

こころよく
我尓はたらく仕事あれ
それを仕遂げて
死なむと思ふ
明治40年10月2日、啄木は、母・妻子を小樽によんで、花園町に居を構えました。仕事は順調でしたが、事務長の小林寅吉と、そりが合わず、退社を決意し、辞表を提出し、同年12月20日、退職しました。退社はしたが、条件の良い働き口はなく、白石社長が推薦する釧路新聞社(現在の北海道新聞社)で働くことにしました。
啄木日記
明治40年10月2日
花園町十四西沢善太郎方に移転したり。室は二階の六畳と四畳半の二間にて思ひしよりよき室なり。ランプ、火鉢など買物し来れば雨ふり出でぬ、妹をば姉の許に残しおきて母上とせつ子と京と四人なり。札幌を都といへる予は小樽を呼ぶに「市」を以てするの尤も妥当なるを覚ふ。
明治40年11月6日
花園町畑十四番地に八畳二間の一家を借りて移る。
明治40年12月
11日 札幌に行き、小国君の宿にとまる
12日 夕刻の汽車にて帰り、社に立寄る。小林寅吉と争論し、腕力を揮はる。退社を決し、沢田君を訪ふて語る。
13日より出社せず。社長に辞表を送る事前後二通、社中の者交々来りて留むれど応ぜず。
20日に至り、社長より手紙あり、辞意を入れらる。
25日 夜、澤田君来り快談数刻、 君、白石社長の意を伝へて、予を釧路新聞に入れむとす。予は社長にして予の条件を容れなば諾せむと答へたり。
26日 朝澤田君に手紙を送り、釧路新聞を如何に経営すべきかに関する予の意見を述べたり
夜、奥村君を呼び、若し白石社長にして予の意見を容れなば共に釧路に入らむことを約したり
小樽公園には宮澤賢治も訪れています。宮沢賢治は岩手県花巻農学校の教員時代の大正13年5月、生徒を引率して、北海道へ修学旅行に行き、小樽公園にも立ち寄りました。学校に提出した「復命書」には、公園の様子を次のように述べています。 「公園は新装の白樺に飾られ北日本海の空青と海光とに対し小樽湾は一望の下に帰す」と。
宮澤賢治には「溶岩流」の詩があります。この焼走り熔岩流は、岩手県八幡平市にあります。岩手山中腹から流出した溶岩流により形成された岩原です。溶岩流の延長は約4キロメートルで、その中には散策路があり自由に見られます。なお、焼走り溶岩流が形成された火山活動の年代は300年ほど前といわれています。近くに温泉があります。高速道西根インターから車で30分ほどです。

岩手山と「溶岩流」


宮澤賢治「溶岩流」
溶岩流 宮沢賢治
喪神のしろいかがみが
薬師火口のいただきにかかり
日かげになつた火山礫堆(れきたい)の中腹から
畏るべくかなしむべき砕塊熔岩(ブロツクレーバ)の黒
わたくしはさつきの柏や松の野原をよぎるときから
なにかあかるい曠原風の情調を
ばらばらにするやうなひどいけしきが
展かれるとはおもつてゐた
けれどもここは空気も深い淵になつてゐて
ごく強力な鬼神たちの棲みかだ
一ぴきの鳥さへも見えない
わたくしがあぶなくその一一の岩塊(ブロツク)をふみ
すこしの小高いところにのぼり
さらにつくづくとこの焼石のひろがりをみわたせば
雪を越えてきたつめたい風はみねから吹き
雲はあらはれてつぎからつぎと消え
いちいちの火山塊(ブロツク)の黒いかげ
貞享四年のちひさな噴火から
およそ二百三十五年のあひだに
空気のなかの酸素や炭酸瓦斯
これら清洌な試薬(しやく)によつて
どれくらゐの風化(ふうくわ)が行はれ
どんな植物が生えたかを
見ようとして私(わたし)の来たのに対し
それは恐ろしい二種の苔で答へた
その白つぽい厚いすぎごけの
表面がかさかさに乾いてゐるので
わたくしはまた麺麭ともかんがへ
ちやうどひるの食事をもたないとこから
ひじやうな饗応(きやうおう)ともかんずるのだが
(なぜならたべものといふものは
それをみてよろこぶもので
それからあとはたべるものだから)
ここらでそんなかんがへは
あんまり僭越かもしれない
とにかくわたくしは荷物をおろし
灰いろの苔に靴やからだを埋め
一つの赤い苹果(りんご)をたべる
うるうるしながら苹果に噛みつけば
雪を越えてきたつめたい風はみねから吹き
野はらの白樺の葉は紅(べに)や金(キン)やせはしくゆすれ
北上山地はほのかな幾層の青い縞をつくる
(あれがぼくのしやつだ
青いリンネルの農民シヤツだ)




























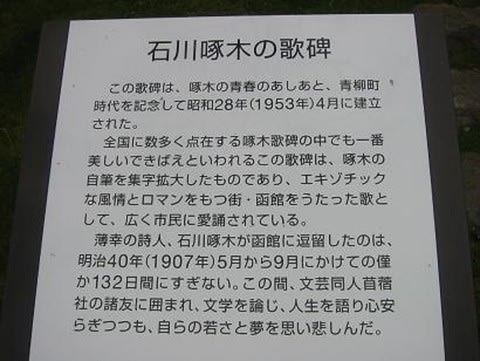 案内板(説明板)
案内板(説明板)








