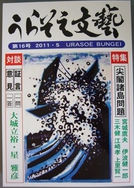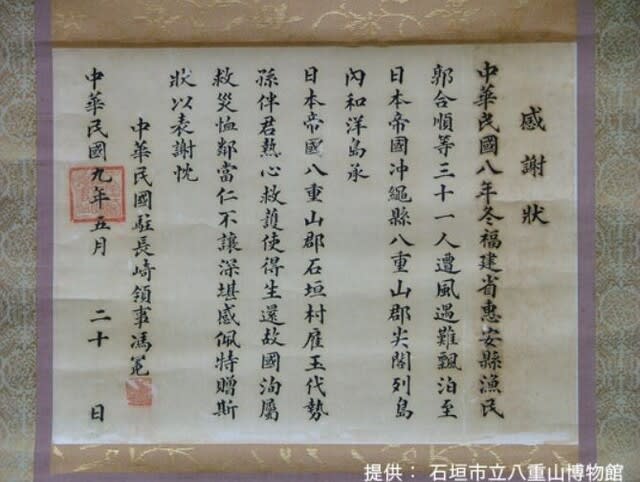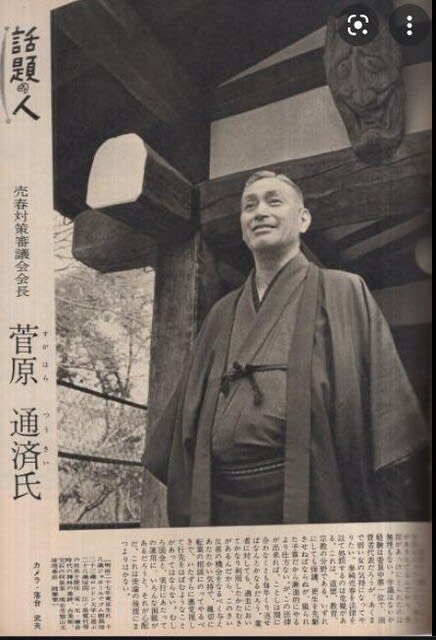★
沖縄の日本復帰直後の経済数値を捉えて、沖縄経済は「米軍基地の恩恵受けていない」などと言い張っても、米軍統治下の沖縄経済は、米軍の存在を無視して語ることはできない。
1950年(昭和25年)米国民政府布令に基づき設立された琉球大学の与那嶺松助・第四代学長は、沖縄と米軍の経済援助についてこう述べている。
「終戦直後の沖縄の経済機能は完全にマヒ状態であったが、住民は米軍の余剰物資である食料と日常必需品等無償配給を受け、原始的な物々交換をして生活していました。 その後貨幣経済が再会され、B型軍票の使用と、公務員、軍雇用者に対する賃金制度の実施、続いて中央銀行の設立と相まって金融経済も活発な歩みを続け、その後琉球銀行の設立、島内産業の勃興、自由経済への移行と今日のようなすばらしい高度な経済成長を遂げたのであります。」(富原守保著『金融の裏窓十五年』)
沖縄が米軍基地の恩恵に浴したのは返還前の米軍統治時代だけではない。
本稿を執筆中の2021年現在でも、沖縄が米軍基地の恩恵を受けている簡単な例を示そう。
■米軍基地は、毎年黄金の卵を生むガチョウ
現役の防衛省職員である里中一人著『「軍用地」投資入門』によると、軍用地(米軍基地)を、黄金の卵を生むガチョウに例えて、こう説明する。
軍用地は年一回借地料という黄金の卵を生む。しかも、黄金の卵は、毎年同じ大きさだが、軍用地料は大きくなる。ガチョウはいずれ死に絶えるが、軍用地は日本に米軍が存在する限り無くなることはない。米軍基地は軍用地地主の懐に確実にお金を生み出してくれる「おいしい果実」というのだ。
著者自身が沖縄市軍用地等地主会の会員でもある野里氏は、米軍基地が「おいしい果実」である理由を同書の中で、こう説明している。
《何故、軍用地(米軍基地)が「おいしい果実」なのか簡単に説明すると、国(日本政府)が軍用地の借地料を支払うため延納の心配がなく、安定的で長期的な収入がみこめるからです。 しかも収入は年々複利的に増えることから、沖縄では多くの会社員などが退職金で購入しています。
担保価値も高いので富裕層に人気の投資物件であり、その利回りは約2~3%です。軍用地は一括して国が管理しているので、所有者は手間いらず。黙っていていてもあなたの口座にお金が振り込まれる仕組みなのです。》
いやはや、驚いた。
沖縄の地元新聞やサヨク学者が蛇蝎のごとく忌み嫌う米軍基地が、ガチョウの卵以上に毎年金の卵を生み、しかも国が保証する手間いらずというのだ。「多くの会社員」が退職金で米軍基地を購入するのもよく理解できる。 著者の里中氏は、県内の空気を忖度して「多くの会社員」と曖昧にしているが、実際は「多くの公務員や教員」と言い換えた方が的を射ている。 さらに「会社員」の中には沖縄タイムス、琉球新報など沖縄メディアの幹部も含まれ、密かに退職後の資産運用として軍用地の地主になっていることは地元沖縄ではは良く知られた事実である。
■軍用地投資のリスクは2~3%の範囲内
さらに言えば、米軍基地投資の唯一のリスクは、米軍基地返還だが、それで土地そのものが消えてしまうわけではない。返還されても通常の土地投資としての担保価値は残るし、場合によっては返還地の再開発などで担保価値が上がる可能性もある。
つまり、米軍基地投資は、返還後のリスクを考慮しても軍用地としての2~3%の利回りが無くなるだけのリスク、つまり2~3%の範囲内の極めて低いリスクでしかない。 結局米軍基地投資は、依然として「おいしい果実」であることに間違いない。

琉球新報に掲載された黄金を生む卵「軍用地」の新聞広告
■イデオロギーは嘘を吐くが経済は嘘をつかない
「米軍基地撤去」は、沖縄の地元2紙を始めデニー県知事が主張するイデオロギー。 イデオロギーは米軍基地撤去に反対しないものは沖縄県民にあらず、という大嘘をまき散らす。 だが、その一方米軍基地派黄金の卵を生むという経済的現実は嘘をつかない。
次項で、「儲かる地域に人は集まる」という経済原則を、奄美の経済と人の流れで検証してみよう。
■米軍統治下に置かれた奄美の経済
終戦後沖縄と同じく米軍統治下でB型軍票の経済圏に組み込まれた奄美群島の経済と沖縄を比較しつつ、米軍統治下の沖縄経済を点描してみよう。
戦後米軍統治下にあった奄美群島は、サンフランシスコ講和条約発効後の1953年12月25日、日本に返還された。
米軍統治下の沖縄では米軍による活発なインフラ投資が行われ、職を求めて多くの「奄美大島人」が沖縄に流入した。
「奄美⇒沖縄」の人口流入については正確なデータが無いので、立命館大学『米軍統治下における奄美―沖縄間の人口移動』に拠って分析してみよう。
奄美の人口は奄美の日本返還(1953年)前後をピークに当初の約半分以下に減少している。
「例えば、一般的な歴史書において『沖縄における本格的な基地建設の開始とともに、奄美から沖縄本島に流入してきた人たちは五万人に近かったと言われるが・・・奄美返還によって『そのまま沖縄に残って外人登録(日本に返還されたので外人扱い)を受けた人たちの数も二万八千人にのぼり、未登録者を含むと、54年頃の在沖奄美出身者は約三万人と推定された』という指摘がある。また『沖縄と共に米軍政下に置かれた奄美から、仕事を求めて沖縄に渡った奄美人は、ピーク時には六万とも七万ともいわれている・・・』とされるなど、5~7万規模の人口移動が一般的通説となっているようだ。」(立命館大学『米軍統治下における奄美―沖縄間の人口移動』)
長々と引用文に付き合っていただいたが、「米軍統治下における奄美―沖縄間の人口移動」の特徴は、片道通行、つまり奄美から沖縄への一方通行に限定されている事実だ。
奄美と沖縄は戦後同時に米軍統治下に組み込まれたが、奄美だけはいち早く日本復帰をしたため、米軍統治下から解放された。
その結果奄美の経済に何が起きたか。
イデオロギーは嘘を吐くが、経済は嘘をつかない。金の儲かるところに人は集まる。
米軍基地のインフラ建設などで復興景気に沸きかえる沖縄へ、日本復帰後の奄美の人口は大幅に流入した。
この厳然たる事実を見たら沖縄メディアや沖縄県が、「基地の恩恵受けず」などといくら叫んでも反基地活動家の遠吠えとしか感じない。
■返還後の奄美の経済状況
奄美群島は沖縄と同時に米軍統制下に置かれたが、1953年12月25日沖縄よりいち早く日本に返還された。 当時の奄美の経済事情を、1956年に発行された『祖国なき沖縄』(日月社刊)から引用してみよう。
《去る12月25日、7年ぶりで祖国へ帰った奄美大島について最近いろいろな雑誌が紹介しているので、その記事を読んだ多くの人たちから感想を聞かれることが多くなった。その中でも「想像したよりもっとひどいところなのですね!!」という種類の同情がおおかった。婦人公論の三月号に掲載されたグラビア写真はいずれも、最低の人間生活はこういうものだろうかとと見る人に同情させ考えさせずにはおかない写真ばかりだった。特にある農家の庭先でソテツの実の皮を剥き、ウスで挽き砕いている老婆の姿はあわれそのものであった。暫く考えたあと、やっと私はこの人の云おうとしたことが、「奄美大島では生活できないから容貌の美しい女性は沖縄へ出て行ってパンパン※(売春婦)になったり仕事を探したりするので、大島には美人は残っていないのですね?」ということだとわかった。私は「婦人公論にはソテツの実を集めている中々の美人の写真もありましたよ」と云っておいたけど、しかし考えてみたら、美人ばかりが出て行ったかどうかは別問題として、多くの男女が沖縄へ出て行ったのは事実だった。(『祖国なき沖縄』日月社刊)
※パンパンとは、戦後混乱期の日本で、主として在日米軍将兵を相手にした街娼の通称である。戦争で家族や財産を失って困窮し、売春に従事することを余儀なくされた女性が多かった。彼女たちの7割は外国人専門の「洋パン」だった。
本文は、当時の状況を反映するため上記引用の『祖国なき沖縄』に従ってパンパンの表現を用いた。
■沖縄の基地経済-「太平洋の要石」「東洋のドル箱」
低賃金ながらも米軍の恩恵を受けて、基地関連の仕事で維持していた沖縄の経済が、一変して繁栄の道に突き進むのは1947年(昭和22年)以降である。
その年1947年のトルーマンドクトリンやマーシャルプラン以降沖縄の共産圏に対する戦略的地位が重要視され、沖縄は太平洋の要石 (Keystone of the Pacific)と呼ばれるようになった。
沖縄経済を支えた第一の源泉は、軍事基地拡張、増設のインフラ投資である。
1949年秋シーツ軍政長官が「琉球の復興促進に関するシーツ政策」として総額五千万ドルに上る軍工事計画を発表してからというものは、基地や軍事施設の拡張、増設は目に見えて急速化し活発化した。沖縄は「建築ブーム」とか「東洋のドル箱」とか騒がれて日米その他の大建設会社が次々と乗り込んできた。沖縄の民間資本による土建会社も、素人でさえ心配になるような勢いで活性化した。
沖縄経済を支えた第二の源泉は、米兵が島内生産品の購入又は観光のために両替するドルとパンパン(外人向け売春婦)が稼ぐドルである。つまり米兵による外需である。
戦前は甘藷や野菜の畑であった旧コザ市(沖縄市)の越来(ごえく)村胡座(こざ)に嘉手納飛行場と隣接して突然都市が出現した。
ビジネスセンターと銘打って誕生したセンター区は、婦人連合会に「公娼制度を廃止させた米軍がふたたび公娼制度を設けるとはけしからん」と反対されたが、心配した通りカフェー街(売春街)となってしまった。
もはや沖縄は米軍基地が無ければ成り立たない構造になっていた。
大多数の労働者は直接あるいは間接的に米軍関係機関や建築現場に雇用先を見つけた。
沖縄の復帰後一番得をしたのは琉球政府職員や各市町村職員それに教員だと言われている。
復帰前までは低賃金だった沖縄版「公務員」が、復帰を境に日本の公務員法が適用され日本の公務員や教員と同じ待遇を受けるようになったからだ。
復帰前、沖縄住民の一番憧れの就職先は米軍関連組織、即ち軍雇用員であり、沖縄では軍作業といわれ就職は難関と言われた。
軍雇用員の採用試験に落ちた住民が、「仕方がないから琉球政府職員か教員にでもなるか」とぼやくほどであった。
沖縄経済を支えた軍作業資金や軍関連資金は地元経済にも経済波及効果をもたらした。
たとえばいわゆる「ハニー街」で客を待つ女性でも、競争を生き抜くには裸一貫で稼ぐわけではなく、それなりの投資が必要であった。
顧客を獲得するために、彼女らは朝から銭湯に行ったり、衣装にアイロンをかけたり、食事にも金をかけ、パーマ屋さんに行って変身に最高の自己投資をした。
勿論お気に入りのパーマ屋さんや衣装屋さんに行くタクシー業界も彼女らの自己投資の恩恵を受けた。ありったけの装身具に派手なドレスで自己投資した彼女たちがズラリと店の前に顔を揃えるとコザの町全体が生き物のように躍動し、520軒あると言われたハニー街の店全体が活気づく。
この華やかな客取り合戦が、結果的に外需を生み沖縄経済を下支えしていたのである。
第三の源泉は輸出によって獲得するドルと海外からの送金であるが、これは前二者に比べて微々たるものであった。
米軍統治下の沖縄の収入にはガリオア資金の恩恵があることは言うまでもない。主に主食の米(細長いビルマ米が多かった)、メリケン粉(小麦粉)肥料、油脂などがガリオア資金で購入され、その回収資金が琉球政府の財政に充てられた。












 ⇒最初にクリックお願いします
⇒最初にクリックお願いします