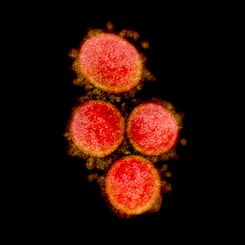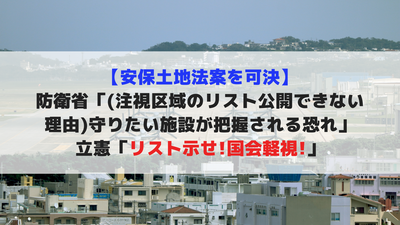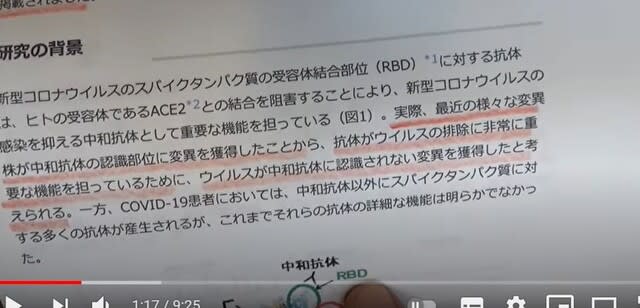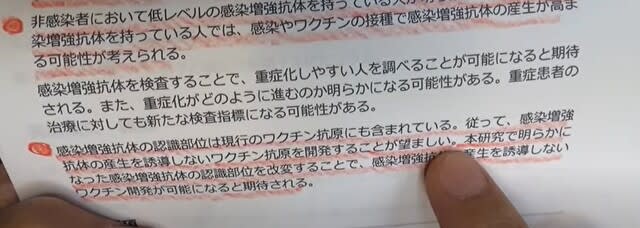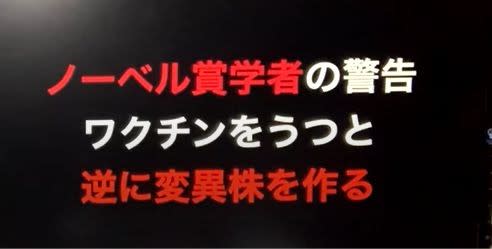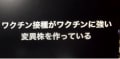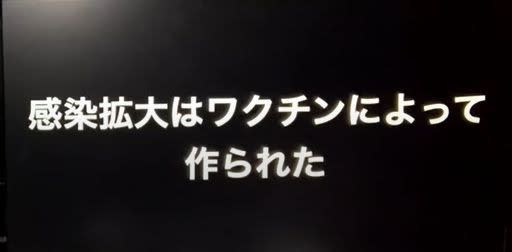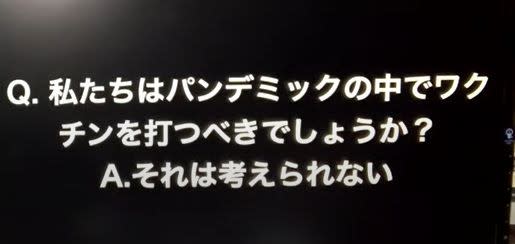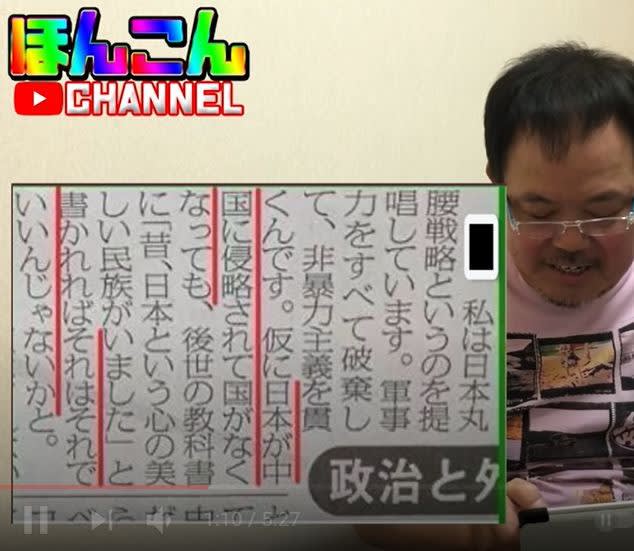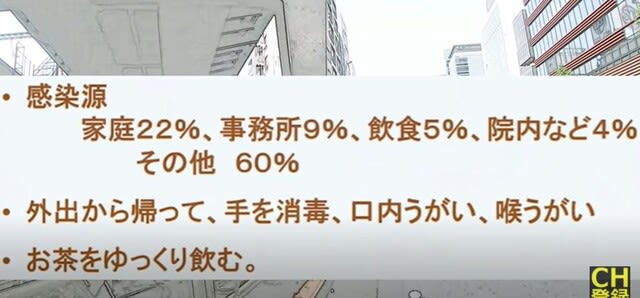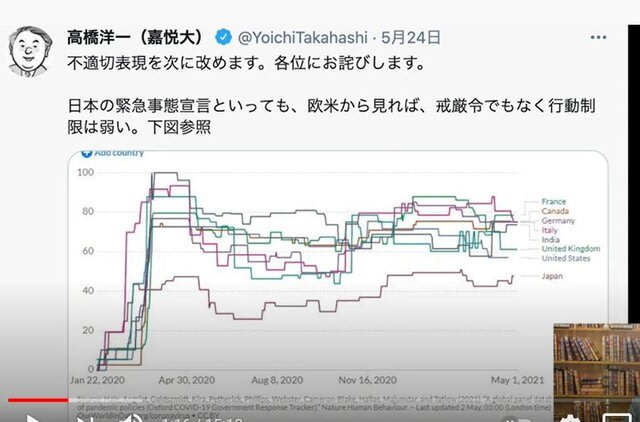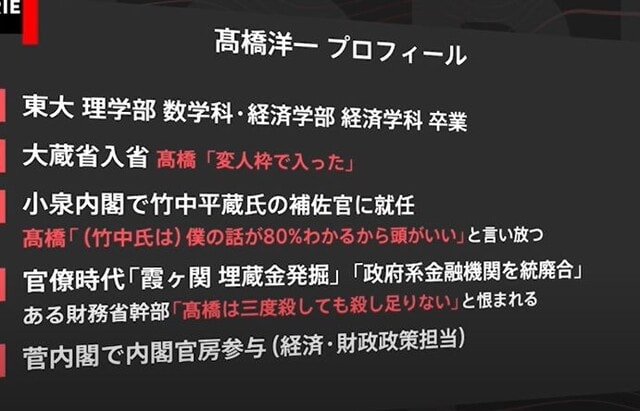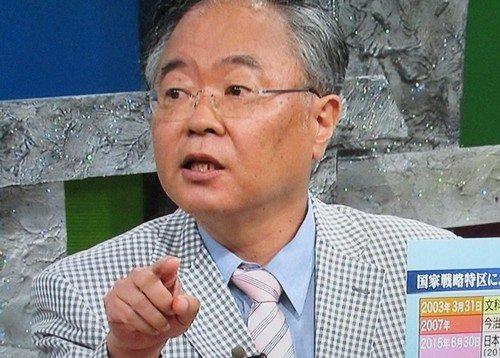昭和24年、沖縄タイムスの太田良博記者は『鉄の暴風』の取材のため、山城安次郎氏(当時の座間味村助役)に取材している。
太田記者の執筆手法には証言や史料の収集を基本とする新聞記者の姿勢はない。
渡嘉敷島や座間味島での現地取材をしていないことは勿論、取材といえば専ら「米軍」が集めた人々の話が主で、それも発言者の名前を記したメモの類もないという。
新聞記者の太田良博氏が、ドキュメンタリー作品の基本ともいえる当事者への取材もないずさんな記述で『鉄の暴風』を書き上げたのに対して、それを批判する立場で『ある神話の背景』を書いた作家・曽野綾子氏のルポルタージュ的記述手法は極めて対照的であった。
曽野氏は伝聞に頼る太田氏のずさんさんな取材手法を同書の中で次のように指摘している。
<太田氏が辛うじて那覇で《捕えた》証言者は二人であった。一人は、当時の座間味の助役であり現在の沖縄テレビ社長である山城安次郎氏と、南方から復員して島に帰って来ていた宮平栄治氏であった。宮平氏は事件当時、南方にあり、山城氏は同じような集団自決の目撃者ではあったが、それは渡嘉敷島で起こった事件ではなく、隣の座間味という島での体験であった。もちろん、二人とも、渡嘉敷の話は人から詳しく聞いてはいたが、直接の経験者ではなかった>
この部分に関して太田氏は、後に沖縄タイムス紙上の曽野氏との論争で宮平、山城の両氏は辛うじて那覇で《捕えた》証言者ではなく、「(両氏が)沖縄タイムス社に訪ねてきて、私と会い、渡嘉敷島の赤松大尉の暴状について語り、ぜひ、そのことを戦記に載せてくれとたのんだことである。そのとき、はじめて私は『赤松事件』を知った」と反論し、「(両氏は)証言者ではなく情報提供者」とも述べている。
太田氏が宮平、山城の両氏とどのように接触したかはともかく、そのとき山城氏は渡嘉敷島の伝聞情報である「赤松大尉の暴状」について語り、「そのことを戦記に載せてくれ」と頼んでおきながら、何ゆえ自分が体験した座間味島のことを語らなかったのか。それが大きな問題なのである。
戦時中、南方に居たという宮平栄治氏のことは論外としても、山城安次郎氏は太田記者が言う情報提供者の枠を超えた実体験者であり、座間味島の集団自決を証言できる証言者のはずである。
事件を追う事件記者が、飛び込んできた事件の当事者を目前にして、他の事件の情報提供だけを受けて、実体験の事件に関しては何の取材もしなかった。
これは記者としてはいかにも不自然である。
太田氏の言うように、その時、何のメモも取らなかったということも、にわかには信じがたいことである。
■大田良博と沖縄タイムスの関係
このように新聞記者としては不適格にも思える太田氏が何ゆえ沖縄タイムスが社を上げて企画をした『鉄の暴風』の執筆を委ねられたのか。
その謎を解く鍵は太田氏の沖縄タイムス入社直前の職にあった。
太田良博記者の略歴を見ると、『鉄の暴風』の監修者の豊平良顕氏や共著者の牧港篤三氏のような戦前からの新聞記者ではない。
そもそも太田記者と沖縄タイムスとの関係は、沖縄タイムスの月刊誌にエッセイ、詩などを寄稿していたが、昭和24年に発表した『黒ダイヤ』という短編小説で注目を引いた、いわば投稿者と新聞社という関係だったという。
太田氏が戦後米民政府に勤務しているとき、沖縄タイムスの豊平良顕氏に呼ばれ、企画中の『鉄の暴風』の執筆を始めたことになっている。
米軍政府が沖縄の統治権を米民政府に移管するのは太田氏が沖縄タイムスに職を変えた後の昭和24年の12月15日以降になっている。
『鉄の暴風』の執筆時に米軍側と沖縄タイムスそして太田氏の間に「共通の思惑」があったと考えても不思議ではないだろう。
曽野氏は『ある神話の背景』の取材で太田氏に会ったとき、米軍と『鉄の暴風』の関係について、同書の中で次のように述べている。
≪太田氏は、この戦記について、まことに玄人らしい分析を試みている。 太田氏によれば、この戦記は当時の空気を反映しているという。 当時の社会事情は、アメリカ軍をヒューマニスティックに扱い、日本軍閥の旧悪をあばくという空気が濃厚であった。太田氏は、それを私情をまじえずに書き留める側にあった。「述べて作らず」である。とすれば、当時のそのような空気を、そっくりその儘、記録することもまた、筆者としての当然の義務の一つであったと思われる。
「時代が違うと見方が違う」
と太田氏はいう。 最近沖縄県史の編纂をしている資料編纂所あたりでは、又見方がちがうという。 違うのはまちがいなのか自然なのか。≫
驚いたことに太田氏は『鉄の暴風』を執筆したとき、その頃の米軍の思惑を執筆に反映させて「アメリカ軍をヒューマニスティックに扱い、日本軍閥の旧悪をあばく」といった論旨で同書を書いたと正直に吐露していたのである。
このとき太田氏は後年曽野氏と論争することになるとは夢にも思わず、『鉄の暴風』を書いた本音をつい洩らしてしまったのだろう。
この時点で曽野氏は太田氏が記者としては素人であることを先刻見抜いていながら、「玄人らしい分析」と「褒め殺し」をして『鉄の暴風』の本質を語らしめたのであろうか。
曽野氏は、後年の太田氏との論争で,「新聞社が伝聞証拠を採用するはずがない」と反論する太田氏のことを「いやしくもジャーナリズムにかかわる人が、新聞は間違えないものだとなどという、素人のたわごとのようなことを言うべきではない」と「玄人」から一変して、今度は、「素人」だと一刀両断している。
◇
以下引用の太田記者の「伝聞取材」という批判に対する反論は、「はずがない」の連発と、
「でたらめではない」とか「不まじめではない」とまるで記者とも思えない弁解の羅列。
これでは曽野氏に「素人のたわごと」と一刀両断されるのも仕方のないことである。
「沖縄戦に“神話”はない」(太田良博・沖縄タイムス)」連載4回目
<体験者の証言記録
『鉄の暴風」の渡嘉敷島に関する記録が、伝聞証拠によるものでないことは、その文章をよく読めばわかることである。
直接体験者でないものが、あんなにくわしく事実を知っていたはずもなければ、直接体験者でもないものが、直接体験者をさしおいて、そのような重要な事件の証言を、新聞社に対して買って出るはずがないし、記録者である私も、直接体験者でないものの言葉を「証言」として採用するほどでたらめではなかった。永久に残る戦記として新聞社が真剣にとり組んでいた事業に、私(『鉄の暴風』には「伊佐」としてある)は、そんな不まじめな態度でのぞんだのではなかった。 >
「「沖縄戦」から未来へ向ってー太田良博氏へのお答え(3)」
(曽野綾子氏の太田良博氏への反論、沖縄タイムス 昭和60年5月2日から五回掲載)
<ジャーナリストか
太田氏のジャーナリズムに対する態度には、私などには想像もできない甘さがある。
太田氏は連載の第三回目で、「新聞社が責任をもって証言者を集める以上、直接体験者でない者の伝聞証拠などを採用するはずがない」と書いている。
もしこの文章が、家庭の主婦の書いたものであったら、私は許すであろう。しかし太田氏はジャーナリズムの出身ではないか。そして日本人として、ベトナム戦争、中国報道にいささかでも関心を持ち続けていれば、新聞社の集めた「直接体験者の証言」なるものの中にはどれほど不正確なものがあったかをつい昨日のことのように思いだせるはずだ、また、極く最近では、朝日新聞社が中国大陸で日本軍が毒ガスを使った証拠写真だ、というものを掲載したが、それは直接体験者の売り込みだという触れ込みだったにもかかわらず、おおかたの戦争体験者はその写真を一目見ただけで、こんなに高く立ち上る煙が毒ガスであるわけがなく、こんなに開けた地形でしかもこちらがこれから渡河して攻撃する場合に前方に毒ガスなど使うわけがない、と言った。そして間もなく朝日自身がこれは間違いだったということを承認した例がある。いやしくもジャーナリズムにかかわる人が、新聞は間違えないものだとなどという、素人のたわごとのようなことを言うべきではない。 >
太田 良博
本名、伊佐良博。1918年、沖縄県那覇市に生まれる。早大中退。沖縄民政府、沖縄タイムス、琉球放送局、琉球大学図書館、琉球新報などに勤務。その間詩、小説、随筆、評論など発表。2002年死去
 ⇒最後にクリックお願いします
⇒最後にクリックお願いします
続・『鉄の暴風』と米軍の呪縛
一昨日のエントリーで米民政府の職員で新聞記者としては素人同然だった太田良博氏が、沖縄タイムスに呼ばれて『鉄の暴風』の執筆を始める事をかいた。
⇒『鉄の暴風』と米軍の呪縛 |
では、素人同然の太田記者に『鉄の暴風』に執筆という重責を委ねた沖縄タイムス社が、交通も通信もままならぬ当時の沖縄で、現在の新聞社のような機動力をもって短期間で「体験者」を集めることが出来たのか。
当時の沖縄では、交通・通信等の手段を独占していた米軍の強大な力なくして、沖縄タイムスが情報源を確保することは考えられないことである。
昭和24年当時は民間人が沖縄全島を自由に通行することが許可されてからまだ2年しか経っておらず(昭和22年 3月22日許可)、何よりも、住民の足となる日本製トラックが輸入されるようになるのが、その年(昭和24年)の12月17日からである。
住民の交通事情をを考えても、その当時米軍の支援なくしての『鉄の暴風』の取材、そして執筆は不可能である。
太田氏が取材を始めた昭和24年頃の沖縄タイムスは、国道58号から泊高橋を首里城に向かって伸びる「又吉通り」の崇元寺の向かい辺りにあった。
その頃の那覇の状況といえば、勿論又吉通りは舗装はされておらず、通行する車両といえば米軍車両がホコリを撒き散らして通るくらいで、沖縄タイムス社向かいの崇元寺の裏手から首里方面に向かう高台には、まだ米軍の戦車の残骸が放置されているような有様であった。
太田記者はドキュメンタリー作品の基本である取材に関しては、何の苦労もすることもなく、米軍筋を通してでかき集められた「情報提供者」達を取材し、想像で味付けして書きまくればよかったのだ。
「取材」は沖縄タイムスの創刊にも関わった座安盛徳氏(後に琉球放送社長)が、米軍とのコネを利用して、国際通りの国映館の近くの旅館に「情報提供者」を集め、太田氏はそれをまとめて取材したと述べている。
三ヶ月という短期間の取材で『鉄の暴風』を書くことができたという太田氏の話も納得できる話である。
余談だが座安氏が「情報提供者」を集めたといわれる旅館は、当時国映館近くの浮島通りにあった「浮島ホテル」ではないかと想像される。
その後同ホテルは廃業したが、通りにその名前を残すほど当時としては大きなホテルで、米軍の協力で座安氏が「情報提供者」を全島から集められるほど大きな「旅館」は、当時では同ホテルを除いては考えにくい。国映館は今はないが、太田記者が取材した昭和24年にも未だ開業しておらず、後に世界館として開業し、国映館と名を変えた洋画専門館である。
このように太田記者の経験、取材手段そして沖縄タイムス創立の経緯や、当時の米軍の沖縄統治の施策を考えると『鉄の暴風』は、米軍が沖縄を永久占領下に置くために、日本軍の「悪逆非道」を沖縄人に広報するため、戦記の形を借りたプロパガンダ本だということが出来る。 当時の沖縄は慶良間上陸と同時に発布された「ニミッツ布告」の強力な呪縛の下にあり、『鉄の暴風』の初版本には米軍のヒューマニズムを賛美する「前書き」があったり(現在は削除)、脱稿した原稿は英語に翻訳され、米軍当局やGHQのマッカーサーにも提出され検閲を仰いでいた。
『鉄の暴風』を書いた太田記者の取材源は、「社」が集め、「社」(沖縄タイムス)のバックには米軍の強大な機動力と情報網があった。
ちなみに民間人の足として「沖縄バス」と「協同バス」が運行を開始するのは翌年、『鉄の暴風』が発刊された昭和25年 の4月1日 からである。
『鉄の暴風』の出版意図を探る意味で、昭和25年8月に朝日新聞より発刊された初版本の「前書き」の一部を引用しておく。
≪なお、この動乱を通じ、われわれ沖縄人として、おそらく終生忘れることができないことは、米軍の高いヒューマニズムであった。国境と民族を超えた彼らの人類愛によって、生き残りの沖縄人は、生命を保護され、あらゆる支援を与えられ、更正第一歩踏み出すことができたことを特記しておきたい≫
米軍のプロパガンダとして発刊されたと考えれば、『鉄の暴風』が終始「米軍は人道的」で「日本軍は残虐」だという論調で貫かれていることも理解できる。
実際、沖縄戦において米軍は人道的であったのか。
彼らの「非人道的行為」は勝者の特権として報道される事はなく、すくなくとも敗者の目に触れることはない。
ところが、アメリカ人ヘレン・ミアーズが書いた『アメリカの鏡・日本』は、米軍の沖縄戦での残虐行為に触れている。
その一方、米軍に攻撃された沖縄人によって書かれた『鉄の暴風』が米軍の人道性を褒め称えている事実に、この本の欺瞞性がことさら目立ってくる。
沖縄戦で米軍兵士が犯した残虐行為をアメリカ人ヘレン・ミアーズが同書の中で次のように記述している。
≪戦争は非人間的状況である。自分の命を守るために戦っているものに対して、文明人らしく振る舞え、とは誰もいえない。ほとんどのアメリカ人が沖縄の戦闘をニュース映画で見ていると思うが、あそこでは、火炎放射器で武装し、おびえきった若い米兵が、日本兵のあとに続いて洞窟から飛び出してくる住民を火だるまにしていた。あの若い米兵たちは残忍だったのか? もちろん、そうではない。自分で選んだわけでもない非人間的状況に投げ込まれ、そこから生きて出られるかどうかわからない中で、おびえきっている人間なのである。戦闘状態における個々の「残虐行為」を語るのは、問題の本質を見失わせ、戦争の根本原因を見えなくするという意味で悪である。結局それが残虐行為を避けがたいものにしているのだ。≫(ヘレン・ミアーズ著「アメリカの鏡・日本」)
『鉄の暴風』が発刊される二年前、昭和23年に『アメリカの鏡・日本』は出版された。
著者のヘレン・ミアーズは日本や支那での滞在経験のある東洋学の研究者。
昭和21年、GHQに設置された労働局諮問委員会のメンバーとして来日し、労働基本法の策定に参加。アメリカに帰国した後、同書を書き上げた。
だが、占領下の日本では、GHQにより同書の日本語の翻訳出版が禁止され、占領が終了した1953(昭和28)年になって、ようやく出版されることとなった。
沖縄人を攻撃したアメリカ人が書いた本がアメリカ軍に発禁され、
攻撃された沖縄人が書いた『鉄の暴風』がアメリカ軍の推薦を受ける。
これは歴史の皮肉である。
【ヘレン・ミアーズ著「アメリカの鏡・日本」の内容】
日本軍による真珠湾攻撃以来、我々アメリカ人は、日本人は近代以前から好戦的民族なのだと信じこまされた。しかし、前近代までの日本の歴史を振り返ると、同時代のどの欧米諸国と比較しても平和主義的な国家であったといえる。開国後、近代化を成し遂げる過程で日本は、国際社会において欧米先進国の行動に倣い、「西洋の原則」を忠実に守るよう「教育」されてきたのであり、その結果、帝国主義国家に変貌するのは当然の成り行きだった。
以後の好戦的、侵略的とも見える日本の行動は、我々欧米諸国自身の行動、姿が映し出された鏡といえるものであり、東京裁判などで日本の軍事行動を裁けるほど、アメリカを始め連合国は潔白でも公正でもない。また日本が、大戦中に掲げた大東亜共栄圏構想は「法的擬制」(本書中にしばしば登場する言葉で、「見せかけ」、「建て前」と類義)であるが、アメリカのモンロー主義同様、そのような法的擬制は「西洋の原則」として広く認められていた。さらに戦前・戦中においては、国際政治問題は「道義的」かどうかではなく「合法的」かどうかが問題とされていたのであり、戦後になって韓国併合や満州事変も含め、道義的責任を追及する事は偽善である。
実際に戦前・戦中の段階で、日本の政策に対して人道的懸念を公式表明した国は皆無であり、自国の「合法性」を主張する言葉でのみ日本を非難し続けるのは不毛であるとする。