
 ⇒最初にクリックお願いします
⇒最初にクリックお願いします
■良書紹介
「自立自尊であれ」
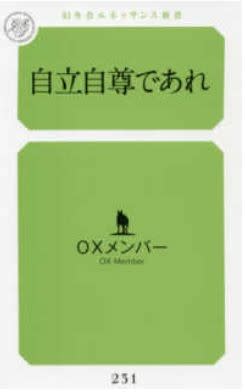
著者:OXメンバー
本書の著者名は「ОⅩメンバー」とする。
メンバーは沖縄県庁のОBとマスコミ関係者あわせて5人。「ОⅩ」は沖縄伝統闘牛の牡牛をイメージした。元沖縄県知事仲井真弘多の人物像と、仲井真県政の仕事を読者に伝えるのが主眼。チームとして2年半かけて取材し、苦闘した本に完成した共同作品である。
従って、個々人の筆名よりもチームであることを優先して編著とした。すべては事実に基づき書かれた。
元沖縄県知事仲井真弘多が語る沖縄振興の現実
普天間基地移設問題、自立経済の確立
教科書では学べない、沖縄のリアリティがここにある。
自立自尊であれ
定価 880円
目次
第一章 奇跡の成果
第二章 理の人 情の人
第三章 強くやさしい自立型社会
第四章 基地問題の「解」
1 普天間飛行場の危険性除去
2 マスコミ不信
3 返還地後利用推進法
4 安全保障環境と防衛
★
「天皇メッセージ」は沖縄を売ったのか! サンフランシスコ講和会議と「屈辱の日」 江崎 孝 (雑誌『正論』の原稿)
■4月28日、沖縄メディアが集団発狂した!
4月28日、沖縄のメディアは、まるでメディア・ジャックそのままに、政府に対し恨みつらみの言葉を投げ続けた。沖縄2大紙の沖縄タイムスと琉球新報は、その日東京で行われた政府主催の「主権回復」式典に抗議するキャンペーンを展開し、地元3テレビ・ラジオもこれに追随した。QABテレビ、RBCテレビ、沖縄テレビなどは、「主権の日」を「4・28屈辱の日」と位置づけて抗議する特別番組を組んだ。
東京では、サンフランシスコ講和条約が発効した1952年4月28日を記念する政府主催の「主権回復・国際社会復帰を記念する式典」が天皇、皇后両陛下御臨席のもと開催されていた。
それと同時刻、沖縄県では「4・28政府式典に抗議する『屈辱の日』沖縄大会」が宜野湾市海浜公園の野外劇場で開かれた。
4000人収容の会場は、一般県民のほか、沖教組、労組や革新政治団体などのノボリを持った人々で埋め尽くされた。沖縄平和運動センター傘下の労組、共産党や社民党などの革新政党、左翼学生団体が参集したが、県知事や自民党、公明党、民主党などは参加しなかった。
■「屈辱の日」の原因は「天皇メッセージ」
沖縄の革新勢力が政府に抗議しマスコミを巻き込んで集団発狂したかのようなキャンペーンを張ることは過去にも良くあることで、特に珍しいことではない。だが、今回の「政治的集団発狂」には昭和天皇を怨嗟する象徴的キーワードが潜んでいた。 「天皇メッセージ」のことである。
「天皇メッセージ」とは、沖縄の祖国復帰7年後の1979年、進藤栄一・筑波大学助教授(当時)が米国の公文書館から「マッカーサー元帥のための覚書」を発掘し、雑誌『世界』で発表したもの。
同覚書には、宮内府御用掛かり寺崎英成がGHQ政府顧問ウイリアム・シーボルトを訪れ、天皇からのメッセージを伝えたと記されている。これがいわゆる「天皇メッセージ」とされるもので、概略こう述べられている。
「天皇の顧問、寺崎英成氏が、沖縄の将来に関する考えを私に伝える目的で、時日をあらかじめ約束したうえで訪ねてきた。 寺崎氏は、米国が沖縄その他の琉球諸島の軍事占領を継続するよう天皇が希望していると、言明した。(略)さらに天皇は、沖縄(および必要とされる他の諸島)に対する米国の軍事占領は、日本が主権を残したままの長期租借ー25年ないし50年、あるいはそれ以上ーの擬制(フィクション)にもとづいてなされるべきだと考えている」
これは沖縄に流布する大きな誤解の一つだが、沖縄保守系の論客の中にも「天皇メッセージ」とは天皇自ら「沖縄をアメリカに売り渡す」と書いた文書が米公文書館から発見された、と誤解する人が多い。
筆者の知人にも終戦当時既に米軍占領下にあった沖縄が米国統治になったのはやむ得ないとしても、「天皇自らが(命乞いのように)沖縄を売り渡す手紙を書いた」のは許せないと息巻く人もいるくらいだが、実際は「天皇の密書」が存在するわけではない。
寺崎が昭和天皇の会話の中から沖縄についての陛下の「思い」を斟酌してシーボルトに伝え、それがシーボルトの手紙という形でワシントンに伝えられたのだ。 「天皇メッセージ」はシーボルトの手紙では"Emperor of Japan's Opinion Concerning the Future of the Ryukyu Islands"と訳されている。
「天皇メッセージの」重要ポイントである「潜在主権」、つまり日本の主権を残したまま米国に統治を委任することを、親子の例えると、子ども(沖縄)を育てる経済力のない親(日本)が金持ち(米国)に、戸籍はそのまま一時里子に出したようなものであり、戸籍を移籍する養子縁組(米国領にすること)とは根本的に異なる。
当時世界一の経済力を誇る米国の統治下にあった沖縄では、食糧不足で喘ぐ祖国日本では食すること出来ない米国産の豊富な食料供給の恩恵に浴した。 その名残の一つがランチョンミート文化であり、戦前の沖縄にはなかったビーフステーキやハンバーガーなど牛肉文化の繁栄である。
■日本の「主権回復の日」は沖縄の「屈辱の日」
安倍内閣が講和条約が発効した1952年4月28日を「主権回復の日」とする閣議決定した3月12日前後から、沖縄メディアは一斉に反発し、沖縄2大紙の紙面には「沖縄を切り捨てて何が主権回復か」とか「沖縄を人質に」「沖縄を捨石に」などのルサンチマンが躍った。QABテレビの「屈辱の日」特番に出演した沖縄国際大学准教授の友知政樹氏は、講和条約と「天皇メッセージ」との関係を問われこう述べた。
<この言葉(天皇メッセージ)によって(沖縄は)切り捨てられた、それによって「屈辱の日」だという風に捉えられがちですけども、切り捨てられた、置いていかれたとの意味での屈辱ではなくて、日本に強制的な施策を沖縄にかぶせられてしまったという意味あいで非常に屈辱と考えています。>
同じ日のテレビ朝日「モーニングバード」に出演した沖縄国際大学の前泊博盛教授は「(4・28主権の日は)沖縄が切り離されて、ある意味切り捨てられた日。沖縄の主権がはく奪された日です」と吐き捨てた。
「屈辱の日」で「政治的集団発狂」の仲間入りをしたのは、地元学者や沖縄のメディアだけではなかった。 県高教組は、講和条約が発効した「4月28日」を高校生に周知徹底させるためと称し、資料「『4・28』について考える」を県下の県立高校に配布した。

その資料では、1952年4月28日を「沖縄の米軍統治が合法化された『屈辱の日』」と位置付け、祖国復帰運動のきっかけになった日と紹介。政府が4月28日に「独立を認識する節目の日」として式典を開くことについて、「新たな『屈辱の日』。沖縄が切り捨てられた日に式典を開くねらいは何なのか考えてみましょう」と呼び掛けた。
まるで政治ビラを髣髴させる同資料は「4:28について考える」と、「主権回復の日? 主権喪失の日?」というタイトルが付けられ次のような祖国日本への呪詛が綴られている。
<1945年5月、米国政府は沖縄を日本本土から切り離し、長期的に保有して基地の拡大を図る政策を決定した。これによって沖縄を「太平洋の要石」に変貌させられることになる。だが、この政策は、米国が一方的に日本に押し付けたものではなかった。 琉球諸島の長期保有をアメリカ側に求めた「天皇メッセージ」でも明らかなように、日本側の意図が強く働いていたのである。 日米両政府は、本土の独立によって平和憲法に基づく非軍事化と民主化を実現するため、沖縄に軍事基地を押し付けたのである。>
新城俊昭沖縄大学客員教授が作成した同資料には「天皇メッセージ」の意図について、「沖縄を米兵に提供することで、天皇制の護持をはかろうとした」と解説されている。
■「天皇メッセージ」は沖縄を売ったのか
では、講和条約締結やその7年前に伝えられたとされる「天皇メッセージ」は、沖縄メディアや地元識者、そして県高教組などが喧伝するように沖縄を犠牲にしたり、捨石にする意図でなされたのか。
日本は沖縄を切り捨てることにより主権を回復したのか。 結論から先に言わせて貰うと、否である。
先ず「天皇メッセージ」が伝えられたとされる昭和23年前後、日本を取り巻く国際情勢はどのようなものであったか。
終戦の反動により共産党や社会党の人気が高く、6月には社会党の片山内閣が成立していた。時代は東西冷戦の幕開けであり、既に21年には、訪米中の元英国首相チャーチルが「鉄のカーテン」で知られる演説で、共産圏の閉鎖性を指摘している。
さらに23年9月には金日成の北朝鮮が成立し、24年には毛沢東の中華人民共和国が成立。翌25年には朝鮮戦争が勃発する。このような時代背景では、敗戦で丸腰状態になった我国は、経済的にも軍事的にもアメリカの支援なくしては独立はありえなかった。戦前との価値観が180度変わったといわれる日本国民は占領国アメリカの庇護の下、戦争放棄が盛り込まれた新憲法草案が審議されている段階で「平和の府・国連」へのバラ色の夢に耽っていた。
国民も政治家たちの関心は、食うや食わずの経済的国内事情に片寄っており、既に始まっていた米ソ冷戦にまで真剣に気を配る余裕などなかった。
そんな中、わが国の安全保障に一番気を配ったのが昭和天皇であった。 近代史の専門家である秦郁彦氏は「天皇メッセージ」についてその著書「昭和天皇五つの決断」(文藝春秋)で、次のように述べている。 「23年早々という早い時点で、アメリカのアジア戦略の動向を正確に探知して、適切な情勢判断を示した天皇の洞察力には脱帽のほかない・・・」
■講和調印当時の日米の立場の差、
講和条約が調印される1951年4月11日、マッカーサーは朝鮮戦争の作戦に関しトルーマン大統領との対立により突然更迭され、後任のマシュー・リッジウェイ中将が第二代最高司令官に就任する(就任後に大将へ昇進)。
当時日本国民にとって守護神のように慕われていたマッカーサーの突然の更迭劇に、マッカーサーを信頼していた昭和天皇と吉田茂首相にも動揺が走った。
「臣吉田」と自称するほど昭和天皇を敬愛していた吉田茂と昭和天皇がマッカーサーの更迭により動揺し、日本の政治に乱れが生じて講和条約の調印が不首尾に至るのを恐れた米国務省は、ダレス政治顧問(後に国務長官)を日本に派遣し、司令官が変わってもGHQの政策に何ら変更もないと説得した。
その時、約5ヵ月後に迫った講和会議の開催地についての意見を問われた吉田は「それより誰が全権か、自分がなるかどうかわからない」などと投げやりな態度で対応した。
吉田はワンマンとあだ名され、健康の秘訣は「人を食うこと」などと人を食った発言で有名な人物。
吉田はマッカーサーの突然の更迭劇に対し不満があったのか、ダレスの問いに投げやりな態度を示したが、これに対するダレスの言葉が、当時の日本とアメリカの力関係を如実に示している。
現在の日米関係では、首相に対しては大統領が対応するのが外交慣例だが、当時吉田首相と講和条約について話し合ったのはマッカーサーを更迭したトルーマン大統領でもなければ国務長官でもなく、公的役職のない米国務省政治顧問のダレスだった。ダレスは日本の首相吉田にこう言い放った。
「講和条約に関する日本政府の立場を君(吉田)は誤解している。 この件は米国政府が義務からではなく、好意と善意をもって進めているので、日本政府は相談を受けるだけの資格しかないのだ」
■「講和条約」は沖縄を売ったのか。
1952年4月28日、講和条約発効の日、当時の沖縄住民は祖国日本の独立を日の丸を掲げて祝賀した。祖国日本が主権を回復してこそ、沖縄の祖国復帰は始まらないことを承知していたからだ。 そう、日本が主権を回復したからこそ、20年後の「5・15(沖縄復帰の日)」は実現したのだ。 先の大戦で沖縄は日本の一部として戦った。そして敗戦の結果米軍の占領下にあった。米軍占領の間は日本に主権がないのは勿論、戦闘は終了したが、国際法上は依然として米国とは戦争状態にあった。 米軍は沖縄上陸当時から、将来も沖縄を日本から分離することを目論んでいた。
物には順序というものがある。
主権もない敗戦国の日本が沖縄分離を目論む戦勝国に対抗するには、先ず日本の主権回復が第一歩ではなかったのか。
■外交文書が語る日本側の努力とは
圧倒的に発言権の強い米国との条約締結交渉に際し、微力ながら抵抗した外務省の苦労話が、2001年に公開され、翌年刊行された『日本外交文書ー平和条約の締結に関する文書』に記されている。 当時の吉田政権は沖縄メディアが喧伝するように、沖縄を犠牲にして自分だけが主権回復する意図はなく、あくまでも沖縄分離を避けるためいろいろの策を検討していた。だが圧倒的に力の差のある米国の厚い壁に阻まれ、将来の沖縄返還のための次善の策として、「沖縄の主権は日本に残した(潜在主権)」状態での租借(リース)にこぎつけた。
これは、7年前の「天皇メッセージ」の意を汲んだものと容易に想像できる。 沖縄の地位に関して頑なな態度を示す米側との話し合いの直前になって外務省が、沖縄に関する案を一部変更した。
外交官出身の吉田茂首相はその豊富な外交経験から得た知識なのか、首相自らの指示により、「バーミューダー方式による租借も辞さない」という一文が付け加えられたのだ。 「バーミューダー方式」とは、1940年にイギリスの植民地バーミューダーに米軍基地を置くため、イギリスから99年間租借した協定を指す。
当時事務方だった外務省の西村熊雄条約局長は、この吉田の態度について、のちにこう回想している。 「(沖縄を)『租借地』にして提供していいから信託統治にすることは思いとどまってほしいといわれる総理の勇断にいたく感銘した」
米国は沖縄侵攻当初から沖縄を「太平洋の要石(かなめいし)」と捉え、日本と沖縄を分断の上永久占領を目論んでいた。
講和条約締結時の日米両国の力関係を言えば、米国は世界一の経済力と軍事力を誇る戦勝国であり、一方の日本は、首都東京をはじめ地方の各都市も空爆により焦土と化した軍備も持たない米軍占領下の敗戦国である。両者の力の差は歴然としており、仮に米国が条文に明記されているように、「(沖縄を)米国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におく」と提案したら、日本は否応なしに同意せざるを得なかった。
沖縄を信託統治にすればいずれは現在のグアムやプエルトリコのように米国の自治領に移行することは必至であった。 ところが不思議なことに米国は、喉から手が出るほど領有を望んだ沖縄を信託統治にする提案はしなかった。
米国は沖縄を日本の主権を残したまま、統治権のみを継続したのだ。昭和天皇の「メッセージ」の通りに。
■吉田茂の決断
1951年1月末、アメリカのダレス特使と吉田首相との間で講和をめぐって話し合いがもたれるが、領土問題に関する米側の態度は、極めてシビアであった。日本側が米側に提出した「わが方見解」なる文書で「バーミューダー方式」の方針を伝えていた吉田に対し、ダレスは率直にこう述べている。 「国民感情はよく解るが、(この問題は)降伏条項で決定済みであって・・・セットル(解決)したこととして考えて貰いたい」。 このダレスのすげない態度に接した日本側は、次善の策を講じて「沖縄の完全分離」に抵抗を示すことになる。
「肉を切らせて骨を断つ」にも似た捨て身の策である。
米側の信託統治構想を拒否するのは困難と判断し、それに異論を挟まないと断った上で、交換条件として次の条件などを米側に求めていくのである。
(1)沖縄住民の日本国籍確保(潜在主権)⇒(天皇メッセージ)
(2)バーミューダー方式⇒(分離ではなく期限付き租借・天皇メッセージ)
(3)本土と同様な教育方針の継続、⇒(文部省教科書の使用、無償措置法の適用)、
(4)そして本土と沖縄との経済関係の維持(⇒援護法の優先的適用など)
いうまでもなく吉田首相の提案は、その4年前に昭和天皇が宮内庁御用掛かり寺崎英成を通じて米側に伝えられたとされる「天皇メッセージ」と同根である。吉田と同じく優秀な外交官出身の寺崎が昭和天皇との会話の中で「バーミューダー方式」を昭和天皇にご進講したことも想像できるが、確証はない。
■1952年「講和発効の日」の沖縄県民は・・・
半世紀以上前の対日講和条約の発効の日の沖縄の状況を、2013年4月20日付琉球新報がこう伝えている。
<対日講和条約が発効した1952年4月28日、県内の新聞は「祖国の独立を祝う」と日本が国際社会に復帰することを歓迎する一方、沖縄の「日本復帰を確信する」との比嘉秀平主席のメッセージを掲載した。 「当時は日本に沖縄の潜在主権があるから、いつか日本に帰れるという安心感があったから、祖国の独立を喜ぶことの方が大きかった」。元琉球新報記者の下地寛信さん(87)は振り返る。(略)52年当時、大学生で、琉球新報東京支社でアルバイトの記者をしていた親泊一郎さん(81)は「当時はよく沖縄は里子だという言葉が使われた。親に返る時は立派に成長して帰り、親に喜ばれなければいかん、それまでじっと我慢して頑張っていこう。そんな雰囲気があった」と話した。>
当時筆者は10歳だったが、学校では先生が「祖国日本が独立したので、沖縄の祖国復帰も近い」といった喜びの言葉で説明したと、おぼろげながら記憶している。
■昭和天皇とマッカーサー
日本を占領したマッカーサーは昭和天皇と11回にも及ぶ面談 をした。
マッカーサーは絶対的権力を誇ったが、意外なことに6年余の日本統治期間に面会した日本側要人は少なく、マッーサーが信頼できる日本側の代表として日本の将来について議論したのは、吉田茂と昭和天皇の2人くらいだったと言われている。
そんな状況で昭和天皇は、当時の日本の政治家の誰もが思いも及ばぬ国際情勢に対する洞察力と政治力を発揮し、マッカーサーを在任中合計11回も訪問し日本の将来について議論をしているが、その内容はマッカーサーとの「男の約束」で現在もその全貌は明らかにされていない。
その間に「天皇メッセージ」がマッカーサーの政治顧問を通じてワシントンに伝えられたとされている。
講和条約で米国と交渉した吉田首相率いる外交当局は、「天皇メッセージ」に見る昭和天皇の思いを実現させるべく、米国側の沖縄分離案に必死に抵抗した。
講和条約にしたためられた「主権条項」は、昭和天皇の「主権は残す」という思いを実現させるため「信託統治を提案されても辞さず」という吉田首相の覚悟が表れている。
昭和天皇と外交当局の捨て身の交渉に、さしもの米国も最後まで「沖縄を信託統治にする」という提案をしなかった。「日本の主権を残した(潜在主権の)ままリースにする」という「天皇メッセージ」こそが当時の日本として実行できる最善の策であった。
■まとめ
「現代の感覚で過去を判断する史家は歴史を過つ」といわれる。 「天皇メッセージ」や講和条約締結の功罪を問う者は、終戦直後の日本を取り巻く国際情勢、即ち「米ソ冷戦の幕開け」と日米両国の圧倒的な国力及び交渉力の格差を思慮に入れなければ歴史の判断を誤ってしまう。
近代史の専門家・秦郁彦氏も驚嘆するように、敗戦直後の社会党政権(片山内閣)下で、当時の社会情勢では政府の誰もが思いも及ばなかった「潜在主権のまま」で、いつかは祖国に帰る日のために統治を委任するという方法を思いついた昭和天皇の判断力の確かさは「天皇メッセージ」というより、「昭和天皇の大御心(おおみごごろ)」と訳した方が的を射ているのではないか。
たとえ講和条約締結の結果、沖縄が米軍の統治下になったとしても、「潜在主権」による期限付き租借(リース)という奇手で、米国の「信託統治の提案」に牽制をかけたことは、まぎれもない歴史の事実である。
「天皇メッセージ」の意を汲んだサンフランシスコ講和条約が国際的に弱い立場の当時の日本が出来た精一杯、かつ最善の意思表示ではなかったのか。(完)
【補記】 沖縄の教育に関しては、米軍統治下で文部省教科書で祖国日本と同じ教育を実施した他に、政府は沖縄の学生だけに限る選抜試験を行い、全国の国立大学に国負担で受け入れている(国費留学制)。 ちなみに仲井眞弘多県知事はこの国費留学制度の恩恵で東京大学を卒業している。























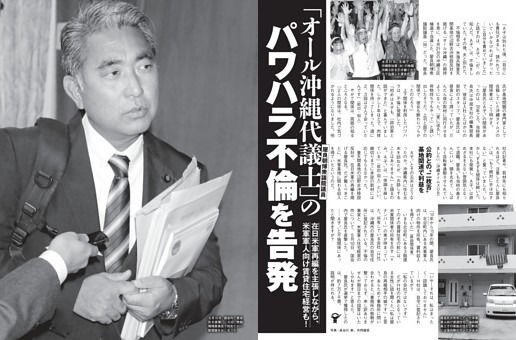





 </picture>
</picture>



