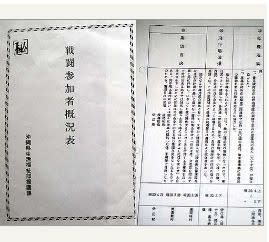読者の皆様には大変ご心配おかけしましたが、念願の拙著『沖縄「集団自決」の大ウソ』(第2刷)が完成いたしました。
皆様のご支援感謝申し上げます。
慣れぬ仕事で配本名簿にミスが生じる可能性もあります。
そこで、ご注文、御献金の方で来週末までに本が未着の場合、下記メルアドまで配送先及び冊数をご一報くださいますよう再度お願いします。
メルアド⇒ ezaki0222@ybb.ne.jp
★
『沖縄「集団自決」の大ウソ』、好評発売中です。
御注文ご希望の方は、下記要領でお申し込み下さい。
購入手続きは、送付先の住所明記の上、下記の金額を指定口座に振り込んでください。
宜しくお願いします。
江崎 孝
振込金額 1冊 1500円 +送料300円 = 1800円
(※三冊以上ご購入の方は、送料は当方で負担しますので、4500円振込)
お振込先
- 金融機関:ゆうちょ銀行
- 名義:江崎 孝
- 記号:17050
- 番号:05557981
ゆうちょ銀行以外からお振り込む場合の振込先
- 金融機関:ゆうちょ銀行
- 金融機関コード:9900
- 預金種目:普通預金
- 名義:江崎 孝
- 店名:708(読み ナナゼロハチ)
- 店番:708
- 口座番号:0555798
新聞「アイデンティティ」2月1日号に拙稿「沖縄を歪めた沖縄戦後史の大ウソ」が掲載されました。
沖縄を歪めた戦後史の大ウソ
~『沖縄「集団自決」の大ウソ』~発刊をめぐり~
 江崎 孝 (ブロガー:「狼魔人日記」管理人)
江崎 孝 (ブロガー:「狼魔人日記」管理人)
沖縄の祖国復帰以来、約半世紀経過した。 だが現在も沖縄には、二つのタブーがある。「米軍基地問題」と「沖縄戦」だ。
そこで、本稿では、8年前の「集団自決」を巡る最高裁判決で被告の大江健三郎・岩波書店側が勝訴して以来、一件落着と思われている沖縄戦の「集団自決」問題について検証して見る。
大江健三郎・岩波書店「集団自決裁判」(以後、大江・岩波訴訟)とは、元沖縄戦戦隊長および遺族が、大江健三郎・岩波書店を名誉毀損で訴えた裁判のことである。
沖縄戦の集団自決について、事実関係はこうだ。
大江健三郎(岩波書店:1970年)の著書『沖縄ノート』に、当時の座間味島での日本軍指揮官梅澤裕元少佐および渡嘉敷島での指揮官赤松嘉次元大尉が住民に自決を強いたと記述され、名誉を毀損したとして梅澤裕氏および赤松秀一氏(赤松嘉次の弟)が、名誉毀損による損害賠償、出版差し止め、謝罪広告の掲載を求めて訴訟を起こした。本訴訟は最高裁に縺れ込んだが結局、2011年4月21日、最高裁は上告を却下。被告大江側の勝訴が確定した。
■沖縄タイムスの印象操作
沖縄には約20数年前の最高裁判決を盾に巧みに印象操作し続けている新聞がある。 その新聞こそ、「集団自決軍命説」の発端となった『鉄の暴風』の出版元沖縄タイムスである。
印象操作報道の一例として、2023年5月29日付沖縄タイムスは大江・岩波「集団自決」訴訟の最高裁判決について次のように報じている。
《沖縄戦時に慶良間諸島にいた日本軍の元戦隊長と遺族らが当時、住民に「集団自決」するよう命令はしていないとして、住民に命令を出したとする『沖縄ノート』などの本を出版した岩波書店と著者の大江健三郎さんに対する「集団自決」訴訟を大阪地方裁判所に起こした。国が07年の教科書検定で、日本軍により「自決」を強制されたという表現を削らせきっかけになる。11年4月に最高裁への訴えが退けられ、元戦隊長側の主張が認められないことに決まった。(敗訴が確定)》
沖縄タイムスの主張を要約すれば、「『集団自決』は軍の命令ではないと主張する元軍人側の主張は、最高裁で否定され、被告大江・岩波側の『集団自決は軍命による』という主張が最高裁で確定した」ということだ。
だが、事実は違う。
沖縄タイムスは、戦後5年米軍票から米ドルに通貨を切り替えるという米軍提供の特ダネと交換条件で、1950年に米軍の広報紙として発行された。
以後同紙編著の『鉄の暴風』は沖縄戦のバイブルとされ、同書を出典として数え切れない引用や孫引き本が出版され続けてきた。
しかし残念ながら元軍人らによる大江岩波集団自決訴訟は敗訴が確定し、集団自決問題は国民・県民の記憶から遠ざかりつつある。
このように、大江岩波訴訟で被告大江岩波側の勝訴が確定し国民の「集団自決」問題が一件落着した思われている今年の9月、筆者は『沖縄「集団自決」の大嘘』と題する書籍を出版した。
さて、すでに決着済みと思われている沖縄戦「集団自決問題」に今さら本書を世に問う理由は何か。
その訳を述べよう。
確かに沖縄の集団自決問題は大江岩波訴訟の結果すでに決着済みと思われている。
この現実を見たら、多くの国民や沖縄県民は、集団自決論争は終焉したと考えても不思議ではない。
だが、岩波大江訴訟で確定したのは、「軍命の有無」ではない。最高裁判決は大江健三郎と岩波書店に対する名誉棄損の「損害賠償請求の免責」という極めて平凡な民事訴訟の勝訴に過ぎない。
肝心の「軍命の有無」については、一審、二審を通じて被告大江側が「両隊長が軍命を出した」と立証することはできなかった。
その意味では原告梅澤、松ら両隊長の汚名は雪がれたことになる。しかし沖縄タイムス等反日勢力は問題をすり替え、あたかも両隊長の「軍命」が確定したかのように、次の目標として「軍命の教科書記載」を目論み、あくまでも日本を貶める魂胆だ。
ほとんどの国民が集団自決問題を忘れた頃の2022年7月10日付沖縄タイムスは、こんな記事を掲載している。
《「軍命」記述を議論 9・29実現させる会 教科書巡り、2022年7月10日
沖縄戦の「集団自決(強制集団死)」を巡り、歴史教科書への「軍強制」記述の復活を求める「9・29県民大会決議を実現させる会」(仲西春雅会長)の定例会合が4日、那覇市の教育福祉会館であった。3月の検定で国語の教科書に「日本軍の強制」の明記がされたことについて意見を交換。社会科の教科書で記述の復活がないことから、今後も活動を継続していく意見が相次いだ。》
■歴史は「県民大会」が決めるものではない
『沖縄「集団自決」の大ウソ』を世に問う第一の目的は、沖縄タイムス編著の『鉄の暴風』が歪曲した沖縄戦歴史を正し、「残酷非道な日本軍」を喧伝する沖縄タイム史観の教科書記述を阻止することである。最高裁による確定後、歴史の是正を巡る状況はさらに新たな展開があった。
『鉄の暴風』が主張する「軍命論」を粉砕する決定的証拠が出てきたのだ。 仮にこの証拠が大江岩波訴訟の前に登場していたら、裁判の判決も逆だった可能性すらある。
これまで「軍命論争」には、「手りゅう弾説」~大江健三郎の「タテの構造説」など数多くの証拠、証言が論じられた。その中で「援護法による軍命説」は、法廷では一つの推論に過ぎず決定的ではないと言われ、証拠として採用されなかった。
■「援護法のカラクリ」が暴く軍命の大ウソ
「戦闘参加者概況表」(裏の手引書)
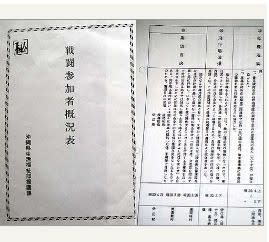

ところが「援護法と軍命のカラクリ」を一番熟知する沖縄戦遺族会から決定的証拠を提供していただいた。 「軍命が捏造であることを示す」県発行の「戦闘参加者概況表」(裏の手引書)である。
この証拠を事前に入手していた「軍命派」の研究者達が、「軍命を捏造した」と白状し、さらに証拠の捏造に「恥を感じる」とまで言い切っている。これ以上の決着はないだろう。この一件こそが本書を世に問う最大の目的である。
次に「『沖縄集団自決』の大ウソ」を出版するもう一つの目的を述べておこう。
本書に収録の記事のほとんどは、約20年間ブログ『狼魔人日記』で書き綴った記事を編集したものである。だが、何事にも終りがある。
ブログ『狼魔人日記』の継続に終りが来た時、収録されて記事は広いネット空間に放り出される。 そして、そのほとんどが人の眼に触れる機会もないだろう。
古来、歴史とは文字に書かれ事物・事象が歴史として刻まれるという。 その伝で言えば、ネット上の記録など歴史としては一顧だにされないだろう。
ネット上の記録を紙に書いた記録にする。これが本書出版のもう一つの目的である。
誤った歴史が教科書に載ることはあってはならない。読者の皆様は印象操作に惑わされず、事実を追求して欲しい。拙著がその一助になることを願っている。完
【『沖縄「集団自決」の大ウソ』の購入方法:⇒ ezaki0222@ybb.ne.jp】

ご購入の方は下記要領でお申し込みください。*
*【購入手続き】*
*1冊 1500円 +送料300円 = 1800円*
*本購入手続きは、送付先の住所明記の上、上記金額を指定口座に振り込んでください。*
*★(振込日、振込人名義、送付先名、送付先住所、注文数をメールでお知らせください。その方がスムーズに書籍発送ができます。メルアド⇒ ezaki0222@ybb.ne.jp)*
*お振込先*
* 金融機関:ゆうちょ銀行
* 名義:江崎 孝
* 記号:17050
* 番号:05557981
*ゆうちょ銀行以外からお振り込む場合の振込先*
読者の皆様には大変ご心配おかけしましたが、念願の拙著『沖縄「集団自決」の大ウソ』(第2刷)が完成いたしました。
皆様のご支援感謝申し上げます。
慣れぬ仕事で配本名簿にミスが生じる可能性もあります。
そこで、ご注文、御献金の方で来週末までに本が未着の場合、下記メルアドまで配送先及び冊数をご一報くださいますよう再度お願いします。
メルアド⇒ ezaki0222@ybb.ne.jp
★
『沖縄「集団自決」の大ウソ』、好評発売中です。
御注文ご希望の方は、下記要領でお申し込み下さい。
購入手続きは、送付先の住所明記の上、下記の金額を指定口座に振り込んでください。
宜しくお願いします。
江崎 孝
振込金額 1冊 1500円 +送料300円 = 1800円
(※三冊以上ご購入の方は、送料は当方で負担しますので、4500円振込)
お振込先
- 金融機関:ゆうちょ銀行
- 名義:江崎 孝
- 記号:17050
- 番号:05557981
ゆうちょ銀行以外からお振り込む場合の振込先
- 金融機関:ゆうちょ銀行
- 金融機関コード:9900
- 預金種目:普通預金
- 名義:江崎 孝
- 店名:708(読み ナナゼロハチ)
- 店番:708
- 口座番号:0555798
新聞「アイデンティティ」2月1日号に拙稿「沖縄を歪めた沖縄戦後史の大ウソ」が掲載されました。
沖縄を歪めた戦後史の大ウソ
~『沖縄「集団自決」の大ウソ』~発刊をめぐり~
 江崎 孝 (ブロガー:「狼魔人日記」管理人)
江崎 孝 (ブロガー:「狼魔人日記」管理人)
沖縄の祖国復帰以来、約半世紀経過した。 だが現在も沖縄には、二つのタブーがある。「米軍基地問題」と「沖縄戦」だ。
そこで、本稿では、8年前の「集団自決」を巡る最高裁判決で被告の大江健三郎・岩波書店側が勝訴して以来、一件落着と思われている沖縄戦の「集団自決」問題について検証して見る。
大江健三郎・岩波書店「集団自決裁判」(以後、大江・岩波訴訟)とは、元沖縄戦戦隊長および遺族が、大江健三郎・岩波書店を名誉毀損で訴えた裁判のことである。
沖縄戦の集団自決について、事実関係はこうだ。
大江健三郎(岩波書店:1970年)の著書『沖縄ノート』に、当時の座間味島での日本軍指揮官梅澤裕元少佐および渡嘉敷島での指揮官赤松嘉次元大尉が住民に自決を強いたと記述され、名誉を毀損したとして梅澤裕氏および赤松秀一氏(赤松嘉次の弟)が、名誉毀損による損害賠償、出版差し止め、謝罪広告の掲載を求めて訴訟を起こした。本訴訟は最高裁に縺れ込んだが結局、2011年4月21日、最高裁は上告を却下。被告大江側の勝訴が確定した。
■沖縄タイムスの印象操作
沖縄には約20数年前の最高裁判決を盾に巧みに印象操作し続けている新聞がある。 その新聞こそ、「集団自決軍命説」の発端となった『鉄の暴風』の出版元沖縄タイムスである。
印象操作報道の一例として、2023年5月29日付沖縄タイムスは大江・岩波「集団自決」訴訟の最高裁判決について次のように報じている。
《沖縄戦時に慶良間諸島にいた日本軍の元戦隊長と遺族らが当時、住民に「集団自決」するよう命令はしていないとして、住民に命令を出したとする『沖縄ノート』などの本を出版した岩波書店と著者の大江健三郎さんに対する「集団自決」訴訟を大阪地方裁判所に起こした。国が07年の教科書検定で、日本軍により「自決」を強制されたという表現を削らせきっかけになる。11年4月に最高裁への訴えが退けられ、元戦隊長側の主張が認められないことに決まった。(敗訴が確定)》
沖縄タイムスの主張を要約すれば、「『集団自決』は軍の命令ではないと主張する元軍人側の主張は、最高裁で否定され、被告大江・岩波側の『集団自決は軍命による』という主張が最高裁で確定した」ということだ。
だが、事実は違う。
沖縄タイムスは、戦後5年米軍票から米ドルに通貨を切り替えるという米軍提供の特ダネと交換条件で、1950年に米軍の広報紙として発行された。
以後同紙編著の『鉄の暴風』は沖縄戦のバイブルとされ、同書を出典として数え切れない引用や孫引き本が出版され続けてきた。
しかし残念ながら元軍人らによる大江岩波集団自決訴訟は敗訴が確定し、集団自決問題は国民・県民の記憶から遠ざかりつつある。
このように、大江岩波訴訟で被告大江岩波側の勝訴が確定し国民の「集団自決」問題が一件落着した思われている今年の9月、筆者は『沖縄「集団自決」の大嘘』と題する書籍を出版した。
さて、すでに決着済みと思われている沖縄戦「集団自決問題」に今さら本書を世に問う理由は何か。
その訳を述べよう。
確かに沖縄の集団自決問題は大江岩波訴訟の結果すでに決着済みと思われている。
この現実を見たら、多くの国民や沖縄県民は、集団自決論争は終焉したと考えても不思議ではない。
だが、岩波大江訴訟で確定したのは、「軍命の有無」ではない。最高裁判決は大江健三郎と岩波書店に対する名誉棄損の「損害賠償請求の免責」という極めて平凡な民事訴訟の勝訴に過ぎない。
肝心の「軍命の有無」については、一審、二審を通じて被告大江側が「両隊長が軍命を出した」と立証することはできなかった。
その意味では原告梅澤、松ら両隊長の汚名は雪がれたことになる。しかし沖縄タイムス等反日勢力は問題をすり替え、あたかも両隊長の「軍命」が確定したかのように、次の目標として「軍命の教科書記載」を目論み、あくまでも日本を貶める魂胆だ。
ほとんどの国民が集団自決問題を忘れた頃の2022年7月10日付沖縄タイムスは、こんな記事を掲載している。
《「軍命」記述を議論 9・29実現させる会 教科書巡り、2022年7月10日
沖縄戦の「集団自決(強制集団死)」を巡り、歴史教科書への「軍強制」記述の復活を求める「9・29県民大会決議を実現させる会」(仲西春雅会長)の定例会合が4日、那覇市の教育福祉会館であった。3月の検定で国語の教科書に「日本軍の強制」の明記がされたことについて意見を交換。社会科の教科書で記述の復活がないことから、今後も活動を継続していく意見が相次いだ。》
■歴史は「県民大会」が決めるものではない
『沖縄「集団自決」の大ウソ』を世に問う第一の目的は、沖縄タイムス編著の『鉄の暴風』が歪曲した沖縄戦歴史を正し、「残酷非道な日本軍」を喧伝する沖縄タイム史観の教科書記述を阻止することである。最高裁による確定後、歴史の是正を巡る状況はさらに新たな展開があった。
『鉄の暴風』が主張する「軍命論」を粉砕する決定的証拠が出てきたのだ。 仮にこの証拠が大江岩波訴訟の前に登場していたら、裁判の判決も逆だった可能性すらある。
これまで「軍命論争」には、「手りゅう弾説」~大江健三郎の「タテの構造説」など数多くの証拠、証言が論じられた。その中で「援護法による軍命説」は、法廷では一つの推論に過ぎず決定的ではないと言われ、証拠として採用されなかった。
■「援護法のカラクリ」が暴く軍命の大ウソ
「戦闘参加者概況表」(裏の手引書)
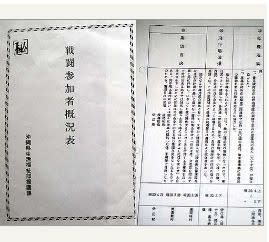

ところが「援護法と軍命のカラクリ」を一番熟知する沖縄戦遺族会から決定的証拠を提供していただいた。 「軍命が捏造であることを示す」県発行の「戦闘参加者概況表」(裏の手引書)である。
この証拠を事前に入手していた「軍命派」の研究者達が、「軍命を捏造した」と白状し、さらに証拠の捏造に「恥を感じる」とまで言い切っている。これ以上の決着はないだろう。この一件こそが本書を世に問う最大の目的である。
次に「『沖縄集団自決』の大ウソ」を出版するもう一つの目的を述べておこう。
本書に収録の記事のほとんどは、約20年間ブログ『狼魔人日記』で書き綴った記事を編集したものである。だが、何事にも終りがある。
ブログ『狼魔人日記』の継続に終りが来た時、収録されて記事は広いネット空間に放り出される。 そして、そのほとんどが人の眼に触れる機会もないだろう。
古来、歴史とは文字に書かれ事物・事象が歴史として刻まれるという。 その伝で言えば、ネット上の記録など歴史としては一顧だにされないだろう。
ネット上の記録を紙に書いた記録にする。これが本書出版のもう一つの目的である。
誤った歴史が教科書に載ることはあってはならない。読者の皆様は印象操作に惑わされず、事実を追求して欲しい。拙著がその一助になることを願っている。完
【『沖縄「集団自決」の大ウソ』の購入方法:⇒ ezaki0222@ybb.ne.jp】

ご購入の方は下記要領でお申し込みください。*
*【購入手続き】*
*1冊 1500円 +送料300円 = 1800円*
*本購入手続きは、送付先の住所明記の上、上記金額を指定口座に振り込んでください。*
*★(振込日、振込人名義、送付先名、送付先住所、注文数をメールでお知らせください。その方がスムーズに書籍発送ができます。メルアド⇒ ezaki0222@ybb.ne.jp)*
*お振込先*
* 金融機関:ゆうちょ銀行
* 名義:江崎 孝
* 記号:17050
* 番号:05557981
*ゆうちょ銀行以外からお振り込む場合の振込先*













 ⇒最初にクリックお願いしま
⇒最初にクリックお願いしま </picture>
</picture>

 米軍キャンプ・シュワブのフェンス沿いで手をつなぎ、「人間の鎖」で新基地建設反対をアピールする参加者=6日、名護市辺野古(ジャン松元撮影)
米軍キャンプ・シュワブのフェンス沿いで手をつなぎ、「人間の鎖」で新基地建設反対をアピールする参加者=6日、名護市辺野古(ジャン松元撮影)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/JPJYJ3J4QVPWPBERUM3N3HGONY.jpg)
 江崎 孝 (ブロガー:「狼魔人日記」管理人)
江崎 孝 (ブロガー:「狼魔人日記」管理人)