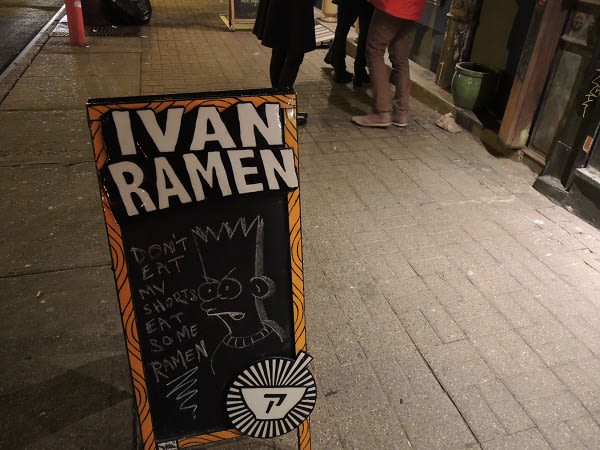ニューヨークに到着したら雪が降っていた。想定外に寒かった。もっとも冬の寒さはこんなものではなかったようだが。
もう、ラーメン屋を探すしかないのだ。と一度決めたら、麺ばっかり。やはり『美味しんぼ』での栗田さんの説のように、アジア人は本能的に麺に向かう。
■ 一風堂
最近アメリカ進出が大きな話題になっている。日本だけの話かと思ったら寒空の下この行列。東京で何度も食べたので入らないが、味は同じなのかな。

■ Nam Son (ベトナム料理)
もう寒くて寒くて汁麺ならばと思い、チャイナタウンのベトナム料理屋に入った。
普通のフォー・ボー。ハノイで食べるより牛肉の量が多い。旨かったがライヴに遅れそうになった。


■ Wok 88(アジア料理、アッパーイースト)
Udonという名の焼うどん。ちょっと油っぽかったが懐かしい感じの味。
そういえば、汁もののうどん屋はあるのかな。剛腕投手の伊良部がアメリカのどこかで経営していたのは、うどん屋ではなかったか。

■ Naruto Ramen(アッパーイースト)
前を通りがかるたびに人が順番待ちをしていた。
黄色くコシのある麺に鶏ガラのスープ(みんなチキンブロスと呼ぶ)。普通に旨い日本のラーメンである。半熟卵にもう少し熟練が欲しいが、それは望みすぎか。チャーシューが厚い。
つい餃子まで付けてしまった。向こう側でタレを入れてくれるので、待っている間に、自分で醤油と酢とラー油をブレンドする楽しみはない。
店員はアラーム付きできびきびと麺をゆでたり餃子を焼いたりしている。



■ Yasha Ramen(アッパーウェスト)
デューク・エリントン通りの近くにある。豚骨味(ポークブロス)、頼むとすぐに出てきた。細麺が柔らかいのはこちらの嗜好に合わせているのだろうか。今後は「バリカタ」とか流行ったりして。


■ Dassara Ramen(ブルックリン)
カタカナで「ダツサラ」とか書かれている。脱サラした方が始めたのかどうか不明だが、ちょっと独創的だった。
「デリラーメン」なるものを注文すると、チキンブロス(ブロスと書くと昔スワローズにいた投手を思い出してしまう)のスープに、セロリ、グリルした牛肉、さらにマッシュポテトの団子(これは合わないと思う)。麺が柔らかすぎたが好みによるだろう。やはり課題は半熟卵の作り方か。今後ニューヨークに進出するラーメン店は、バッチリした半熟卵を供すると差別化できるに違いない。
大相撲湯呑で水を飲んでいると不思議な気分。


■ Meijin Ramen(アッパーイースト)
牛骨スープ(ビーフブロス)の麺を注文したところ、予想以上にテイストが牛牛していた。ついでにミニカレーを付けた。
せっかく旨いのに、入りにくい雰囲気のせいか客が少なかった。



■ Ivan Ramen(ロウワーイースト)
あの有名店アイバンラーメンである(日本で食べたことがないので違いがわからない)。完全にバーの作りで、奥に個室まであり、みんな酒を飲んでいる。夜中にラーメンだけ食べるのは申し訳ない感じ。
塩ラーメンを食べた。チキンブロスと魚介系のダブルスープで、わたし的には嬉しい。もう少し熱ければよかった。やはり半熟卵が(以下略)。

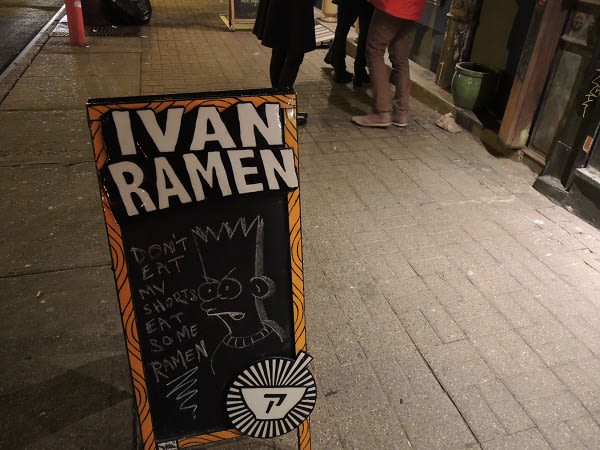
■ Gong(タイ料理)(アッパーイースト)
こじゃれたタイ料理屋。タイであろうとどこであろうと、わたしはいつもパッタイを食べる。タイ料理であれば必ずあり、まずい味にはなりようがないからだ。当然、予想通り旨かった。

■ Momofuku Ramen(イーストヴィレッジ)
やややわらかめの麺に、ほぐしチャーシューに、角煮。近所にあったらしょっちゅう通う味だろうね。やはり順番待ちが多かった。温泉卵がユニークだがやはり半熟卵のほうが(以下略)。


■ Ramen-ya(グリニッジヴィレッジ)
グレッグ・ハッチンソンのライヴがソールドアウトで入れず、ふて腐れてラーメン。去年もここにあったっけ?
すべて豚骨ベースの塩や醤油や味噌(と、日本人の店員さんが教えてくれた)。この界隈のライヴハウスに行くときにはぜひ。


●参照
ニューヨークのハンバーガー、とか
ラーメンは国境を超える(笑)
旨い札幌(2)(すみれ)
「らーめん西や」とレニー・ニーハウス
今田敬一の眼(五丈原)
北海道版画協会「版・継承と刷新」、杉山留美子(えぞっ子、雪あかり)
「屯ちん」のラーメンとカップ麺
「東京の沖縄料理店」と蒲田の「和鉄」
海原修平写真展『新博物図鑑』(凪)
海原修平写真展『遠い記憶 上海』(凪)
「ますたに」のラーメンとカップ麺
博多の「濃麻呂」と、「一風堂」のカップ麺
恵比寿の「香月」
齋藤徹による「bass ensemble "弦" gamma/ut」(ひごもんず)
18年ぶりくらいの「荻窪の味 三ちゃん」
沖縄そば(2)
沖縄そばのラーメン化
伊丹十三『タンポポ』、ロバート・アラン・アッカーマン『ラーメンガール』
旨いジャカルタ その4(カレーラーメン)
旨いハノイ(「フォー24」)
ミャンマーの麺
韓国冷麺
上海の麺と小籠包(とリニア)
北京の炸醤麺、梅蘭芳
中国の麺世界 『誰も知らない中国拉麺之路』