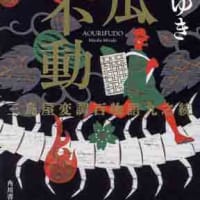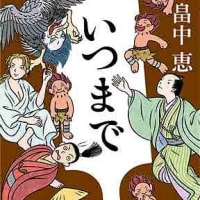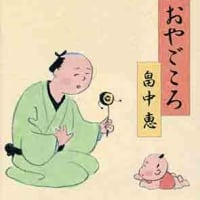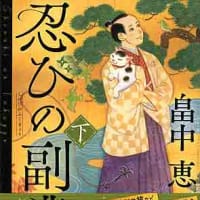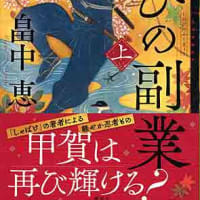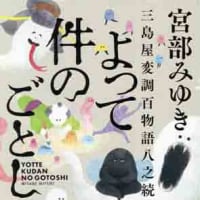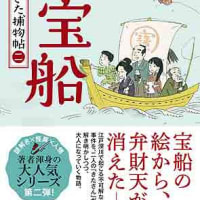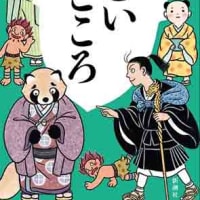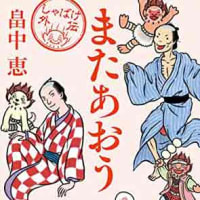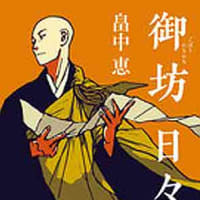2009年5月発行
2009年5月発行天和3年(1683)、京都の大経師の妻おさんが手代の茂兵衛と密通し、それを手引きした女中おたまと丹波に潜んでいたところを捕えられ、磔刑に処せられた史実を元に、井原西鶴が貞享3年(1686)「好色五人女」巻三「中段に見る暦屋物語」を刊行し、近松門左衛門の戯作「大経師昔暦」が正徳5年(1715)に上演されたのをベースにした長編作品。
序幕
藤の花
浮き世と憂世
婚嫁
旅立ち
江戸
洛中
中幕
そののち
江戸そののち
逃避行
千々に乱るる
蜜月
追手
貞享歴
終幕
安井の藤と呼ばれる藤の名所寺真性院境内で、室町の今小町と評判のおさんに一目ぼれした、大経師(暦の出版元)の浜岡権之助は、おさんを嫁に欲しいと請う。
だが、知らない男に嫁ぐのは嫌なおさんは、物陰から権之助の店を伺ってみたところ、手代の茂兵衛によきめきを感じるのだった。
嫁いで後も、茂兵衛への気持ちを押さえ切れないおさんは。次第に茂兵衛もおさんに惹かれ、二人は逢瀬を重ねていき…。
男であれば、奉公人に手を付けても何ら障りはないが、女主人と奉公人である為に、磔の極刑が待っている。そんな世の中の矛盾にを受け入れながらも思いを募らせる二人の姿を、随所に織り込みながら、男女の因果を描いている。
不倫の恋が進む一方で、夫の仕官の為、商人の妾になった武家の妻と、その夫の苦悩を対照的な結末で締め括る。
女敵が双方の決着の付け方になるが、一方は助けようと嘘を付き、他方は訴え出る。だが結末は双方ともが思わぬ方向へと…。
また、茂兵衛へ思いを寄せながらも、好いた人の為に親身に尽くすおたまと、好いた相手を手に入れる為に嫉妬の炎を燃やすおみつの二人の女心も同時に描かれ、それを井原西鶴、近松門左衛門が遠くから傍観するといった技法のかなり深い作品である。
ただ惜しむらくは、浜岡権之助が暦商大経師である事から、暦に絡む話に裂いた頁が多く、色恋沙汰の進行を気にする読者にとっては、浜岡家の商いの様子が鬱陶しくもあり、史実から暦に興味のある読者には、妾奉公の武家の妻の話はいらないだろう。
視線がぶれてしまうのと、登場人物が多すぎ、読み辛さを覚えたのと、主軸であるおさんと茂兵衛の最期があっさりし過ぎていた感が否めない。
主要登場人物
平山藤五(井原西鶴)...天神町→鎗屋町隠居、浮世草子・人形浄瑠璃作者、俳諧師
杉森信盛(近松門左衛門)...公家侍、人形浄瑠璃・歌舞伎の作者
倉田具之丞晴光...京都所司代戸田伊賀守忠昌家臣(戸田家所領は五畿内)
浜岡権之助...下京区烏丸通りの暦商大経師(暦の出版元)
おさん...権之助の妻、岐阜屋道順の娘
茂兵衛...暦商浜岡家の手代、元杉田屋の手代
岐阜屋道順...順番飛脚問屋の主、おさんの父親
おたま...おさん付きの女中
おあき...おさんの乳母
おかつ...道順の女房、おさんの母親
杉田屋茂兵衛...元四条通り人形屋の主
おみつ...杉田屋茂兵衛の娘
久左衛門...杉田屋の番頭
多田右京...牢人(=浪人)、元福知山藩士の末裔
あやめ...右京の妻、杉田屋茂兵衛の妾
木次要之助...相模小田原藩稲葉丹後守家臣
幸徳井友傳(11代)...陰陽寮次官=陰陽助
幸徳井友信(12代)...友傳の嫡男