前回(→こちら)の続き。
1994年末から1995年の初頭にかけて、日本列島は「七冠王」フィーバーで、湧きに湧いていた。
そこで、まずは「七冠王」までの道程を紹介しているわけだが(「七冠王」をかけた第44期王将戦に興味のある方はこちらまで飛ばしてください)、その主役である羽生善治はデビュー以来、各種棋戦で次々と優勝。
「対局数 勝率 勝数 連勝」の記録部門独占、最優秀棋士賞受賞、竜王獲得など、スーパーエリート街道を驀進していた。
その後、少しばかり挫折の時期があり、初タイトルの竜王を充実著しかった谷川浩司に奪われる。
1勝4敗というスコアもさることながら、内容的にも圧敗で
「谷川が強すぎる」
「羽生の棋界制覇はまだ先の話だ」
というアピールをゆるしてしまったが、そのダメージもなんのそので、すぐに棋王を南芳一から奪い無冠を返上する。
さらには福崎文吾から王座も奪って二冠に輝き、NHK杯と全日プロでそれぞれ2回目の優勝。
トップ選抜の日本シリーズも制するなど、相変わらずの安定ぶり。
1992年の第5期竜王戦(→こちら)では、谷川浩司竜王にリベンジマッチを挑みフルセットの末奪取。
同時に、谷川を挑戦者にむかえた棋王戦(→こちら)でも防衛で「往復ビンタ」を喰らわせる。
ここがターニングポイントとなったようで、「谷川三冠」「羽生二冠」が「谷川二冠」「羽生三冠」になったインパクトが強烈だった。
これで谷川に対して、苦手意識を植えつけたのか、続く棋聖戦でも勝ち四冠王に。
なんと運命の王将戦まで、谷川は羽生にタイトル戦でシリーズ7連敗を喫するという、信じられない偏りになってしまう。
「ナンバー2を叩け」
という、テニスのロジャー・フェデラーも実践した王者の必勝パターンを確立した羽生は、今度は同世代のライバル郷田真隆から、王位をストレートで奪い五冠王。
本人も認めるように、このあたりから周囲も
「え? 七冠王あるの?」
色めき立つが、翌年の第6期竜王戦で、佐藤康光に敗れて一歩後退。
このときの佐藤は踏みこみも素晴らしく、とても強い将棋だったから、ここで少し取り上げてみたい。
今でも憶えているのは第5局。
羽生と佐藤康光の初タイトル戦で、それぞれ先手番をしっかりキープして2勝2敗のタイ。
この第5局も、そのころの2人らしいガッチリとした相矢倉になって、むかえたこの局面。
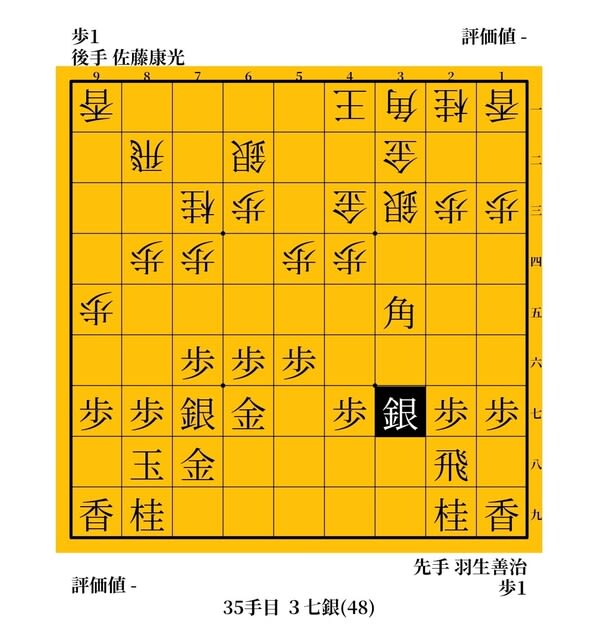
まだ序盤で駒組の段階だが、実はすでに勝負所である。
テレビの解説によると、この局面はかなり研究が進んでおり、ここで△55歩と仕掛ければ、後手が指せるという結論になっていたそう。
このころ名人戦と竜王戦は1日目と2日目両方とも、朝と午後4時から6時まで、最後にダイジェストが放送されていた。
2日目の6時で終わりとか、一番ええところ見られへんやんけ!
不満タラタラだったが、まあ、そういう時代だったのである。
でだ、1日目の午後4時にテレビをつけると、画面に映ったのがこの図だった。
△55歩の解説からはじまって、あれこれやっているのだが、だんだんと妙な空気になってきたのは、佐藤七段に、まったく次の手を指す気配がないから。
将棋に長考はつきものである。ましてやそれが、持ち時間8時間の竜王戦なら。
しかしだ、それにしても長い。
次の手は、ほぼ△55歩で決まりなのである。
それでも指さない。佐藤はひたすら盤上に没入している。
解説はすべての変化を語ってしまった。雑談するにも限度がある。まさか「早く指して」とカンペを出すわけにもいかない。
今なら、こういうときメールを読んだり、おやつを食べたりできるが、そういう文化もなかった。
そもそも、手が進まないと「気まずい」のが、将棋中継の持つ最大の弱点だ。
「長いなあ」とあきれること2時間、なんと佐藤康光はそのまま1手も指さず、封じ手に入ったのだ。
羽生と佐藤康光のタイトル戦を楽しみにテレビをつけたら、なんたることか、そこから手がまったく動かなかった。
ちょっと待てーい!
果たして翌日、封じ手によって示された手は「△55歩」だった。
「それやったら、早く指せよ!」
……とは、もちろん言えないんだけど、そりゃあんまりやで康光センセ、とブツブツ言ってた私は、この後の展開を見て、その不明を恥じることになる。
なんと、この△55歩以下、佐藤康光はそのままノンストップで攻めまくって、羽生にチャンスらしいチャンスをあたえないまま、押しつぶしてしまったのだ!
これには、驚きのあまり言葉がなかった。
え? もう勝っちゃったの? と、お口あんぐりである。
あの空気を読まない大長考で、この男はすべてを読み切っていたのだ。
われわれが、呑気にあくびをしている間に、羽生はとっくに鍋に入っていた。勝負は1日目の昼すぎ、すでに着いていたのだ。
少なくとも、佐藤康光の頭の中では。
すさまじい読みの力であり、まだ駒もぶつかってないのに
「ここで仕留める」
と決意を示した、その気迫と集中力には怖気が走ったもの。
若手時代の佐藤といえば「優等生」キャラだったが、そのイメージがはじけ飛んだのが、この将棋だった。
この人は気が狂っている。優等生なんて、どこの国のパプアニューギニアや。もうムチャクチャに、カッコええやんかー!
終盤も見事だった。
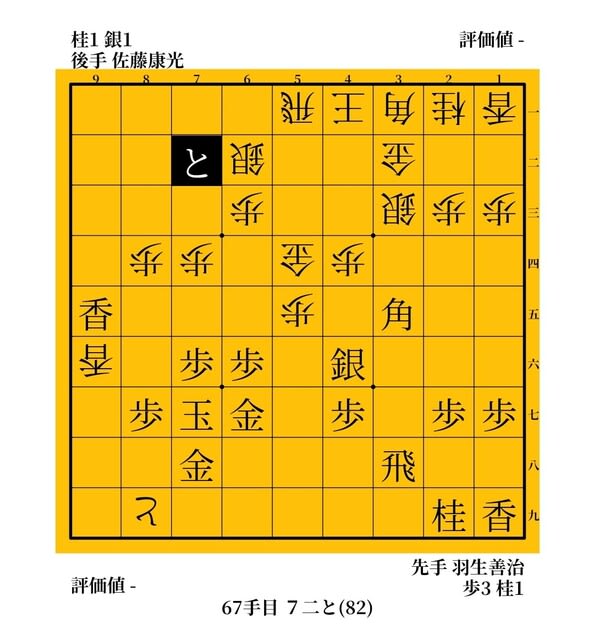
▲72と、とせまられ、次に▲62とと取られる形が飛車当たり。
△31の角が壁になってるのも気になるが、次の手が好手である。

△71銀とするのが、カナ駒を1段目に引きずり降ろして威力を弱めるという、おぼえておきたい受けの手筋。
▲同と、しかないが、これでと金を使いにくくして△97角成が、敵陣にせまりながら自玉の逃げ道を開通させる、すこぶるつきに味のいい手。
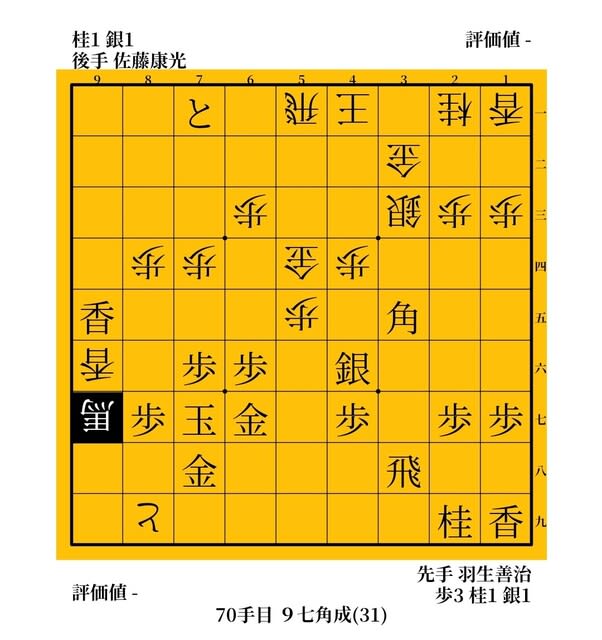
見事な将棋で羽生の先手番をブレークした(こういうとき「後手番ブレーク」という人がいるが、これはテニスのサービスゲームをイメージしてる言い回しだから、先手番を「キープ」「ブレーク」が正解)佐藤康光は第6局も制し初タイトルを獲得。
大長考のド迫力といい、その腕力といい、こういうのを見ると、
「羽生も強いけど周りもすごいから、七冠とか口で言っても、そう簡単ではないか……」
という気にもさせられ、それがふつうの感想のように思われたが……。
七冠熱は少し冷めたとはいえ、現実的に「四冠王」というのは棋界制覇といっていい内容。
その勢いはおとろえることを知らず、今度はA級順位戦で勝ち星を重ね、プレーオフでまたも谷川を下して挑戦者に。
「50歳名人」で話題になった米長邦雄から名人を奪い、すぐさま五冠復帰どころか、翌年の竜王戦で佐藤康光から竜王も奪い返し(羽生はこのように失冠後すぐ奪い返すケースが多い)、とうとう六冠。
一歩後退どころか、まさかの「七冠王」にリーチがかかった。
もちろん、その間のタイトル戦はすべて防衛しているわけで、とんでもない勝ちっぷり。
そうなると注目は、当然王将戦に集まるわけで、羽生はここでも期待に応え、強豪ひしめく王将リーグを5勝1敗でフィニッシュ。
挑戦者決定プレーオフでも郷田を破って、なんと谷川王将の待つ七番勝負に上がってきてしまったのだ。
少々かけ足だが、羽生のデビューから「七冠フィーバー」まで、当時の状況はこういう感じであった。
ふつうに考えればありえない「七冠王」だが、この強さを見せられれば、もはや実現しても不思議ではない。
しかも、相手にしているのは谷川浩司、森下卓、佐藤康光、森内俊之、郷田真隆、村山聖といった、すごすぎる面々。
さらには高橋道雄、南芳一、中村修、塚田泰明、島朗ら「花の55年組」などを加えれば、史上最強クラスといえる時代だ。
ここをつるべ打ちしての結果なのだから、数字以上の偉業であり、その価値はまさにはかり知れない。
単に強いだけでなく、島朗八段の
「ここまできたら、一度は七冠王を見てみたい気もする」
という発言のような、世論の後押しもありマスコミはかつてないほど将棋界に群がり、一般の関心まで高まるという大事件に発展していったのだ。
(続く→こちら)

























