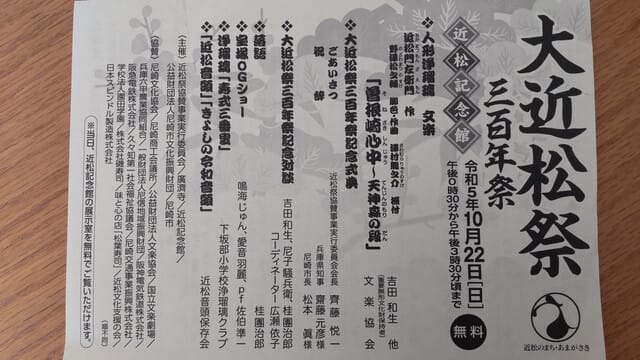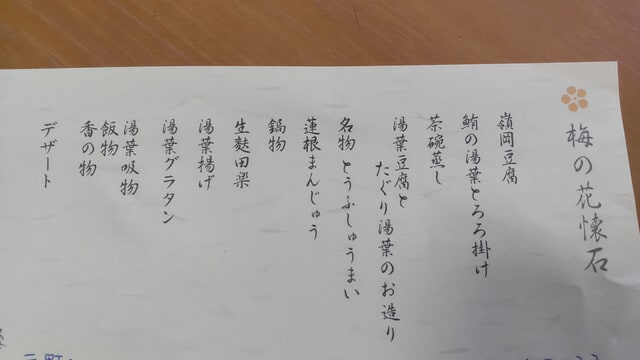新暦の、およそ12月31日~1月4日ごろの今の時期は
旧暦では冬至の末候、
「雪下麦を出だす(せっかむぎをいだす)」
です。
雪下麦を出だす とは、
降り積もる雪の下で、麦が芽を出すころ。
植物は、地中や冬木立の枝先で、芽吹くちからを育んでいるのですね。
今年を締めくくり、来たるべき新年へつながる時候となりました。
あっという間に過ぎたように思える1年の間にも、
いろいろあったあれこれが思い返されます。
事故で骨折し、せっかく治癒した左膝をまた転んで負傷したとか
(打撲と擦過傷ですんでよかったです、ホント;;)
ついにコロナにやられてしまい、しばらくウツが続いたとか
歌はとうとう、すべて1年お休みしてしまったとか
着物はちっとも上達しないとか
川柳はいつも締め切りギリギリであせってばかりだとか
不覚に思える事態やできごともありますが。。。
とにもかくにも、
ぶじに元気に生きてこられました。
くたびれぎみの夫も、大病などせず元気でいてくれましたし、
必要なお世話や見守りが増えたりんも、
がんばってくれています。
家族そろって、ぶじに年越しできるしあわせに感謝!
今年のうちに、おなじみご近所のお寺さんの
今月のことばをご紹介いたしますね。

すぐれた人のようにはできなくても、
自分なりにがんばってきた1年。
ねぎらってやってもいいかな。。。
そしてまた、あたらしい年も
ぼちぼちむりのないペースで、自分の歩みを進めていきましょうっと♪
みなさま、今年もあたたかいご縁をありがとうございます。
どうぞよいお年をお迎えくださいね^^
かろやかにまたねと跳ねて去るうさぎ さくら
旧暦では冬至の末候、
「雪下麦を出だす(せっかむぎをいだす)」
です。
雪下麦を出だす とは、
降り積もる雪の下で、麦が芽を出すころ。
植物は、地中や冬木立の枝先で、芽吹くちからを育んでいるのですね。
今年を締めくくり、来たるべき新年へつながる時候となりました。
あっという間に過ぎたように思える1年の間にも、
いろいろあったあれこれが思い返されます。
事故で骨折し、せっかく治癒した左膝をまた転んで負傷したとか
(打撲と擦過傷ですんでよかったです、ホント;;)
ついにコロナにやられてしまい、しばらくウツが続いたとか
歌はとうとう、すべて1年お休みしてしまったとか
着物はちっとも上達しないとか
川柳はいつも締め切りギリギリであせってばかりだとか
不覚に思える事態やできごともありますが。。。
とにもかくにも、
ぶじに元気に生きてこられました。
くたびれぎみの夫も、大病などせず元気でいてくれましたし、
必要なお世話や見守りが増えたりんも、
がんばってくれています。
家族そろって、ぶじに年越しできるしあわせに感謝!
今年のうちに、おなじみご近所のお寺さんの
今月のことばをご紹介いたしますね。

すぐれた人のようにはできなくても、
自分なりにがんばってきた1年。
ねぎらってやってもいいかな。。。
そしてまた、あたらしい年も
ぼちぼちむりのないペースで、自分の歩みを進めていきましょうっと♪
みなさま、今年もあたたかいご縁をありがとうございます。
どうぞよいお年をお迎えくださいね^^
かろやかにまたねと跳ねて去るうさぎ さくら