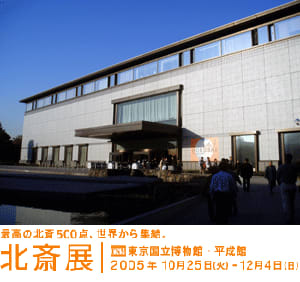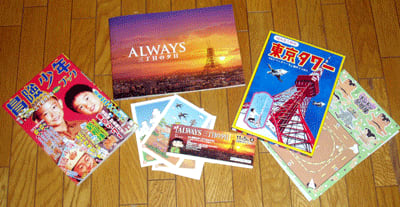東京に来ています。
アース21という北海道の工務店・住宅ビルダーの勉強会の定例会です。
いつもは北海道内で、地域持ち回りでさまざまな住宅建築を巡るテーマで
研鑽を深める趣旨で、経営向上策から工法の研究と
幅広い建築の探求をしている会です。これは別に報告します。
スケジュールが突然、空いたので友人から情報を聞いていた
「北斎展」、行ってきました!
すごく、感動!
世界に散逸してしまった、日本最高峰の絵画の天才の画業を
一気に見ることができます。
葛飾北斎といっても、教科書程度の知識しかなかったのですが
こうして、里帰りした作品も含めて、その時系列ごとに
わかりやすく見てみると、その天才ぶりがまざまざと実感できます。
「画狂人」というサインをしている時期もあるのですが
とにかく、その構想力・企画力、力強い構図のメッセージパワー
色彩の感覚、など圧倒されまくった次第です。
とくに、やはり「富岳百景」は、かれの代表作ということが
ホントによく理解できました。
これは、って思えた作品は判で押したように
「メトロポリタン美術館所蔵」
とくに、むむむ、と動けなくなった
富岳三十八景・常州牛掘。
復刻画もさっそく買ってきましたが。
原板のすばらしさに触れて、はじめてこころから
理解できる、一種の体験ですね。
アメリカは、日本に勝った、日本は負けたんだという
歴史的事実の重さを知ることにもなりましたがね。
こんな機会は、たぶんもうない、感じがします。
こういう天才を持った、わたしたちの文化の誇らしさを感じました。
言葉はありません、ただ、感動しました!
アース21という北海道の工務店・住宅ビルダーの勉強会の定例会です。
いつもは北海道内で、地域持ち回りでさまざまな住宅建築を巡るテーマで
研鑽を深める趣旨で、経営向上策から工法の研究と
幅広い建築の探求をしている会です。これは別に報告します。
スケジュールが突然、空いたので友人から情報を聞いていた
「北斎展」、行ってきました!
すごく、感動!
世界に散逸してしまった、日本最高峰の絵画の天才の画業を
一気に見ることができます。
葛飾北斎といっても、教科書程度の知識しかなかったのですが
こうして、里帰りした作品も含めて、その時系列ごとに
わかりやすく見てみると、その天才ぶりがまざまざと実感できます。
「画狂人」というサインをしている時期もあるのですが
とにかく、その構想力・企画力、力強い構図のメッセージパワー
色彩の感覚、など圧倒されまくった次第です。
とくに、やはり「富岳百景」は、かれの代表作ということが
ホントによく理解できました。
これは、って思えた作品は判で押したように
「メトロポリタン美術館所蔵」
とくに、むむむ、と動けなくなった
富岳三十八景・常州牛掘。
復刻画もさっそく買ってきましたが。
原板のすばらしさに触れて、はじめてこころから
理解できる、一種の体験ですね。
アメリカは、日本に勝った、日本は負けたんだという
歴史的事実の重さを知ることにもなりましたがね。
こんな機会は、たぶんもうない、感じがします。
こういう天才を持った、わたしたちの文化の誇らしさを感じました。
言葉はありません、ただ、感動しました!