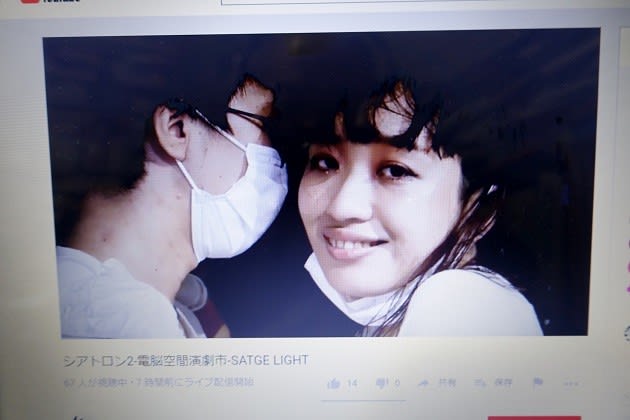(承前)
6時半、帰宅。
秋刀魚の塩焼き、サラダ、茄子の味噌汁、ごはん。

今年の秋刀魚は細身だ。

今日のカフェめぐりの最後に神楽坂の「梅花亭」でチアキさんにお土産に買っていただいた栗蒸し羊羹を食べる。栗がこれでもかというほどのっている。作り立ての蒸し羊羹はウイロウのような食感。

劇団獣の仕業の芝居『タイトル』をユーチューブで観る。24時間生配信フェス「シアトロン2ー電脳空間演劇市」の参加作品である。所定の時間に一回限りの配信だが(つまりオンデマンドではない)、舞台(スタジオ)からの実況中継ではなく、あらかじめ収録した芝居を配信するのである。
芝居が始まる前に出演の二人、立夏と小林龍二が挨拶。

「タイトル」と題された芝居である。「本作は2016年に立夏が執筆した未上演戯曲「(タイトル未定)」を演劇の現在地から見つめなおし改稿・改題した作品である。シアトロン2で初演」と立夏のブログで説明があった。原作の戯曲は→こちら
「演劇の現在地」とはコロナ的日常の中で劇場でのライブ上演ができない現状のことを直接には指しているのだろうが、芝居のテーマそのものは、もっと普遍的なもの(コロナ的日常になる以前から存在しているもの)、立夏の言葉でいえば「演劇というフォーマットそのものを問い直す」ということ、言い換えれば、「演劇する」ことの意味という演劇人にとっての基本問題を問うたものである。すでに立夏は『THE BEAST』(獣の仕業第13回公演、1918.12.22-24、吉祥寺魁スタジオ)で演劇人にとっての切実な問題、学生時代に足を踏み入れた演劇の世界から社会人になって一人二人と去っていく仲間たちを見送りながら自分がこの世界に踏みとどまっていることの意味を問うていた。今回の『タイトル』も同じ系列に属する作品ということができるだろう。コロナ的日常はそうした通奏低音的なテーマに演劇人が向き合うことを後押ししたといえるだろう。

ネットに事前にアップされていたポスターでは、小林龍二は作務衣を着ていたが、本番では立夏と同じ白いTシャツを着ていた。そして二人とも白いマスクと手袋をしていた。稽古の過程でそうなったのだろう。下の2枚の写真は私がパソコンの画面をデジカメで撮ったものではなく、立夏から送ってもらったスチル写真(撮影は、かとうはるひTwitter@muhuhuhuhuuu)。
芝居は、立夏演じる演劇人と小林龍二演じる「演劇」(演劇神のようなもの?)の対話で展開される。対話といっても二人が椅子に座って対談をするわけではなく、獣の仕業らしい身体的パフォーマンスを絡ませながらの対話である。

対話は演劇人が苦悩を語り、「演劇」がそれにクールに答えるという形で進行する。(以下に引用するのは公開されている元の戯曲からである)。
「私がここに立っているのは私がみんなを呼んだから。メールをして電話をして呟いて顔と顔を見合わせて本を書いて、それで集まったのがこの人達。今日は最初の日。明日はすぐに最後の日。今日と明日で合計4回。100人。もうちょっと調子が良く伸びたとしても200人。ねえこれはとても多いと思う? それとも少ないと思う? あなたはどう思うだろう。ねえ、あなた。みんなってあなたのことよ。あなたの判断をして、あなたの意見を聞かせて。」
「違うまずは君が自分の話をすることだ。先に君が。」
「私はもう言葉を尽くして同じテーマをずっと繰り返しているだけじゃない何年も何年もずっと。それが真実だと思わない?私はいつまで先出しを続ければ良いんだろう。後出しじゃんけんでみんなは何だって言いたい放題なのに。しかもそれは私が望んだことなのだ。そしてそれはサービスと言われる。ああ、ねえ、私は大切にしているたったひとつのことだけがあって同じテーマを、海辺にして病院にして家の中にしたり親子にしてみたり恋人だったり手を品を変え続けてタネを100年前に明かした手品をずっと披露しているような気持ち。」
演劇人の苦悶はさらに続くが、「演劇」冷たく言う。
「だったら辞めてしまえばいい今すぐに。」
演劇人は「演劇」への愛を語り始める。
「どうしてそんな言い方しかしないんだろう。どうして私のやることをすべて否定するのだろう。あなたには私が辞めたいように見えるの。逆よ。私はこれを続けたくてどうしようもないから苦しい。私はこれをくだらないと言ったことは一度もない。思ったこともない。・・・私はあなたが好き。何故だと思う。あなたが私を救ってくれたから。あなたが私を救ってくれたからあなたは他の人も救えると思うから。」

しかし、演劇人は自身の「演劇」への愛に、いや、その愛し方に、疑問を感じてもいる。それを「演劇」にぶつけてみる。
「私はもうあなたの影を追うことを辞めようと思っている。あなたの抜け殻を、まるでこのプロセスさえ踏めば自動的にあなたになれるだろうと思われている架空のものをすべて捨てようと思う。明日から私は、明かりがついても何も喋らないかも知れない。大きな声を出さないかも知れない。名前はなくなるだろう。スクリプトは停止するだろう。あなたの、あなたの本質ではない、まるであなたの仕組みを構築してる振りをしているかのようなシステムを、すべて停止して、何が残ると思う? 」
「演劇」はその質問には答えない。しかし、反語的に答える。そして、その語りは熱を帯びている。
「質問をしないで欲しい。キミにそんな権利はない。まずはやることだ。私がそれを見ている。そうして視線が残る。まずはやってみることだ。私は実践することでしか現れない。・・・明かりはとっくについている。これは私の光だ。唐突に停電するかも。それもまた私の暗闇だ。気まぐれに音楽は鳴るかも知れない。それは私の音だ。キミの名前をまだ誰も知らない。それは最後まで分からないだろう。壁がある。この壁は私の壁だ。椅子がある。床がある。私の床だ。すべてキミのものではない。みんながキミを見ているようだが、しかしその実みんなが見ているのは私だ、キミではない。視線は反射するから。・・・まさか90分で辞めるつもりじゃないだろうな? 始まればやがて90分かそこらで自動的に終わることができるなんてそんな甘いことは言わないだろうな。それこそキミが心底うんざりしている擦られ続けてきた私の架空っていうやつかなにかのプロセスの一つだろう。キミはキミが自分自身にうんざりしないためにこのうんざりする静寂から逃げてはならない。これで最後だ。絶対に途中でキミを助けたりはしない。 私はもう二度と喋らない。」
最後に演劇人はこう語る。
「私、ずっとあなたのことを見ていた。私が表現したかったのは私ではなくあなたのことだった。失敗だとしても。これを始まりとして。またやっていけばいい。あなたは黙っていた。みんなも黙っていた。みんな何かを考えていた。思考していた。それはここでしか考えられなかったこと。ここでしか産まれなかったあなただけの思考。私たちは人間だ。一生あなたの奴隷だとしても。あなたの中で、私は思考している。あなたの意識。これがはじまり。だから早く幕を閉めて欲しい。」
演劇人はマスクをとって「演劇」に口づけをする。そしてカメラ(観客)に向かってほほ笑む。(終)
一つの芝居の終りは、次の芝居の初まりを予告するものである。
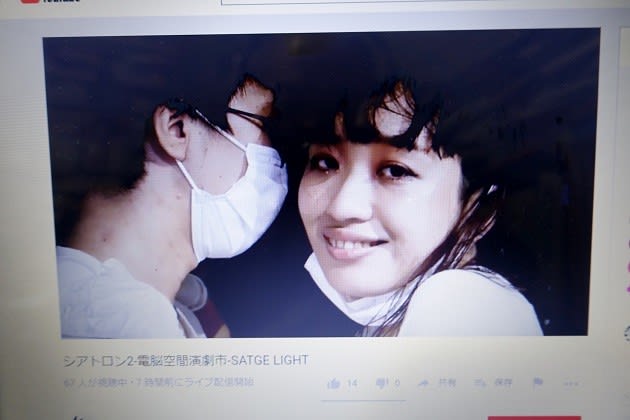
句会仲間の月白さんと渺さんが今回の芝居を観た感想を句会LINEに書いていた。
「見ました。立夏さん、熱演!小劇場を熱心に見ていた若い頃を思い出しました(歳が💦)。最初はどうなるかと思ったけど😅抽象化された演劇との対話、切なく面白かったです。そういう葛藤というかジレンマは他の芸術でもあるかもしれない。途中、マスクで呼吸困難になるんじゃないかと心配になりましたが、これも2020年ならではですね。 」(月白)
「見ました。芝居って苦手で、映画ほど見に行く気にならないんだけど、そのあたりの違和感に意識的な話で最後まで楽しめました。でも、これってお芝居?映像作品?無機的なイントロも良かったです。 」(渺)
渺さんの質問に対して立夏はこう書いている。
「演劇が無観客配信で映像化を強いられる中、映像になった演劇は、演劇なのか?というかつてからあった問いがさらに顕在化しています。これは演劇だ、と言い張る人も、いや、映像になったら演劇じゃなくて映像でしょという人も、いますね。」
これはまるで「演劇」の答えのようだ(笑)。立夏本人はどうなのだろう。たぶん「これは演劇だ、と言い張る人」なのではないかしら。
「演劇する」人たちを撮った映像は、演劇している人からすれば演劇だし、その映像を見ている人たちからすれば映像である。実際、劇場で座席という固定した視点から演劇を観ているときとは違って、複数のハンディカムで撮った映像は視点が複数あり、しかも複数の視点はそれぞれに移動し、出来上がって映像には編集作業が加わっている。劇場で公演される芝居を固定カメラで撮ってテレビで放送するというのとは違う。最初から演劇と映像のハイブリッドを意図した作品だ。考えてみれば「従来の演劇」というのはその殻を破ろうとする演劇人たちによって常に破られてきた歴史がある。舞台と客席の境界を取っ払うとか、劇場の外に飛び出して街中で演劇をするとか。コロナ的日常の中での「無観客演劇」(のオンライン配信)というのもその歴史の一頁である。演劇の実践、「演劇する」というのは「従来の演劇」(立夏の言い方では「演劇のフォーマット」)との緊張関係を常に内在したものであり、違和感と解放感とは紙一重というか、表裏一体のものである。私はそれを楽しんだ。

風呂を浴びてから、『桑田佳祐のやさしい夜遊び』をrahikoで聴きながら、今日の日記とブログ。

1時15分、就寝。明日は日曜日だが午前中から大学で仕事がある。