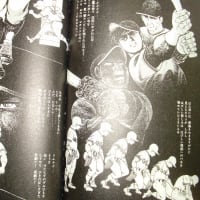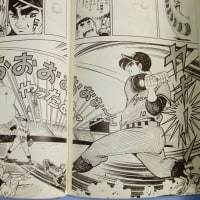芥川龍之介が神経質だったのは有名である。
いや、彼は神経質の代名詞であり、端的に言って「THE 神経質」である。

実際、彼は神経衰弱で35歳のとき自殺した。
また彼の作品には「神経」という言葉が頻出し、神経を病んだ状態の心理の描写が多い。
晩年の告白調の作品は、いわゆる「病的に研ぎ澄まされた神経」によって書かれているように感じる読者が多いであろう。
「歯車」「蜃気楼」「夢」「河童」「手紙」「影」・・・・・など。
ちなみに「夢」というのは大正15年の作品だが、その冒頭で彼は次のように書いている。
「夢の中に色彩を見るのは神経の疲れている証拠であると言う。が、僕は子供の時からずっと色彩のある夢を見ている」。
つまり、彼は子供のころから神経が疲れていたのだ。
また、同年の作品「僕は」には次のように書かれている。
「僕はどういう良心も、-- 芸術的良心さえ持っていない。が、神経は持ち合わせている」。
彼にとっていかに「神経」というものが大切かを示す言葉である。
また、遺稿というか遺書「或旧友への手記」には次のように書かれている。
「僕の今住んでいるのは氷のように澄み渡った、病的な神経の世界である」。
「病的な神経の世界」、これこそ芥川ワールドである!!
私は彼の作品を18歳ぐらいから愛読し、玩味熟読してきた。
といっても初期から中期の歴史物には興味がなく、もっぱら晩年の告白調短編を偏愛してきた。
周知のように彼の母は統合失調症(=精神分裂病=早発性痴呆)で夭折した。
それゆえ彼は常に自己の精神病発症を危惧していた。
しかし、彼は神経症レベルにとどまるうつ病という診断が適切な状態で推移した。
最後に自殺に至ったのも、うつ病の特徴を示している。
これを大正時代には神経衰弱と呼んでいたのである。
とにかく、彼の後期の作品には神経に関する話が豊富で、神経哲学にとって極めて貴重な文学的遺産である。
今回は前書き程度の本記事にとどめるが、そのうち本格的に考察しようと思っている。