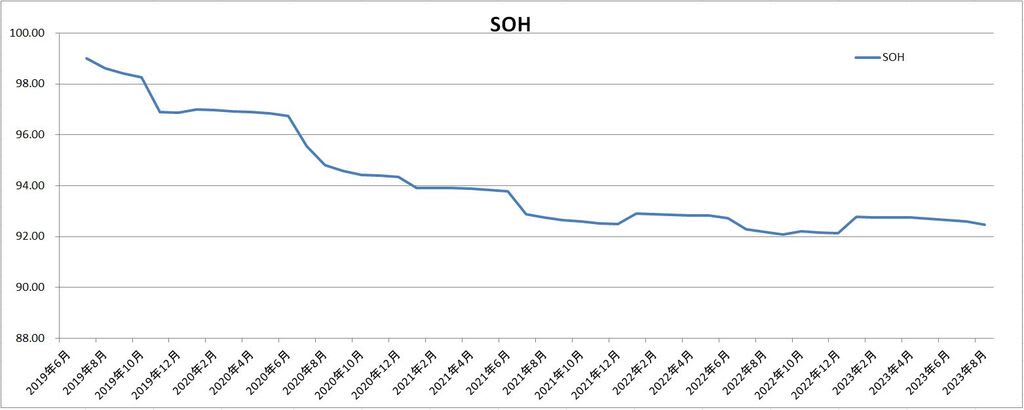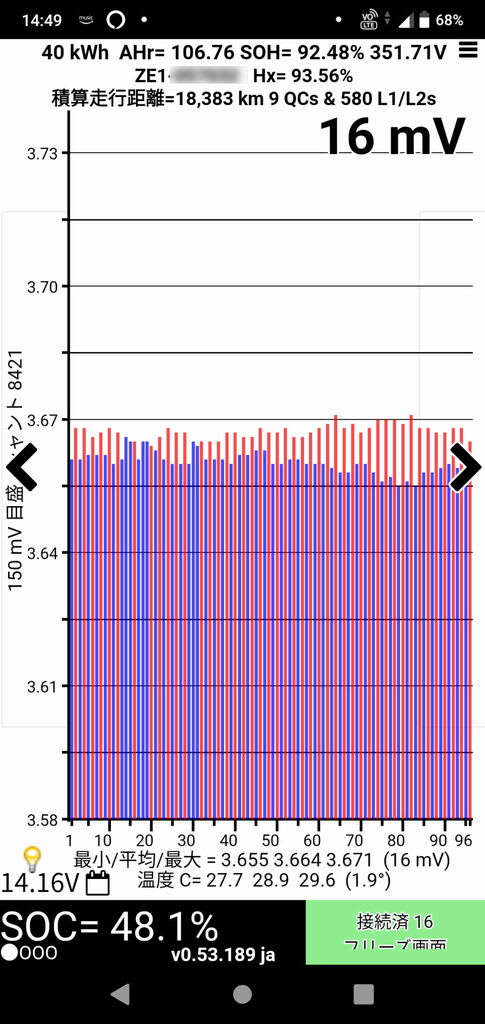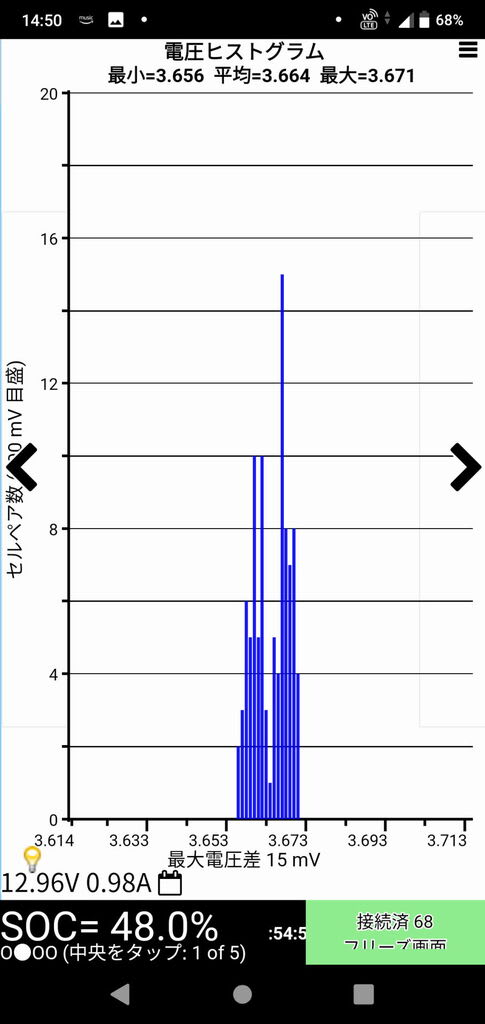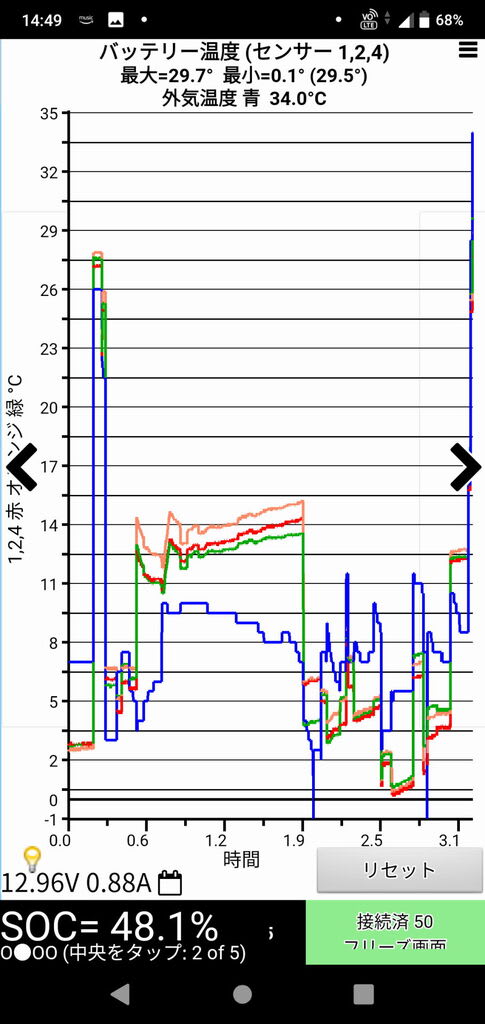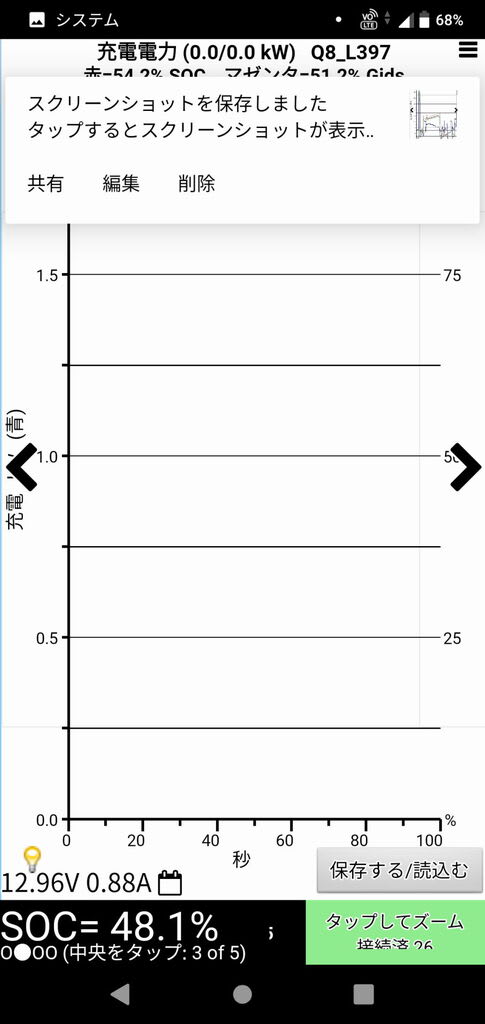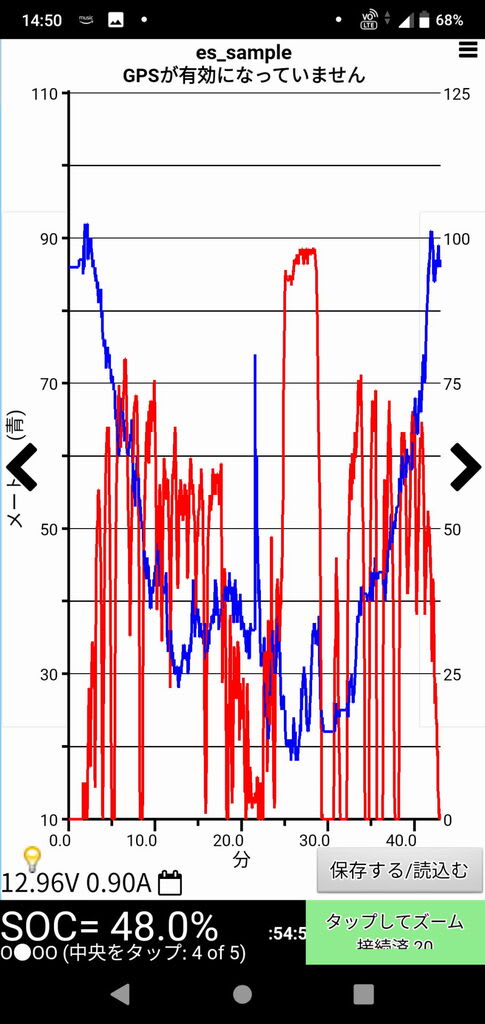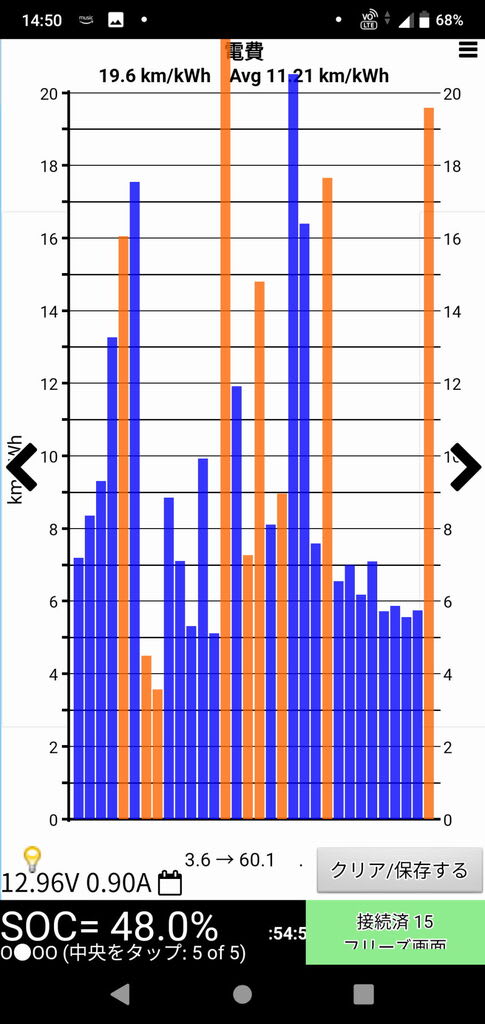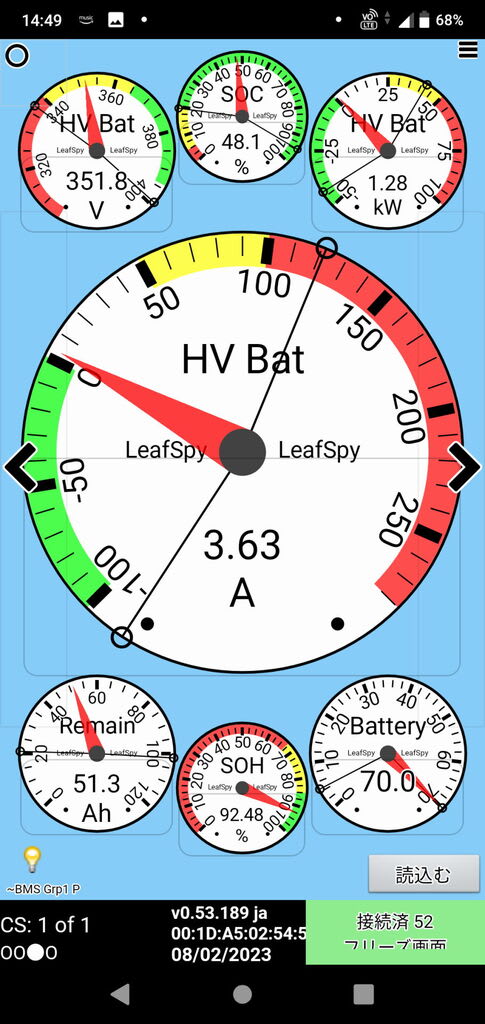前回は星空を投影するフィルムの修繕でしたが、今回は投影するための光源に関するところの「改善」です。
修理ではありません。
依頼主からは「電池だと直ぐに電池切れになるので、外部電源接続にしたい」との切なるご要望がありました。
そうは云っても、電池方式は可搬性が売りな訳でそれをやめて外部電源だけに依存するのも、もったいないなぁ。
そこで、何時ものアイディア炸裂です。
分解して構造を良く観察しました。
電池と外部電源のハイブリットにするには既存のスイッチでは対応できません。
単純に電池ボックスに外部電源を接続すると、もし電池が入ってる事に気づかずに外部電源を接続すると乾電池に電圧が掛かって破裂する可能性もありますので、完全にスイッチで入力ルートを切り替える必要があります。
50年も前から様々な電子部品を段ボール2箱分も持っていたりする変人なので、大抵の部品は揃います。
似たようなスイッチを探すと、ありました。
2回路3接点の物で、これで切り替えが出来ます。
多少サイズが合わないので、スイッチの角部分をやすりで削ってカットアンドトライです。
次に既存の光源は懐中電灯等で昔から使われてる3V(正式には2.5V)の豆球ですが、これは電気食いなのでLED化出来れば電池の持ちもかなり良くなると思って、ネットで探しまくって、やっと使えそうな物を購入しました。
電源は現代で最もポピュラーな5VのUSBからの電源供給にします。
側面に穴を開けて電源ジャックの受け口を取り付けます。
今回のLEDは電池でも使える様に3VのLEDにしました。
そのためUSBの5Vを直にLEDに流すとLEDが壊れてしまいますから、15Ωの抵抗を通しての接続にします。
良いんじゃないですかぁ。
豆球よりも明るいです。
と、ところが夜になって投影実験したら・・・
星像がボケボケ。
原因はLEDの発光部の面積があるためか、LEDの発光部を保護するためのレンズ的な保護膜があるためか?
ピンホールカメラ的に投影するこの装置ではボケてしまったのでしょう。
勿論想定内のことでしたが、様々なLED商品の中でこれが一番発光面が小さくて発光面が一つだけしか無いため、上手く行くかも知れないと期待していましたがダメでした。
これ以上条件の良い豆球タイプのLEDは無かったのでLED化は断念します。
さて、フィラメントの豆球への電力供給するには5Vを3V以下に落とす必要があり、2Ωくらいの抵抗を接続しないといけませんが、1A近い電流が流れるので抵抗が熱くなってしまいます。
抵抗はそもそも放熱する構造にはなっていないので、ちょっと無理です。
実際に5.6Ωの抵抗があったので4本並列にして3Vになりましたが、1/2W形抵抗ですが結構熱くなります。
そこで、昔懐かしの三端子レギュレターを使って電圧変換しようと思いましたが、3Vの三端子レギュレターは手持ちに無かったし、三端子レギュレターを使うほどシビアな電圧制御は必要ありません。
そこで、更にアイディア炸裂!!
昨年、自作電池ボックスの並列接続の電池セット間の漏れ電流を防ぐために買った3Aまで流せるダイオード(IN5408)を思い出しました。
20本セットで買ったので、まだまだいくらでもあります。
ダイオードやトランジスタのNP半導体って、勉強した事のある人は知ってる事ですが順方向への電流が流れると電流の大小に関わらず、ほぼ0.7V~1V程度の電圧降下が起きます。
3本直列に繋ぐと2V以上の電圧降下が望めます。
5Vー2V=3V
でしょ。
それに3Aまで流せると云う保証があります。
実際にやってみると、個々のダイオードではお決まりの0.75Vの電圧降下で2つで1.5Vの電圧降下ですが、2.9Vになりました。
結局USB充電器側も負荷が掛かると電圧が4.5Vくらいまで落ち込むようです。
様々なUSB端子で確認しましたが、どれもほぼ同じでした。
暫く通電してみましたが、発熱も許容範囲で充分使えます。
という事で最終形はこうなりました。
スイッチの部分もON/OFFでは無く 電池/USB としました。
電池も入っていて、USBも繋がっているとスイッチをどちらに倒しても電球は消えません。
中間点のあるスイッチなら中間で消せますが、今回のスイッチではそれは出来ないので、USBの線を抜いて頂いて消すことになります。
勿論、電池が入っていなければ電池側にすればUSBを抜かずともスイッチ操作で消すことが出来ます。
●注意点としては、豆球は1A近い電流が流れるので、USBから電源供給する際には1A流せるUSBから電源供給する必要があります。
今回は、先程紹介した1A対応の充電器を使います。
台座とフィルムの合体は至って簡単で、フィルムの間口は自由に変形するので台座のお皿の様な部分に間口を変形させて斜め横から滑り込ませて一旦被せる感じになります。
そのままフィルム部を上に引き上げると台座の爪の部分に乗って固定されます。
単純だけどよく考えられた構造です。
ただ、その際に春分点を合わせた上で設置する必要があります。
フィルム部の一か所に矢印が付いていて、これを3月21日の春分に合わせるため五角形の一片を合わせます。
そうすることで、見たい星空の日付けダイヤルと時刻ダイヤルを合わせるとその時の星空を見る事が出来ます。
勿論、緯度も東京なら35度くらいに合わせれば星座の傾きなども正確に表現できます。
完成形がこちら。
最後に最終チェックで約10畳の部屋の真ん中に置いて投影してみました。
これはスゴイ!
これが雑誌の付録!?
下部中央に有るのがプラネタリウムの投影機です。
8月1日の20時の星空にしてあります。
画面中央には夏の大三角もしっかりあるでしょ。
上部には北斗七星も有って、右上の大きな星はうしかい座のアークトゥルスですね。
右下のカーテンのところにはさそり座もあります。
左のカーテンには秋の四辺形のペガススとその左にはアンドロメダ座。
私の〇万円の投影機だとほぼ天井にしか星は写りませんが、この投影機はご覧の様に壁から床までも一面星が写っています。
まるで、宇宙空間に浮遊しているかの様です。
クローゼットの扉は茶色なので星が茶色く見えています。
それにしても素晴らしい価値ある 3,278円 だと思います。
子供達の夏休みの工作にも最適かと・・・
私のホームスターも分類は「玩具」に位置しますが、大平さんの手掛けるものは玩具の域を遥かに超えます。
実際、30年以上前の巨大なプラネタリウムの投影可能な星の数の数倍の星が投影出来ていますから、その時代にこれを持って行ったらどれほど驚かれるか。
やっぱり日本人はスゴイ!!
この完成品を依頼主さんにも早く届けてあげたいですね。
本日午後に発送の予定です。