入社したばかりのペーペーの頃、事業の海外展開についてまとめていて、うろ覚えの「グローバリズム」なる言葉を使ったら、それを言うなら「グローバリゼーション」だろうと上司にたしなめられたことがある(笑)。あれから30年以上、最近は「グローバリズム」という言葉の方が多用され、厳密に区別されることなく混同して使われるように見受けられるが、言語感覚的には、「グローバリゼーション」は、人・モノ・カネ・情報が国境を越えて自由に行き交う(価値判断抜きの)現象を指し、「グローバリズム」はその現象をよしとするイデオロギーを指すのだろう。コトバンクが「世界を国家や地域の単位からではなく、連関した一つのシステムとしてとらえる考え方。地球主義。」と書くのは、国家間の関係を前提とするインターナショナリズムとの対比をも意識しているからだと思われるが、この言葉が登場した時代背景を思い起こせば、単純な主義・主張にとどまらず、ネオ・リベラリズムと相俟って、経済強者が弱者に押し付ける強者の論理の意味合いを帯びる。これを支えるのは経済合理性(あるいは資本の論理)であろう。再びコトバンクによれば「経済的な価値基準に沿って論理的に判断した場合に、利益があると考える」ことである。そう考えると、グローバリズムとは、Wikipediaが言うように「地球を一つの共同体と見なして、世界の一体化(グローバリゼーション)を進める思想」と言ってしまうと誤解を招きかねず、飽くまで国によって格差があり、言い換えると競争優位がそれぞれに異なる現実の世界を前提とするものであることが分かる。
そのため、最近のポピュリズムに見られるように、行き過ぎたグローバル化が格差社会をもたらしたとして、経済的な理由からグローバリゼーションは修正を迫られるようになった。さらに最近の技術覇権を巡る米中対立に見られるように、安全保障上の理由からもグローバリゼーションは修正を迫られるようになった。これらはいずれも同根とまで言い切るつもりはないが、いずれに対しても大きな役割を演じた存在がある。原則自由な資本主義と対立する国家資本主義を奉じる中国である。かつて13億(あるいはネット人口8億)の低賃金労働力を提供し、今はマーケット(14億あるいはネット人口9億)として立ち上がりつつあって、世界中、どの国とて中国を無視できるものではなく、中国との共存や競争のために多少なりとも自国内の産業構造変革を迫られて来た。日本で非正規雇用が増えたのは、煎じ詰めれば「世界の工場」中国に対抗するべく人件費を抑えるためだったに違いない。こうして見ると、グローバリズムは、冷戦崩壊後、アメリカ一極の覇権のもとでこそ機能し得たものだったと言えるのかも知れない。中国が経済的に台頭した今、グローバリズムをナイーブに叫ぶことはない。
戦争が、軍事合理性としての殲滅や破壊を単純に貫くことが出来ず、クラウゼヴィッツが言ったように政治の延長にあるものとして、政治の制約のもとに置かれるように(但しクラウゼヴィッツはナポレオンに見られる総力戦の出現を新たな革命的な現象であると高く評価した)、経済合理性もまた政治の制約のもとに置かれる。所謂「経済安全保障」の考え方である。軍事にしても経済にしても、政府の主要な行政機能の一つと位置づけられるからに他ならない。1985年という早い段階で“Economic Statecraft”と題する書籍を出して啓発されたDavid A. Baldwin教授は、政治による影響力行使の試みとしてのstatecraft(国政術)を以下の4つに分類された。
(1)経済力の行使によって影響を及ぼすeconomic statecraft
(2)軍事力の行使や威嚇によるmilitary statecraft
(3)交渉によって影響を及ぼすdiplomacy
(4)言語シンボルの意図的操作によるpropaganda
大抵の対外政策はこれらのツールの組合せである。如何に自由競争の経済と言えども、フリーハンドたり得ない。あのアダム・スミスも、市場が提供できないサービスとして、国防、司法行政、公共土木工事の三つを挙げ、国防は富裕(経済)に優先し、遥かに重要だと述べている。
私たちは、冷戦後のアメリカ一極支配下におけるネオ・リベラルなマインド・セットから脱却しなければならないのだろう。そういう意味で、経済合理性の申し子、典型とも言える孫正義さんは危なっかしく感じてしまう。もとより孫さんのことは尊敬するでもなく無視するでもなく、ただ小耳に挟むニュースから判断するに過ぎない。例えば、モバイル機器向けプロセッサーの中核を担う「コア」の設計情報で世界シェアの9割超を握るイギリスのアーム社を、ソフトバンク・グループは2016年に約3兆円で買収した。アーム社は中国に100%子会社を持っており、2018年に51%を現地企業に売却したが、中国投資(CIC)やシルクロード基金など政府系ファンドが実質株主となるため、技術流出の可能性があるとして、米国の対米外国投資委員会(CFIUS)は懸念を示したとされる。また、ソフトバンクは最近、イオンモールの施設に子会社が提供する顔認証技術と赤外線カメラ搭載の人工知能(AI)検温システムが導入されたと発表した。この技術は中国の商湯科技(センスタイム)が開発したもので、米商務省は昨年10月、中国・新疆ウイグル自治区に住むウイグル族やカザフ族に対する人権弾圧に関与したとして、この会社を含む民間企業や政府機関など計28社をEntity Listに掲載した。実質的な禁輸措置である。孫さんの行動は経済合理的だったに過ぎないのだろうが、中国と深く付き合う限りは、アメリカが設定するレッドゾーンに踏み込まないとは限らない。
折しも、グレアム・アリソン教授(ハーバード大学・政治学)は、冷戦後、アメリカが「勢力圏」を認識しなくなったのは、「勢力圏」の時代が終わったからではなく、アメリカの覇権という圧倒的な現実によって、他の(例えば旧・ソ連の)勢力圏が崩壊し、一つに統合されたに過ぎない、しかし、今やアメリカの覇権も崩れ始め、中国とロシアは、それがアメリカの利益と衝突するとしても、自国の利益や価値を促進するためにパワーを行使するようになり、ワシントン(米政府)も今や「大国間競争の時代」にあることを認識しつつある、と言われる(フォーリン・アフェアーズ日本語版3月号)。それはその通りだろうが、問題は、「アメリカの新しい役割が何であるか」をうまく定義できずにいることだと指摘され、戦略とは、「手段」と「目的」に関する意図的な調整によって描かれるもの(戦略が破綻するパターンは、表明した目的を動員・維持できる「手段」では実現できないか、理想にとらわれて達成できもしない「目的」を盲目的にビジョンとして掲げるかの、二つのミスマッチに派生するもの)という意味で、今後、アメリカの政策決定者は、彼らが夢見る「世界のための実現不可能な野望」は放棄し、「勢力圏が地政学を規定する中核要因であり続ける」という事実を受け入れなければならないと警告を発しておられる。既に兆候は現れているが、アメリカは同盟関係の棚卸しをするべき、ということだ。
アメリカ一極支配の覇権をポスト冷戦と呼ぶならば、昨今の米中対立はポスト・ポスト冷戦である。私たちビジネス・パーソンにとっては、なんとも悩ましい息苦しい時代に入った。
そのため、最近のポピュリズムに見られるように、行き過ぎたグローバル化が格差社会をもたらしたとして、経済的な理由からグローバリゼーションは修正を迫られるようになった。さらに最近の技術覇権を巡る米中対立に見られるように、安全保障上の理由からもグローバリゼーションは修正を迫られるようになった。これらはいずれも同根とまで言い切るつもりはないが、いずれに対しても大きな役割を演じた存在がある。原則自由な資本主義と対立する国家資本主義を奉じる中国である。かつて13億(あるいはネット人口8億)の低賃金労働力を提供し、今はマーケット(14億あるいはネット人口9億)として立ち上がりつつあって、世界中、どの国とて中国を無視できるものではなく、中国との共存や競争のために多少なりとも自国内の産業構造変革を迫られて来た。日本で非正規雇用が増えたのは、煎じ詰めれば「世界の工場」中国に対抗するべく人件費を抑えるためだったに違いない。こうして見ると、グローバリズムは、冷戦崩壊後、アメリカ一極の覇権のもとでこそ機能し得たものだったと言えるのかも知れない。中国が経済的に台頭した今、グローバリズムをナイーブに叫ぶことはない。
戦争が、軍事合理性としての殲滅や破壊を単純に貫くことが出来ず、クラウゼヴィッツが言ったように政治の延長にあるものとして、政治の制約のもとに置かれるように(但しクラウゼヴィッツはナポレオンに見られる総力戦の出現を新たな革命的な現象であると高く評価した)、経済合理性もまた政治の制約のもとに置かれる。所謂「経済安全保障」の考え方である。軍事にしても経済にしても、政府の主要な行政機能の一つと位置づけられるからに他ならない。1985年という早い段階で“Economic Statecraft”と題する書籍を出して啓発されたDavid A. Baldwin教授は、政治による影響力行使の試みとしてのstatecraft(国政術)を以下の4つに分類された。
(1)経済力の行使によって影響を及ぼすeconomic statecraft
(2)軍事力の行使や威嚇によるmilitary statecraft
(3)交渉によって影響を及ぼすdiplomacy
(4)言語シンボルの意図的操作によるpropaganda
大抵の対外政策はこれらのツールの組合せである。如何に自由競争の経済と言えども、フリーハンドたり得ない。あのアダム・スミスも、市場が提供できないサービスとして、国防、司法行政、公共土木工事の三つを挙げ、国防は富裕(経済)に優先し、遥かに重要だと述べている。
私たちは、冷戦後のアメリカ一極支配下におけるネオ・リベラルなマインド・セットから脱却しなければならないのだろう。そういう意味で、経済合理性の申し子、典型とも言える孫正義さんは危なっかしく感じてしまう。もとより孫さんのことは尊敬するでもなく無視するでもなく、ただ小耳に挟むニュースから判断するに過ぎない。例えば、モバイル機器向けプロセッサーの中核を担う「コア」の設計情報で世界シェアの9割超を握るイギリスのアーム社を、ソフトバンク・グループは2016年に約3兆円で買収した。アーム社は中国に100%子会社を持っており、2018年に51%を現地企業に売却したが、中国投資(CIC)やシルクロード基金など政府系ファンドが実質株主となるため、技術流出の可能性があるとして、米国の対米外国投資委員会(CFIUS)は懸念を示したとされる。また、ソフトバンクは最近、イオンモールの施設に子会社が提供する顔認証技術と赤外線カメラ搭載の人工知能(AI)検温システムが導入されたと発表した。この技術は中国の商湯科技(センスタイム)が開発したもので、米商務省は昨年10月、中国・新疆ウイグル自治区に住むウイグル族やカザフ族に対する人権弾圧に関与したとして、この会社を含む民間企業や政府機関など計28社をEntity Listに掲載した。実質的な禁輸措置である。孫さんの行動は経済合理的だったに過ぎないのだろうが、中国と深く付き合う限りは、アメリカが設定するレッドゾーンに踏み込まないとは限らない。
折しも、グレアム・アリソン教授(ハーバード大学・政治学)は、冷戦後、アメリカが「勢力圏」を認識しなくなったのは、「勢力圏」の時代が終わったからではなく、アメリカの覇権という圧倒的な現実によって、他の(例えば旧・ソ連の)勢力圏が崩壊し、一つに統合されたに過ぎない、しかし、今やアメリカの覇権も崩れ始め、中国とロシアは、それがアメリカの利益と衝突するとしても、自国の利益や価値を促進するためにパワーを行使するようになり、ワシントン(米政府)も今や「大国間競争の時代」にあることを認識しつつある、と言われる(フォーリン・アフェアーズ日本語版3月号)。それはその通りだろうが、問題は、「アメリカの新しい役割が何であるか」をうまく定義できずにいることだと指摘され、戦略とは、「手段」と「目的」に関する意図的な調整によって描かれるもの(戦略が破綻するパターンは、表明した目的を動員・維持できる「手段」では実現できないか、理想にとらわれて達成できもしない「目的」を盲目的にビジョンとして掲げるかの、二つのミスマッチに派生するもの)という意味で、今後、アメリカの政策決定者は、彼らが夢見る「世界のための実現不可能な野望」は放棄し、「勢力圏が地政学を規定する中核要因であり続ける」という事実を受け入れなければならないと警告を発しておられる。既に兆候は現れているが、アメリカは同盟関係の棚卸しをするべき、ということだ。
アメリカ一極支配の覇権をポスト冷戦と呼ぶならば、昨今の米中対立はポスト・ポスト冷戦である。私たちビジネス・パーソンにとっては、なんとも悩ましい息苦しい時代に入った。














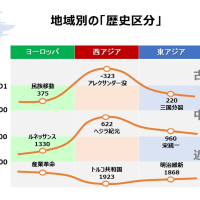




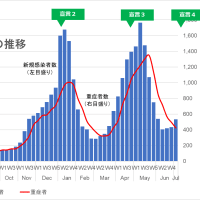






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます