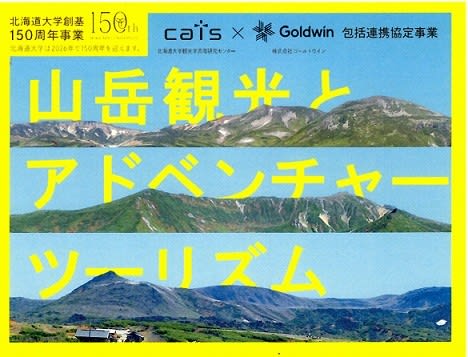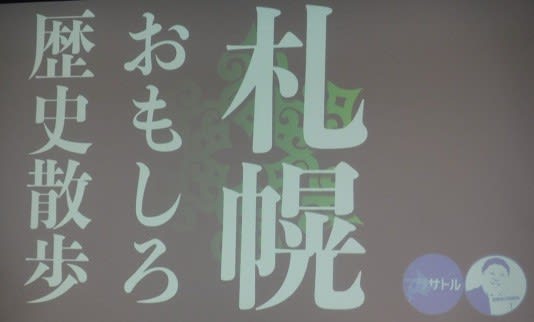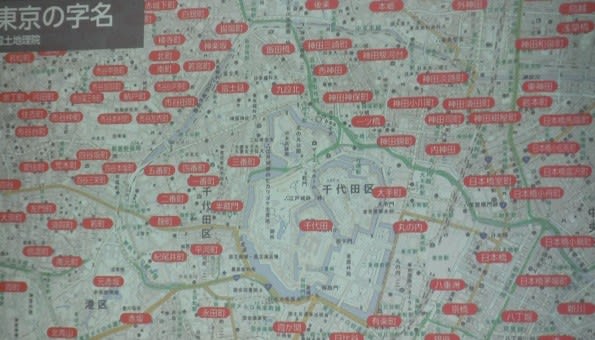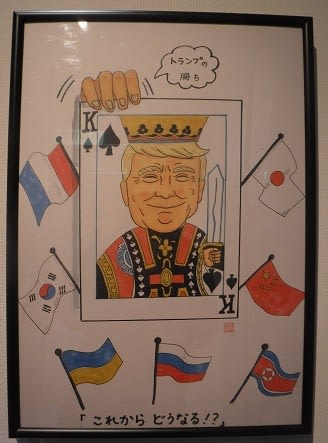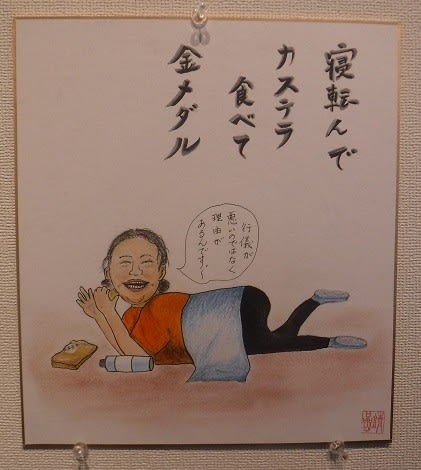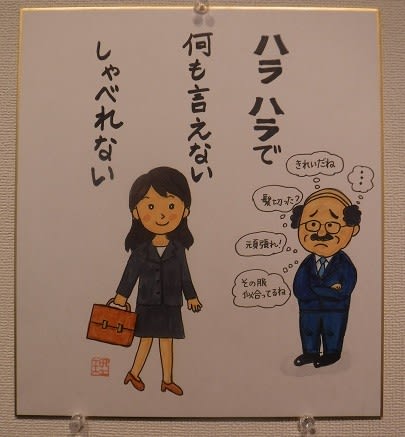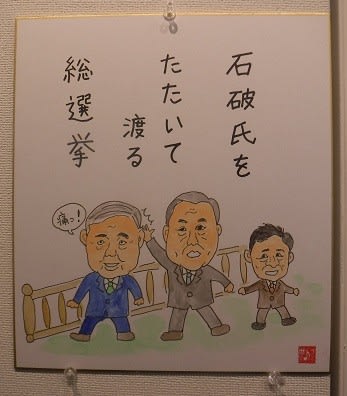元旭山動物園長の小菅氏は語ります。言葉を持たない動物たちから小菅氏は「すべてを教わった」と…。北海道弁を丸出しにして話す小菅氏の言葉の端々から動物への限りない愛の深さを感じさせられました。
昨日(1月12日)午後、かでる2・7において「民放クラブ講演会」が開催され参加した。今回の講師&テーマは、元旭山動物園長の小菅正夫氏が「すべて動物たちから教えてもらった」と題して講演したものでした。
昨日(1月12日)午後、かでる2・7において「民放クラブ講演会」が開催され参加した。今回の講師&テーマは、元旭山動物園長の小菅正夫氏が「すべて動物たちから教えてもらった」と題して講演したものでした。

小菅氏の業績については多くの方がご存じかと思いますが、振り返ってみると日本最北にある「旭山動物園」は、小菅氏が中堅の頃、来園数が伸び悩み閉園の危機に陥っていました。そうした状況の中で、小菅氏は長年動物たちを飼育する(付き合う)中で、動物たちの本性を突き止め、動物たちが生き生きと動き回る姿を来園者に見ていただく「行動展示」という方法を開発し、旭山動物園を来園者数日本一に導いた方です。
小菅氏は今回の講演を五つの柱を立ててお話されました。その五つの柱とは…、
① 時間に縛られない
② 幸福感
③ 生きる意味
④ 死生観
⑤ 明日は…
小菅氏のお話の内容を全てレポすることはとてもできませんが、小菅氏がお話されたエキスのようなものをお伝えすることができればと思います。
その一つは、動物たちは時間などに縛られて生きてはいないということを、チンパンジーの飼育を担当して教えられたと言います。動物(チンパンジー)は自然の変化を指標にして生きている。夜明けとともに活動し、夕暮れの前に寝床をつくる。ヒトも動物の一種と考えた時、小菅氏は腕時計を外したそうです。つまり、飼育を担当する者が時間に縛られた生活をしていて、飼育する動物の気持ちを理解することなどできないと小菅氏は教えられたようです。
また、動物たちはどのようなとき最も幸せを感ずるかというと、食べ物を探して採る時と、子を育てる・命を繋ぐ時だと教えられたということです。
「生きる意味」についても同様なことが言えると小菅氏は言います。小菅氏は「生きる意味についてたくさんの動物たちに尋ねてきました」と小菅語(?)で話されました。その過程でカバが明確な答えをしてくれたと言います。
カバは動物たちの中でも多産系のようです。旭山動物園でもゴン&ザブコのペアは何頭もの子どもを出産したそうです。しかし、ゴン&ザブコが高齢となり身体も痩せ細ってきたことから出産が無理と判断して動物園としては2頭を離して飼育していたそうです。
ところが2頭は一瞬の隙をついて交尾し、出産したそうです。小菅氏はカバから次のように教えられたと言います。「私たちは子どもを産んで、育てるために生きている」と…。つまり動物たちは「生きているかぎり、命を繋いでいく」ということを教えられたと小菅氏は話されました。
そして最後に「死生観」です。
動物は死を特別なこととは考えていません。人間はことさらに死を意識しているように思えますが、ゾウもトラもオオカミも、平気で死を迎えます。まさに悟りの境地にあるようです、と小菅氏は話された。

こうした対話を動物たちと重ねながら小菅氏は37年間の旭山動物園での生活を終えるのですが、これで小菅氏の動物たちとの付き合いが終わったわけではありません。
小菅氏は退職後、個人としてやり残したと思われることに取り組みます。そのやり残したこととは、
① ゾウの繁殖
② ゴリラの飼育
③ 生息地を知る
これらの解明のために、小菅氏はスマトラ、ボルネオ、ウガンダ、コンゴといった国々を飛び回り、動物の不思議を追い求めます。
そのことが2015年に札幌市環境局参与(円山動物園担当)を委嘱されることになります。そして、円山動物園にアジアゾウが導入される際は、導入するゾウの選定から、ゾウの繁殖(タオの誕生)まで指導的立場で現在も活躍中の方です。
小菅さんは飾らない人柄、動物の生態を北海道弁丸出しで話されるユーモアな話しぶりが、主婦層からは大人気のようです。この日の講演会でも多くの女性が詰めかけ、小菅氏に一言、一言に歓声を挙げながら聴き入っているのが印象的でした。
北海道だけではなく、今や国内的にも動物園界の指導的役割を果たしておられる小菅氏のますますの活躍を祈念したいと思います。