地形図で見る黒部峡谷
腰の具合も悪いし歳でもあるので、家の中で、地形図で峡谷を垣間見ることにしました。先ず、1/20万地勢図で、日本では最も規模の大きいといわれる黒部峡谷の概略を観ました。
そして、この度は黒部峡谷の十字峡と下廊下を地形図で眺めました。
先ず、1/2.5万地形図で見ると、
十字峡は、黒部川に垂直に交わる二つの支流の交差点です。
西からは立山・剣岳から流れてくる剣沢。東からは爺が岳・鹿島槍ヶ岳から流れてくる棒小屋沢です。
この剣沢と棒小屋沢がこの黒部川で十字に交わる極めて稀な峡谷を「十字峡」と呼んでいます。
そして、そこへ流れ出す激流が「下廊下」です。
黒部峡谷でも最も急な激流の流れで、長さ約4Kmあります。
道幅は約30cm(一尺)程度で、ひどいところでは100m以上もある断崖絶壁の上です。直下には黒部川の激流が走っています。
山容は幼年期から壮年期に属し、下刻の凄まじいV字谷と尖った周囲の山々を窺うことができます。命の保障のない路だそうです。ですから、私には無理です。
なお、「下廊下」があるので、当然「上廊下」(奥廊下も)もあります。黒部ダムのさらに上流部です。
人はほとんど立ち入れないそうです。
なお、帝国書院発行の『新詳高等地図』から「河食による地形の変化(地形の輪廻)」をお借りして地形の輪廻にふれると
先ず、隆起したり火山爆発などにより荒々しい地形が出現します。ここでは、侵食前の地形を表すために高原状のなだらかな地形のみが表現されていますが、火山爆発により生じた荒々しい原地形も混じります。( A 原地形)
それが、河川の浸食が始まると、V字谷を生み、急流や滝を造ります。一部には高原状の地形も残しますが・・・。それを幼年期地形( B )といっています。
そして、長い年月の浸食で、山尾根は鋭くとがり、谷はV字谷となり、谷の近くの平地(谷底平野)はほとんど見られない荒々しい地形になります。これを壮年期地形( C )と呼びます。
今回の黒部川沿いの地形はその典型です。
その断面図を上流に向かって並べると、下のようになります。
しかし、それでも比較的なだらかな地形が残っています。
例えば、右端の断面図の「内蔵助平」です。
幼年期の名残の地形といえます。
そして、行き着く先が老年期地形( D )です。
谷幅は広くなり、谷底と谷壁の堺が不明瞭になります。時には湿原も見られます。
そして、山頂や尾根は低く丘陵状になります。所々、硬質の岩石からなる丘(残丘)が残りますが。
年老いた私などが登れる山は老年期の地形ですね。ハイキングの山です。
地図でゆっくり、楽しみましょう。


























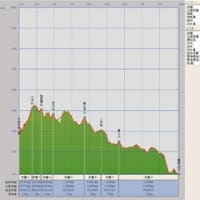
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます