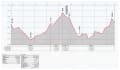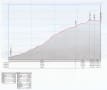日本百名山 48 剣岳(2998m)
「北アルプスの南の重鎮を穂高とすれば、北の俊英は剱岳(つるぎだけ)であろう。
層々たる岩に鎧われて、その豪宕(ごうとう)、峻烈、高邁の風格は、
この両巨峰に相通ずるものがある。」
と、書き出されている。
これらの山の記述には、これっきゃないという、山の “おごそかさ” の文字が書き記されています。
 (仙人山山頂より)
(仙人山山頂より)
設定: カメラ:PRO、レンズ:35mm、風景:地形図と合成、高さ強調1.5倍。
「(前人未踏の)その剱岳の神秘の開かれる日が来た。
明治四十年(1907)七月十三日、陸地測量部の一行によって、ついにその頂上が踏まれた。
ところが、
人跡未踏と思われていたその絶頂に初めて立ったのは彼らではなかった。
彼等より以前にすでに登った者があった。
測量部一行は頂上で槍の穂と錫杖の頭を発見したのである。・・・
古来登山者絶無と見なされていたこの峻烈な山に、誰か勇猛果敢な坊さんが登っていたのである。
それはいつの頃で、どのコースを採ったのであろうか。・・・」
「この発見から二年後に、純粋な登山を目的とする四人のパーティーによって登頂されたが、
それを案内したのは、前の測量隊に同伴した宇治長次郎であった。
そしてその時一行の登路に採った雪渓に長次郎谷という名が与えられた。
宇治長次郎と並んで、わが国近代登山黎明期の越中の名ガイドと呼ばれた佐伯平蔵は、
やはり剱岳当面の雪渓に平蔵谷の名を遺した。
そして長次郎谷と平蔵谷を分かつ岩稜は、
やはり名ガイドの一人の名をとって、源次郎尾根と呼ばれている。」
(新潮社刊、深田久弥著『日本百名山』より引用)
ここに、その3ルートの地図と経路断面図を並べます。
但し、今はこのルートはあまり使われていないそうです。
さて、数年前、私も 『剱岳』 新田次郎著・文春文庫 を読んだことがあります。
その裏表紙には、こうまとめられていました。
「日露戦争直後、前人未到と云われ、決して登ってはいけない山と恐れられた北アルプス、剱岳山頂に
三角点埋設の至上命令を受けた測量官、柴崎芳太郎。
機材の運搬、悪天候、地元の反感など様々な困難と闘いながら柴崎の一行は山頂を目指して進んでゆく。・・・」
そして、その本の巻頭には
「点の記とは三角点設定の記録である。
一等三角点の記、二等三角点の記、三等三角点の記の三種類がある。
三角点標石埋定の年月日及び人名、覘標(測量用やぐら)建設の年月日及び人名、測量観測の年月日及び人名の他、その三角点に至る道順、人夫賃、宿泊施設、飲料水等の必要事項を収録したものであり、
明治二十一年以来の記録は永久保存資料として国土地理院に保存されている。・・・」
この小説には、先ごろ映画にもなりました木村大作カメラマンによる、厳しい山の天候との闘いが記録されています。
私もその映画を見、小説も読みました。
つい先日見た『春を背負って』の映画は、その時のカメラマンが、監督もかねて撮影されたものです。
われわれの山の会にも、この山に登ったものが数人います。その中には女性も混じっています。
恐ろしい会に入ったものです。
でも、今の私はハイキング・オンリーですが・・・